世界はトランプ政権をどう見るか No.2
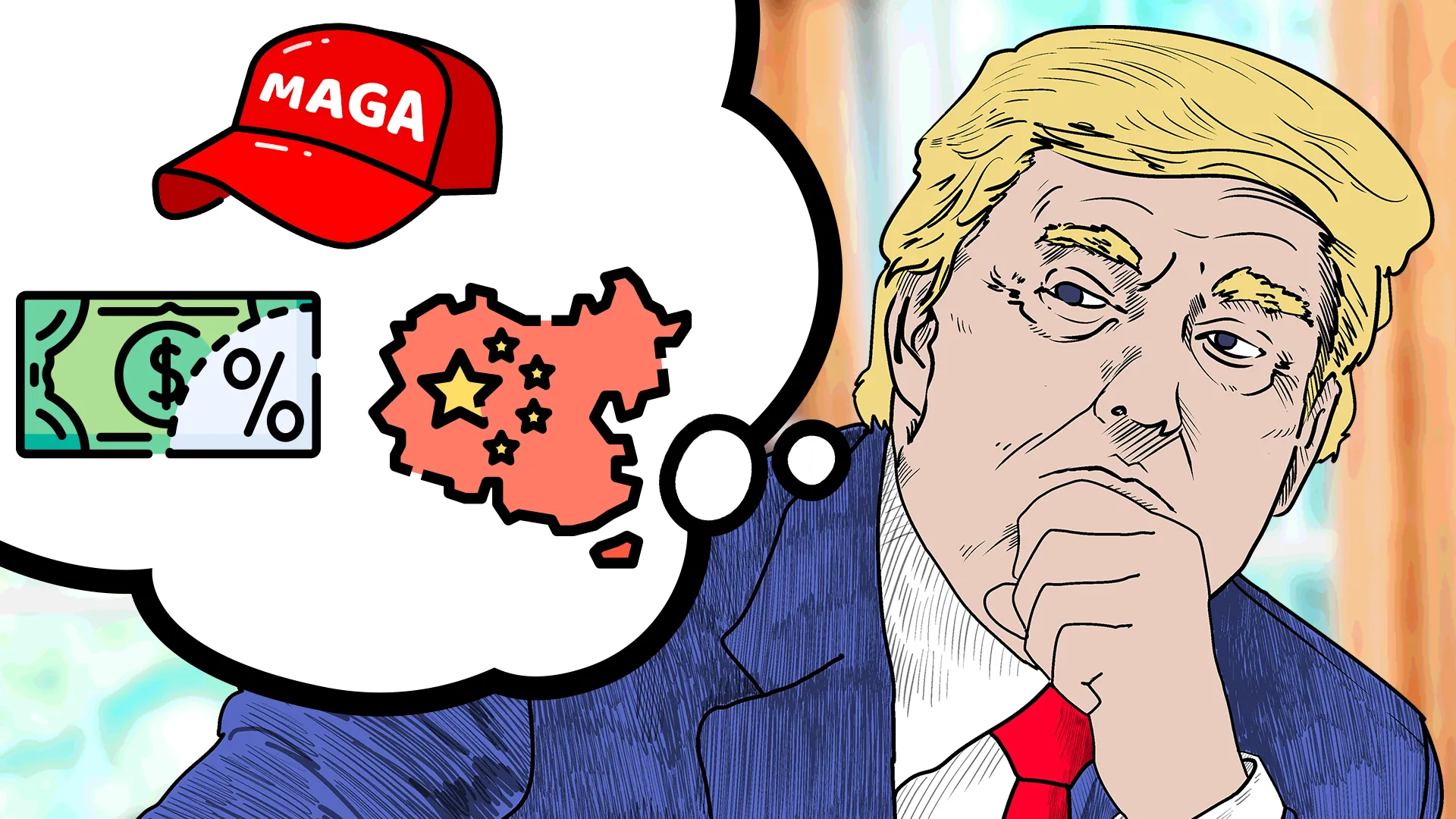
世界はトランプ政権をどう見るか(主要論考の紹介)

特集「2025年 トランプ政権は世界をどう変えるか」
トランプ第二次政権の動向がグローバル経済や国際秩序にどのような変化をもたらすのか、そして他国はどのように対応するのかが注目されます。本特集では、2025年のトランプ政権の政策動向とその影響を分析し、国際社会に与えるインパクトについて考察します。
①「TikTok問題は、米国民は中国と本気で対峙する覚悟がないことを示している」
Hal Brands, “TikTok Saga Shows Americans Can’t Be Bothered to Take On China,” Bloomberg, January 22, 2025
第2期トランプ政権の対中政策は、TikTok問題の対応から幕を開けた。米連邦議会は昨年、ByteDance社にTikTokを売却するか、2025年1月19日までに米国内での運営を停止することを義務づける法案を可決したが、トランプは就任直後、大統領令でその執行を75日間延期する措置を講じた。この決定には賛否両論が巻き起こったが、その中で特に広い視点からこの動きの問題を指摘したのが、ジョンズ・ホプキンス大学および保守系シンクタンクAEI(アメリカン・エンタープライズ研究所)で国際政治を研究するハル・ブランズである。
ブランズは、TikTokをめぐるトランプの対応が、米国が国民に負担を強いることなく米中冷戦を遂行しようとしている重大な弱点を浮き彫りにしていると主張する。このような態度では、米国が台湾防衛に駆けつける可能性は低く、対中抑止力の強化も中途半端に終わるだろうと警鐘を鳴らしている。TikTokへの対応は、トランプ政権の対中政策を示唆する象徴的な前兆といえるだろう。
②「トランプ-バイデン-トランプの外交政策」
Richard Fontaine, “The Trump-Biden-Trump Foreign Policy,” Foreign Affairs, January 20, 2025
第2次トランプ政権の対外政策について、バイデン政権との継続性に着目して予測した論考である。2008年の米大統領選で共和党のジョン・マケイン候補の外交政策アドバイザーを務め、国務省・国家安全保障会議・上院外交委員会等での勤務経験も豊富なリチャード・フォンテーンが『フォーリン・アフェアーズ』に寄稿した。
フォンテーンは、バイデン政権が外交政策上の多くの問題で第1次トランプ政権のアプローチを維持したと指摘する。中国とロシアの戦略的競争相手という位置付けの継続、対中関税の維持、技術移転規制の拡大、トランプ政権とタリバンとの間で交渉されたアフガニスタン撤退合意の実行などがその例であり、こうした連続性が第2次トランプ政権でも維持されるだろうとしている。トランプ政権のセンセーショナルな側面が強調されることが多いが、外交政策に関しては継続性への注目も非常に重要である。「中間層のための外交政策」に象徴されるように、多国間主義への復帰を掲げたバイデン政権も、結果的に国内産業保護を強く意識した保護主義的な政策を実施した。国際的な関与からの撤退は、米国外交の一貫した方向性になるかもしれない。
③「アメリカ造船業を再び偉大に—米国建造船舶の関税を削減せよ」
Craig Hooper, “Make American Shipbuilding Great Again—Cut Tariffs For U.S.-Built Ships,” Forbes, January 5, 2025, updated January 17, 2025
トランプ政権の関税引き上げ政策には、財政やインフレなど多岐にわたる論点があるが、米国の海洋安全保障政策の専門家クレイグ・フーパーは、米国の衰退した造船業と結びつけた独自の提言を行っている。彼の主張によれば、米国の造船業を再活性化し、有事の際に米軍を支援可能な米国船籍を増やすためには、関税を一律引き上げる一方で、米国内で建造され、米国に船籍が登録され、米国籍の船員が運用する船舶を利用した輸入品には関税を引き下げるべきだという。このような政策を実施すれば、米国の造船業が復活する可能性があると論じている。
トランプは当初、就任直後に関税引き上げを実施すると予想されていたが、90日間のレビュー期間を設けることを選んだ。この間、フーパーの提案のような米国内製造業の強化を目指した具体的な関税政策が提案され、それがトランプ政権の政策の方向性を形成していくと考えられる。
④「習近平はトランプの駆け引きに報復する計画を持っている」
Evan Medeiros, “Xi has a plan for retaliating against Trump’s gamesmanship,” Financial Times, January 5, 2025.
米中貿易戦争をはじめとする米中対立は、第2次トランプ政権下の国際関係の中でも最大の焦点である。国家安全保障会議のアジア上級部長、大統領特別補佐官(アジア問題担当)を歴任するなど、オバマ政権の対中政策の中枢を担ったジョージタウン大学教授のエヴァン・メデイロスは、中国の第2次トランプ政権への対応戦略について論じている。
メデイロスによると、習近平政権は、輸出規制や投資制限といった米国が仕掛けてくる政策を模倣して米国企業に痛みを与える「報復」、中国の国内経済の強化による米国との対立への「適応」、米国以外の貿易相手国との経済的結びつきを拡大する「多元化」の三つの戦略を駆使して米国との長期的な競争に打ち勝つ準備を行っている。第2次トランプ政権の外交政策を主導するマルコ・ルビオ国務長官とマイク・ウォルツ国家安全保障問題担当大統領補佐官はともに対中強硬派とされるが、トランプ大統領が習近平国家主席との直接的なディールに乗り出す可能性もあり、トランプ政権の対中政策は予断を許さない。その中で、中国側がどのように対応しようとしているかを見極めることは極めて重要となる。
⑤トランプの『アメリカらしさ』が中米関係に与える影響
林宏宇「特朗普的“美国性”对中美关系的影响」『亜太日報』、2024年12月1日。
筆者の林宏宇は中国共産党中央統一戦線工作部所掌の華僑大学(福建省)の教授を務める人物。本稿の出所は本拠地を香港に構える新華社系『亜太日報』であるが、中国のニュースポータルサイト「網易」にも掲載されている。トランプ2.0の影響が懸念される中、トランプ再選は中米関係に影響を与えず、むしろ両国関係に利益をもたらすかもしれないと主張する。この点において注目に値するだろう。
筆者は今回の大統領選を、米国に溜まる不満がトランプをMAGAの旗の下、ホワイトハウスに再び送り込んだと評する。そのうえで、対中関税賦課は不可避と予想し、中国は国内改革や供給改革、国内市場の育成に努め、こうした現状をむしろ「世界の工場+世界の市場」へと変化する新たな機会ととらえるべきであると主張する。
台湾問題にも限定的ながら言及している。トランプは「有償」の同盟関係を提唱するが、これは台湾も対象である。トランプは幻の「民主共同体」のために無駄な労力は費やさないだろうと述べ、こうした状況は両国関係にとってむしろ好都合であるとも主張する。
最後に、「マー・ア・ラーゴ会談」やトランプ1.0時代の中国への国賓訪問が束の間の蜜月関係をもたらしたことを忘れてはいけないと述べ、もしも中国が彼をうまく導くことができれば、中米関係における歴史的突破口を開くことができるかもしれないと論考を締めくくる。総じていえば、前向きな論調といえよう。世界がトランプを「危険視」するなか、むしろチャンスをもたらすかもしれないと述べている点において注目に値する。
⑥「安定した中米関係は両国の共通利益にかなう」
「鐘声」署名記事「稳定的中美关系符合两国共同利益」『人民日報』、2024年11月8日。
本記事は『人民日報』に掲載されたものであるが、2つの意味において注目に値する。第一に、「鐘声」の名で署名されていること。中国語で「鐘」は中国の「中」の字と発音が同じであり、それゆえ「鐘声」は「中国の声」と解される。それゆえ注目される。第二に、トランプ再選直後に掲載されたものであること。米国に対し相互尊重、平和共存、協力・ウィンウィンこそが肝要であると述べつつも、中国にはレッドラインがあると主張するが、掲載時期を考えるに、これはトランプ2.0へのメッセージと理解できる。この意味においても注目に値するだろう。
本記事は、11月7日、習近平がトランプに対し祝電を送ったと述べることから始まる。そして以下のように続ける。歴史を振り返るに、中米関係には多くの波乱があった。だが、常に前向きに発展してきたのであり、相互尊重、平和共存、協力・ウィンウィンこそが、過去50余年の歴史から導出された進むべき道であるといえる。これは両国民の利益にかなうものであろう。
本記事は両国間の経済関係がいかに深いものであるかについても、データを示し論じている。しかも、両国は伝統・新興分野を問わず広範な利益を共有しており、双方には無限の協力の余地があるとまで述べている。
しかし、記事後半では、両国は協力すればともに利益を得るが、争えばともに傷つく。中国の封じ込めでは、米国は自国の問題を解決できないだろうとも述べ、けん制することを忘れてはいない。続けて、中国には守らなければならない利益と原則があり、レッドラインがあるとも述べている。すなわち、本稿は米国に対するラブレターでありつつも、やはり中国にとって重要な点では妥協しないことを明言する文章でもあるのである。中国がいかにトランプ2.0と向き合おうとしているのかを考察するうえで注目に値する記事といえよう。
-
 India and EU Sign Mother of All Deals2026.02.09
India and EU Sign Mother of All Deals2026.02.09 -
 Orbán in the Public Eye: Anti-Ukraine Argument for Delegitimising Brussels2026.02.04
Orbán in the Public Eye: Anti-Ukraine Argument for Delegitimising Brussels2026.02.04 -
 Trump, Takaichi and Japan’s Strategic Crossroads2026.02.03
Trump, Takaichi and Japan’s Strategic Crossroads2026.02.03 -
 Analysis: When Is a Tariff Threat Not a Tariff Threat?2026.01.29
Analysis: When Is a Tariff Threat Not a Tariff Threat?2026.01.29 -
 Takaichi’s Strengths and the Need for ‘Strategic Signaling’2026.01.23
Takaichi’s Strengths and the Need for ‘Strategic Signaling’2026.01.23
 Oil, Debt, and Dollars: The Geoeconomics of Venezuela2026.01.07
Oil, Debt, and Dollars: The Geoeconomics of Venezuela2026.01.07 It’s Now or Never: India’s Ambitious Reform Push2026.01.09
It’s Now or Never: India’s Ambitious Reform Push2026.01.09 Orbán in the Public Eye: Anti-Ukraine Argument for Delegitimising Brussels2026.02.04
Orbán in the Public Eye: Anti-Ukraine Argument for Delegitimising Brussels2026.02.04 Analysis: When Is a Tariff Threat Not a Tariff Threat?2026.01.29
Analysis: When Is a Tariff Threat Not a Tariff Threat?2026.01.29 Navigating Uncertainty in U.S. Space Policy: Decoding Elon Musk’s Influence2025.04.09
Navigating Uncertainty in U.S. Space Policy: Decoding Elon Musk’s Influence2025.04.09












