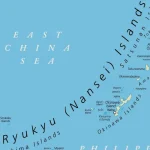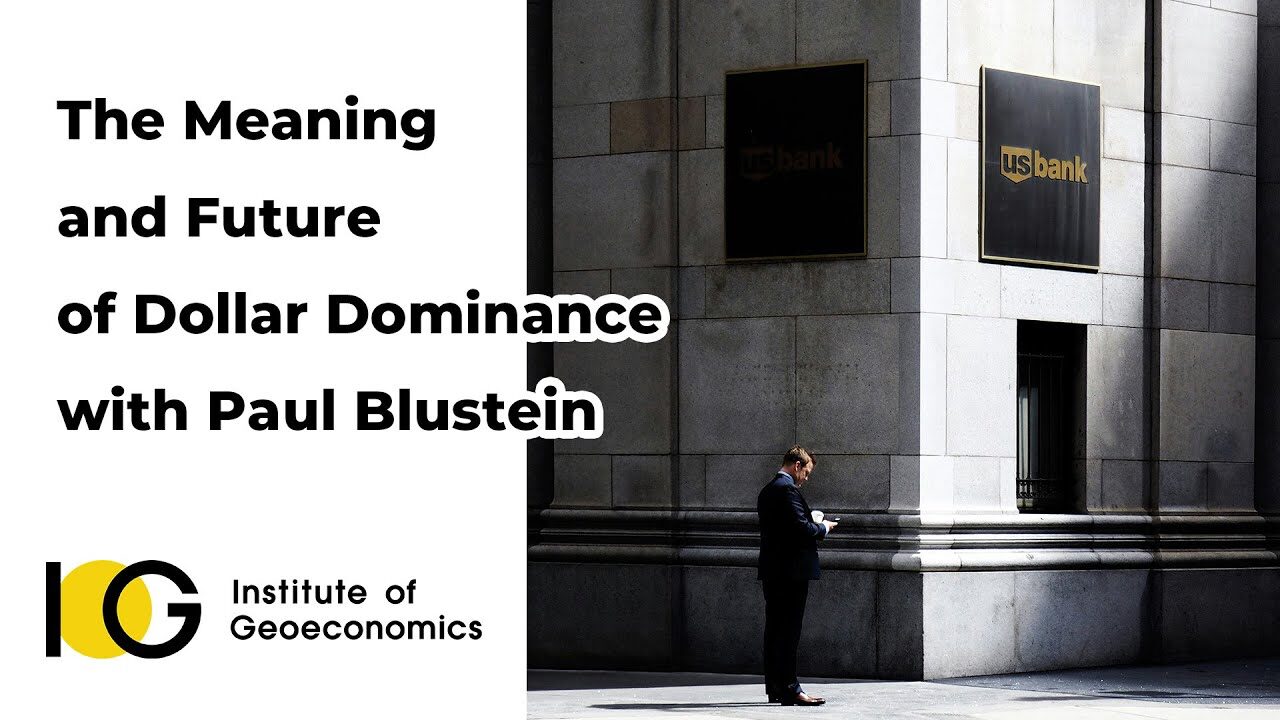防衛力の抜本的強化に求められる反撃能力と継戦能力の在り方

有識者会議では「防衛力の抜本的強化による経済成長への貢献」が主題であったが、本稿ではあえて抑止力に関する提言に焦点を当てる。報告書は、戦争は一旦始まれば終わらせることが困難であるため、そもそも戦争を起こさせない抑止力が重要だと主張する。そして、その「抑止力の鍵」が反撃能力であり、それをさらに強化するためには、長期戦に耐えうる継戦能力の整備が必要だと論じる。これらを実現するために、無人アセット、VLS搭載潜水艦、太平洋側における防衛体制構築に資する防衛装備を整備するべきだと提言している。
では、果たして反撃能力は抑止力の要となり得るのか。反撃能力を抑止の中核に据えるには何が求められるのか。抑止力を強化する継戦能力をいかに構築すべきか。本稿ではこれらの問いを検討する。
対中抑止力に求められる要素
抑止力は、攻撃の際に発生するコストを高めて敵の行動を躊躇させる懲罰的抑止と、敵に目標達成の見込みがないと判断させて攻撃を断念させる拒否的抑止に分けられる。有識者会議の報告書からは、引き続き後者の強化を進めるべきとの主張が読み取れる。効果的な拒否的抑止には「十分な能力」と「実行する意思」が必要であり、ここでいう能力とは、相手の「勝利の方程式(TOV: theory of victory)」を崩すために必要な因果的対応力を指す。では、報告書が重視する反撃能力は相手のTOVを崩壊させるうえで有効な手段となりうるのか。
日本の安全保障コミュニティで最大の注目を集めるシナリオは、中国による台湾への本格侵攻が発生した事態に日本が巻き込まれるケースである。仮にそのような事態が発生した場合、中国は短期間で作戦目標を達成することを志向すると考えられてきた。すなわち、中国軍のTOVは、日米のC4ISRを麻痺させ、海空軍種の基地を打撃し、米軍の増援到着前に台湾への上陸等を達成する、という短期決戦モデルである。その証に、中国は長射程火力の強化、宇宙・サイバー・電磁領域における攻撃能力の整備、さらには軍の智能化を進めてきた。
中国軍のTOVを崩壊させる方法は大別して二つ考えられる。一つ目は「第一撃を阻止する」ことである。これを実現するには、中国が攻撃を開始する前に打撃作戦を実施する必要があるが、このアプローチは危機安定性を著しく損ないかねない。加えて、政府は反撃能力の導入を説明する際にあくまで「相手からの更なる武力攻撃を防ぐ」手段であり、先制攻撃は許されないと繰り返し強調してきたことから、有事に第一撃の阻止を選択する可能性は低いだろう。
二つ目の方法は、第一撃の被害を最小限に抑えつつ、その後に中国軍が短期で勝利を収めることを困難にするいわゆる拒否戦略と呼ばれるアプローチである。具体的には、積極・消極防御手段を通じて第一撃の被害を低減し、その後、継続的に中国軍の作戦目標達成を妨害することで相手方のTOV成立を拒むというものである。この観点からすれば、反撃能力は「抑止力の鍵」となるかどうかは別として、拒否戦略に合致した手段の一つであるといえる。さらに、中国軍を執拗に妨害するためには、相応の継戦能力が求められる。
反撃能力は「抑止力の鍵」たりえるのか
最適な拒否戦略のアプローチとは何か。それは相手のTOVを崩すことに有効であり、かつ、エスカレーション・ドミナンスを相手方に取られるリスクが低い方法である。では、報告書が提言する反撃能力は、この二つの要件を満たし得るだろうか。
有識者会議は、次世代の動力を用いる「VLS搭載潜水艦」(報道では原子力潜水艦)の導入といった「能力(capability)」の向上をうたっているが、有効な反撃能力には「規模(capacity)」も重要である。中国軍は高い防空能力を有し、強固な施設を多数そろえているため、仮に航空基地を撃破するのであれば同時に大量のミサイルを投入しなければならない。しかし、言うは易く行うは難しであり、米海軍が2017年にシリアの航空基地をトマホーク59発で攻撃した際も、数時間後に同基地から航空機が発進していることが確認されている。さらに、中国の東部戦区には日本より多くの航空基地が点在しており、ある基地を機能不全にしても他の基地や空港に退避することが比較的容易であるため、同時に複数の基地を破壊しなければならない。加えて、一度に限らず何度にもわたって繰り返していかなければならないため、それを可能にするだけの備蓄が求められる。
VLS搭載潜水艦は、隠密性や機動性の側面から一見して望ましい選択肢のように見えるが、建造・維持にかかる費用が大きく、多数の乗員を必要とするため制約が大きい。そのため数を揃えにくく、その分だけ同時発射能力は低下する。加えて、搭載ミサイルを使い尽くした場合、再装填のために潜水艦が入港し最も脆弱な状態に晒される必要が生じる。そして、仮に1隻でも失えば反撃能力に与える損失は甚大であることから、システム全体としての残存性にも疑義が残る。なお、報告書では盛り込まれていないが、発射台付き車両(TEL)であればこうした問題は克服されやすい。
反撃作戦の実施に伴うエスカレーションのリスクは、米国による拡大核抑止の信憑性が高ければある程度克服できた問題かもしれない。しかし、報告書が論じるように、アメリカ・ファーストの姿勢が「米国の構造的変容であり、一過性のものとならない可能性がある」と考えられる現在、米国の核戦力によるバックストップの信憑性は、同盟国である日本にとっても、抑止対象である中国にとっても低下していると評価せざるを得ない。これは、中国がエスカレーションを進める上で優位性を得やすい状況を生み出す一方、日本の反撃作戦が中国の核恫喝などによって抑止されやすくなることを意味する。こうして中国がエスカレーション・ドミナンスを確立しやすい環境が整いつつあるなか、日本政府が有事の際に反撃作戦の実施を決心できるかには疑問が残る。反撃能力は整備すべき手段である一方、米国のコミットメントが薄れている中でそれを「抑止力の鍵」と位置づけることは最適な拒否戦略のアプローチとは言えない。反撃能力の位置づけは、戦略環境の変化に応じて常に見直す必要があり、米国の拡大核抑止の信憑性が低下している今、その重要性は相対化していると考えられる。
継戦能力の諸課題
今回の有識者会議による日本の防衛議論への最も大きな貢献の一つが、継戦能力を強調した点であろう。短期戦を目指す相手に対して、こちらが長期戦に備えていることを示せば、「第一撃を受けても戦い続けられる」というメッセージを伝えることができ、相手に自らのTOVを見直させる効果が期待できる。また、仮に抑止が失敗して有事に発展した場合も、高い継戦能力を保持していれば、その分だけ自衛隊の作戦の自由度が高まり、粘り強い戦い方が可能になる。
防衛省・自衛隊は、戦略三文書の公表以降、継戦能力の強化に取り組んでおり、弾薬・部品の備蓄や弾薬庫の整備を進めている。加えて、自衛隊海上輸送群を編成するなどして、南西諸島での戦闘に適した体制づくりを図っている。しかし継戦能力に関しては、依然として多くの課題が残っているのもまた事実である。これらの課題は、自衛隊自身が抱えるものと、防衛産業を取り巻く環境に起因するものの二つに大別できる。
継戦能力にかかる前提の見直し
継戦能力に関して自衛隊が抱える問題は二つある。第一は、弾薬備蓄に関する前提を見直す必要がある点だ。整備すべき継戦能力を最も単純化して図式化すると、以下のような方程式になる。
(想定される戦闘の烈度×戦闘期間)―(同盟国・同志国の支援)=防衛省が整備すべき継戦能力
各項目はいずれも変数であるため、備蓄すべき弾薬の数量や求められる防衛産業の緊急増産・修理能力の規模を一概に示すことはできないが、冷戦期に立てられていた前提と今日の動向を比較することでいかに継戦能力を計算するための前提を見直さなければならないかが分かるだろう。
基盤的防衛力構想のもとで防衛力整備を進めていた冷戦後期、自衛隊は、米軍が短期間で大規模な来援部隊を確実に送ってくれると想定していた。そのため、ソ連による北海道侵攻シナリオに対して、わずか2週間分の弾薬のみを備蓄する計画を立てていたとされる[1]。
しかし、戦略環境が当時から大きく変わった現在、継戦能力を算出するために必要な各要素も大きく変化した。台湾有事は長期戦に発展するとの見方が台頭しつつあり、戦闘の烈度は戦いが推移していくうえで変化するものの、極めて苛烈なものになると予想されている。加えてアメリカ・ファーストが広がる米国が来援する意思を持っているかはもはや自明ではなく、仮に来援する意思があったとしても、そのミサイル備蓄量からして限界がある。こうした状況下で米国の来援に期待を寄せることはリスクが高く、新たな前提に基づいた弾薬や部品の備蓄や防衛産業の強化が求められる。
自衛隊が抱える継戦能力に関する二つ目の問題は、南西諸島に展開している部隊への補給手段である。現時点では国内政治上の制約から、南西諸島に大規模な弾薬庫を多数設置することは難しく、事前集積の試みは大きく遅れている。そのため有事には本土から弾薬を輸送せざるを得ないが、周辺海空域での優勢確保が以前にも増して困難となると考えられている中、シグネチャーの大きい輸送機や輸送艦での輸送は極めて危険であり現実的ではない。そうであるならば、海兵隊が運用試験を進める半潜没型の小型無人艇のような新たな補給手段を検討する必要があるが、そうした手段を配備する計画はおろか、開発の動きすら見られない。
有事を念頭に置いていない防衛産業政策
継戦能力は平時からの備蓄のみならず、有事における防衛産業による戦力回復の試みによっても大きく支えられている。一般に防衛産業は、有事において修理・増産・改良・開発といった役割を担うとされ、戦略三文書でもその重要性を踏まえ「防衛力そのもの」と位置づけている。しかし、今日の防衛産業政策は基本的に平時のみを意識したものであるため、防衛産業を有事において十分な役割を果たせるような準備がなされていない。
防衛産業が平時と有事で直面する最大の違いは二つある。第一に、需要の急増であり、特に弾薬の製造を大幅に増やす必要がある。ウクライナ戦争が示したように、大規模な戦争では、往々にして従来の想定をはるかに上回る速度で弾薬を消費していく。防衛産業は有事においてこれを継続的に補充しなければならないが、平時から有事を見越して大規模な余剰生産能力を企業が維持することは非現実的である。そのため、海外では政府が所有し企業が運営する国有施設民間操業(GOCO)方式を採用する例がある。防衛省は同方式の導入を打ち出したが、依然として実現させていない。有識者会議はこの点について「国自身が必要な装備品の製造や整備を行う」ことも検討すべきだと指摘している。
二つ目は、防衛産業は「防衛力そのもの」であるがゆえに攻撃対象になるという点である。防衛産業が担う戦力回復の役割の重要性は短期戦ではそれほど高くないが、戦闘が長期化すれば飛躍的に重要性を増し、それに比例して攻撃されるリスクも高まる。実際、ウクライナでも防衛企業が攻撃対象となっている。このように極めて重要かつ攻撃リスクの高い存在でありながら、防衛企業が有事において、自衛隊に物品や役務を確実に提供できる体制にはなっておらず、自衛隊も防衛産業を防護する体制を整えられていない。
特に大きな問題は、有事の際に防衛企業が業務に従事し続けられるかどうかが不透明である点だ。現行法では防衛産業に対して業務従事命令を出すことができない。自衛隊法第103条第2項は、自衛隊の行動にかかる地域以外のうち内閣総理大臣が告示する地域において、医療や土木建築工事、輸送を業とする者に対して業務従事命令を出せると規定しているが、装備品や弾薬を製造・整備する企業や者はその対象に含まれていない。また、仮に法改正で防衛産業を対象に含めたとしても、ミサイルや特殊部隊の脅威を考えれば日本全国が「自衛隊の行動にかかる地域」に指定される可能性もあるため、結果として第2項の地域区分が事実上消失して防衛省が民間事業者に業務従事命令を出せなくなる恐れもある。
こうした問題は業務従事命令ではなく、契約によって解決することも考えられる。しかし、一部の防衛企業は基地に隣接しており、さらに造船所は中国本土に地理的に近い瀬戸内や九州北部に集中しているため、工場自体が攻撃・破壊されるリスクが高い。加えて、経営陣や労働組合が従業員の安全を理由に操業停止を判断すれば、実質的に生産が停止してしまう可能性がある。防衛産業を自衛隊が優先的に防護する対象と位置づければ、従業員の安全を担保したうえでの稼働継続が期待されるが、現状では、防衛産業は重要防護施設にすら指定されておらず、防護を前提とした訓練も行われていない。
結びにかえて
有識者会議が抑止力強化の必要性を指摘した点は高く評価できるものの、十分に論じ切れていない部分が多い。反撃能力を「抑止力の鍵」とする主張も、他のアプローチとの比較が示されておらず唐突に聞こえる。さらに、特定のプラットフォームの重要性を過度に強調する一方で、なぜそのアセットでなければならないのかという説明が不足している。加えて、米国による拡大核抑止の信憑性低下がもたらす影響についても十分に検討されていない。継戦能力については、この問題に光を当てた点自体は重要な貢献といえるが、分析は表面的にとどまり、構造的・制度的課題への踏み込みに欠けている。
いずれにせよ、同報告書は、これまで公に議論されてこなかった重要な論点を多数問題提起しており、次期国家防衛戦略に与える影響は計り知れない。今後もさまざまなシンクタンクから提言書が公表され、活発な議論が行われることを期待したい。
(出典:防衛装備庁)
[1] 「防衛上「有事」二つのシナリオ、現実離れ(時時刻刻)」『朝日新聞』1996年9月2日。


Research Associate
Rintaro Inoue is a Research Associate at the Asia Pacific Initiative (API) & the Institute of Geoeconomics (IOG), the International House of Japan (IHJ), a Tokyo-based global think-tank, where he focuses on U.S. security policy, the U.S.-Australia alliance, Japanese defense policy, and economic statecraft including defense industrial base policy. Prior to assuming his current position, he joined the Asia Pacific Initiative (API) as an intern and contributed to multiple projects including the Japan-U.S. Military Statesmen Forum (MSF). He is currently researching defense industrial policies of other countries in the International Security Order Group. He received his BA and MA in law from Keio University and is now a PhD student.
View Profile-
 It’s Now or Never: India’s Ambitious Reform Push2026.01.09
It’s Now or Never: India’s Ambitious Reform Push2026.01.09 -
 Oil, Debt, and Dollars: The Geoeconomics of Venezuela2026.01.07
Oil, Debt, and Dollars: The Geoeconomics of Venezuela2026.01.07 -
 Analysis: Ready for a (Tariff) Refund?2025.12.24
Analysis: Ready for a (Tariff) Refund?2025.12.24 -
 China, Rare Earths and ‘Weaponized Interdependence’2025.12.23
China, Rare Earths and ‘Weaponized Interdependence’2025.12.23 -
 Are Firms Ready for Economic Security? Insights from Japan and the Netherlands2025.12.22
Are Firms Ready for Economic Security? Insights from Japan and the Netherlands2025.12.22
 The “Economic Security is National Security” Strategy2025.12.09
The “Economic Security is National Security” Strategy2025.12.09 Oil, Debt, and Dollars: The Geoeconomics of Venezuela2026.01.07
Oil, Debt, and Dollars: The Geoeconomics of Venezuela2026.01.07 The Tyranny of Geography: Okinawa in the era of great power competition2024.02.09
The Tyranny of Geography: Okinawa in the era of great power competition2024.02.09 Is China Guardian of the ‘Postwar International Order’?2025.12.17
Is China Guardian of the ‘Postwar International Order’?2025.12.17 The Real Significance of Trump’s Asia Trip2025.11.14
The Real Significance of Trump’s Asia Trip2025.11.14