世界はトランプ政権をどう見るか No.10
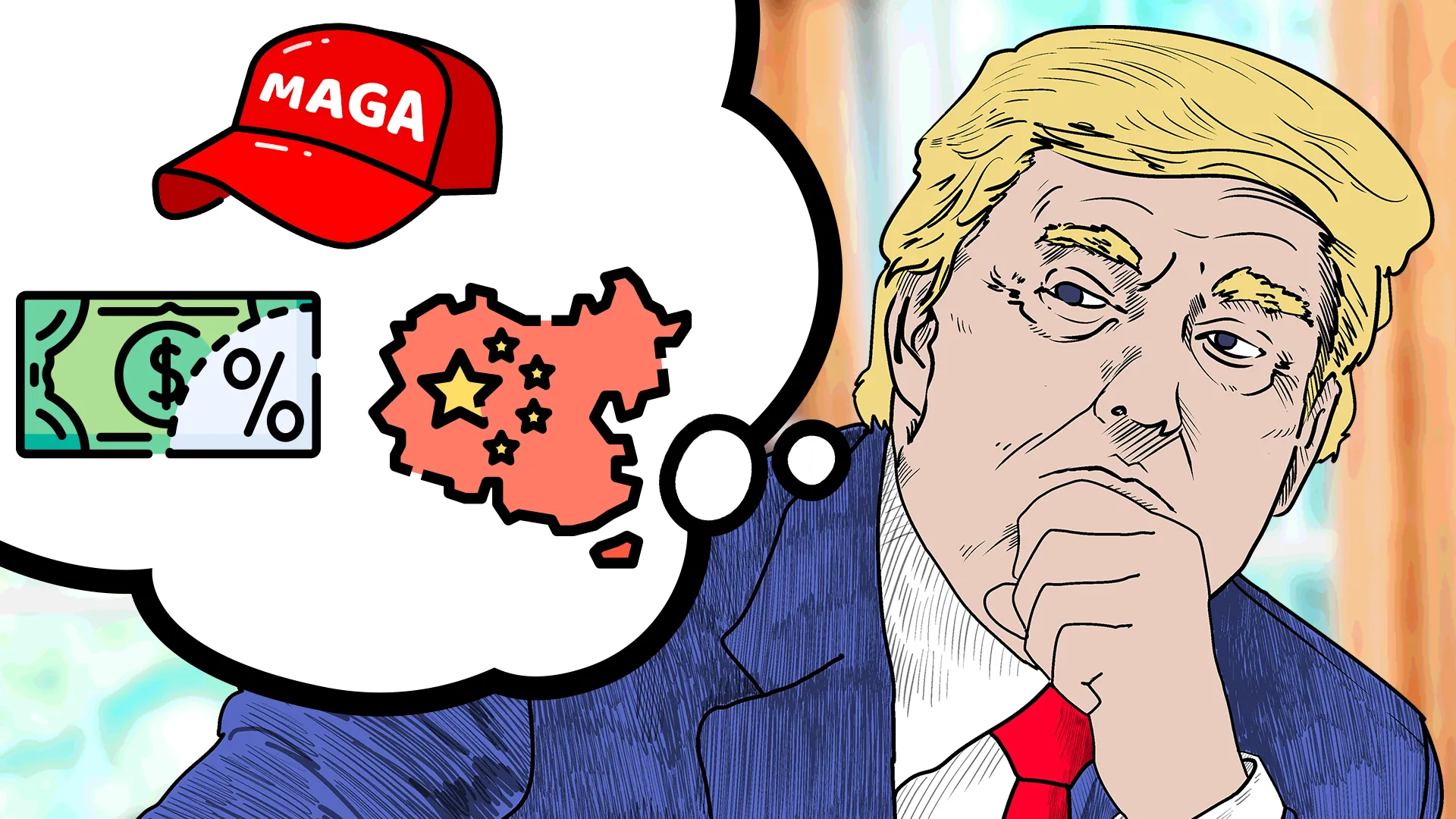
世界はトランプ政権をどう見るか(主要論考の紹介)

特集「2025年 トランプ政権は世界をどう変えるか」
トランプ第二次政権の動向がグローバル経済や国際秩序にどのような変化をもたらすのか、そして他国はどのように対応するのかが注目されます。本特集では、2025年のトランプ政権の政策動向とその影響を分析し、国際社会に与えるインパクトについて考察します。
①「トランプ関税の立役者:トランプ後の米国はどこへ向かうべきか」
Oren Cass, “This Is the Moment We Find Out if Trump Is for Real,” The New York Times, September 3, 2025.
米シンクタンク「アメリカン・コンパス」創設者で、政権への影響力も大きいと言われるオレン・キャスは、第二次トランプ政権の発足後、既存の貿易秩序や官僚機構の「解体」がいわゆる「旧体制」に反発し、新たな枠組みを求める人々にとって心躍る展開だったと、『ニューヨーク・タイムズ』紙へ寄稿したこの論考の中で論じている。
キャスによれば、政権の真価は崩壊した旧秩序の先にある新たな構想、すなわち米国の労働者階級の利益に資する『経済と国家機関を長期的かつ安定した軌道に乗せる』計画を実行できるかどうかにかかっている。
一方で、現政権においては、一貫した思想体系に基づくような政策が見られず、むしろ矛盾が目立つ点に対してキャスは不満を隠さない。とりわけ、米国人の賃金に直結する中国や不法移民への対応では、強硬姿勢を示しながらも、懐柔策を好む経営層への配慮が同時に見られる点を問題視している。キャスが求めるのは、米国政府による産業横断的な労働者への「投資」であり、これは従来の共和党が掲げてきた新自由主義や新保守主義とは一線を画すものである。
キャスは、ヴァンス副大統領やルビオ国務長官といった次世代の共和党政治家とも近いといわれ、この論考ではヴァンスの労働者重視の姿勢をキャスが肯定的に評価している様子が見られる。
キャス自身が描く「改革」を実現するためにはまだ道半ばであり、共和党を真に労働者の利益を代表する政党へと再構築するための強い意欲が、この論考の中でも示されている。この論考は、トランプ政権に対する批判を含めた支持の姿勢を示すものとも理解できるが、他方で潜在的には「トランプ後』の米国を見据えた、新しい設計図についてのラフスケッチともいえるのではないか。
②「[米韓首脳会談の評価]米国は現金、韓国は信頼を得たが、『荒っぽい取引』は終わっていない 」
「미국은 현금, 한국은 신뢰 챙겼지만…’거친 거래’ 안끝났다 [한·미 정상회담 평가]」、中央日報』、2025年8月28日。
2025年8月にワシントンで行われた米韓首脳会談を、韓国の外交・安保・通商分野の専門家22人が共同評価して『中央日報』紙に掲載した記事である。この論評は、米韓首脳会談について、「米国は現金(投資)を、韓国は信頼を得たが、課題は終わっていない」と総括する。李在明大統領は、「安米経中(安全保障は米国、経済は中国)」路線からの脱却を公式に宣言した。CSISでの李大統領の演説では、「もはや安米経中の立場は取れない」と述べて、米国の懸念を一定程度和らげた。しかし戦略的柔軟性や在韓米軍任務拡大など、核心的争点についての合意は文書化には至っておらず、これはあくまでも「半分の成功」だとする、慎重な評価も少なくない。さらに、3,500億ドル規模の対米投資計画においても、収益配分や基金構造をめぐる隔たりが残っている。農畜産品市場解放への米側圧力も予想されるなど、通商課題は山積している。
今回の会談で浮き彫りになったこのような米韓関係の緊密化への限界は、第2次トランプ政権が掲げる「同盟の現代化」が単なる防衛費増額の要求にとどまるものではなく、米韓同盟の構造の再編を伴う可能性を示しているとしている。韓国は、米国との信頼を深めつつ、中国との経済・安全保障の均衡を維持する複合的な外交戦略を練り、同盟再定義の主導権を確保する必要がある。今回の首脳会談は、そのような観点からも、激化する米中戦略競争と北朝鮮の核戦力高度化という複合的な安全保障環境で、韓国がどのような役割と外交的自律性を確保できるかを占う重要な分岐点となるだろう。
③「欧州はトランプに魂を売っている」
Martin Sandbu, “Europe is selling its soul to Trump,” Financial Times, August 25, 2025.
英『フィナンシャル・タイムズ』紙で、欧州経済を担当するマーティン・サンドブによる論考である。サンドブは、米国との関税合意における欧州の指導者の姿勢を、欧州政治の「トランプ化」を加速するものだと、痛烈に批判している。その理由として、より良い交渉結果を得るために真実を語らず、政治をパフォーマンス化したこと、また、成果が民主主義的な熟議と合意形成ではなく、「偉大な個人間の交渉」によってもたらされるかのような印象を与えたことを、挙げている。
サンドブの主張の特色は、単なる米EU間の関税交渉に関する評価にとどまらず、欧州の政治指導者の交渉姿勢を通じて、欧州のリベラル民主主義そのものの危機を訴えている点にある。サンドブは、トランプを宥めることに注力するあまり、説明責任をおろそかにして、トランプ流のディール優先主義、さらにはそこに内在する権威主義を受け入れてはならないと警告する。これは、トランプ政権と向き合う各国にとって、分野を超えて傾聴に値するのではないか。
④「我々はいかに欧州大陸の今後進路を変えるのか?」
Mario Draghi, “Comment changer la trajectoire de notre continent?,” Le Grand Continent, August 22, 2025.
イタリアで開催されたカトリック系国際イベント「リミニ・ミーティング」で、元欧州中央銀行(ECB)総裁であり、前イタリア首相のマリオ・ドラギが行った演説は、欧州の政策関係者やシンクタンク界で大きな反響を呼んだ。巨大市場に支えられたEUの経済的なサイズの大きさが、地政学的なパワーや国際貿易上の発言力に帰結するうという幻想は、すでに崩れ去ったドラギは論じる。その上で、市場改革や技術投資をEU共同債で賄うという、新たなアプローチが必要だと訴えた。この演説は、欧州のさまざまなメディアにおいて、重要な論考として紹介された。
この論考が注目を集める背景として、ドラギ自身が欧州金融危機を経験し、政策の当事者であったということがその要因の一つとして挙げられる。ユーロ危機の際、ECB総裁として「ユーロを守るためには何でもやる(whatever it takes)」と強い姿勢を表明し、市場との巧みな対話で信用不安を抑え込んだことは、依然として記憶に新しい。イタリアの首相退任後も影響力を持つドラギは、2024年9月に「ドラギレポート」として知られる『欧州の競争力の未来(The Future of European Competitiveness)』と題する、EUから依頼による報告書をとりまとめ、発表した。経済安全保障・脱炭素・成長戦略の三分野における欧州の地位低下への危機感が高まる中、同報告書は米国と競争力の格差の拡大を指摘し、AI活用や規制緩和、大規模投資、共同債による支援を提言している。
今回のドラギ演説も、この報告書の内容と重なる部分が多い。とりわけトランプ関税に対するEUの対応への批判的な声が広がり、大国間競争における地経学的なアクターとしてのEUの影響力の低下への不安が広がる中で、「傍観者から主体へ」、「統合の新段階へ」、そして「共通債(良い債務)へ」という三つの大きな提言がこの報告書特徴である。ドラギ演説の後に、イタリアのメローニ首相は自らの演説の中でそれへの賛意を示した。また、欧州委員会のフォンデアライエン委員長は、仏紙への寄稿で、EU域内の障壁が外国の関税以上に成長を阻害していると指摘し、ドラギ氏の主張と重なる見解を示した。
EUレベルでの共同債発行へ向けては、ドイツやオランダの強い反対が残るのも現実だ。ドラギは、「世界は我々に優しくなく、また待っていてもくれない」と、その演説を締めくくった。第二次トランプ政権がもたらすリベラルな国際秩序の揺らぎによって、欧州は統合の進化へ向けて時間的な猶予がなくなっている。もしもそのような国際環境において、欧州が主体的な行動を示せなければ、国際秩序の再編へ向けた客体へと追いやられることになるであろう。ここでとりあげたドラギ前首相の演説は、まさにそのような厳しい現実を反映した内容となっている。
⑤「弱いプレーヤーにとっての最も悪くない選択肢」
Thorsten Benner, “The least bad option for a weak player,” Agenda Pública, August 18, 2025.
ベルリンのシンクタンク、グローバル国際公共政策研究所(Global Public Policy Institute; GPPi)で所長を務めるトーステン・ベナーによる論考である。EUと米国の関税合意を「屈辱的」と評しつつ、その責任を欧州委員会にのみ帰すのは安直であると指摘する。むしろ、EU加盟各国が分裂しており、EUとしての決断力が欠けていたこと、そして、これまでEUが軍事および単一市場を十分に強化してこなかったことの当然の帰結であると、論じている。さらに、EUが米国に対してより強い姿勢で交渉に臨む余地はあったとしながらも、EUの軍事的脆弱性を踏まえ、もしトランプから数年の「庇護」が得られるのであれば、今般の交渉に伴うリスクとコストは正当化されうると述べている。
EUと米国の関税合意については、不平等性や、EU側が一方的に譲歩を迫られたことを批判する論調が多い中、ベナーは米国への軍事・安全保障上の依存という現実を冷静に受け止め、交渉の妥結を一定程度評価している。また、最後に、トランプとの交渉や合意に意識を奪われるあまり、中国というより深刻な脅威を見失ってはならないと警鐘を鳴らしており、単なる対米関税合意への評価にとどまらない示唆を提示している。
⑥「欧州の屈辱は常套手段――そこにこそ問題がある」
Nicolai von Ondarza, “Europe’s humiliation is a common strategy – and that’s the problem,” Euractiv, August 5, 2025.
2025年7月にEUと米国の通商合意が発表されると、欧州の論壇ではその合意内容をめぐり、批判的な論調が相次いだ。今回の合意は、EUにとって「戦略なき譲歩」とも評される。トランプ政権が示す行き当たりばったりな関税戦術に対し、EUが十分な結束を示せず、不利な条件を押しつけられたとの見方が広がった。元仏外相ドミニク・ド・ヴィルパンは「欧州史の屈辱」と断じ、また第一次フォンデアライエン委員会で貿易担当欧州委員を務めたセシリア・マルムストロームも「これは合意ではない」と非難した。
そうした中、ブリュッセル拠点の独立系メディア『ユーロアクティブ』に寄稿した、ドイツ国際安全保障問題研究所(SWP)EU・欧州研究部長ニコライ・フォン・オンダーツァは、批判一色の論調とは異なる見解を提示した。今年6月のNATO首脳会議で、欧州各国が「防衛費をGDP比5%に引き上げる」と発表した事例になぞらえ、彼は今回の合意を、米国への象徴的な譲歩として「見せかけの屈辱」を受け入れ、欧州安保への米国の関与の低下や、トランプ政権によるさらなる高関税発動を防ぐための戦略だったと論じている。
確かに、EUは4億5,000万人規模の市場を背景に規制力や市場力を有しているが、それが直ちに米国との交渉における実効的なレバレッジとなるわけではない。第二次世界大戦後、欧州共同体(EC、後のEU)とNATOが成立して、それぞれ経済と軍事の領域での中心的な機構として発展、拡大し、その協働が現在のヨーロッパの地域秩序の基礎となっている。2022年2月に始まるロシアによるウクライナ侵攻を経て、この分業体制はむしろ強化されたとの見方もある。第二次トランプ政権は、そのようなEUとNATOの分業体制によって創られた秩序の持続性への欧州側の不安と、自律へ向けたより強い志向性をもたらした。とはいえ、即時の転換は困難であろう。オンダーツァの論考は、米国に対する欧州の側の自律とその限界との間の揺れ動きという問題を、克明に示す内容となっている。
8月のトランプ大統領とプーチン大統領のアラスカでの首脳会談の直後に、欧州各国首脳はゼレンスキーと共にホワイトハウスを訪れた。その会談で、トランプ大統領は米国のウクライナに対する長期的な「安全の保証」への関与に言及した。これは、欧州にとって外交的成果とみなすこともできる。オンダーツァの論考を踏まえれば、象徴的な譲歩としての通商合意は、欧州のウクライナ戦争対応に交渉材料をもたらし、ウクライナに新たなカードを与えたとも解釈し得る。トランプ関税への対応とは、単なる貿易問題にとどまるものではなく、安全保障秩序全体の文脈からも考慮する必要があることは、重要な視座であろう。
-
 India and EU Sign Mother of All Deals2026.02.06
India and EU Sign Mother of All Deals2026.02.06 -
 Orbán in the Public Eye: Anti-Ukraine Argument for Delegitimising Brussels2026.02.04
Orbán in the Public Eye: Anti-Ukraine Argument for Delegitimising Brussels2026.02.04 -
 Trump, Takaichi and Japan’s Strategic Crossroads2026.02.03
Trump, Takaichi and Japan’s Strategic Crossroads2026.02.03 -
 Analysis: When Is a Tariff Threat Not a Tariff Threat?2026.01.29
Analysis: When Is a Tariff Threat Not a Tariff Threat?2026.01.29 -
 Takaichi’s Strengths and the Need for ‘Strategic Signaling’2026.01.23
Takaichi’s Strengths and the Need for ‘Strategic Signaling’2026.01.23
 Oil, Debt, and Dollars: The Geoeconomics of Venezuela2026.01.07
Oil, Debt, and Dollars: The Geoeconomics of Venezuela2026.01.07 It’s Now or Never: India’s Ambitious Reform Push2026.01.09
It’s Now or Never: India’s Ambitious Reform Push2026.01.09 Analysis: When Is a Tariff Threat Not a Tariff Threat?2026.01.29
Analysis: When Is a Tariff Threat Not a Tariff Threat?2026.01.29 Navigating Uncertainty in U.S. Space Policy: Decoding Elon Musk’s Influence2025.04.09
Navigating Uncertainty in U.S. Space Policy: Decoding Elon Musk’s Influence2025.04.09 Orbán in the Public Eye: Anti-Ukraine Argument for Delegitimising Brussels2026.02.04
Orbán in the Public Eye: Anti-Ukraine Argument for Delegitimising Brussels2026.02.04












