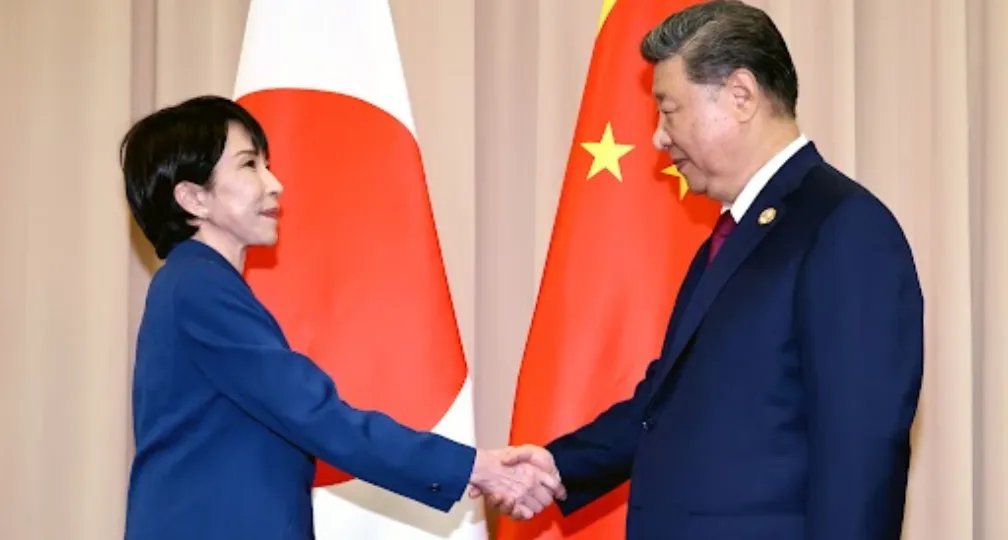非戦略核の軍事的合理性を再考する――石破総理「ハドソン論文」に見える核抑止論の検証

石破論考で示された核共有は、戦略的評価という根本部分でも疑問符がつく。中国が米国との関係で戦略的安定を確立した場合、最も危険なのは通常戦力以下のレベルにおける冒険的行動だ。最優先すべきは米核戦力の拡充・多様化ではなく、日本の反撃能力を、核戦力の次元も想定しながら、米国の通常打撃力や核戦力と「統合的な」形で行使するために核協議を充実させることだと言えるだろう。
(本稿は、新潮社フォーサイトからの転載です。)
かつて日本には、米軍の核兵器が配備されていた。正確には、日本への返還前の沖縄に、である。1954~55年の第一次台湾海峡危機及び1958年の第二次危機を受けて中台の軍事的緊張が高まると、同盟国中華民国(台湾)への攻撃を抑止するため、米空軍は核を搭載したメースB戦術地対地巡航ミサイルを1961年から沖縄に配備した。良く知られるように沖縄返還交渉においては、この沖縄配備核兵器の取扱いが大きな論点となり、いわゆる「密約」の問題を孕みつつも佐藤栄作総理が「核抜き・本土並み」を決断し、1972年にこれが実現した。
一方、あまり知られていないのが、「核抜き」でも軍事合理的に問題ないと考える専門家の影響力である。冷戦期の防衛政策に大きな影響を及ぼした内務・防衛官僚だった海原治は、国防会議事務局長を務めていたおそらく1967年頃、幹事長等を歴任した自民党の田中角栄を訪問した際、沖縄の核付き返還の是非を問われた。そこで海原は、「別に核は要らない」、「メースA、Bとありますが、古い方です。こんなものは役に立たないし、ポラリス潜水艦もできたことだし、沖縄に核は要らない」と応じた[1]。沖縄に配備された核は兵器として時代遅れであり、また核弾頭搭載の潜水艦発射弾道ミサイル(SLBM)である「ポラリス」も運用されているのだから、不要だとしたのである。
また、佐藤総理の諮問機関として若泉敬、高坂正堯ら民間有識者を集めて設置された「沖縄問題等懇談会」分科会の「沖縄基地問題研究会」も、佐藤の「核抜き」方針表明に影響を与えたとされる。1969年に同研究会は報告書を提出したが、そこで沖縄への核配備の重要性の低下を指摘したのである[2]。この結論を下支えしたのが、研究会を構成する有識者のほか、同研究会が開催した「沖縄及びアジアに関する日米京都会議」に出席した米国の核専門家であった。そこで米国核戦略の基礎を築いたアルバート・ウォルステッターは、脅威に対する核戦略上の近接基地の役割低下と東アジアにおける核アセットの必要以上の重複を理由として、返還後の沖縄米軍基地に対する、本土と同様の安保条約に基づく事前協議制の適用を主張した[3]。「核抜き」沖縄返還の背景にこうした戦略論の観点からの下支えがあったことが、その実現を確かなものとしたと言える。
こうして考えると、核抑止の議論には軍事的有効性(military effectiveness)の裏付けが不可欠であることが分かる。しかし核抑止論は、核兵器も兵器である以上、戦場において軍事的効果を発揮するために用いられるという前提をしばしば忘れてしまう。石破茂総理が総理大臣選出直前に米国ハドソン研究所ウェブサイトに寄稿した、アジア地域での核共有や米国の核の展開を主張した論文も、その一つの例である。
そこで本稿では、核兵器、中でも特に戦場等での使用が想定され得る非戦略核・低出力核の軍事的有効性について改めて考えてみたい。
石破論考の核抑止論を軍事効果から検証する
石破論考で提言された内容のうち、国内外から最も多くの批判を招いたのがアジア版NATO創設であった。そして、これと並んで重要なのが、「アジア版NATO」によって目指すという、核共有や核持ち込みによる核抑止力強化をめぐる部分である。
NATO(北大西洋条約機構)における核共有をそのまま「アジア版NATO」に移植する議論の粗さはさておき、石破論考の核抑止論で特に問題となるのが以下のくだりだろう。石破論考によると、「最近では、ロシアと北朝鮮は軍事同盟を結び、ロシアから北朝鮮への核技術の移転が進んでいる。北朝鮮は核・ミサイル能力を強化し、これに中国の戦略核が加われば米国の当該地域への拡大抑止は機能しなくなっている」とされる。
就任前とはいえ現職となる日本の総理大臣が米国の拡大抑止に疑問を呈したまま、何らの政策的手当ても施されない状態はあまり健全とは言えない。米国の拡大抑止への疑念の背景にある論理は石破氏自身が明確に示すべきであり、この不明瞭な一文はその役割を果たしているとは言えない。
だが、その上で、あえて石破氏の論理を探れば、次の二通りが考えられる。
▼第一の解釈は、核開発を進める北朝鮮に核保有国であるロシアが援助を行うとともに、中国が戦略核のレベルで米国を抑止すれば、非戦略核以下のレベルにおける北朝鮮の軍事行動を抑止することができない、という主張である。いわば中朝、ロ朝の二つの同盟による抑止力がもたらす「安定・不安定パラドクス」(戦略核レベルでの安定性がそれ以下のレベルでのエスカレーションを招くという逆説)とでも言うべきものだろう。
▼第二の解釈は、よりシンプルに、北朝鮮と中国が核戦力を強化することにより、それぞれとの間で安定・不安定パラドクスが生じるという主張であろう。
これらに対処するための手段が、おそらく非戦略核を念頭に置いた地域への米核戦力の導入ということになる。
石破氏がどちらの立場をとっているのかは判然としないが、いずれの論理にも問題がある。
▼第一に、北朝鮮が非脆弱な戦略核戦力を構築していない以上、戦略核のレベルにおいて米国の北朝鮮を対象とした拡大抑止が機能していないというのは言い過ぎだろう。
▼第二に、北朝鮮が戦略核レベルの対米抑止を「核同盟」に依存し、非戦略核や通常戦力レベルにおいて韓国や日本への冒険的行動に打って出るとの前提は、思考実験としては面白いが必ずしも強い説得力は持たない。特に、自らが達成していない戦略抑止力を同盟国に依存せざるを得ない構造の中で、戦略レベルにエスカレートする可能性のある非戦略核の投入に打って出るほどの楽観的な戦略観を金正恩が有しているとは思えない(そうであるがゆえに、北朝鮮はICBM=大陸間弾道ミサイル=の開発・能力向上に注力しているのだろう)。
▼第三に、中国単体との関係における安定・不安定パラドクス対処についても、非戦略核の強化が最も優先させるべき課題だとの主張は疑わしい。確かに米国防省の見積りどおり、中国が核弾頭を1000発以上にまで増加させるとともに、ICBMの多弾頭化(DF-41等)やサイロ化、米本土まで到達し得るSLBM(JL-3)の運用を進めれば、将来米国との間で戦略的な安定性を獲得する可能性はある[4]。そして、それが非戦略レベルでの中国の冒険的行動を促進するかもしれない。しかし、かかる冒険的行動が通常戦力レベルで頻発し得ても、非戦略核のレベルで起こる可能性が高いとまでは言えない[5]。中国が日米などに対して通常戦力において深刻な劣勢にあるわけではないからだ。
冷戦期、米国アイゼンハワー政権の下で採用された大量報復戦略により、東側の大規模通常戦力を抑止するため欧州に大量の戦術核が導入された。そこではNATO側の通常戦力における劣勢を補完するため、敵地上兵力に対する戦術核の投射が想定されていた。
一方、現在の西太平洋地域において、単純な量的比較では、中国が日本や前方展開する米軍を凌駕する兵力を有している[6]。また、地続きの欧州とは異なり海上・航空領域が主体となるインド太平洋正面においては、分散する地上兵力を面制圧するために核を使用するといった誘因が小さい。海上・航空領域では、基本的に戦闘は艦艇、航空機といったプラットフォームを中心に行われるが、陸上と異なりそれらを無数に分散して運用することはできないからである。
したがって、敵の艦艇、航空機を撃破するためには通常弾頭を搭載した精密誘導火力を用いれば足りるのであり、非戦略核の方がより高い軍事効果を得られるような戦闘様相は、あまり考えられない(これは日米側にとっても同様だろう)。
例外の一つは、艦艇、航空機が港湾や基地に所在する場合に、これらを一網打尽にすることだろう。しかしこの方法は、緒戦で奇襲的に非戦略核を用いる場合には使えても、徐々にエスカレーションラダーを上げる中で用いる場合には、艦艇、航空機が機動・分散展開している可能性を踏まえると現実的な有用性に疑問が生じる。
もう一つの例外は、海上・航空戦闘において多数の無人機が投入される場合である。米海軍は、分散型海洋作戦(DMO)構想により、無人水上艇(USV)・水中艇(UUV)と有人艦艇を組み合わせて大規模艦隊を分散的に運用する戦い方の導入に注力している。仮に将来このような態勢が構築されれば、海上作戦が地上作戦に類似した戦い方、すなわち広範囲にプラットフォームが分散した戦い方となる可能性があり、これを無力化するため非戦略核の有用性が向上するかもしれない。ただし、将来の戦い方に備える必要性は論を俟たないものの、これが喫緊の課題であるとまでは言えないだろう。
▼第四に、中国の非戦略核戦力の運用は、通常戦力と統合されていない。確かに米国防省の中国軍事力報告書は、中国の戦略家の議論を紹介しつつ、中国が低出力核に一定の役割を見出していることを指摘する[7]。しかしそこで論じられているのは、紛争抑止あるいは米国の非戦略核に対する均衡的手段としての保持であり、使用する場合の具体的用途が明確化されていないことに注意を払う必要がある。そのためなのか、2016年に発足した中国の5大統合戦区は、DF-21やDF-26といったロケット軍所属の長射程ミサイル部隊への戦時指揮権は有しておらず、それらを含め、核戦力部隊への指揮権は中央軍事委員会に留保されている[8]。このことを踏まえれば、中国は非戦略核(米本土に到達しない射程の核)であっても、専ら地域における戦略目標への用途を考えており、戦場での使用を念頭に置いた体制は現時点においてとれていないと捉えるのが穏当だと思われる。
これらの問題を踏まえると、中国が米国との関係で戦略的安定を確立した場合、最も危険なのは通常戦力以下のレベルにおける冒険的行動であろう。だからこそ、その可能性に備える意味でも、日本は通常戦力を強化しなければならない。実際に使用された場合の有効性を考えない核抑止論は、資源投下の優先順位を誤る危険を孕んでいる。
非戦略核のプラットフォームにおける問題も見過ごせない
石破論考に言うような「核共有」を米国が実際に認めるか否かはさておき、次にそれをどのような手段で実現するかも問題となる。この点を分かりやすく整理した論考も既にあるので詳細は省くが、最も大きな問題は、現在米国の事実上の非戦略核(低出力核)オプションが、①核・通常両用航空機(DCA)で運用するB-61核爆弾(100個)、②SLBMに搭載する低出力核W76-2(25個)、③戦略爆撃機B-52Hに搭載する空中発射型巡航ミサイル(ALCM)(500個)という3つに限られるという点である[9]。このうち、②及び③は遠距離からの投射が可能であるため日本への配備や共有は必要なく、①では中国の密度の濃い対空脅威を突破できるか疑問が残る。このような状況を踏まえれば、現時点で核共有や日本への持ち込みを行う米国側のインセンティブはなく、日本側にそれを求める軍事的根拠も弱い。
一方、これらよりはまだ地域への展開に軍事的効果が見込めるものとして、トランプ政権が着手し、バイデン政権が中止した海上発射型核巡航ミサイル(SLCM-N)(スリコム・エヌと読む)がある。
SLCM-Nは、1980年代に配備が開始され、1991年にジョージ・H・W・ブッシュ大統領により運用から外され、2010年にバラク・オバマ大統領によって廃止が決定された核トマホーク(TLAM-N)の機能を継承するものであるが、他の手段との機能重複、資源配分における優先順位上の問題などにより、バイデン政権が開発を中止していた。しかし米議会は開発予算を計上し続け、政府に開発を義務付けている。2024年4月、ウィリアム・ラプランテ取得担当国防次官は、海軍にプログラム・オフィスを立ち上げ、兵器としての有効性の分析に着手することを指示したと明らかにしている[10]。バイデン政権がSLCM-Nの開発に少なくとも前向きではないことは明らかだが、その開発動向は今後の米政権交代にも左右されることとなり確定的なことは言えない状況にある。
このSLCM-Nの導入による核オプションの充実化に対して、米国の専門家や日本の専門家の中では肯定的な受け止めが見られる。また、日本政府の元高官の中にも、SLCM-Nを搭載した攻撃型原潜の日本への一時寄港(そして、おそらく理想的には日本との共同運用)を求める意見もある。
しかし、そのような見方には一定の留保が必要である。SLCM-Nの共有が現実的に難しいことはその提唱者も認めるとおりである。しかし、より本質的に重要なのはSLCM-Nがおそらくコスト・ベネフィット比較のボーダーライン上に位置する能力であることだろう。
LCM-Nの推進者は、W76-2の数量やそれを搭載し得る戦略原潜(SSBN)の数に限りがあり[11]、また戦略爆撃機も一定の脆弱性や滞空時間に制約があることを踏まえ、SLCM-Nがより柔軟なオプション(数的な充実、前方展開によるプレゼンス)を提供することを期待している[12]。ただ、これについては見過ごしてはならない論点が少なくとも2つある。
▼一点目は、インド太平洋正面において非戦略核はどのような使用を想定されているのかという点である。
先に述べたとおり、中国側には、通常戦力を補完することにより戦場で優位に立つという軍事的効果を求めてあえて非戦略核を用いるインセンティブが乏しいと考えられる。また核戦力が中央軍事委員会の排他的な指揮下にあることも併せれば、その目的は米軍の拠点や(残念ながら)日本、台湾の政治中枢、産業基盤といった地域における戦略目標となる可能性が高い。実際、例えばDF-26用の核弾頭は200~300kt(広島型は16kt)と、小型・低出力とは言えないレベルの威力を持つとされる[13]。このため、中国の非戦略核は、戦場における戦術的な使用よりも、核恫喝やエスカレーションのための手段として用いられる可能性が高い。
そうだとすれば、これに対抗するための均衡的な抑止手段として米国の低出力核や戦略核オプションを揃えておく必要がある一方で、必ずしも非戦略核(低出力核)のレベルでその数的規模を充実させることまでは要しないかもしれない。すなわち、中国の核恫喝を抑止するための低出力核には、通常戦力から戦略核戦力まで、エスカレーションを無理なく導くための梯子としての政治的役割が求められているのではないか。そうであれば、現在米国が保有しているSLBMやALCM搭載の低出力核で、手段として不足だとは言い切れない。
一方、北朝鮮の非戦略核は、中国と異なり韓国の主要軍事基地に向けた対兵力の用途が想定されている可能性が高い。しかし同時に、戦略核の脆弱性が解消されていない段階での非戦略核の本格的使用の可能性には疑問が残る。したがって、米国が中間的なエスカレーション手段(低出力核)を保持すること自体の重要性は明らかだが、米国や同盟国にとってその拡充よりも優先すべきは、むしろ戦略抑止力の強化(戦略核の維持、北朝鮮の戦略核を無力化し得る通常精密打撃力の強化、ミサイル防衛等の損害限定策の強化)だと思われる。
▼第二に、SLCM-Nの導入は確かに低出力核のオプションを多様化・充実化させるかもしれないが、他の次元における能力への制約を伴う。それは投下できる開発予算・人的資源にとどまらず、有事における運用プラットフォームの制約として表れ得る。
SLCM-Nの搭載プラットフォームとして考えられるのは、水上艦 のほか、バージニア級攻撃原潜(SSN)と改オハイオ級巡航ミサイル原潜(SSGN)であろう。ここで問題となるのが、米国の攻撃原潜は、中国に対する非対称的能力の中核を成す「王冠の宝石(crown jewel)」と位置付けられ、対潜水艦戦(ASW)から対地攻撃、対艦攻撃に至るまで、多様な任務を負っている点である。特に、インド太平洋正面においては、南シナ海で活動する中国の戦略原潜への対応による戦略抑止力の強化と、台湾有事で活動し得る中国の空母打撃群等水上艦部隊への攻撃能力としての価値が極めて高い。
したがって、攻撃原潜1隻に複数の任務が割り当てられる可能性は否定できないとはいえ、これに核任務が付与された場合、任務遂行の現実的なトレードオフは確実に発生すると考えられる。通常戦力と戦略核戦力のレベルにおける能力を制約して得られるベネフィットが、上記で述べたとおり主要なものとは言えない場合、その開発への支持が浸透しないことに不思議はない。SLCM-Nを巡る米国の判断のぶれは、政権交代に伴う党派性というよりは、その能力に関する戦略上の評価のぶれによるところが大きいのだろう。
振り返れば、退役したTLAM-Nも、その起源を辿ると元々は対艦ミサイルとして開発が始まった1970年代前半は海軍内の広範な支持を得ていたわけではなかった。対艦ミサイルは、特に海軍航空兵科からは艦載機の運用と競合するものとして敬遠されていた 。このため、改革志向の海軍将官・士官と第一次戦略兵器制限交渉(SALT I)対象外の巡航ミサイルによる核戦力の拡充を求めた国防省文民指導部・議会の主導があって初めて、開発・継続が可能となった。
文民指導部と議会はTLAM-Nに対し、戦略核により確立された安定性を向上させるという、効率的な予備的核戦力としての役割を期待した。他方で海軍指導部は、TLAM-Nの派生型として開発される通常弾頭搭載の対艦攻撃バージョン(TASM)を重視した。両者の利益が一致した結果、その連携によって開発が続けられ、海軍内で配備が受け入れられていったのである。
言い換えれば、海軍がTASMという派生型とのパッケージなしにTLAM-Nの開発を進めたかは疑わしい。本稿前編で触れたウォルステッターは、トマホークの通常弾頭搭載型対地攻撃バージョン(TLAM-C)を提案し、これを海軍が受け入れて速やかな開発プロセスが実現したが、これと比べてTLAM-N開発に係る意思決定過程の複雑さは際立っている。
仮に今後SLCM-Nを本格的な開発段階に乗せるのであれば、この経緯と同様に、既存の核あるいはプラットフォームの通常任務との関係性を精緻に整理することや、文民指導部や軍種内での広範な合意の取付けが鍵となる。特に、軍種内でのボトムアップの推進なしには難しい。現在の米国政府における定まらない方向性は、そのような合意と勢いの不足を物語っているのかもしれない。
日本がとるべき拡大抑止強化策とは
以上を踏まえると、インド太平洋正面の脅威に対応するに当たって、今ある米核戦力のハードウェアを拡充・多様化していく緊要性はそれほど高いものではないと考えられる。もちろん不断の近代化は必要であるし、極超音速滑空弾(HGV)への迎撃能力など、損害限定の取り組みも怠ってはいけない。しかし日本にとって、核戦力の強化よりむしろ重要なのは、ソフト面の充実、とりわけ核協議の内容充実だと考えられる。
日米拡大抑止協議(EDD)は、近年防衛大臣級会合を開催するなど、その政治的重要性が増している。そこでは両国の脅威認識のすり合わせや、米国の拡大抑止コミットメントの確認、部隊視察や机上演習等を通じた米国の核戦力への専門的理解の促進などが行われている。
これらの項目の重要性は自明だが、さらに特筆すべき内容も公表されている。それは、通常戦力との関係性を組み込んだ議論である。例えば、2024年6月の拡大抑止協議では、「日米共同の統合的な(integrated)抑止力を強化する方途を追求」したとされる。また同年7月の閣僚会合で発表された共同発表では、「同盟における核及び非核の軍事的事項の間の関係性について緊密に協議する両国のコミットメントを再確認した」とされている。協議の詳細は非公表だが、これらの文言が示唆するのは、米国の核戦力がもたらす核抑止のみならず、両国の通常戦力が核抑止や潜在敵の核戦略にどのような影響を与えるのかについても議論がなされている可能性である。
核戦力と通常戦力の強い関連性を踏まえれば、これは当然かつ重要な取り組みである。そもそも核ミサイルを迎撃するミサイル防衛は、通常戦力により損害限定を行い、核戦力バランスに重大な影響を及ぼす典型例である。そして、それだけではなく、日本が戦略三文書に基づき反撃能力を構築することで、通常打撃力を通じて相手の核戦力に影響を及ぼす経路も想定し得る。
例えば中国の中距離弾道ミサイルDF-26は通常・核両用とされているが、通常弾頭のDF-26が日本に飛来し、更なる攻撃を防ぐために日本がその発射機か、それが難しいとしても関連施設に対する反撃を行う場合を仮定したとする。中国側にとってDF-26は貴重な非戦略核手段であるため、その損耗は中国の核エスカレーション・シナリオに影響を与える。そうだとすれば、日本の反撃能力は、核戦力の次元を想定しながら、米国の通常打撃力や核戦力と「統合的な」形で行使されなければ軍事的な迫力(すなわち抑止の説得性)に乏しいものとなってしまう。拡大抑止協議における「日米共同の統合的な抑止力」強化への言及は、そのような認識を踏まえ、日米の防衛力が通常戦力の低次元から高次元へ、そして核戦力も低次元から高次元へと隙間なく構築されるべきことについての、政治レベルの一致を反映するものである。
拡大抑止の強化に当たって、非核国が核を保有する同盟国に核戦力の強化を一方的に頼み込む構造は、あまり健全なものとは言えない。非核国の取り組みが同盟の統合的な抑止力の強化に貢献して初めて、拡大抑止を提供するというコミットメントも信頼性をもって期待できるというものである。非戦略核の域内展開よりも優先されるべきは、まさにこのような取り組みであろう。
核兵器は使われないことに意義がある抑止の兵器、平時の兵器である。しかし有事において実際に使われたときの軍事的効果を考えない核態勢は、抑止の信頼性を低下させる。そしてその軍事的効果を検証するに当たって、通常戦力との関係性を踏まえることは極めて重要である。通常戦力による投射なしに、核兵器を軍事的に用いることはできないからだ。そこに日本を含む非核国の果たす役割がある。拡大抑止は、核・通常戦力を統合した視点なしには議論できない。
(Photo Credit: Roger-Viollet/アフロ)
注
- [1] 『C.O.Eオーラル・政策研究プロジェクト海原治オーラルヒストリー(下巻)』政策研究大学院大学、2001年、187頁。
- [2] 沖縄基地問題研究会「沖縄基地問題研究会報告」1969年3月8日、ジャパンデジタルアーカイブズセンター『オンライン版楠田實資料』https://j-dac.jp/KUSUDA/index.html。
- [3] 日米京都会議実行委員会「日米京都会議報告書資料開会挨拶・問題提起・議長報告」1969年1月31日『楠田實資料』;小伊藤優子「佐藤政権期における基地対策の体系化:ふたつの有識者研究会の考察を中心に」河野康子及び渡邉昭夫編『安全保障政策と戦後日本1972~1994:記憶と記録の中の日米安保』千倉書房、2016年、47-74頁。
- [4] 神保謙「中国:「最小限抑止」から「確証報復」への転換」秋山信将及び高橋杉雄編『「核の忘却」の終わり:核兵器復権の時代』勁草書房、2019年、第3章。
- [5] 後瀉桂太郎「欧州とアジアにおける「核の閾値」―非戦略核をめぐる思考実験」岩間陽子編『核共有の現実:NATOの経験と日本』信山社、2023年、199頁。
- [6] もっとも、米軍の兵力は西太平洋の前方展開兵力だけではなく、ハワイ、本土西海岸など米国内の増援兵力も踏まえて評価することが必要である。いずれにせよ、少なくとも中国は自らの通常戦力が大幅に劣勢にあるとまでは考えていないだろう。
- [7] Office of the Secretary of Defense (OSD), US Department of Defense, “Military and Security Developments Involving the People’s Republic of China (CMPR) 2023” (October 2023), 111-112.
- [8] 杉浦康之『中国安全保障レポート2022:統合作戦能力の深化を目指す中国人民解放軍』防衛研究所、2021年、47、54頁;Wu Riqiang, “Assessing China-U.S. Inadvertent Nuclear Escalation”, International Security 46, no. 3 (Winter 2021/22), 155.
- [9] SIPRI年鑑2024年版による。
- [10] Anya L. Fink, “Nuclear-Armed Sea-Launched Cruise Missile (SLCM-N)”, In Focus (Congressional Research Service, October 2024), https://crsreports.congress.gov/product/pdf/IF/IF12084.
- [11] SIPRIによれば、低出力核任務を付与された戦略原潜は、平時は大西洋と太平洋とでそれぞれ1隻ずつ割り当てられているとされている。
- [12] Fink, “Nuclear-Armed Sea-Launched Cruise Missile (SLCM-N)”.
- [13] SIPRI年鑑2024年度版による。
- [14] 脆弱性があり、通常戦力との混同が生じるためあまり良いオプションとは言えない。
- [15] Bradd C. Hayes and Douglas V. Smith, eds., The Politics of Naval Innovation (Newport: US Naval War College, 1994), 16–42, https://apps.dtic.mil/sti/tr/pdf/ADA288792.pdf; Thomas G. Mahnken, Technology and the American Way of War Since 1945 (New York: Columbia University Press, 2008), 138–42; Kenneth P. Werrell, The Evolution of the Cruise Missile (Maxwell Air Force Base, Alabama: Air University Press, 1985), 150–55.
- [16] SIPRI年鑑2024年度版による。


Senior Research Fellow
Hirohito Ogi is a senior research fellow at the Institute of Geoeconomics (IOG) studying military strategy and Japan’s defense policy. Before joining the IOG, Mr. Ogi had been a career government official at the Ministry of Defense (MOD) and Ministry of Foreign Affairs (MOFA) for 16 years. From 2021 to 2022, he served as the Principal Deputy Director for the Strategic Intelligence Analysis Office, the Defense Intelligence Division at the MOD, where he led the MOD’s defense intelligence. From 2019 to 2021, he served as a Deputy Director of the Defense Planning and Programming Division at the MOD. He holds a Master’s degree in international affairs from the School of International and Public Affairs (SIPA), Columbia University, and a Bachelor’s degree in arts and sciences from the University of Tokyo. He is the author of various publications including Comparative Study of Defense Industries: Autonomy, Priority, and Sustainability (co-authored, Institute of Geoeconomics, 2023).
View Profile-
 Japan’s Sea Lanes and U.S. LNG: Towards Diversification and Stabilization of the Maritime Transportation Routes2026.02.24
Japan’s Sea Lanes and U.S. LNG: Towards Diversification and Stabilization of the Maritime Transportation Routes2026.02.24 -
 Fed-Treasury Coordination as Economic Security Policy2026.02.13
Fed-Treasury Coordination as Economic Security Policy2026.02.13 -
 What Takaichi’s Snap Election Landslide Means for Japan’s Defense and Fiscal Policy2026.02.13
What Takaichi’s Snap Election Landslide Means for Japan’s Defense and Fiscal Policy2026.02.13 -
 Challenges for Japan During the U.S.-China ‘Truce’2026.02.12
Challenges for Japan During the U.S.-China ‘Truce’2026.02.12 -
 India and EU Sign Mother of All Deals2026.02.09
India and EU Sign Mother of All Deals2026.02.09
 Orbán in the Public Eye: Anti-Ukraine Argument for Delegitimising Brussels2026.02.04
Orbán in the Public Eye: Anti-Ukraine Argument for Delegitimising Brussels2026.02.04 Fed-Treasury Coordination as Economic Security Policy2026.02.13
Fed-Treasury Coordination as Economic Security Policy2026.02.13 When Is a Tariff Threat Not a Tariff Threat?2026.01.29
When Is a Tariff Threat Not a Tariff Threat?2026.01.29 Oil, Debt, and Dollars: The Geoeconomics of Venezuela2026.01.07
Oil, Debt, and Dollars: The Geoeconomics of Venezuela2026.01.07 India and EU Sign Mother of All Deals2026.02.09
India and EU Sign Mother of All Deals2026.02.09