世界はトランプ政権をどう見るか No.7
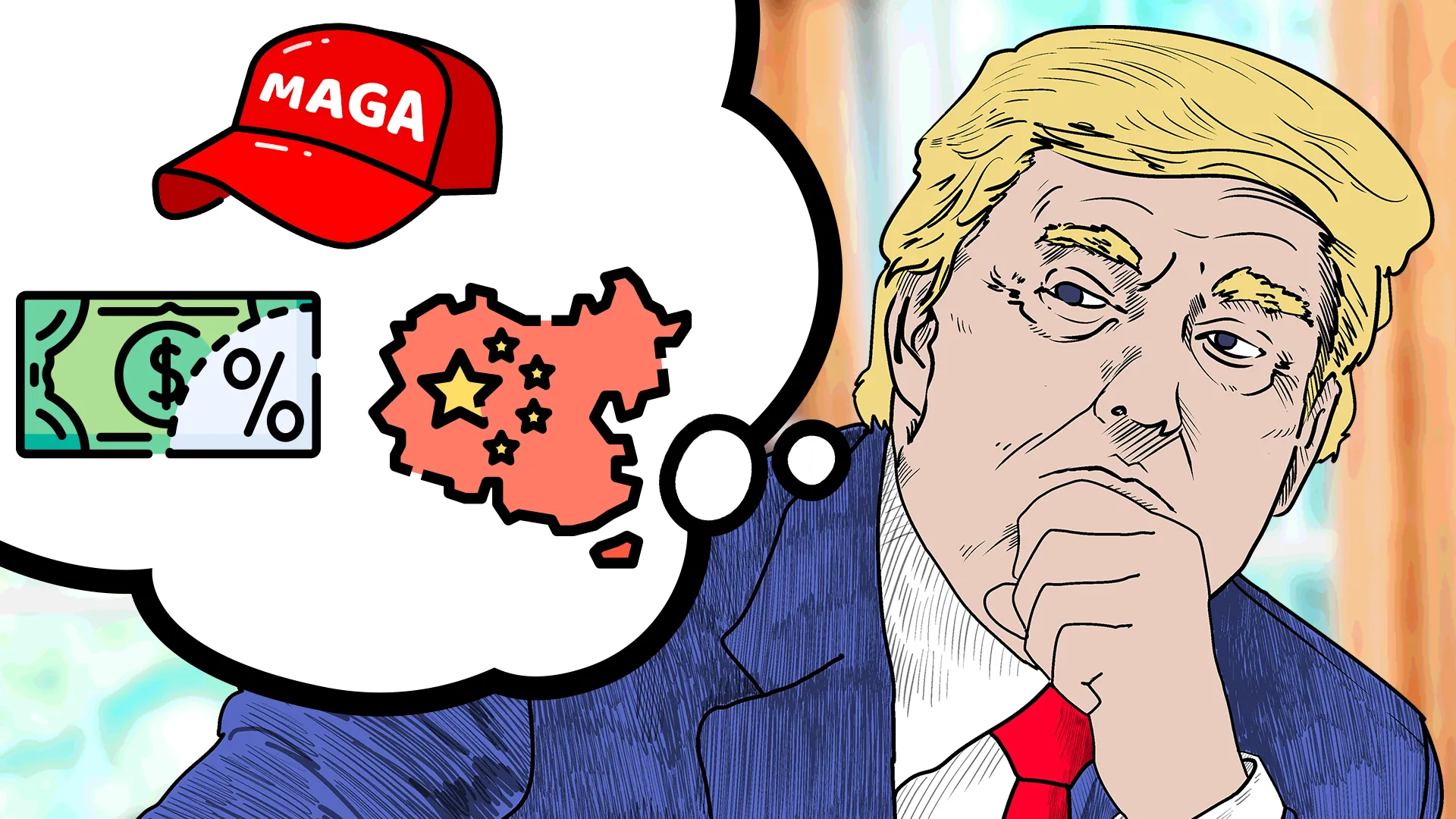
世界はトランプ政権をどう見るか(主要論考の紹介)

特集「2025年 トランプ政権は世界をどう変えるか」
トランプ第二次政権の動向がグローバル経済や国際秩序にどのような変化をもたらすのか、そして他国はどのように対応するのかが注目されます。本特集では、2025年のトランプ政権の政策動向とその影響を分析し、国際社会に与えるインパクトについて考察します。
①「大手製薬会社は関税を武器にEUを揺さぶっている」
Nick Dearden (Global Justice Now) and Peter Maybarduk (Public Citizen), “Big Pharma is using tariffs to hold Europe to ransom,” Politico Europe, May 15, 2025.
NGOに所属する2人の専門家によって米国ニュースメディア「ポリティコ」欧州版に寄稿された記事である。トランプ大統領が最近関心を寄せて、発言をくり返している医薬品価格に関する問題を扱っている。2人の著者によれば、トランプ政権が発表した薬品価格を引き下げるための大統領令を受けて、製薬会社は、大きな利益を得てきたこれまでの制度を維持しさらに強化するためにも、欧州連合(EU)に対して治験規制の緩和や知的財産保護の強化を求めている。このような動きに対し著者たちは、EUはむしろ社会全体の利益を守るための政策を実施すべきだと提案している。
米欧間の製薬貿易統計を見ると、米国とEUは互いにとって最も重要な貿易パートナーである。EUの対米輸出額は1,190億ユーロを超え、輸入額は460億ユーロにのぼる。これらの統計は、かつては米欧間の強固な貿易関係を象徴するものだったが、第二次トランプ政権ではむしろ米国が外国から搾取されているという主張の根拠として利用されている。
国際的な貿易摩擦が続く中、EUの製薬会社は米国政府からの圧力に対してますます弱い立場になっているようだ。だとすれば、サプライチェーンの見直しや、薬品市場のこれまでの制度を改革すべき段階にきているともいえる。この記事が明らかにしているように、鉄鋼や自動車産業の分野に限らず、製薬分野においてもまた国際貿易の将来がよりいっそう不透明になっているといえるだろう。
②「中東各界がみるトランプの中東政策」
新華社特稿「中东各界眼中的特朗普中东政策」『新華社』、2025年5月2日。
これは、中国国営新華社が発表した「特稿」と冠された論考である。「特稿」とは、特定のテーマに絞り深く論じる論考であり、その意味において注目に値する内容となっている。この論考では、中東各国の専門家やメディアがトランプ政権の中東政策をいかに見ているのかを引用しまとめて紹介している。他方で、新華社が編纂し掲載している以上、そこで描かれている見解は中国自身のそれと大きく乖離するものではないことを認識する必要がある。
この論考が論じるには、第二次トランプ政権の発足以降、中東各国の識者の目に映るアメリカの中東政策の姿は惨憺たるものであった。ここでは、それを論じる上でパレスチナやイスラエルの専門家の発言や、カタールのアルジャジーラの報道など参照する。この論考の中で、トランプのことを「命を軽視する放火魔」、「ルールを無視するいじめっ子」であると、かなり批判的に描写している。
イスラエル・ガザ問題に関して、トランプのたった一つの関心事は自身の功績のみであり、和平には興味がないと、ここでは論じられている。そして、アメリカ政府が現在、イランに対して制裁をちらつかせ脅し、さらにはスエズ運河の無償通航を認めるようエジプトに迫っていることなどを紹介し、パレスチナやイスラエル、エジプト、サウジアラビアやカタールの専門家や政治家の発言を引用している。その上で、アメリカが現在、中東からの信頼を完全に失ったという分析も示している。
この論考からは、中国がサウジアラビアとイランの国交回復において重要な役割を果たしていることを紹介し、よりいっそう「ポジティブな」存在感を示す中国と、よりいっそう信頼を失う米国という対比した構造を提示する、中国側の認識を見て取ることができるだろう。
③「『アメリカのソフトパワーは蒸発しつつある』――アメリカのソフトパワー衰退と覇権の没落」
新華社論評(「国際観察」)「“美国软实力正在蒸发”——美国的软实力衰退与霸权走向没落」『新華網』、2025年4月29日。
これは、中国国営新華社が発表した「国際観察」と冠された社説である。「国際観察」とは国際関係に関する重要な論考であることを示す用語であり、この社説も注目に値するものといえる。欧米を含む各国メディアの記事を参照し、トランプ政権が関税を武器として振りかざし、米国内政はもとより世界を混乱に陥れていることが論じられている。それゆえ米国は急速にソフトパワーを失い、そして覇権も失っているのだと、この社説では評している。
米国がソフトパワーを失っているという批判の裏には、経済・軍事のみならず文化的な側面においても、中国がいまや「強国」となりつつある自国への自信を垣間見ることができよう。事実、2025年2月、『人民日報』が報じたように英国のコンサルティング会社が世界100か国を対象に行った調査をもとに発表する「世界ソフトパワー指数2025」において、中国は初めて英国を抜き世界第2位(1位は米国)に躍り出た。そのようなことからも、トランプ政権の下で没落しつつある米国と、「躍進」する中国を対比するという構図を提示したい中国の認識が透けて見える。
④「欧州はその偉大さを失う可能性がある」
Anu Bradford, R. Daniel Kelemen, and Tommaso Pavone, “Europe Could Lose What Makes It Great,” Foreign Affairs,, April 21, 2025
EUは、単一市場を基盤とする高い水準の規制を通じて、域外にも影響力を及ぼしてきた。このような、いわゆる「ブリュッセル効果(Brussels Effect)」と呼ばれる現象は、EUの国際的な強みとして日本でも注目されている。「ブリュッセル効果」の提唱者であるアニュ・ブラッドフォード米コロンビア大学教授は、『フォーリン・アフェアーズ』誌への寄稿で、EUの規制力は市民の権利保護という規範的価値に根差しており、地経学的課題が顕在化する今こそ、それを国際的影響力の源泉として維持・活用すべきだと論じている。
しかし、米国トランプ政権は、EUの環境・デジタル規制が米国企業に過度な負担を課しているとし、それを「不当な貿易障壁」として批判を強めている。他方で、このようなトランプ政権の主張は欧州域内において、欧州委員会による規制強化こそが欧州の競争力を損ねているとする極右政党の主張を補強する側面がある。結果として、EUの規制力は外部からの政治的圧力と内部からの反発の板挟みにある。
今日、規制政策はもはや産業政策の枠を超え、地経学的競争の「主戦場」となっている。トランプ政権によるEU規制への攻撃は、EUが長年培ってきた「規範的パワー」の根幹を揺るがしかねない。また、ブリュッセル内部でもそれが及ぼす影響に対する警戒感が高まっている。ブラッドフォードの論考は、こうした米欧間の規制をめぐる地経学的対立において、EUの立場を理解する上での有用な視座を提供している。
⑤「我々には仲間内もオリガルヒもいない」
Ulrich Ladurner and Bernd Ulrich, “We have no bros and no oligarchs,” Die Zeit,, April 15, 2025
「私たちが知っていた西側世界(the West)は、もはや存在しない」。ドイツ紙のインタビューでそう語った欧州委員会のウルズラ・フォンデアライエン委員長の発言は、第二次トランプ政権の成立を受けて対米関係の根本的な見直しを迫られている欧州において、大きな注目を集めた。防衛、エネルギー、貿易といった分野において、EUがより自律的なアクターへと転換する必要性を訴える彼女の主張には説得力がある。
もっとも、EUによる自律性の追求は、いまになって始まったことではない。2016年以降、防衛政策を出発点として、産業・貿易、さらにはデジタル分野へと、自律を摸索する姿勢は広がってきた。しかし、第二次トランプ政権下で鮮明となった米国の敵対的な対EU姿勢は、これまで「価値観を共有する同盟国」として描かれてきた米国像に、根本的な疑問を投げかけることとなった。EUの政策決定コミュニティの一部からは、米国を安全保障上の脅威と見なす声すら聞かれる。
「頼れる米国」という幻想が完全に崩れ去った今、EUの戦略的自律(strategic autonomy)への追求は、新たな段階へと至った。それはまた、第二次世界大戦後の「平和プロジェクト」として始まった欧州統合の意義を、あらためて問い直す契機ともなっていると言えよう。
-
 India and EU Sign Mother of All Deals2026.02.09
India and EU Sign Mother of All Deals2026.02.09 -
 Orbán in the Public Eye: Anti-Ukraine Argument for Delegitimising Brussels2026.02.04
Orbán in the Public Eye: Anti-Ukraine Argument for Delegitimising Brussels2026.02.04 -
 Trump, Takaichi and Japan’s Strategic Crossroads2026.02.03
Trump, Takaichi and Japan’s Strategic Crossroads2026.02.03 -
 Analysis: When Is a Tariff Threat Not a Tariff Threat?2026.01.29
Analysis: When Is a Tariff Threat Not a Tariff Threat?2026.01.29 -
 Takaichi’s Strengths and the Need for ‘Strategic Signaling’2026.01.23
Takaichi’s Strengths and the Need for ‘Strategic Signaling’2026.01.23
 Oil, Debt, and Dollars: The Geoeconomics of Venezuela2026.01.07
Oil, Debt, and Dollars: The Geoeconomics of Venezuela2026.01.07 It’s Now or Never: India’s Ambitious Reform Push2026.01.09
It’s Now or Never: India’s Ambitious Reform Push2026.01.09 Orbán in the Public Eye: Anti-Ukraine Argument for Delegitimising Brussels2026.02.04
Orbán in the Public Eye: Anti-Ukraine Argument for Delegitimising Brussels2026.02.04 Analysis: When Is a Tariff Threat Not a Tariff Threat?2026.01.29
Analysis: When Is a Tariff Threat Not a Tariff Threat?2026.01.29 Navigating Uncertainty in U.S. Space Policy: Decoding Elon Musk’s Influence2025.04.09
Navigating Uncertainty in U.S. Space Policy: Decoding Elon Musk’s Influence2025.04.09












