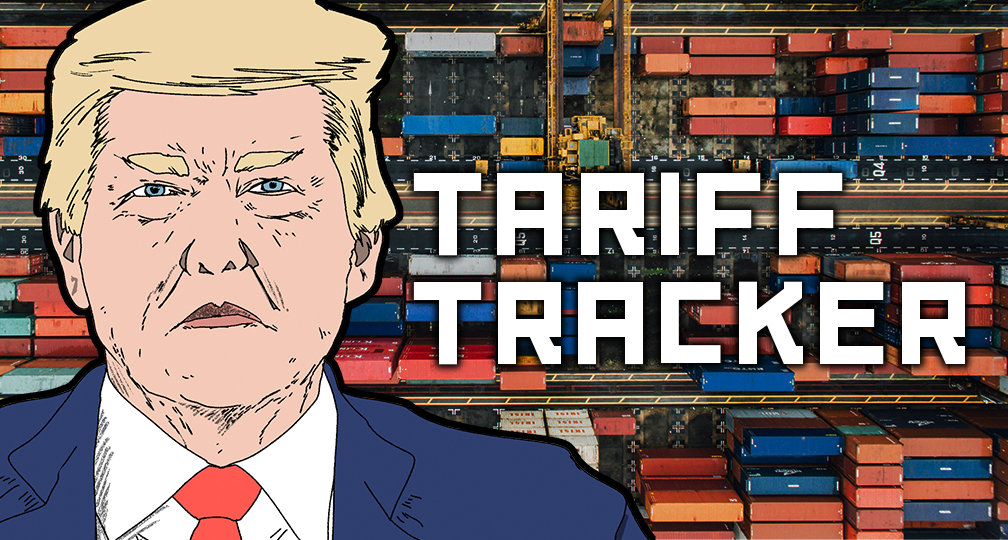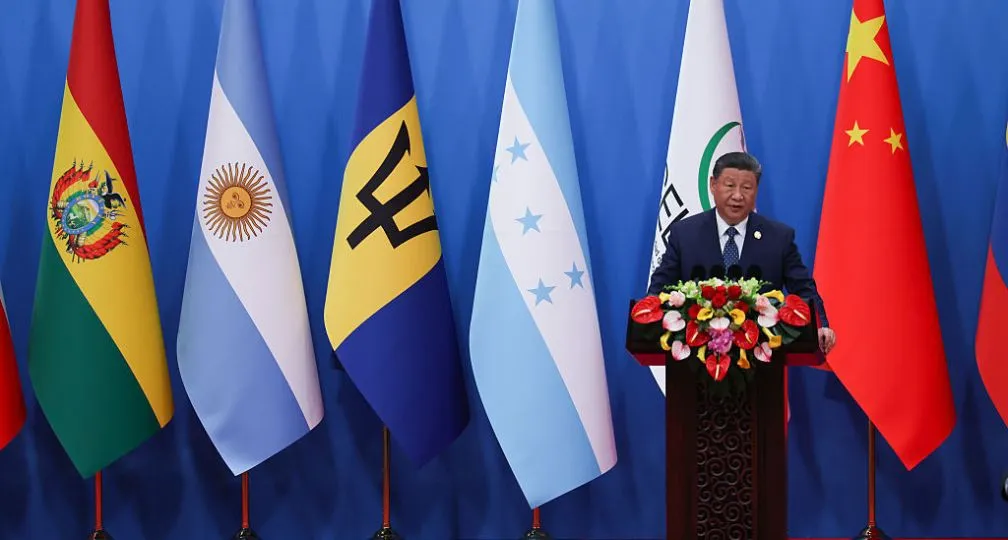オーストラリアへの新型FFM移転 ②装備移転に向けた3つのリスク

移転先が新規参入企業にとってビジネスしやすい相手であればよいが、オーストラリア海軍は「企業泣かせの顧客」として知られている。これまでにも多くの外国企業が、その仕様変更や建造場所の要求に苦しめられてきた。日本の防衛企業は、以下の3つのリスクを事前に把握し、同じ轍を踏まないようにしなければならない。
造船基盤の空洞化
新型FFMの移転にはさまざまなリスクが潜んでいるが、その中でも最大の障壁はオーストラリア国内の建造能力である。オーストラリア国防省の発表によれば、新型FFM11隻のうち3隻を日本で建造し、残る8隻をパース近郊ヘンダーソン地区の造船所で建造する計画だ。しかし、これを成功させるためには、まずはオーストラリアの建造能力、とりわけ深刻な人材不足の解消が不可欠となる。
ヘンダーソンでの建造を担う予定のオースタル社は、米海軍向けのステルス艦であるインディペンデンス級沿海域戦闘艦(LCS)の建造実績を有し、その高度な精度要求を満たしてきた。ステルス艦は、1ミリ単位の精度が求められるため、高度な技術力と豊富な経験が必要であり、この点から、一見するとオースタル社は十分な能力を備えているように思われる。しかし、インディペンデンス級を建造したのは米国拠点の子会社オースタルUSA社であり、ヘンダーソン地区のオースタル社の造船所が持つものではない。仮に子会社から親会社に技術情報や教訓が共有されていたとしても、実際にステルス艦建造を担った米国人技術者や工員が移籍しているわけではない。加えて、同社はアルミ製艦船の建造には豊富な経験を持つ一方、鉄鋼製艦船の建造経験はほとんどない。すなわち、鉄鋼製のステルス艦である新型FFMを建造できる人材は、オースタル社には現状ではほぼ存在していないのである。
オーストラリア国防省もこの課題を認識しており、対策として2024年に発表した統合投資計画および艦艇建造維持計画で、沿海域機動艇を2026年から2037年にかけて計26隻建造する方針を発表した。高度な建造技術を必要としない鉄鋼製の艦艇を建造することで、技術者や工員を育成する狙いである。しかし、この計画はすでに暗礁に乗り上げている。国防省と建造会社のオースタル社、設計会社のバードン社との間で合意に至らず、着手は当初予定から2年遅れていると報じられており、オーストラリア国内で建造予定の新型FFMにも影響を及ぼす可能性が高い。日本の防衛産業も国内で深刻な人材不足に直面しているが、それでもオーストラリアの人材育成を支援する必要に迫られる可能性がある。
政治・同盟の要請による設計改変
二つ目のリスクは、オーストラリア海軍による度重なる仕様変更である。同海軍が近年開発・調達を進めてきたアラフラ級哨戒艦や新型FFM導入の契機となったハンター級フリゲートも、この「悪癖」に翻弄された。アルバニージ政権はこれに歯止めをかけるべく、法令遵守に必要な最小限の改修にとどめるよう指示しており、日本国内で建造する分については、リスクは低いように見える。だが、オーストラリア国内建造分に関しては、大規模な仕様変更が求められる可能性が高い。それは2つの要因によるものである。
一つ目は、雇用創出である。オーストラリアは民生分野の工業力が貧弱であるため、工業全体に占める国防産業の比重が相対的に大きい。その結果、装備品の選定では、いわゆる「軍事的合理性」だけでなく国内雇用への影響も重視されやすい。この傾向は、新型FFMの採用決定時に国防産業担当大臣がX(旧ツイッター)で発信した内容にも表れている。同大臣は、安全保障上の意義よりも雇用創出効果を前面に押し出していた。このことから、オーストラリア国内建造分では、自国企業の参画を最大限拡大する取組が進む可能性が高い。改修内容がヌルカと呼ばれるオーストラリア製のデコイシステムのように比較的容易に外付けできる装備であればハードルは低い。しかし、レーダーのような水上戦闘艦としての中核的な要素にオーストラリア企業のCEAテクノロジーズ社製のレーダーを組み込む必要が生じた場合、大規模な仕様変更につながる恐れがある。
オーストラリア国内建造分で大規模な仕様変更が求められる二つ目の理由は、米海軍との相互運用性の向上である。たとえば、オーストラリア海軍が米国製のイージスシステムを新型FFMに搭載するよう、日本の防衛企業に要請してくる可能性がある。オーストラリア海軍は有事の際に、米海軍と極めて密接に連携し、共同作戦を行うことが予想されており、これまでにも米海軍との相互運用性を重視してきた。そのため、現在運用されているホバート級や今後導入予定のハンター級はいずれもイージスシステムを採用している。この背景を考慮すると、新型FFMの仕様変更に伴う開発コストやリスクよりも、米海軍との相互運用性を重視されることになる。特に、遠隔交戦(EOR)能力を獲得する上で、日本製の23式艦対空誘導弾とFCネットワークではなく、オーストラリア海軍のイージス艦でも導入されているSM-6とNIFC-CAの採用を望む可能性が高い。そうなれば、新型FFMの設計思想から大きく乖離した艦になってしまい、日本の防衛企業は新型FFMのシステム全体の大幅な改修を求められることとなる。さらに、米国企業の参画に伴う複雑な調整を行う必要に迫られる。こうしたオーストラリア側の仕様変更の要求に備えておかなければならない。
契約変更・中止リスク
日本の防衛企業が注意すべき三つ目のリスクは、前述の2つに起因するものである。すなわち、オーストラリアが十分な建造能力を確保できなかったり、度重なる仕様変更を求めたりした結果、調達価格が大幅に上昇し、建造隻数が大きく削減される可能性である。
事業の難航を受けて規模を縮小すること自体は、場合によっては合理的な判断といえる。しかし、過去の事例では、その原因の多くが豪海軍や豪国防省側にあった。例えば、ドイツのリュールセン社が受注したアラフラ級哨戒艦は、当初12隻の建造が計画されていたが、雇用維持のために2つの造船所で分割建造する方針が採用された。さらに、進水後には残存性向上を求める仕様変更が加えられた結果、就役までに3年の遅延が生じ、調達費用も増大した。最終的に調達数は6隻に削減された。
ハンター級フリゲートも同様である。度重なる仕様変更により大幅な遅延とコスト増が発生し、1隻あたりの調達価格は35億豪ドルから50億豪ドルへ上昇した。その結果、調達隻数は9隻から6隻に削減されてしまった。さらに最大規模の事業変更は、アタック級潜水艦である。2016年にフランス製通常動力型潜水艦の調達が決定されたが、価格高騰を理由に2021年9月、契約は突然中止され、英米との原子力潜水艦供与・建造合意であるAUKUSに切り替えられた。この決定により、アタック級向けに構築されていたサプライチェーンは甚大な打撃を受けた。
これらの結果、AUKUS関連事業を含む大型案件を複数受注しているBAEシステムズ社を除き、2つの造船会社はオーストラリアでのプレゼンスを大幅に縮小した。リュールセン社は事業を売却して撤退を表明し、アタック級建造を予定していたフランスのナバル・グループ社も、2019年に現地法人を設立したものの、2021年以降は活動規模を大きく減らしている。オーストラリアが新型FFMを建造する能力を十分に備えていない現状と、大規模な仕様変更が生じ得る可能性を踏まえれば、予測不可能性は極めて高い。日本の防衛産業も、過去の事例と同様のリスクに直面する恐れがあるといえよう。
結びにかえて
もちろん、その他にも課題は存在する。例えば、知的財産の移転や技術情報の共有、教育・訓練、第三国への移転に関する問題などである。しかし、最も深刻なのは前述の3点、すなわち①オーストラリア国内における造船基盤の空洞化、②雇用問題や同盟上の要請に基づく仕様変更、③調達数の大幅削減である。これらはいずれも、事業そのものを中止に追い込む危険性が高い。
こうした問題を抑制するためには、2026年初頭に締結が予定されている契約が極めて重要である。契約主体はオーストラリア国防省と日本の防衛企業との間にとどめず、日本政府も当事者として関与し、予測不可能性を最大限低減できる枠組みとすべきである。その際、豪英両国がAUKUSに内在する不確実性の低減を目的として2025年7月に締結したジーロング条約のような枠組みが参考となろう。
新型FFMがオーストラリア海軍の次期汎用フリゲートに選定された今、日豪は同型の装備品をめぐり、今後半世紀にわたって頻繁にやり取りを行うことになる。良好な関係を維持するためにも、国防省と海軍の過去の傾向を事前に把握し、過大な期待を避けつつ、契約を通じて予測不可能性を抑えることが不可欠である。
(Photo Credit: AAP/アフロ)


Research Associate
Rintaro Inoue is a Research Associate at the Asia Pacific Initiative (API) & the Institute of Geoeconomics (IOG), the International House of Japan (IHJ), a Tokyo-based global think-tank, where he focuses on U.S. security policy, the U.S.-Australia alliance, Japanese defense policy, and economic statecraft including defense industrial base policy. Prior to assuming his current position, he joined the Asia Pacific Initiative (API) as an intern and contributed to multiple projects including the Japan-U.S. Military Statesmen Forum (MSF). He is currently researching defense industrial policies of other countries in the International Security Order Group. He received his BA and MA in law from Keio University and is now a PhD student.
View Profile-
 Will Trump’s tech policies propel U.S. success against China?2025.08.08
Will Trump’s tech policies propel U.S. success against China?2025.08.08 -
 The “Reciprocal” Tariffs Are Now in Effect – But for How Long?2025.08.07
The “Reciprocal” Tariffs Are Now in Effect – But for How Long?2025.08.07 -
 The rift between Trump and the EU: can Italy’s Meloni become a bridge-builder?2025.08.06
The rift between Trump and the EU: can Italy’s Meloni become a bridge-builder?2025.08.06 -
 Tariff Tracker: A Guide to Tariff Authorities and their Uses2025.08.06
Tariff Tracker: A Guide to Tariff Authorities and their Uses2025.08.06 -
 Japan’s Upper House Election: Political Fragmentation and Growing Instability2025.07.25
Japan’s Upper House Election: Political Fragmentation and Growing Instability2025.07.25
 Japan’s Upper House Election: Political Fragmentation and Growing Instability2025.07.25
Japan’s Upper House Election: Political Fragmentation and Growing Instability2025.07.25 Why the EU economy faces hard choices between Trump and China2025.07.24
Why the EU economy faces hard choices between Trump and China2025.07.24 The “Reciprocal” Tariffs Are Now in Effect – But for How Long?2025.08.07
The “Reciprocal” Tariffs Are Now in Effect – But for How Long?2025.08.07 DOGE Shock and Crisis in U.S. Credibility2025.07.14
DOGE Shock and Crisis in U.S. Credibility2025.07.14 Unchecked and unbalanced: The future of U.S. economic policymaking2025.07.07
Unchecked and unbalanced: The future of U.S. economic policymaking2025.07.07