世界はトランプ政権をどう見るか No.9
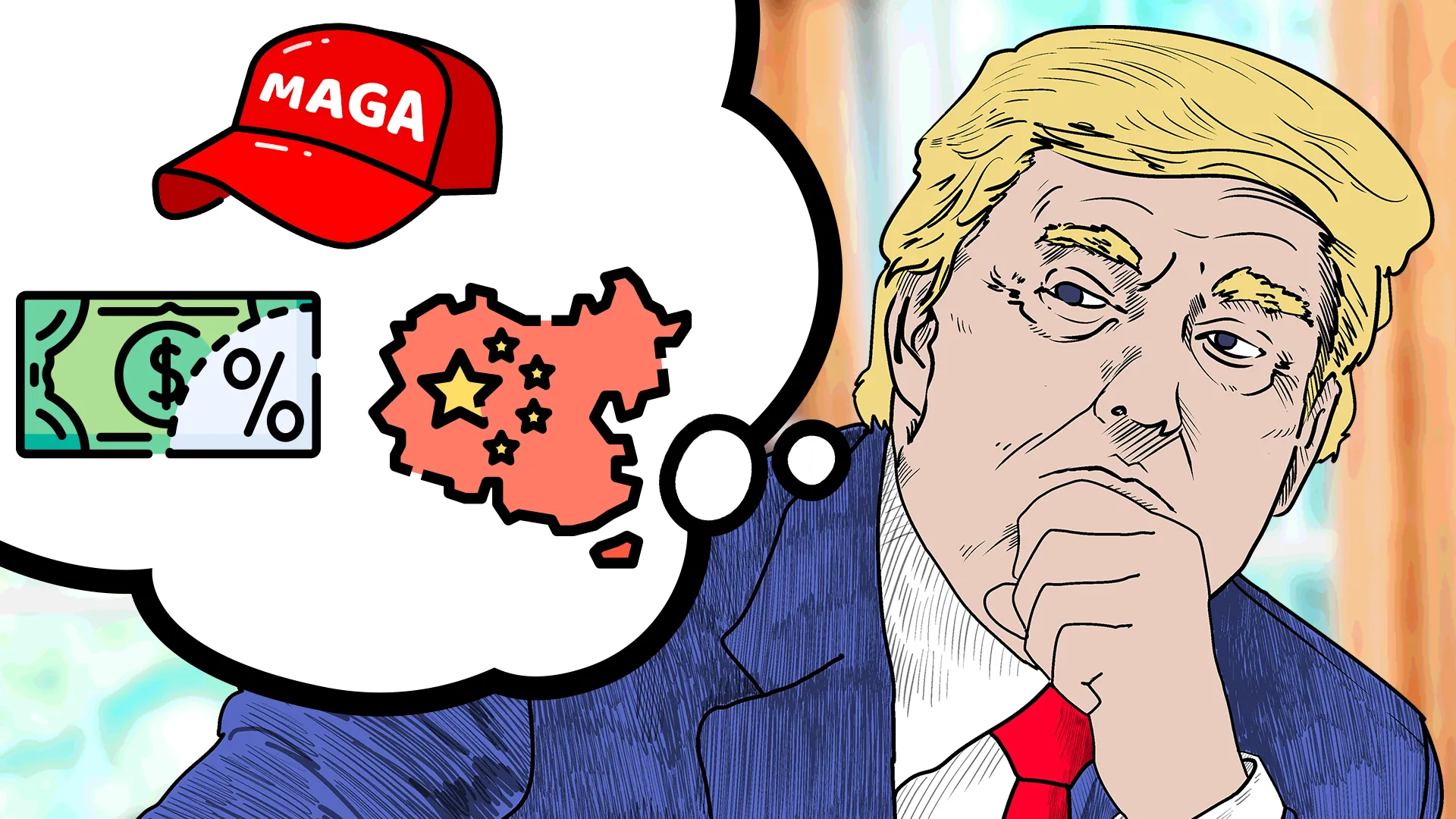
世界はトランプ政権をどう見るか(主要論考の紹介)

特集「2025年 トランプ政権は世界をどう変えるか」
トランプ第二次政権の動向がグローバル経済や国際秩序にどのような変化をもたらすのか、そして他国はどのように対応するのかが注目されます。本特集では、2025年のトランプ政権の政策動向とその影響を分析し、国際社会に与えるインパクトについて考察します。
①「トランプの通商代表が語る:なぜ私たちは世界秩序を作り直したのか」
Jamieson Greer, “Trump’s Trade Representative: Why We Remade the Global Order,” The New York Times, August 7, 2025.
トランプ政権で通商代表部(USTR)で通商代表を務めるジェミソン・グリアによる、『ニューヨーク・タイムズ』紙への寄稿である。WTOを中心とする従来の自由貿易体制が米国の貿易赤字を拡大させ、米国産業の生産能力や雇用、経済安全保障に打撃を与えてきたとして批判し、トランプ大統領が関税と海外市場へのアクセス、投資を組み合わせた新たな世界貿易秩序の構築を始動させたと論じている。
グリアによると、各国との交渉において米国は、国内で十分な関税を確保しながら他国での貿易障壁を体系的に撤廃しており、サプライチェーンの安定化のための協力や巨額の投資約束、不履行があれば迅速に高関税を再び課すことができる実効性を兼ね備えたディールにより、米国の製造業は復活するという。強力で断固とした措置が至急必要だという、トランプ政権の関税政策を理論的に正当化するこの論考に顕れているように、トランプ政権の高官たちは、自らを「関税男(タリフマン)」と称するトランプを利用して国際経済秩序自体の再構築を試みていると言える。
米国の貿易赤字と製造業の停滞への強い危機感に端を発するトランプ政権内部のそうした思考様式を理解する上でも、極めて価値ある論考である。
②「マクロン仏大統領:EUはトランプ氏に「手強さ」を示すことができずに、良い貿易協定を逃した」
Clea Caulcutt, Sarah Paillou and Giorgio Leali, “Macron: EU wasn’t ‘feared enough’ by Trump to get good trade deal,” Politico Europe, July 30, 2025.
ニュースメディア「ポリティコ」欧州版が、EUと米国の相互関税合意に対するフランス政府の反応を報じている。
2025年4月、トランプ米大統領が「解放の日」と謳って相互関税を発表した後、マクロン仏大統領は公の場で反対の意を示していたが、その後、欧州委員会のフォンデアライエン委員長と連携し、イタリアのメローニ首相にEU米間の橋渡し役(地経学ブリーフィングはこちら)に託してからは、公に非難することを控えていた。しかし7月末にフォンデアライエン委員長とトランプ大統領が関税合意を発表して以降、フランスからの批判が相次いでいる。バイルー仏首相、極右派政治家ルペン氏、マクロン大統領らは、関税合意によってビジネスがより安定する点に理解を示しつつも、EUの単一市場としてのレバレッジを使い、よりEUに有利なディールが可能であったと批判する。
この関税合については、EU内では賛否が分かれている。イタリアやドイツは今回の合意をおおむね支持しており、高関税による国内経済への打撃を考慮しながら、今回の対米交渉でEU側にとってこれ以上有利な結果を出すのは困難だったと見ている。だがEU加盟国内では、合意内容に反対する政党も複数あり、トランプ大統領との関税合意がEU内の政治的な対立を深めたといえる。
③「トランプのチキンゲームにおいて、EUには引き下がる余地がない」
Nathalie Tocci, “In Trump’s game of chicken, the EU cannot afford to back down,” The Guardian, July 15, 2025
2025年7月27日、スコットランドでの会談において、トランプ米大統領と欧州委員会のフォンデアライエン委員長は貿易合意に達し、数カ月にわたる米欧間の関税対立は一時的に収束した。合意では、米国が自動車などへの関税を15%に引き下げる一方、EUは7500億ドル規模のエネルギー購入と6000億ドル超の対米投資を約束した。この内容については、欧州内で「戦略なき譲歩」との批判が強まり、即興的なトランプ政権の関税戦術に対し、EUが結束を欠いたまま不利な条件を受け入れたとの見方が広がっている。
こうした評価は、英紙『ガーディアン』に合意の約2週間前に寄稿された、過去2代の(EU外相に相当する)EU外務・安全保障政策上級代表の特別顧問を務めたナタリー・トッチによる論考とも一致する。彼女もまた、EUが対抗措置を取れず防御的な立場に追い込まれている現状を厳しく指摘していた。
トッチは、2016年にボレル上級代表の下で「EUグローバル戦略」の策定に中心的に関与した国際政治の専門家であり、同戦略では「戦略的自律」が「欧州がその内外において平和と安全を促進する能力の基盤」として繰り返し強調された。この概念は、防衛を出発点に産業・貿易・デジタル分野へと展開し、米中対立を含む混迷する国際秩序の中で、EUの利益と安全保障を守るための指針として欧州の政策コミュニティ内で繰り返し議論の俎上に載せられてきた。
実際、トランプ政権による関税措置を受け、EU域内では950億ユーロ規模の報復関税や米国企業への市場アクセス制限といった「反威圧措置(Anti-Coercion Instrument; ACI)」の発動が検討された。4億5000万人規模の市場を有するEUは、多くの米企業にとって完全に無視することは不可欠であり、こうした措置の発動を示唆することは交渉上の強みであると同時に、戦略的自律を実践する好機でもあったと考えられる。しかし、NATOにおける米国の関与を重視する国々や、米市場への依存が強いドイツの慎重姿勢により、この措置の実際の発動は見送られた。結果としてEUは不利な条件を受け入れることになり、戦略的自律の理念との乖離を示す例になったとの批判も見られる。このトッチの論考は、こうした展開を的確に予見していたものであったと言えるだろう。
④「フランスはトランプ劇場の端役を降りるべきだ」
Bruno Le Maire, “Bruno Le Maire : «La France doit cesser dʼêtre un figurant du show perpétuel de Donald Trump,” Le Figaro, July 3, 2025
第二次トランプ政権を前に、欧州は「覚醒」しつつあるのだろうか。
マクロン大統領の下で7年間にわたり経済・財務相を務めたブリューノ・ルメールは、米国のイラン核施設攻撃後に『ル・フィガロ』紙に寄せた論考において、米国大統領を「パパ」と見なしている限り、欧州は「子供」のままであると嘆いた。さらに、「子供」はあくまで、「大人」の決定に服することになると加える。同論考が公開される約1週間前には、オランダのハーグで開催されたNATO首脳会議の折、トランプ大統領がイスラエルとイランの紛争を「校庭での子供の喧嘩のようだ」と評したのに対して、ルッテNATO事務総長が「パパは彼らを止めるため、時に強い言葉を使わなければならない」と返し、波紋を呼んでいた。
フランスを含む欧州諸国は、これまで中東情勢に積極的に関与を続けてきた。2015年にイランと「EU3+3」(英・仏・独・米・中・露)の間で結ばれたイラン核合意では、交渉が難航するなか、EUの外務・安全保障政策上級代表が交渉の調整役を務めるなど、欧州が重要な役割を果たしたとされる。しかしその後、米国は第1次トランプ政権期に同合意から離脱。今回も、トランプは、欧州諸国が中東における「問題解決の役に立たないだろう」と言い放った。ルメールは、欧州が日和見的で支離滅裂なトランプ劇場の端役に終わってしまった、と指摘する。
こうした状況において、マクロン大統領が積極的に追求し、ルメールも繰り返し言及してきた欧州の戦略的自律という概念が、重みを増している。マクロン大統領は7月24日、フランスとしてパレスチナ国家を正式に承認すると発表した。この動きを、中東において米国と異なる道を選び、パレスチナ寄りのグローバル・サウスに対する影響力拡大を意図したものと捉えることも可能だろう。フランスと欧州は、トランプ劇場の端役を降り、「大人」として振る舞うことができるのだろうか。今後の動きが注目される。
⑤「中東和平をめぐり、ドナルド・トランプと欧州の立場には意外にも多くの共通点がある」
Michel Duclos, “Michel Duclos, ancien ambassadeur : « Sur la paix au Proche-Orient, il y a plus de convergences qu’il n’y paraît entre Donald Trump et l’Europe »,” Le Monde, June 27, 2025
2000年から2014年にかけてEU、国連、中東でフランス大使などを歴任した元外交官ミッシェル・デュクロは、仏紙『ル・モンド』への寄稿で、中東情勢における欧州の一貫性を欠く対応に触れつつも、トランプ政権と欧州はイラン核開発阻止や湾岸諸国との関係で共通の利害を有する、と論じている。2025年7月下旬には、マクロン大統領がイスラエル・ハマス衝突の終結とガザへの人道支援を訴え、G7で初めてパレスチナ国家を承認する方針を表明した。デュクロはこれをフランスの主権的判断と捉え、グローバル・サウスとの信頼回復に資する動きと評価している。
しかし、国家承認が実効的な中東和平の構築に資するかは依然として不透明である。トランプ大統領は「どうでもいい」と退け、ルビオ国務長官も「和平を後退させる」と批判。イスラエルとの「特別な関係」にあり、中東和平の主要アクターである米国との根本的な認識のずれは、フランスの試みにとって大きな制約となる。
米仏間の温度差は今に始まったことではない。1960年代以降、フランスはアラブ諸国との関係強化に舵を切り、第三次中東戦争後にはイスラエルへの武器輸出を停止するなど、アラブ寄りの立場を鮮明にした。1973年に勃発した第四次中東戦争では、米国がパレスチナ問題を棚上げにして和平交渉を優先する一方で、フランスは欧州諸国と連携し、パレスチナ問題の解決を含む包括的な和平を主張したが、結果的に米国との対立や欧州内の足並みの乱れを招いた。結局、フランスが和平プロセスにおいて主導権を握ることはなく、その後誕生するEUも中東和平において「プレイヤー(player)」ではなく「ペイヤー(payer)」と揶揄されたように、影響力の限界が浮き彫りとなった。2023年10月に中東情勢が悪化して以降も、欧州はイスラエルの自衛権とガザの人道危機への懸念を併せて示しているが、一貫性を欠き、フランスも明確なリーダーシップを示せていない。
こうした経緯を踏まえれば、パレスチナ承認に強く反発するトランプ政権の下で、フランスの動きが国際的合意に結実する可能性は乏しい。本論考も明確な答えを示してはおらず、理念と現実のあいだで揺れるフランス外交のジレンマが改めて浮き彫りとなっている。
-
 India and EU Sign Mother of All Deals2026.02.09
India and EU Sign Mother of All Deals2026.02.09 -
 Orbán in the Public Eye: Anti-Ukraine Argument for Delegitimising Brussels2026.02.04
Orbán in the Public Eye: Anti-Ukraine Argument for Delegitimising Brussels2026.02.04 -
 Trump, Takaichi and Japan’s Strategic Crossroads2026.02.03
Trump, Takaichi and Japan’s Strategic Crossroads2026.02.03 -
 Analysis: When Is a Tariff Threat Not a Tariff Threat?2026.01.29
Analysis: When Is a Tariff Threat Not a Tariff Threat?2026.01.29 -
 Takaichi’s Strengths and the Need for ‘Strategic Signaling’2026.01.23
Takaichi’s Strengths and the Need for ‘Strategic Signaling’2026.01.23
 Oil, Debt, and Dollars: The Geoeconomics of Venezuela2026.01.07
Oil, Debt, and Dollars: The Geoeconomics of Venezuela2026.01.07 It’s Now or Never: India’s Ambitious Reform Push2026.01.09
It’s Now or Never: India’s Ambitious Reform Push2026.01.09 Orbán in the Public Eye: Anti-Ukraine Argument for Delegitimising Brussels2026.02.04
Orbán in the Public Eye: Anti-Ukraine Argument for Delegitimising Brussels2026.02.04 Analysis: When Is a Tariff Threat Not a Tariff Threat?2026.01.29
Analysis: When Is a Tariff Threat Not a Tariff Threat?2026.01.29 Navigating Uncertainty in U.S. Space Policy: Decoding Elon Musk’s Influence2025.04.09
Navigating Uncertainty in U.S. Space Policy: Decoding Elon Musk’s Influence2025.04.09












