世界はトランプ政権をどう見るか No.11
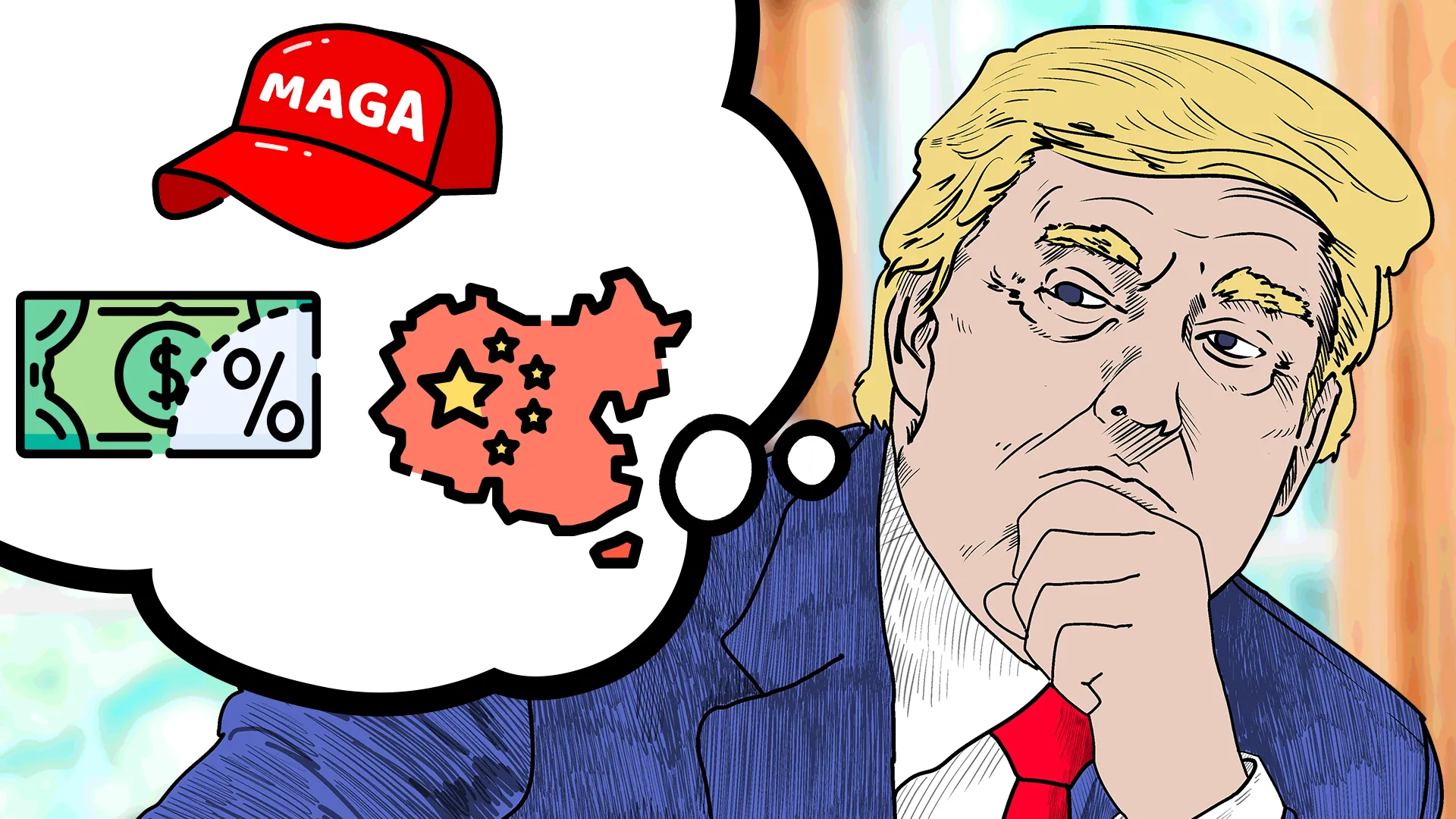
世界はトランプ政権をどう見るか(主要論考の紹介)

特集「2025年 トランプ政権は世界をどう変えるか」
トランプ第二次政権の動向がグローバル経済や国際秩序にどのような変化をもたらすのか、そして他国はどのように対応するのかが注目されます。本特集では、2025年のトランプ政権の政策動向とその影響を分析し、国際社会に与えるインパクトについて考察します。
①「第2次トランプ政権の外交政策を擁護する」
Robert O’Brien, “The Case for Trump’s Second-Term Foreign Policy”, Foreign Affairs, November 5, 2025.
第1次トランプ政権で国家安全保障問題担当大統領補佐官を務めたロバート・オブライエンが、外交専門誌『フォーリン・アフェアーズ』に寄せた論考である。就任から10ヶ月が経過した時点での、第2次トランプ政権の外交・安全保障政策の成果を概観し、トランプ大統領の追求する「力による平和(peace through strength)」こそが世界の平和と安定をもたらしているとして、その政策を強く擁護している。
この論文の中でオブライエンは、第二次トランプ政権のこれまでの成果として、米国自身による軍事非の増加や、ミサイル防衛構想の推進、NATOやインド太平洋における同盟国・パートナー国へのGDP比5%へ向けた防衛負担の増加要求などを指摘している。さらには、イスラエルへの全面的な支援や、イランへの「最大限の圧力」政策の再開と核濃縮施設の攻撃、関税や制裁を梃子とした世界各地での地域紛争の停戦仲介、西半球における国境警備の強化や麻薬密輸の取り締まりにも、言及し、それらの政策の正当性を主張する。その上で、トランプ政権下における強い米国こそが、本土防衛を確かなものにし、さらには世界中の紛争に終止符を打つと述べる。
本論文で、「トランプが同盟を弱体化させたという批判は誤りであり、むしろ同盟国に圧力をかけて自ら防衛負担を増やさせることで、米国の納税者に負担をかけることなく同盟を再び活性化させたのだ」とオブライエンは主張している。本論考では、大きく批判を受けているトランプ政権の対外政策を、伝統的な共和党員が受け入れられるようなナラティブへと翻訳している印象を与える。確かに、米中間のディールや、同盟国やパートナー諸国への安全保障上のコミットメントなど、依然としてトランプ政権の対外政策には不確実性は大きい。それでも、本論文を通じて第2次トランプ外交の輪郭を徐々に浮き彫りにすることができるのではないか。
②「トランプの砲艦外交を支える理論的支柱」
Thomas P.M. Barnett. “The Theory Behind Trump’s Gunboat Diplomacy”, Politico, October 25, 2025.
スルーライン社で上級ビジネス戦略担当を務めるトーマス・P・M・バーネットは、オンライン政治誌『ポリティコ』への寄稿論考において、トランプ政権の外交政策におけるラテンアメリカ諸国の比重が増大していることを指摘し、その中に内向的でありながら同時に対外膨張的な論理が併存していると論じている。
この主張は一見すると、自国の対外関与を減らそうとしていた従来のトランプ外交のイメージとは相反している。また、21世紀に入って以降の中東地域における「テロとの戦い」や、中国・ロシアとの大国間競争を前提として展開されてきたここ数十年の米国外交を踏まえると、ベネズエラをはじめとするラテンアメリカ地域全体を重視していく傾向は、これまで見られなかったものである。
しかし、バーネットによれば、米国が西半球を射程に置く姿勢は、「米国の最も初期の大戦略への回帰」であり、「建国の父たちからトランプに至るまで一本の線でつながる系譜の一部」である。すなわち、ラテンアメリカを自国の「裏庭」として強く認識していた時代への逆行が生じているということである。さらに、トランプの「関税障壁」と「領土的野心」への執着は、高関税を掲げて米西戦争においてフィリピンとキューバを獲得したマッキンリー大統領を彷彿とさせる。
興味深いのは、トランプ自身がその戦略を体現している点である。トランプも、そして西半球を優先する政策も、バーネットによれば「懐古的でありながら革命的、内向的でありながら帝国的、防御的でありながら拡張的」なのである。バーネットの論考によると、トランプ外交は歴史から脱線したものではなく、伝統的な米国外交という本来のレール上へと再び乗り直した動きなのである。
③「[コラム]日韓協力は選択ではなく、生存のための必然だ)」
윤영관「[선데이 칼럼] 한·일 협력은 선택이 아니라 필수다」『中央日報』、2025年10月25日.
韓国紙、『中央日報』に寄稿した尹永寛・前外交通商部長官(現アサン政策研究院理事長)の論考である。トランプの再登場により、米国の同盟政策は再び「取引型」へと傾き、同盟国に対する防衛費や投資拡大の要求が強まっている。こうした状況の中で、尹理事長は東アジアの同盟秩序が新たな転換点を迎えていると指摘し、日韓協力を「生存のための必然的戦略」と位置づける。尹理事長は、トランプ政権が同盟の規範的基盤を揺るがせた結果、韓国外交が米国中心の秩序再編にいかに能動的に対応するかという現実的課題に直面していると述べる。その問題意識には、韓国が単なる受動的な同盟国ではなく、不安定な国際環境の中で自律的連携を模索するミドルパワーとしての自覚がにじむ。
韓国では近年、経済安全保障やサプライチェーン協力を通じて、同盟を「従属」ではなく「協働」の枠組みとして再構築しようとする議論が広がっている。尹理事長の提言は、まさにその潮流を反映したものであり、韓国が同盟再定義の過程でより能動的な役割を果たそうとする意志を示している。
尹理事長は、日韓両国が民主主義、法の支配、航行の自由といった価値を共有する「価値同盟」として、半導体・AI・気候変動などの分野で実質的協力を深化させるべきだと提言する。これは、トランプ時代の不確実性の中で韓国社会が追求する新たな外交方向を象徴しており、韓国が「協力の設計者」として東アジア秩序の再編に参画しようとする姿勢を理解する手がかりとなる。
④「EUは鉄鋼関税案を再考すべきだ」
Ignacio García Bercero, “The EU should moderate its steel protection plan”, Bruegel, October 13, 2025.
世界的な鉄鋼の過剰生産とトランプ政権による25%の鉄鋼関税を受け、EU域内でも自らの産業保護を求める声が高まるなか、欧州委員会は2025年10月7日、無関税枠を超える鉄鋼製品に50%の関税を課す新制度案を発表した。これは現行のEUのセーフガード措置の関税率を倍増させるもので、無関税枠も2024年比で半減させる方針だ。欧州委員会は加盟国との協議を経て速やかな導入を目指しており、シェフチョビッチ委員(通商・経済安全保障担当)は「EUは自由貿易を重視しつつも、欧州の利益を守るために行動が必要だ」と強調した。
一方、韓国・インド・米国との主要FTA交渉でEU側の首席交渉官を務めた元欧州委員会高官のイグナシオ・ガルシア・ベルセロは、ブリュッセルの経済政策シンクタンク「ブリューゲル」に掲載した論考において、今回の提案は国際貿易における保護主義を拡大させると批判した。彼によれば、同提案は鉄鋼セーフガード措置の後継として過剰生産に対抗する狙いがあるものの、関税引き上げと無税枠縮小は脱炭素目標やWTO・FTA義務との整合性を欠き、市場混乱と川下産業の競争力低下を招くおそれがある。また、欧州委員会は、FTA締結国を措置の対象外とする考えを否定し、除外すれば効果が損なわれるとの立場を示している。これらの国々はEU鉄鋼輸入の約3分の2を占め、過剰生産の一因ともされるためだ。ガルシアは一方で、FTA締結国にも関税を課せば報復関税を招く恐れがあると警告している。
ベルセロの懸念は、EUと経済連携協定を通じて世界最大級の自由貿易圏を形成する日本にとっても、決して無関係ではない。今年7月の日・EU定期首脳協議で発足した「日・EU競争力アライアンス」が示すように、ルールに基づく自由貿易体制のパートナーとして、EUの重要性は日本にとって一層高まっている。一方で、今回の鉄鋼関税案は、トランプ政権の関税政策を契機として強まった、EUの「戦略的自律」の名の下に進む保護主義的傾向の表れともいえる。鉄鋼関税案の行方は、EUの通商政策の方向性のみならず、日本が掲げる自由貿易推進というビジョンの行方をも左右する試金石となるだろう。
⑤「米中サプライチェーンを巡るポーカーで優位に立つのはどちらか?」
Graham Allison, “Who Holds the High Cards in Sino-American Supply Chain Poker?“, Foreign Policy, October 6, 2025.
ハーバード大学ケネディ行政大学院教授の、グレアム・アリソンによる米中経済関係に関する論考。アリソン教授は、米中対立について「トゥキディデスの罠」という概念を提唱したことでも著名である。そのアリソンはこの論考の中で、重要物資であるレアアースの供給を中国が握り米国がそれに依存しているため、サプライチェーンを巡る米中間の競争について、中国が優位に立っていると指摘している。
アリソンは、4月2日にトランプ大統領が課した関税措置によって幕を開けた米中の貿易競争をていねいに振り返り、中国が2010年代から重要物資について他国を中国に依存させ、脆弱性を増大させ、それらの諸国に対して中国が強制することを可能とする状況確立してきたことを指摘する。ところが、米国はそのような経済安全保障上の自国の脆弱性への備えを十分にしてこなかった。他方で、先端半導体やドル基軸の通貨体制等では、中国が依然として米国に依存し、両国の経済は不可分に依存し合っている。10月末にソウルで実現した米中首脳会談では、両国が関税を引き下げて輸出規制を緩和し、中国によるレアアースの輸出規制も先送りすることで合意し、一時「休戦」状態となった。だが、対立の再燃の可能性は常に存在しており、予断を許さない。国際政治学の泰斗による、時宜を得た地経学の論考である。
⑥「リアリティショー:欧州がトランプの文化戦争に屈してはならないワケ」
Pawel Zerka, “Reality show: Why Europe must not cave in Trump’s culture war”, European Council on Foreign Relations, September 23, 2025.
「おはよう!それと、もし会えなかったら――こんにちは、こんばんは、そしておやすみなさい!(Good morning, and in case I don’t see ya, good afternoon, good evening, and good night!)」――ジム・キャリー演じるトゥルーマン・バーバンクのこの名セリフで知られる1998年の映画『トゥルーマン・ショー』は、自らの人生がすべて隠しカメラによって放送されていたことに気づいた男が、偽りの世界からの脱出を試みる姿を描いた名作である。
欧州の有力シンクタンクである欧州外交問題評議会(ECFR)で世論動向を専門とするパウェル・ゼルカは、トランプ政権下の混乱に翻弄されるEUや欧州諸国の姿を、映画『トゥルーマン・ショー』の主人公になぞらえている。彼によれば、欧州の指導者たちもまた、アメリカによる関税措置やウクライナ侵攻をめぐるロシアへの対応といった、自らが生み出したわけではない「ドラマ」に日々直面しているという。こうした「ドラマ」に直面する欧州に対し、トランプ政権はMAGA運動などを通じて、はたして「西側」とは何かをめぐる対立を深めている。同時に、欧州防衛への関与低下をほのめかしつつ、それまでよりも高い関税を押し付けることで、EUの自律性と信頼を揺るがせている。ゼルカに言わせれば、これは米欧間の「文化戦争」にほかならない。
ゼルカは、近年の複数の世論調査のデータを参照しつつ、欧州域内では依然としてEUへの期待が強く、加盟国政府の大半が親欧州派によって主導されている点を指摘する。極右の台頭や、トランプ前大統領の扇動により深まる分断、さらには各国で影響力を拡大するMAGAへの同調者の存在にもかかわらず、各国政府は依然として親欧的な路線を維持しているという。こうした状況を踏まえ、彼は、欧州というアクターが米国から自立し、自ら「ショーの監督」として行動すべき時が来ていると論じている。
しかしながら、前述のアレマンノによる指摘や、いわゆる「ブリュッセル効果」と称されるEUの影響力の限界にも示されるように、現実の欧州はなお「リアリティーショー」的状況から抜け出せていない。重要なのは、欧州の政治指導者たちが、自らがそうしたショーの舞台にいるということをどれほど自覚しているかである。その自覚と、適切な対応こそが、地経学アクターとしてのEUの将来を左右する要素となるだろう。
⑦「フォンデアライエンの正念場」
Alberto Alemanno, “Von der Leyen’s Breaking Point”, Project Syndicate, September 12, 2025.
9月10日、欧州委員会のフォンデアライエン委員長は欧州議会で一般教書演説を行い、「自由」や「独立」といった華麗なレトリックを用いて議場を拍手で湧かせる結果となった。しかし、フランスのエリート養成機関グランゼコールの最高峰であるHECパリでEUの民主的正統性について研究を行うアルベルト・アレマンノは、その演説がEUの構造的な問題を直視せず、トランプ政権下で揺らぐ米欧関係への明確な方向性を示さなかったことを批判した。さらに同氏は、「彼女は、欧州で果たされることのない約束の象徴となりかねない」と警鐘を鳴らしている。
アレマンノの指摘の背景には、フォンデアライエンを取り巻く政治的圧力の高まりが存在する。コロナ禍のワクチン契約をめぐるメッセージ開示訴訟での敗訴、7月に欧州議会で提出された不信任案、さらにはトランプ政権との通商合意に対する反発など、委員長の足場はかつてなく揺らいでいる。
この不安定さは、2028〜34年のEUの新中期予算(MFF)案をめぐる激しい反発にも表れている。産業競争力と防衛強化を前面に掲げ、農業・地域政策を大幅削減した総額約2兆ユーロの欧州委員会の案に対し、倹約派は「巨額すぎる」、左派は「農業切り捨て」と批判。数値は発表直前まで伏せられ、委員会内部も詳細を知らぬまま承認を迫られた経緯が議会とメディアの不信を深めた。
アレマンノは、トランプ政権下で地経学的競争が激化する中でフォンデアライエンが加盟国の抵抗を突破するには、貿易やエネルギー政策の議決における全会一致からの脱却、第三国による制裁回避を封じる措置の実施、そして委員会自身の財政レバレッジの活用など、強力な政治的リソースが不可欠だと論じる。しかし、フォンデアライエン委員長の実際の政策においては、その推進力が乏しいと見る。
「危機こそ欧州統合を進める」と説いた欧州統合の父ジャン・モネの言葉は、いまや皮肉に響く。中央集権的で秘密主義的とも受け取られかねないフォンデアライエンの手法は、加盟国の警戒を強めている。行政機関である欧州委員会が直接選挙で選ばれず、その民主的正統性が右派ポピュリズムから長く疑問視されてきた中、現状の彼女をめぐる状況はその批判を一層後押ししている。米欧関係が揺らぐなか、EUが掲げる「戦略的自律」の実現も不透明さを増していると言えよう。
-
 India and EU Sign Mother of All Deals2026.02.09
India and EU Sign Mother of All Deals2026.02.09 -
 Orbán in the Public Eye: Anti-Ukraine Argument for Delegitimising Brussels2026.02.04
Orbán in the Public Eye: Anti-Ukraine Argument for Delegitimising Brussels2026.02.04 -
 Trump, Takaichi and Japan’s Strategic Crossroads2026.02.03
Trump, Takaichi and Japan’s Strategic Crossroads2026.02.03 -
 Analysis: When Is a Tariff Threat Not a Tariff Threat?2026.01.29
Analysis: When Is a Tariff Threat Not a Tariff Threat?2026.01.29 -
 Takaichi’s Strengths and the Need for ‘Strategic Signaling’2026.01.23
Takaichi’s Strengths and the Need for ‘Strategic Signaling’2026.01.23
 Oil, Debt, and Dollars: The Geoeconomics of Venezuela2026.01.07
Oil, Debt, and Dollars: The Geoeconomics of Venezuela2026.01.07 It’s Now or Never: India’s Ambitious Reform Push2026.01.09
It’s Now or Never: India’s Ambitious Reform Push2026.01.09 Orbán in the Public Eye: Anti-Ukraine Argument for Delegitimising Brussels2026.02.04
Orbán in the Public Eye: Anti-Ukraine Argument for Delegitimising Brussels2026.02.04 Analysis: When Is a Tariff Threat Not a Tariff Threat?2026.01.29
Analysis: When Is a Tariff Threat Not a Tariff Threat?2026.01.29 Navigating Uncertainty in U.S. Space Policy: Decoding Elon Musk’s Influence2025.04.09
Navigating Uncertainty in U.S. Space Policy: Decoding Elon Musk’s Influence2025.04.09












