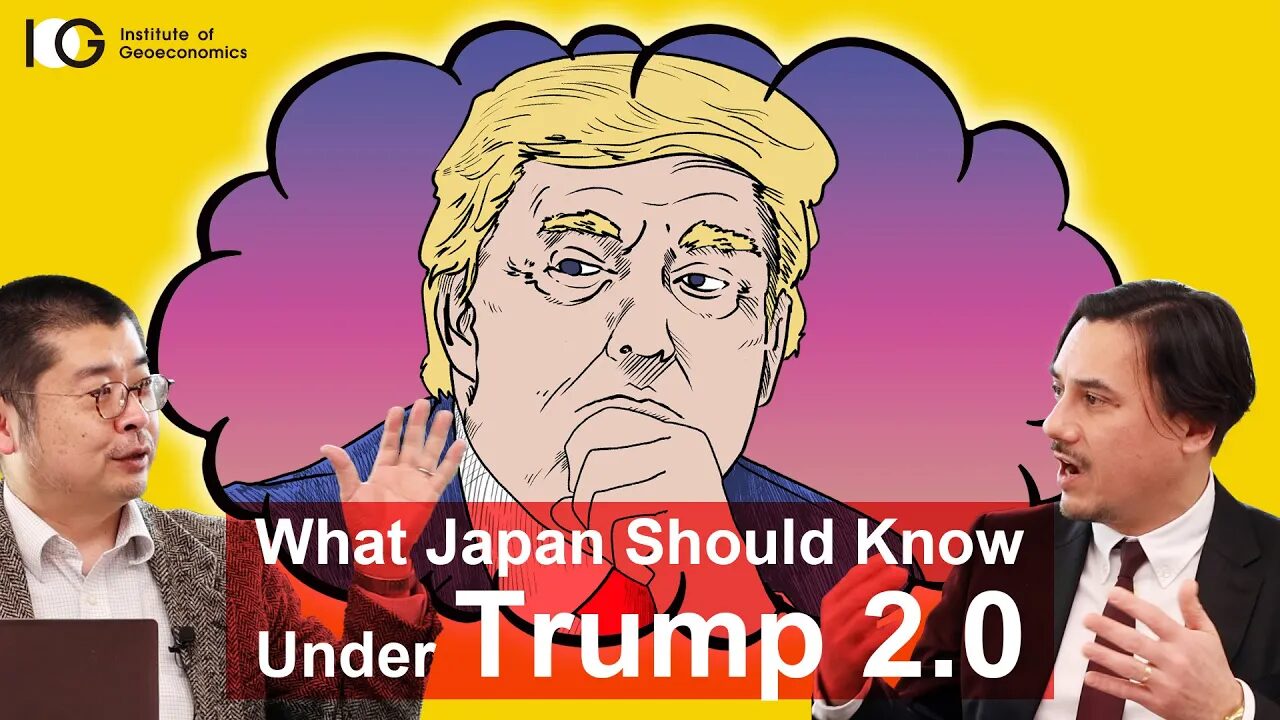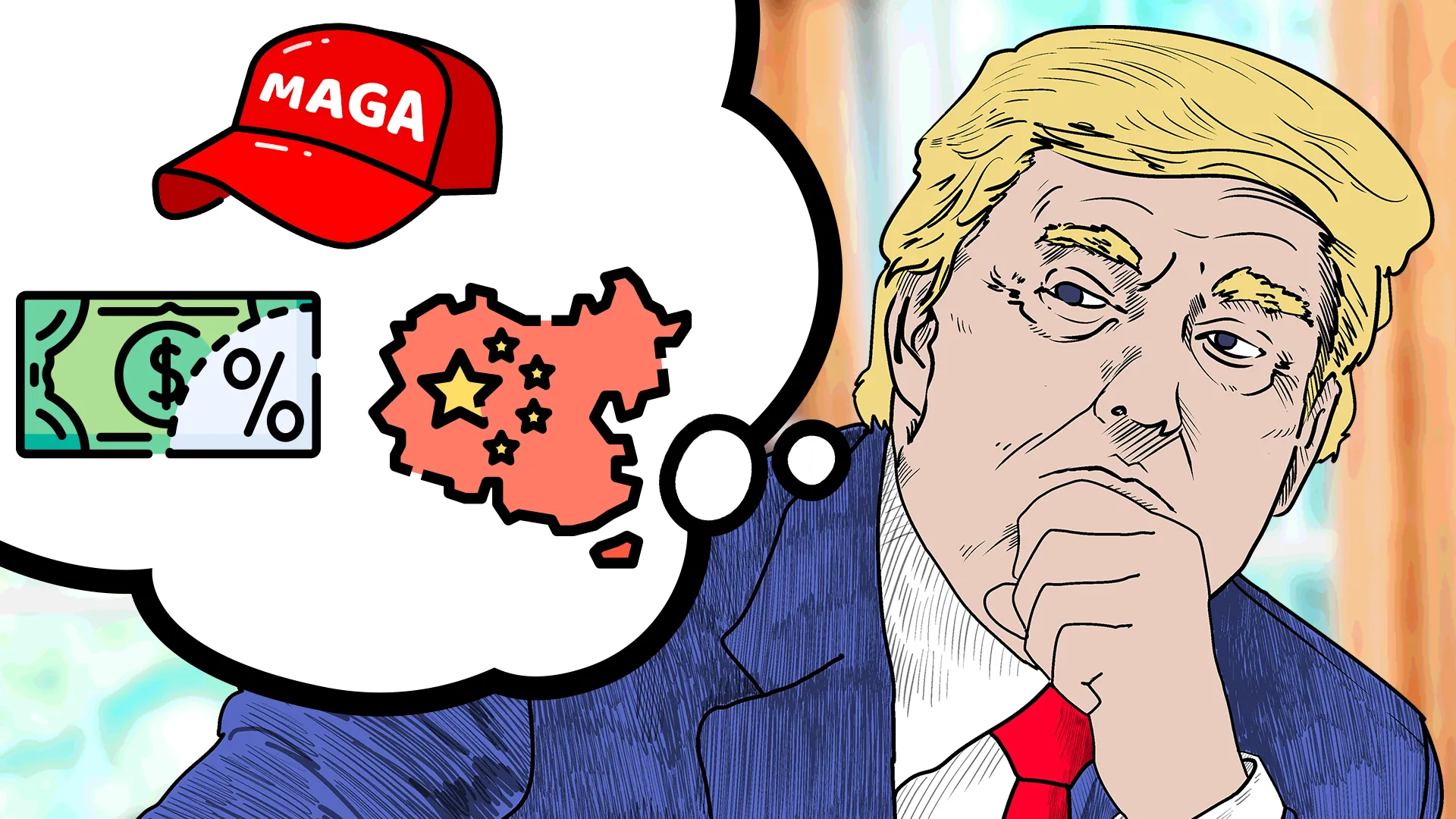日本が相対すべき「トランプ主義」とは何か

ドナルド・トランプ(Donald Trump)の大統領再就任が近づいている。大統領本人の奇矯で攻撃的な言動は相変わらずだが、閣僚や補佐官といった政権の主要ポストを「大人たち」と呼ばれた経験豊かな…(以下、本文に続きます)
新しい政策的立場なのか
ドナルド・トランプ(Donald Trump)の大統領再就任が近づいている。大統領本人の奇矯で攻撃的な言動は相変わらずだが、閣僚や補佐官といった政権の主要ポストを「大人たち」と呼ばれた経験豊かな人々が占めた第一期政権とは異なり、第二期政権ではトランプの言動に熱烈に共鳴する人物が重要閣僚や補佐官に指名されている。
トランプの再登場と彼に共鳴する人物が多く政権入りすることは、アメリカの民主主義に何をもたらすのだろうか。彼の政策や政治的立場は、しばしば「トランプ主義(Trumpism)」と表現されるが、その内実は意外に曖昧である。以下では、トランプ主義とはどのような政治的立場なのか、それが民主主義といかなる関係にあるのか、日本はどう対応すべきかを考えたい。
大統領選挙中にトランプが具体的に訴えた政策としては、メキシコとの国境封鎖など移民政策の厳格化、中国をはじめとするアメリカの競争相手国に対する関税の大幅引き上げ、国内における石油開発の推進と気候変動対策の緩和、第一期政権で実現させた大規模所得減税の恒久化、ウクライナ支援継続への消極姿勢、中東でのイスラエル支援の強化などであった。人工妊娠中絶については、連邦政府が禁止すべきという一部の保守派の主張を退け、各州の判断に委ねる姿勢を示していた。
これらを敷衍して考えると、トランプの政策は次のような基本的特徴を持つことが分かる。すなわち、対外経済面では厳格な移民政策や高関税政策により人と物の国際的な流れを弱める典型的な保護主義である一方、国内では総じて社会経済活動への政府の関与を縮小する「小さな政府」論の系譜の上にある。国際関係において正統性や人道の観点を重視せず、強者による弱者の支配を容認して戦争を終わらせる没理想の現実主義である。日本を含めた同盟国に対しても短期的視点からの自国優先主義を貫徹し、もっぱら二国間交渉を通じて、従来の経緯や枠組みを度外視した自主防衛努力の強化などを求めるであろう。
対外的な保護主義や理想なき現実主義、自国優先主義、国内での「小さな政府」を追求する自由放任主義や州権の重視は、南北戦争(1861-65年)終結後の産業革命期には、共和党が主導しながらほぼ一貫して取られていた政策であった。トランプ主義という言葉が彼の政策的立場に新規性があることを含意しているのだとすれば、それは不正確である。
核心は民意への応答
19世紀後半の産業革命期には、人心の拝金主義傾向が目立つとともに、貧富の格差も拡大した。政治社会学者のロバート・パットナム(Robert David Putnam)らは、この時代と今日のアメリカ社会が多くの点で共通しており、共同体ではなく狭小な自己利益を優先させがちであることを指摘する(『上昇(アップスウィング)』)。当時は移民が大規模に流入していたが、移民は労働者としても消費者としても経済成長の原動力となる一方で、社会不安や政治腐敗の原因だと見なされていた。
社会の動きとの整合性は、トランプと民主主義の関係を考える上で無視できない。政治家が人々の意識や期待に応じた政策を取るのが民主主義の存在意義の一つだと考えれば、彼が先に述べたような政策を唱えるのは、それ自体が非民主主義的だとはいえない。彼は何よりも、政策としての整合性や効果は疑わしいが、それを無視して敵を作り出しつつ有権者の歓心をひたすら買うポピュリストなのである。
そう考えると、トランプが再び大統領になることで、アメリカや世界の民主主義が直接的に危機に直面するといった見方は、単純には受け入れがたい。19世紀後半のアメリカ政治の場合、ポピュリストの台頭は政治改革や社会改革の原動力となった。紆余曲折を経つつも、その後のアメリカは民主主義を国内的に深化させ、世界的に拡大する上でも大きな役割を果たした。先に言及したパットナムらは、1960年代までのアメリカは次第に自国内における他者の存在や境遇に意を用いる社会になり、それが民主主義を強めたと指摘する。
問題は、アメリカの有権者の間に、20世紀前半に生じたような個人指向から共同体指向への反転の兆しが見られないことである。連邦議会での二大政党間の対立の強まりから始まった分極化は、今日では無党派層を含む一般有権者にまで広がり、自らが支持しない政党を支持する他人への不信や低評価を伴った「感情的分極化(affective polarization)」が生じている。
その背景には、国としての繁栄が個々人の豊かさに結びつかない経済的要因、伝統的価値観の強調やキャンセルカルチャーへの相互反発といった社会文化的要因、SNSを通じたフェイクニュースの横行などの情報的要因が、複雑に絡み合っている。感情的分極化が続けば他者への共感や協力を強めることは困難であり、それがアメリカの民主主義に悪影響を与えることが懸念される。
もう一つのリスクは、政治的な多元性が弱まることである。第一期トランプ政権による判事指名により連邦最高裁の保守派優位は強まったが、その背景には共和党のイデオロギー的結束があった。かつて多様な考え方の個人や集団が共存していたアメリカの二大政党は、今日では党内の同質性を著しく強めている。アメリカ社会の多様性や多元性は低下していないため、政党は社会と政治をつなぐ回路として機能していない状況にある。
多元性はオルタナティブ(政策の大きな方向性についての代替的選択肢)を準備し、民主主義の破綻を防ぐ存在である。19世紀末から20世紀初頭のアメリカの諸改革は、二大政党から従来とは異なる政策路線を模索する動きが出現し、それに支えられた面があった。現状ではこの点も決して楽観できない。社会的多元性を政治に媒介する機能を政党が再び担えるかどうかが、今後のアメリカにとって大きな意味を持つだろう。
日本はどう向き合うべきか
大統領選挙と連邦議会選挙で勝利を収め、両院多数党を含めて共和党が確保した状態、いわゆる「トリプルレッド」として第二期トランプ政権は発足する。そのため、一見したところ政権は強力そうだが、実際には2つの大きな制約がある。
1つには、連邦議会における共和党多数の存続期間は、恐らく2年間に限定されることだ。分極化が強まったオバマ政権以降、すべての大統領は就任2年後の中間選挙で議会多数党を失った。トリプルレッドの2年間に共和党が自らのアジェンダを推進すれば、減税と高関税の組み合わせがインフレを昂進させるなどにより、今回の勝利の原動力だった非富裕層の離反を招くことは想像に難くない。第二期トランプ政権も、2026年中間選挙で議会(恐らくは下院)の多数党を失うと予想される。
もう1つには、政治家としてのトランプがポピュリストなのであれば、有権者の支持を失いかねない政策の展開には躊躇する可能性は小さくない。それは、外交においてウクライナ問題への関与の継続などを妨げるが、内政では先鋭的な保守派も多い議会共和党との対立につながる。政権内をどれだけ忠誠心の高い人物で固めようとも、またイーロン・マスク(Elon Musk)のように強い個性を持った人物の進言であっても、議会での多数派が確保できないとき、大統領が行使できる政策的な影響力は大きく制約される。
中間選挙で議会における勢力が後退すれば、現在はトランプの考え方や言動に同調する傾向が強い共和党内で、異論が強まることも考えられる。アメリカの政治制度は権力分立を根幹に据えて、同じように有権者の信任を受けていても、大統領と議会が異なる立場をとることを本来的に想定している。試行錯誤を繰り返しつつも、それがアメリカの民主主義体制を長く存続させてきた大きな要因であった。
また、合衆国憲法修正第22条により、第二期トランプ政権は4年を超えて続くことはない。トリプルレッドが2年で終わるとすれば、中間選挙後には急速にレイムダック化する可能性の方が大きいであろう。ただしその場合、政権側の自由度が高い外交・安全保障政策での遺産を残そうと、国際関係のさらなる攪乱要因になる恐れはあり、民主主義体制やアメリカという国家に対する国際的な信頼が低下することも想定される。
したがって、日本が第二期トランプ政権に相対するに際しては、トランプ主義という特異な政策的立場が明瞭に存在するわけではなく、あくまで政権と議会共和党の立場が一致する範囲で、主に当初の2年間に限り従来の常識とは異なる、しかし歴史的には先例のある政策が打ち出されると考える方が良い。また、トランプの人格が権威主義的だとしても、政治家としてはポピュリストであって、世論を無視して憲法体制を崩壊させるようなことにはつながらない。社会の多元性が維持される限り、中長期的にはアメリカという国家の基本的性格は変わらないと見ておくべきだろう。
アレクシ・ド・トクヴィル(Alexis de Tocqueville)が訪れた時代から、アメリカは世界の民主主義にとっての壮大な実験場であり続けてきた。その歴史が教えるのは、民主主義には完成型や最終型はなく、不断にそれに挑戦する動きや応答としての自己改革が繰り返されることだ。現在のアメリカは、またもそのような挑戦を受けているのであり、今回の挑戦に応答できないと考える理由は乏しい。トランプ政権からの要求を日米同盟に対する内省や自己点検の機会と捉えつつ、恐らく2年後に始まるアメリカ政治の「次の局面」に備え、共和党内のトランプとは距離を置く政治家、そして民主党との関係も維持しておくことは、日本にとって不可欠である。
(Photo Credit: ロイター/アフロ)

待鳥 聡史(京都大学法学部教授)
1971年生まれ。京都大学法学部卒業。京都大学大学院法学研究科博士後期課程(政治学専攻)中途退学。京都大学博士(法学)。大阪大学助教授などを経て、2024年12月現在は京都大学法学部教授。専攻は比較政治論。著書に『首相政治の制度分析―現代日本政治の権力基盤形成』(千倉書房、サントリー学芸賞受賞)、『代議制民主主義―「民意」と「政治家」を問い直す』(中公新書)、『政党システムと政党組織』(東京大学出版会)、『アメリカ大統領制の現在』(NHKブックス)など。

地経学ブリーフィング
コロナウイルス後の国際政治と世界経済の新たな潮流の兆しをいち早く見つけ、その地政学的かつ地経学的重要性を考察し、日本の国益と戦略にとっての意味合いを精査することを目指し、アジア・パシフィック・イニシアティブ(API)のシニアフェロー・研究員を中心とする執筆陣が、週次で発信するブリーフィング・ノートです(編集長:鈴木一人
地経学研究所長、東京大学公共政策大学院教授)。
おことわり:地経学ブリーフィングに記された内容や意見は、著者の個人的見解であり、公益財団法人国際文化会館及び地経学研究所(IOG)等、著者の所属する組織の公式見解を必ずしも示すものではないことをご留意ください。
-
 Identifying choke points in the semiconductor supply chain2025.05.04
Identifying choke points in the semiconductor supply chain2025.05.04 -
 The dollar paradox: Toward a bifurcated currency order?2025.04.30
The dollar paradox: Toward a bifurcated currency order?2025.04.30 -
 The Tariff Plans Need Clarity and Credibility if They’re Going to Work2025.04.15
The Tariff Plans Need Clarity and Credibility if They’re Going to Work2025.04.15 -
 Is China overproducing highly qualified talent?2025.04.11
Is China overproducing highly qualified talent?2025.04.11 -
 India in a Tariff-ied World2025.04.11
India in a Tariff-ied World2025.04.11
 The Tariff Plans Need Clarity and Credibility if They’re Going to Work2025.04.15
The Tariff Plans Need Clarity and Credibility if They’re Going to Work2025.04.15 After tariffs: Is there a plan to restructure the global economic system?2025.04.03
After tariffs: Is there a plan to restructure the global economic system?2025.04.03 Navigating Uncertainty in U.S. Space Policy: Decoding Elon Musk’s Influence2025.04.09
Navigating Uncertainty in U.S. Space Policy: Decoding Elon Musk’s Influence2025.04.09 Is China overproducing highly qualified talent?2025.04.11
Is China overproducing highly qualified talent?2025.04.11 India in a <i>Tariff</i>-ied World2025.04.11
India in a <i>Tariff</i>-ied World2025.04.11