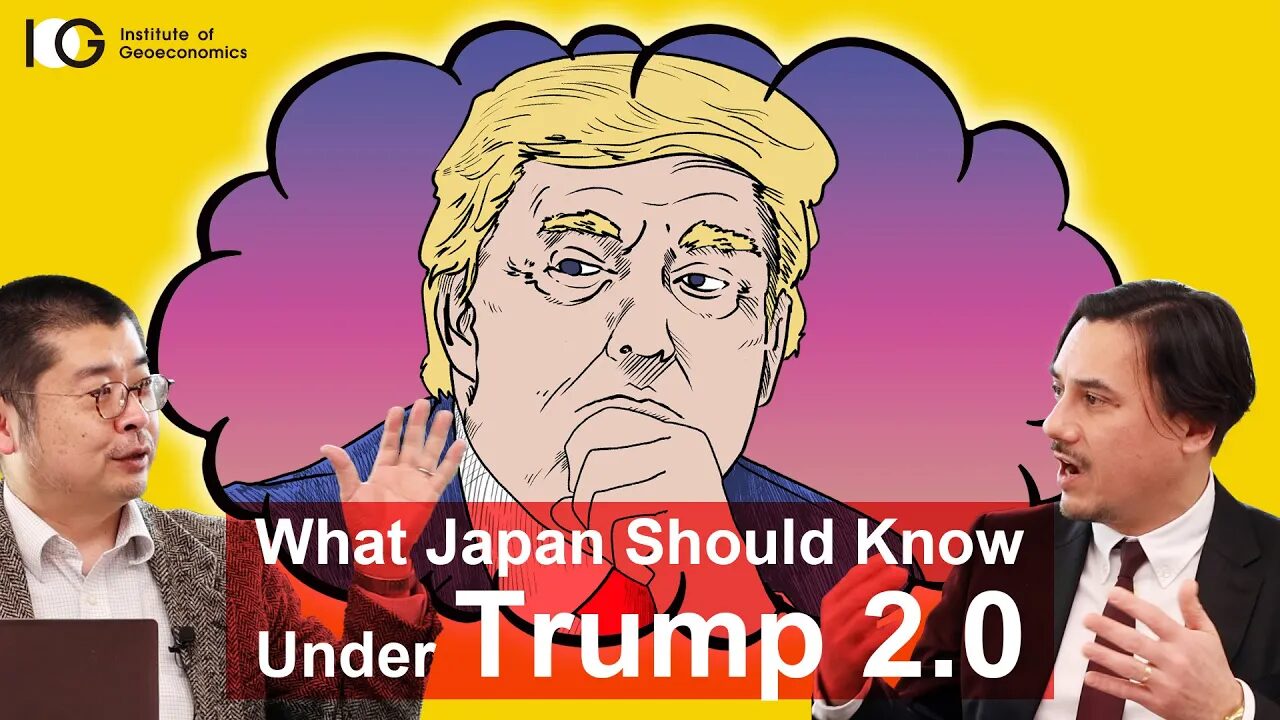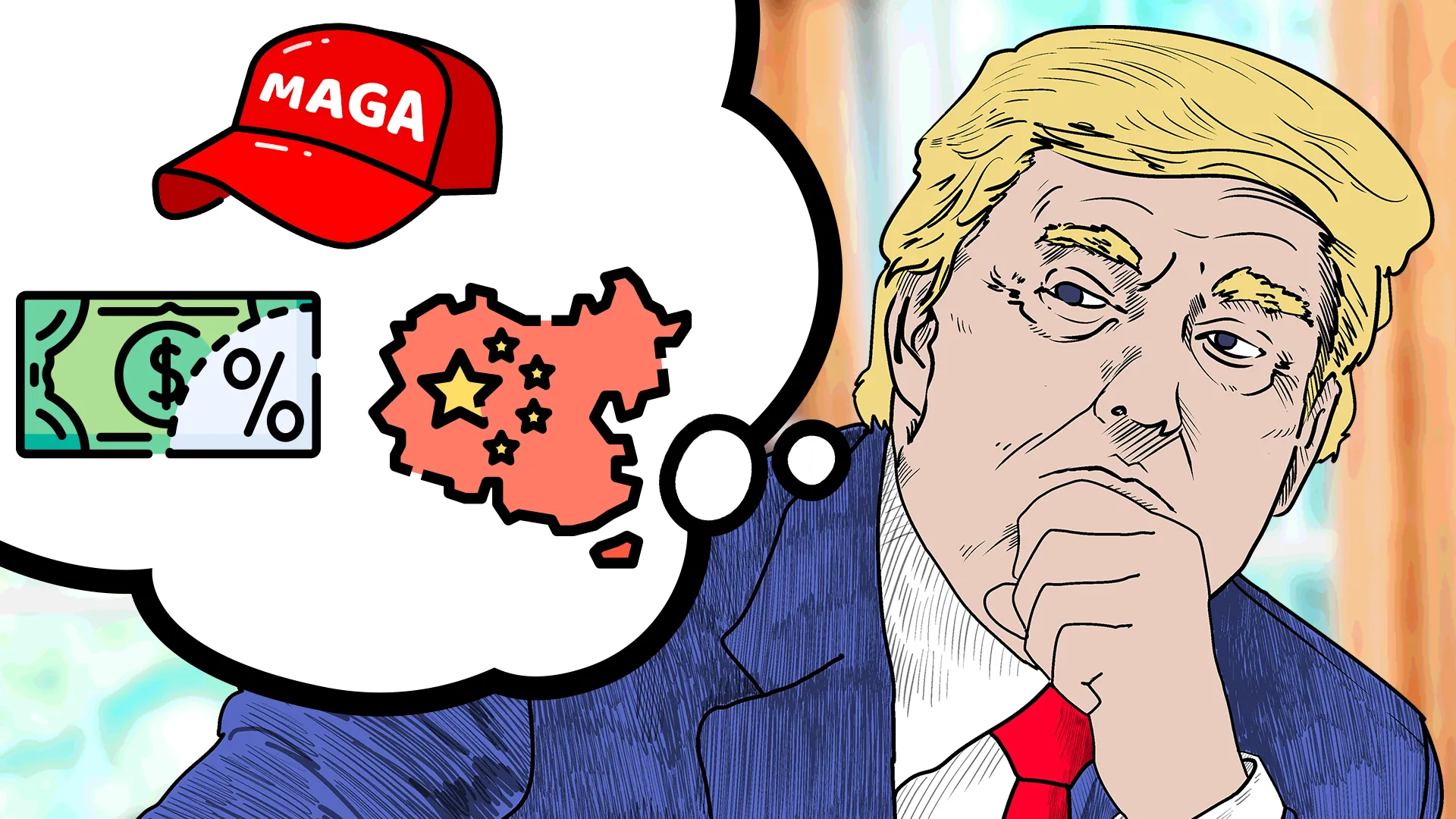米海軍が直面する戦略資源配分の課題 -核と通常戦力をめぐるディレンマ

多正面と複数任務に対応してきた歴史
米軍は2025年1月現在、事実上の三正面作戦を余儀なくされ、オペレーションの継続に苦心している。欧州戦域では長期化するウクライナ戦争とロシアとの対立があり、同時に中東ではイスラエル・ハマス間の紛争に加え流動化するシリアを含む不安定な情勢が継続する。米海軍は欧州方面でロシアに対する牽制として展開していた空母打撃群(Career Strike Group: CSG)を当面の間地中海東部など中東情勢を念頭において行動させなければならない。そして、米海軍にとっての三つ目の正面となるアジアでは、最大の競争相手である中国の海洋進出に対し長期的に対峙する必要がある。
安全保障環境が長期的に不安定化する過程で、より深刻な問題となるのは将来的なアセットの開発・調達とこれを方向付ける戦略構想である。冷戦期以来、米海軍は複数の主要任務に資源を配分することを強いられてきた。1974年に刊行された米海軍大学校長スタンフィールド・ターナー中将(Stansfield Turner)の論文「米海軍の任務」(“Missions of U.S. Navy”)では、米海軍の任務として「制海」・「プレゼンス」・「戦力投射」・「戦略抑止」の4点を示している。世界中に散在する同盟国とのネットワークを利用した前方展開とグローバルな作戦を考慮すれば、これら主要任務はターナー論文から半世紀を経た現在も本質的に不変である。しかし、多極化=相対的な米国の国力低下に伴い、将来的な開発・調達に伴うディレンマは21世紀初頭に比べ、より深刻なものとなっているだろう。
急拡大する中国のシーパワーと核戦力
近年、中国海軍は「A2/AD戦略」と呼ばれる拒否戦略によって北東アジアにおける局地的な軍事的優位(米軍の作戦行動を制約し、戦力投射を阻害する)を獲得しつつある。しかし中国の海洋軍事戦略はA2/ADだけではない。同時に外洋作戦能力(制海(sea control)能力)の向上が図られており、それは攻撃原潜(093型)や多機能レーダーを搭載したミサイル駆逐艦(Luyang II/III級)・巡洋艦(Renhai級)などからなる。現時点で就役中の空母は遼寧(Liaoning)、山東(Shandong)ともカタパルトを有していない。搭載機の戦闘行動半径あるいはペイロードに制限があるため、大規模な対地攻撃(戦力投射)能力はなく、また大型の早期警戒機なども運用できない。しかし現在試験中の福建(Fujian)あるいは新型の強襲揚陸艦(076型)などは電磁カタパルトを装備しており、これらのアセットが米海軍の同種艦艇と同等のパフォーマンスを獲得した場合、米海軍のCSGに匹敵する制海、戦力投射能力を獲得する可能性がある。
加えて中国戦略ロケット軍の質量両面における急速な核戦力の増強に対応するため、核オプションの近代化更新と拡充も深刻な問題となっている。冷戦後米国の核戦力は、いわゆる「核の三本柱」(Nuclear Triad)と呼ばれる戦略核戦力(ミニットマンICBM、戦略原潜搭載トライデントSLBMそしてB-2/B-52戦略爆撃機搭載の巡航ミサイル)に特化してきた。オバマ政権が戦術核トマホークを2010年に退役させた後、非戦略核は少数の低出力核(Low Yield Nuclear)トライデントミサイルと、欧州における核共有のために保有する自由落下型爆弾(gravity bomb: B-61)が存在するのみである。現状、ロシアに対してNATOは通常戦力において圧倒的な優位にある。仮にロシアがウクライナで戦術核の限定使用に踏み切ったとしてもNATOは通常戦力で相応の報復が可能である(そしてこのことが予見されるため、ロシアが核の限定使用を決断することは極めて困難である)が、通常戦力で局地的に優位に立とうとする中国に対し、このスタンスは成立しない。よって米国がエスカレーション・ラダーの欠落部分を埋め、戦略的安定と抑止の機能を確実なものとするためには戦略核に加え、中国軍が保有・開発を進めるDF-21/26中距離弾道ミサイル(対地・対艦)、あるいは極超音速飛翔体(HGV)搭載可能とされるDF-17といった非戦略核に対応し得るオプションを準備しなければならない。
米海軍が直面する3つのニーズ
したがって米海軍は今後通常戦力を主体としつつ、核オプションを含む3つの能力を維持・向上する必要がある。すなわち中国の濃密なA2/AD戦力に対抗し、第一列島線周辺海域より中に斬り込んでいく①「カウンターA2/AD」、グローバルに展開する中国の大型水上艦艇部隊を制する②「制海」、そして③「戦略/非戦略核戦力」である。
①は相手の脅威下で残存し、作戦行動することが求められ、インサイドフォースとも呼ばれる。それはF-35などステルス性に優れる先進的な航空アセットと潜水艦、そして各種無人アセットが中心となる。特に無人アセットは質的な面だけでなくコスト面や量的な拡大が問題となるだろう。米海軍では「分散海洋作戦」(Distributed Maritime Operation: DMO)と呼ばれるコンセプトに基づき、これらの開発に所要の投資がなされている。
②はCSGと遠征打撃群(ESG)といったある種レガシーで自己完結的な海軍力である。これらは地上航空/ミサイル戦力の援護が期待できない外洋や敵の威力圏内で作戦遂行するため、今後も主要な海洋戦力を構成する。CSG、ESGを構成するアセットは空母・強襲揚陸艦に加え、これらを護衛するミサイル駆逐艦/巡洋艦、そして水上部隊の前方で哨戒にあたる攻撃原潜である。レガシー、とはいうものの、サイバー・電磁領域・戦闘システム等の近代化で高コスト化が進む。
③核戦力については老朽化する戦略核アセットの更新、海軍関連であればオハイオ級の代替更新であるコロンビア級戦略原潜が中心となるが、2035年に初期作戦能力(IOC)獲得を目指して開発が開始された潜水艦発射型核巡航ミサイル(Submarine Launch Cruise Missile Nuclear: SLCM-N)発射プラットフォームの建造も重要となる。
この3つを同時に、かつ十分に達成することは容易ではない。①に関わる新しいアセットは今後開発・試験段階を経て実装へと進む過程で大きな財源を必要とするが、その必要財源とリソースは現時点で非常に不透明であり、本論では議論の対象としていない。一方、現時点ですでに②と③の間で大きなコンフリクトが顕在化している。
熟練工不足、コスト上昇とサプライチェーンの不安定化といった要因により、オハイオ級退役に合わせ2027年に就役予定であったコロンビア級戦略原潜の1番艦建造は12か月から16か月遅延しているとされ、同様に2014~2018会計年度に調達が決まったヴァージニア級(ブロックⅣ)攻撃原潜は予定よりも36か月も遅延している。水上艦についても同様であり、最重要アセットともいえる原子力空母(エンタープライズ: CVN-80)の建造についても18か月から26か月の遅延が見込まれ、他の主要水上艦艇についても建造ペースは要求水準に及ばない。
こうした調達ベースの遅延に加え、ミッションの多様化という問題がある。前述のヴァージニア級攻撃原潜は最新のブロックⅤ以降、ヴァージニア・ペイロード・モジュール(Virginia Payload Module: VPM)と呼ばれる垂直発射装置を搭載する。VPM搭載のヴァージニア級攻撃原潜は20隻建造が計画され、1隻あたり28発の巡航ミサイルを搭載する。これによって現在1隻あたり154発のトマホーク巡航ミサイルを搭載する、オハイオ級巡航ミサイル原潜4隻の退役を埋め合わせる予定である。これは将来的にSLCM-Nも搭載するため、通常戦力の投射だけでなく核オプションのプラットフォームとしても重要なアセットとなる。
第二期トランプ政権における喫緊の課題
米海軍が平時に実施するオペレーションの大半はCSG・ESGなど通常戦力によっている。しかしこれらの根幹となる空母、大型水上艦艇や攻撃原潜などの建造は遅延し、ヴァージニア級攻撃原潜については将来的に核を含む戦力投射(対地攻撃)ミッションにも振り向けなければならず、空母の護衛や敵戦略原潜の追尾・監視といった本来任務に穴を開けかねない。そして長期間にわたる戦略原潜の建造は、需要に追い付かない造船サプライヤーのリソースをさらに削り取ることになる。有限のリソースを通常戦力と核アセットにそれぞれどれだけ振り向けるべきなのか、海軍だけではなく戦略軍にとっても悩ましい問題である。
折しも第二期トランプ政権のヘグセス(Pete Hegseth)国防長官は任命に先立つ上院公聴会において、核戦力の増強や第6世代戦闘機プロジェクトと合わせ、「米海軍「355隻艦隊」確立に向け、米国の造船能力(回復)は国家安全保障上喫緊の優先順位にある」と述べている。とはいえ老朽化した造船インフラと人的リソースの回復は一朝一夕にできるものではない。
このような状況を見るに、今後米海軍のアセット不足が直ちに解消する公算は低い。エルブリッジ・コルビー(Elbridge Colby)国防次官などは就任前から同盟国に対する防衛予算増額に関して発言しているが、それは単に「応分の責任を果たせ」という政治的姿勢に加え、こうした背景があることも理解しておく必要がある。
一方で中長期的にみれば、米国の造船能力補完に際し日米が艦船建造を協力する枠組みを構築することで、現下の情勢は同盟をより実効的に深化させる契機ともなり得る。そしてこれは、長期にわたって縮小統合を繰り返してきた日本造船業界の艦船建造部門エコシステムを再び活性化させる可能性を含んでいる。
(Photo Credit: US Navy)

後瀉 桂太郎
海上自衛隊幹部学校 主任研究開発官 1等海佐。 練習艦隊司令部、護衛艦みねゆき航海長、護衛艦あたご航海長、海上自衛隊幹部学校研究部員、防衛省海上幕僚監部防衛課勤務(内閣府 総合海洋政策推進事務局出向)、統合幕僚学校主任研究官などを経て2023年3月より現職。 1997年防衛大学校国際関係学科卒業、2017年政策研究大学院大学 安全保障・国際問題プログラム博士課程修了、博士(国際関係論)。2018年オーストラリア海軍シーパワーセンター/ニューサウスウェールズ大学キャンベラ校客員研究員。著書に『海洋戦略論 大国は海でどのように戦うのか』(勁草書房、2019年)がある。

地経学ブリーフィング
コロナウイルス後の国際政治と世界経済の新たな潮流の兆しをいち早く見つけ、その地政学的かつ地経学的重要性を考察し、日本の国益と戦略にとっての意味合いを精査することを目指し、アジア・パシフィック・イニシアティブ(API)のシニアフェロー・研究員を中心とする執筆陣が、週次で発信するブリーフィング・ノートです(編集長:鈴木一人 地経学研究所長、東京大学公共政策大学院教授)。
おことわり:地経学ブリーフィングに記された内容や意見は、著者の個人的見解であり、公益財団法人国際文化会館及び地経学研究所(IOG)等、著者の所属する組織の公式見解を必ずしも示すものではないことをご留意ください。
-
 The Tariff Plans Need Clarity and Credibility if They’re Going to Work2025.04.15
The Tariff Plans Need Clarity and Credibility if They’re Going to Work2025.04.15 -
 Is China overproducing highly qualified talent?2025.04.11
Is China overproducing highly qualified talent?2025.04.11 -
 India in a Tariff-ied World2025.04.11
India in a Tariff-ied World2025.04.11 -
 Can the Trump Administration Address the U.S. Military’s Multi-Front Resource Dispersion?2025.04.11
Can the Trump Administration Address the U.S. Military’s Multi-Front Resource Dispersion?2025.04.11 -
 Why deploying U.S. Army in the Middle East can strengthen deterrence in the Western Pacific2025.04.09
Why deploying U.S. Army in the Middle East can strengthen deterrence in the Western Pacific2025.04.09
 The Tariff Plans Need Clarity and Credibility if They’re Going to Work2025.04.15
The Tariff Plans Need Clarity and Credibility if They’re Going to Work2025.04.15 After tariffs: Is there a plan to restructure the global economic system?2025.04.03
After tariffs: Is there a plan to restructure the global economic system?2025.04.03 Navigating Uncertainty in U.S. Space Policy: Decoding Elon Musk’s Influence2025.04.09
Navigating Uncertainty in U.S. Space Policy: Decoding Elon Musk’s Influence2025.04.09 Is China overproducing highly qualified talent?2025.04.11
Is China overproducing highly qualified talent?2025.04.11 India in a <i>Tariff</i>-ied World2025.04.11
India in a <i>Tariff</i>-ied World2025.04.11