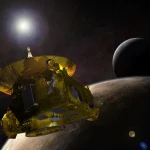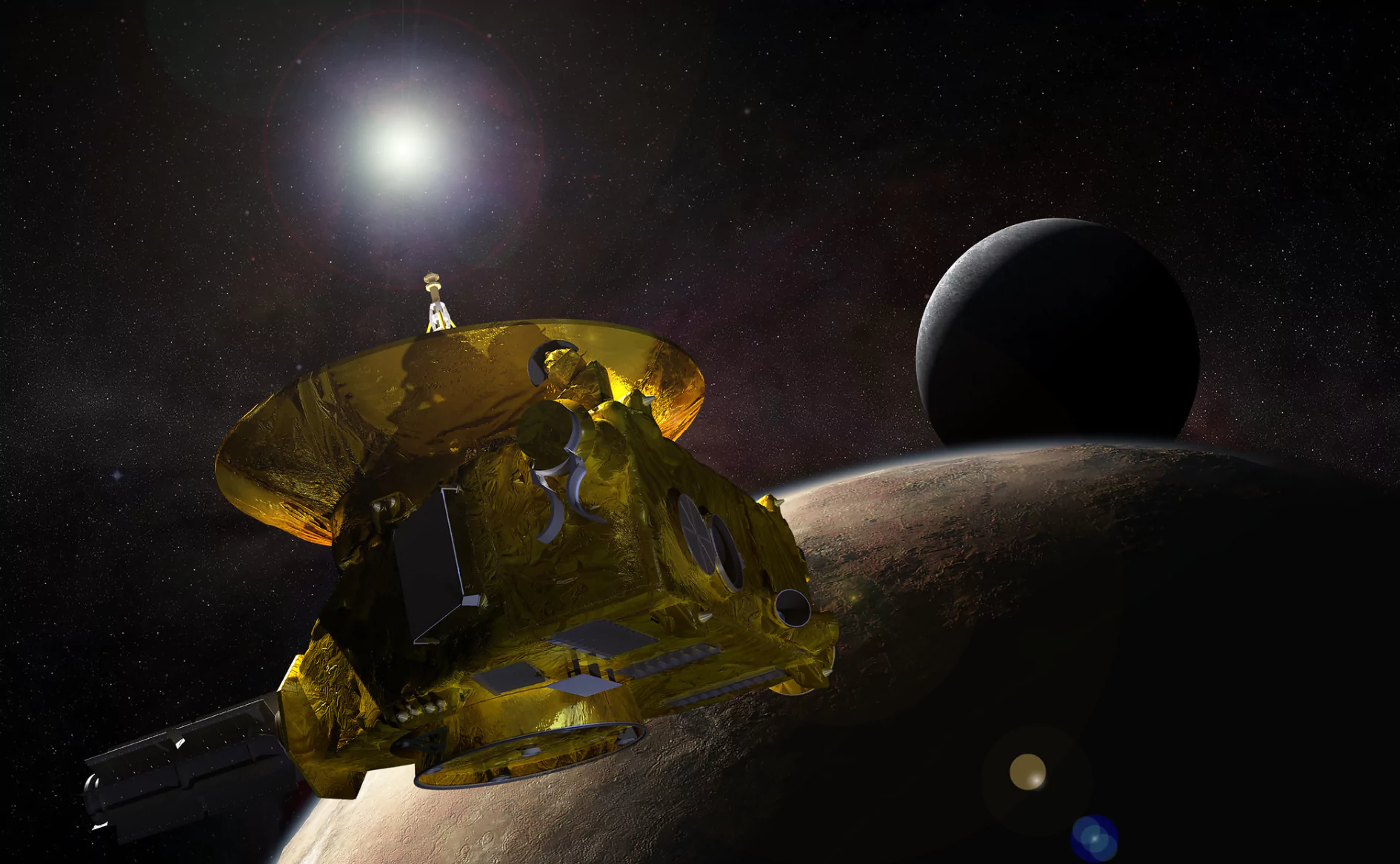第二次トランプ政権期の韓米関係 ――「未来志向の包括的戦略同盟」へ向けて――

2025年1月の発足以来、第二次トランプ政権は全面的な関税戦争を展開している。トランプ大統領が二国間主義を強く好むことは第一次政権の初期から広く知られていたが、第二次政権の特徴は、複数の国と同時に交渉を進める「並行的二国間主義」を追求している点にある。
この戦略を実行するため、トランプ政権はまず一国に対して最大限の圧力をかけて迅速に合意を取り付け、その成果を次の交渉の基準とする手法を採用した。その結果、米国は1関税を15%に引き下げる譲歩をしたにもかかわらず、EU(欧州連合)などの主要貿易相手国から6000億ドル規模の投資パッケージと防衛費増額の約束を引き出し、実質的に大きな成果を得ることに成功した。
首脳会談への険しい道のり
韓国は、2024年12月以降の非常戒厳の発令およびその後の大統領弾劾によって予期せぬ政治的混乱期に入った。当初、韓国政府の交渉戦略は、米韓自由貿易協定(KORUS FTA)の恩恵を維持することにあった。しかし、トランプ政権がいかなる例外も認めなかったため、この方針が功を奏することはなかった。さらに、当時野党であった「共に民主党(Minjoo Party、現与党)」は、拙速な妥協による過度な譲歩を行わないよう政府に警告した。
こうした政治情勢が政策決定の自由を大きく制限したため、韓国政府は新政権に合わせて状況を調整する戦略へと転換した。2025年6月3日の大統領選挙で李在明(イ・ジェミョン)大統領が当選した後、韓国はようやく8月25日に米国との首脳会談を開催することができた。これは、日米首脳会談から半年以上遅れての実現であった。韓国政府は、EUや日本に劣らぬ条件を確保することを目指し、自動車を含む主要輸出品の関税率を15%に引き下げることに焦点を当てた。NH投資証券は、関税率が25%のままであれば現代自動車(Hyundai Motor)の年間関税負担は5.1兆ウォンに達すると試算していた。
この首脳会談は、予想を上回る成果を上げたと評価された。交渉の中心は、米国が関税を15%に引き下げる代わりに、韓国が総額3500億ドルの投資を行うというものであった。その内訳には、造船分野への1500億ドルをはじめ、エネルギー、重要鉱物、バッテリー、半導体、医薬品、AI、量子コンピューティングなどへの投資が含まれていた。
首脳会談直後に米戦略国際問題研究所(CSIS)で演説した李大統領は、「もはや安全保障は米国、経済は中国という従来の方針を維持できる環境にはない」と明言し、米国側が韓国に対して持つ政策整合性に対する疑念を払拭した。また、「安全保障と経済の同盟を超え、両国関係を未来志向の包括的戦略同盟へと進化させる」と宣言した。
板挟みの現実
この首脳会談は、関税交渉における主要な障害を取り除いたかに見えた。しかし、9月4日、米移民・関税執行局(ICE)がジョージア州にある現代自動車とLGエナジーソリューションの合弁バッテリー工場を急襲し、317名の韓国人労働者を拘束するという予期せぬ事件が発生した。これにより、李政権は政治的に極めて難しい立場に追い込まれ、トランプ政権に対して大胆な譲歩を行うことが困難となった。
また、首脳会談で合意に達したと見られていた内容の細部において、韓米間の見解の相違が顕在化した。韓国政府は、投資基金の大部分を融資および融資保証とし、出資投資は約5%にとどまると想定していたが、トランプ政権は大部分を出資とすべきであると主張した。この乖離が明確になったのは、9月26日にトランプ大統領が韓国の投資資金は「前払い」になると明言した時であった。
こうしたトランプ政権の攻勢により、李政権は国内的にも困難な政治状況に直面した。企業側からは、交渉の遅れにより日本などの競合国に比べて不利になるのではないかとの懸念が表明された。世論もまた、米国が一方的に「ゴールポストを動かし続けている」との批判を強めている。
内外からの二重の圧力に直面する中で、李政権は投資パッケージをめぐる意見の相違を縮小しつつ、経済的な安全策を構築する方向で戦略を再調整した。韓国政府は、3500億ドルの投資が2024年の韓国の国内総生産(GDP)の18.7%に相当し、日本の13%を大きく上回ることを強調した。また、米国が特別目的事業体(SPV)を設立して投資案件を指定し、相手国政府が2か月の審査を経て米国の投資促進機関に資金を移すという日本型モデルの採用は困難であると主張した。
さらに、韓国政府は3500億ドル規模の対米投資が韓国のマクロ経済の安定を損なう可能性があるとして、無制限の通貨スワップ協定の締結を要請した。特に、この金額が韓国の外貨準備高の84%に相当することを指摘し、為替危機を引き起こす潜在的なリスクを強調した。
経済安全保障協力への道
関税交渉は、李政権が掲げる「国益中心の実用外交」の最初の試金石となる可能性が高い。第一に、李政権は韓米協力を外交の基軸としながらも、米国への過度な譲歩を避けるバランスの取れたアプローチをしている。米国に対しては、協力を進めるには国内の政治環境の整備が必要であるという一貫したメッセージを発し、協定をめぐる不確実性を減らすための具体的な措置を迅速に策定した。その結果、完全ではないものの一定の進展が見られた。韓国の交渉チームは現在、投資パッケージに関する了解覚書(MOU)の文言を最終調整していると報じられている。もし韓国が妥協点の確保に成功すれば、それはEUや日本とは一線を画す、対米交渉の韓国モデルを打ち立てることを意味することになる。
第二に、李政権は関税交渉を超えた経済安全保障協力への焦点移行を目指している。トランプ大統領は経済と安全保障を分離し、それぞれの分野で譲歩を引き出す交渉戦略を取っているが、韓米協力が経済と安全保障の好循環を生み出しうることも明らかである。李政権が提案した「米国造船業を再び偉大に(Make American Shipbuilding Great Again, MASGA)」構想はその代表例である。当初は韓国が米国の艦船の整備・修理・点検(MRO)および人材の教育訓練を担う形で始まるが、中長期的には米国の先進的な海軍能力の共同開発へと発展する可能性がある。これは、半導体、バッテリー、AI、量子技術、宇宙などの先端産業分野で両国協力を深化させる政策とも整合する。
第三に、李政権は日本に対して柔軟な姿勢を示している。トランプ大統領との首脳会談に向かう途中で石破首相と会談したことがその表れである。この局面において、日韓協力は極めて重要な意味を持つ。日韓関係の安定的な運営は、韓米日の三国協力の再活性化の基盤となる。また、李政権が「環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定(CPTPP)」への加盟を検討していることを踏まえ、韓日両国は21世紀型のルールに基づく国際秩序の構築に向けた協力を進めることができる。
(出典: Bloomberg / Getty Images)

Seungjoo Lee中央大学(韓国・ソウル)教授
スンジュ・リー(Seungjoo LEE)氏は、中央大学(韓国・ソウル)社会科学大学の部長であり、政治学および国際関係学の教授です。また、東アジア研究院(EAI)における「貿易・技術・変革研究センター」所長、カリフォルニア大学バークレー校のバークレーAPEC研究センター(BASC)上級研究提携者、さらに英国アラン・チューリング研究所の「新興技術・安全保障センター(CETaS)」客員フェローを務めています。
現在、同氏は首相が議長を務める「量子戦略委員会」の委員、外務省の「経済安全保障・外交諮問委員会」の委員、そして教育省傘下の「国家研究財団」審査委員長も務めています。

地経学ブリーフィング
コロナウイルス後の国際政治と世界経済の新たな潮流の兆しをいち早く見つけ、その地政学的かつ地経学的重要性を考察し、日本の国益と戦略にとっての意味合いを精査することを目指し、アジア・パシフィック・イニシアティブ(API)のシニアフェロー・研究員を中心とする執筆陣が、週次で発信するブリーフィング・ノートです(編集長:鈴木一人 地経学研究所長、東京大学公共政策大学院教授)。
おことわり:地経学ブリーフィングに記された内容や意見は、著者の個人的見解であり、公益財団法人国際文化会館及び地経学研究所(IOG)等、著者の所属する組織の公式見解を必ずしも示すものではないことをご留意ください。
-
 From Decline to Surge: The Defense Industry in the Era of Excess Demand (Executive Summary)2025.10.24
From Decline to Surge: The Defense Industry in the Era of Excess Demand (Executive Summary)2025.10.24 -
 Hungary’s Electoral System: Constructing a System Favorable to the Governing Party and Its Future Prospects2025.10.20
Hungary’s Electoral System: Constructing a System Favorable to the Governing Party and Its Future Prospects2025.10.20 -
 US-China Misperceptions in the Race for Strategic Autonomy2025.10.17
US-China Misperceptions in the Race for Strategic Autonomy2025.10.17 -
 Navigating Uncertainty: India’s Quiet Strategic Moves2025.10.15
Navigating Uncertainty: India’s Quiet Strategic Moves2025.10.15 -
 Trump’s Tariff Policy through a Geoeconomic Perspective2025.10.10
Trump’s Tariff Policy through a Geoeconomic Perspective2025.10.10
 Event Report: Nuclear Weapons, Eighty Years After the War and the Atomic Bombings2025.09.25
Event Report: Nuclear Weapons, Eighty Years After the War and the Atomic Bombings2025.09.25 What Comes Next after the Supreme Court Rules on IEEPA?2025.10.02
What Comes Next after the Supreme Court Rules on IEEPA?2025.10.02 Trump and America’s tech giants: Coexistence or collaboration?2025.10.03
Trump and America’s tech giants: Coexistence or collaboration?2025.10.03 A Looming Crisis in U.S. Science and Technology: The Case of NASA’s Science Budget2025.10.08
A Looming Crisis in U.S. Science and Technology: The Case of NASA’s Science Budget2025.10.08 US-China Trade and the "Great Rebalancing"2025.09.19
US-China Trade and the "Great Rebalancing"2025.09.19