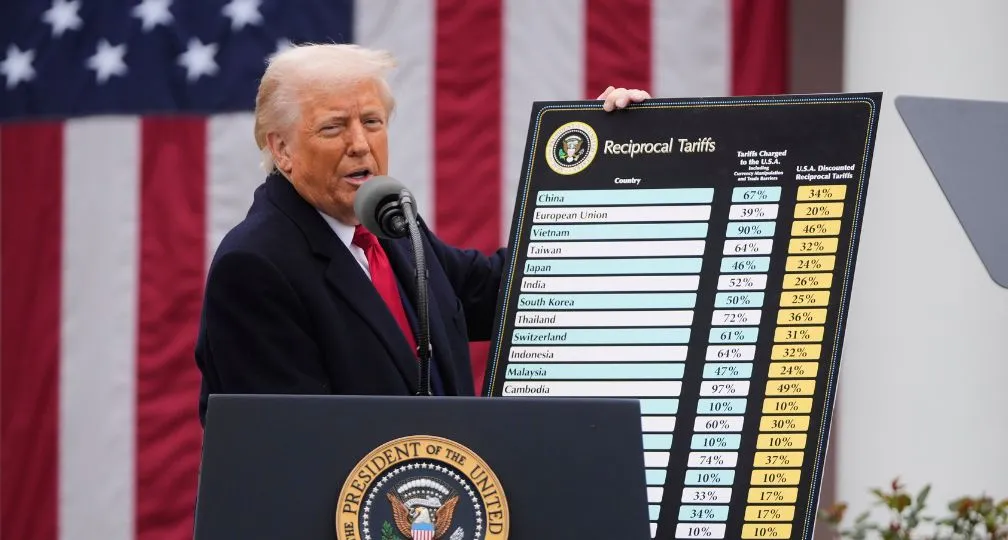低空飛行する中国経済は「低空経済」で再び舞い上がれるのか

だが、中国の産業政策と警戒されているものの中には、中国政府が以前から行ってきた政策が、中国の経済成長とともに注目され、問題視されるようになった側面もある。中国経済が不振に苦しむなか、習近平政権はどのように産業政策を使おうとしているのか。中国政府が最近推し進めている「低空経済」に注目して考えてみたい。
「中国の特色ある産業政策」
「産業政策」は様々な意味で使われるが、ここでは、政府が特定の国内産業の発展を目的として税制優遇や財政援助などの介入を行い、企業を支援するものとする。中国政府は、2005年に「科学技術発展中長期計画綱要(2006-2020)」を策定して以降、2010年に第12次5カ年計画、2015年には「中国製造2025」を制定し、戦略的に重要な産業を指定して、税の減免や補助金の提供といった支援を行ってきた。特に「中国製造2025」は、中国が世界の最先端産業の支配を狙う計画とも警戒されたが、ここに挙げられた重点産業は、2005年の「綱要」にある重点産業と重なるものが多い。中国は、産業の先進化を突然始めたのでなく、長期的取組として製造業の発展を支援してきている。
このような産業政策はすべてが成功してきた訳ではない。例えば、中国政府は半導体産業に多額の補助金や投資基金を拠出してきたが、2021年に紫光集団(UNIS)が経営破綻したように、政府の支援があっても経営が成り立たない企業も多く、国産化率も目標に達していない。しかし、車載電池で世界最大のシェアを持つ寧徳時代(CATL)や、世界第一のディスプレイパネルメーカーの京東方(BOE)など、世界的な中国メーカーの多くが外国企業の先進的技術を利用し、政府の補助金を得て研究開発を進め、経営面でも補助金に助けられ成長した。
中国の産業政策は、特定の産業に優遇策を出して多くの企業を参加させ、市場での競争を通じて競争力のある企業が残るのを待ち、生き残った企業に更なる支援を与えて国際的な競争力を持たせてきた。これは「中国の特色ある産業政策」と言うことができ、競争の過程では淘汰される企業もあるが、補助金により競争力のないまま生き残るゾンビ企業も出る。また、過当競争により過剰生産のような問題も起きるが、中国市場の大きさがこれら問題を吸収してきた。中国政府は、費用対効果などを厳しく問われずに企業に支援を行えるので、特定の重点分野に継続的に支出し、多くの企業を市場で競争させることで強い企業を生み出してきた。
【中国の重点産業の変遷】

「低空経済」推しを始めた習近平政権
習近平政権が新しく重要産業に追加したのが「低空経済(low-altitude economy)」である。この耳慣れない産業は、低空空域(中国では一般に高度1,000メートル以下)において、民用機や無人機などを使って展開される様々なビジネスの総称とされる。例えば、広東省深圳市では、出前アプリを使って料理を注文すると、ドローンで配達されるサービスが始まっている。また、深圳市から海を隔てた対岸の珠海市まで人を運ぶ「空飛ぶタクシー」の運用に向けた準備が進んでいる他、ドローンを使った農薬の散布などが行われている地方もある。
中国では空域管理が厳しく、低空空域を利用したビジネスはあまり発展しなかったが、2021年2月に次世代交通のあり方の1つとして「低空経済」が国の計画に盛り込まれ、重視され始めた。2023年12月の中央経済工作会議は、「戦略性新興産業」にバイオや商用衛星と並んで「低空経済」を追加し、2024年3月の全人代における政府活動報告も「低空経済」を積極的に発展させていく旨明記した。厳格なコロナ対策や不動産市場の低迷などの影響により中国経済が低空飛行するなか、中国政府は「低空経済」により景気を回復させ、新しい産業を発展させようとしている。
地方政府も競って「低空経済」を政策に取り入れ、各種支援策を取り始めた。2023年の活動報告に「低空経済」に言及した省レベルの地方政府は16に過ぎなかったが、2024年には、全国に31ある省レベルの地方政府のうち29の地方が「低空経済」の発展を語った。また、湖南省が研究開発投資や低空での航空旅行などに補助金を拠出したり、黒龍江省が飛行機材や電池システムへの研究開発に投資する企業に最大50%の出資をしたりするなど、地方政府が次々と支援策を打ち出している。
「低空経済」に託された思惑
習近平政権が「低空経済」を重要産業として支援する背景には、まず、「低空経済」がもたらす経済的効果の広さがある。「低空経済」を担うヘリコプターやドローンを始めとするeVTOL(電動垂直離着陸機)は、エンジンやバッテリーなど数多くの部品から造られ、自動車と同様に裾野の広い産業である。「低空経済」によりドローンなどの活用が進むことで、機材や部品にかかわる数多くの企業に経済効果を及ぼすことができる。
また、「低空経済」にはヘリコプター観光や小型機の操縦、無人機によるインフラの保守点検等、低空空域を使った様々な活動が含まれる。創意工夫により、ドローンやヘリコプターを活用した新しいビジネスの可能性もある。「低空経済」は、これまで使われていなかった低空空域を利用した人の移動や商品の運送を可能とし、交通や運輸を含め、幅広い産業の発展を促すことが出来る。そして、それに伴って新たな労働需要も生まれる。
もちろん、ドローンや無人機といった「低空経済」に使われる航空機やこれに関連する技術が、軍事活動にも転用可能であることも、中国がこの産業を重視する背景にはある。
「低空経済」で争う国際的影響力
「低空経済」は中国が世界で先行している分野であることも重要だ。特に、広東省深圳市にあるメーカーである大疆創新(DJI)のドローンは、低価格で高い性能を誇り、世界の7割とも言われる高いシェアを持っている。空飛ぶ自動車やeVTOLにおいても中国メーカーが積極的に開発を進め、実装実験なども進めている。中国としては、先行分野で中国企業を支援して先端技術の開発を進め、国際市場での主導的地位を築こうとしている。
また、eVTOLやヘリコプターは、世界的に今後の成長が見込まれている有望産業である。自動運転や「空飛ぶタクシー」の開発を見据え、安全性や操縦・運航などに関する国際的な規格標準の議論も始まっている。中国メーカーが先行してシェアを拡大し、世界市場をリードすることで、中国の技術標準を国際標準にしたいという思惑もあるだろう。
さらに、「低空経済」は曖昧な概念なので、低空空域を使った何らかの事業が進めば成功例とできる。習近平政権は中国の言説が国際社会で影響力を持つという「話語権」を重視しており、「低空経済」を発展させ宣伝することで、中国は世界に自らの成功の物語を発信できる。
日本の強みを生かした対応を
中国は1990年代から自動車産業を重視してきたが、ガソリン車では世界に追いつけないと見るや、EVの開発を支援して国内で競争させ、比亜迪(BYD)などの国際的競争力のあるEV企業を誕生させた。また、ブランド力のある中国メーカーを輩出できない中、新しいデジタル分野でテンセントやアリババなどグローバル展開する中国企業が出てきた。「低空経済」を推進することで、中国は、国際的な成長産業に中国企業の参入を促し、世界の最先端に一気に躍り出ろうとしている。
もっとも、「低空経済」は成長が約束されたものではない。そもそも中国の低空空域は、カナダの3,800mや米国の5,400mに比べて低い上、軍事施設の上空などの飛行禁止区域が多く、商業用に利用できる空域が狭い。民間用飛行場やドローンなどが離発着できる場所の数が少ないというインフラ上の問題も指摘されている。また、エンジンや機体の素材などの重要な装備品は中国で製造できておらず、欧米や日本に頼っているという弱点もある。
とはいえ、eVTOLや飛行機などの航空機産業は軍事にも利用可能な、安全保障上も重要な産業である。米国では、国防総省がDJIを中国軍の協力企業と指定した他、米国内でのDJI製ドローンの使用禁止を模索する動きもある。中国も高性能なドローン及び関連部品を輸出規制の対象としており、米中間ではお互いを切り離しつつある。今後、低空空域に関するビジネスには、経済安全保障がより求められるだろう。
日本は、航空機の機材に使われる炭素繊維複合材、ドローンに使われるモーターやバッテリー等、機材や部材の分野で高い技術を持ち、国際的競争力を持っている。このような日本が強みを持つ分野で技術を守り、先端技術を更に開発して優位性を保持し、国際的なサプライチェーンで不可欠な存在となることが重要である。気がついたときに中国がこの産業で主導的な地位にあるような事態を避けるべく、低空空域に関する中国の産業政策が始まった今から、日本の特長を生かし、取組を進めていく必要がある。
(Photo Credit: 新華社/アフロ)

地経学ブリーフィング
コロナウイルス後の国際政治と世界経済の新たな潮流の兆しをいち早く見つけ、その地政学的かつ地経学的重要性を考察し、日本の国益と戦略にとっての意味合いを精査することを目指し、アジア・パシフィック・イニシアティブ(API)のシニアフェロー・研究員を中心とする執筆陣が、週次で発信するブリーフィング・ノートです(編集長:鈴木一人
地経学研究所長、東京大学公共政策大学院教授)。
おことわり:地経学ブリーフィングに記された内容や意見は、著者の個人的見解であり、公益財団法人国際文化会館及び地経学研究所(IOG)等、著者の所属する組織の公式見解を必ずしも示すものではないことをご留意ください。


Visiting Senior Research Fellow
MACHIDA Hotaka is a visiting senior research fellow in Institute of Geoeconomics at International House of Japan. He joined the Institute in October, 2022. Prior to leaving his role in government, he served as a career diplomat in Japan’s Ministry of Foreign Affairs from 2001 to 2022, focusing on Japan-China relations. He studied at Nanjing University in China and Harvard University in the United States, followed by working at Embassy of Japan in China as second secretary from 2006-2008. After that, he was posted in China-Mongolia division in the Ministry and completed the negotiations with China over the issues of launching the “High-Level Consultation on Maritime Affairs” as well as finalizing the “Maritime Search and Rescue (SAR)” agreement. He also worked in Status of Forces Agreement (SOFA) division in the North America Bureau in the Ministry leading the negotiations with the US on SOFA-related issues. He was counsellor in the Permanent Mission of Japan to the United Nations (2017-2020) and Embassy of Japan in China (2020-2022) covering the Security Council reform and Japan-China economic relations respectively. He holds a M.A from the Graduate School of Arts and Science at Harvard University, and a Bachelor from Law Faculty at Tokyo University.
View Profile-
 The Case that it Could All Work Out (for Everyone Else)2025.05.13
The Case that it Could All Work Out (for Everyone Else)2025.05.13 -
 Japan Inc. cautiously optimistic despite rising uncertainty2025.05.02
Japan Inc. cautiously optimistic despite rising uncertainty2025.05.02 -
 The dollar paradox: Toward a bifurcated currency order?2025.04.30
The dollar paradox: Toward a bifurcated currency order?2025.04.30 -
 Is there a method behind the Trumponomics madness?2025.04.28
Is there a method behind the Trumponomics madness?2025.04.28 -
 Japan needs clarity as an antidote to contradictory tariffs2025.04.25
Japan needs clarity as an antidote to contradictory tariffs2025.04.25
 The Case that it Could All Work Out (for Everyone Else)2025.05.13
The Case that it Could All Work Out (for Everyone Else)2025.05.13 The Tariff Plans Need Clarity and Credibility if They’re Going to Work2025.04.15
The Tariff Plans Need Clarity and Credibility if They’re Going to Work2025.04.15 After tariffs: Is there a plan to restructure the global economic system?2025.04.03
After tariffs: Is there a plan to restructure the global economic system?2025.04.03 The Tyranny of Geography: Okinawa in the era of great power competition2024.02.09
The Tyranny of Geography: Okinawa in the era of great power competition2024.02.09 The dollar paradox: Toward a bifurcated currency order?2025.04.30
The dollar paradox: Toward a bifurcated currency order?2025.04.30