G7は拡大するべきか? 対米自立へ舵を切る欧州、背を向ける米国、「アジア代表」日本の矜持
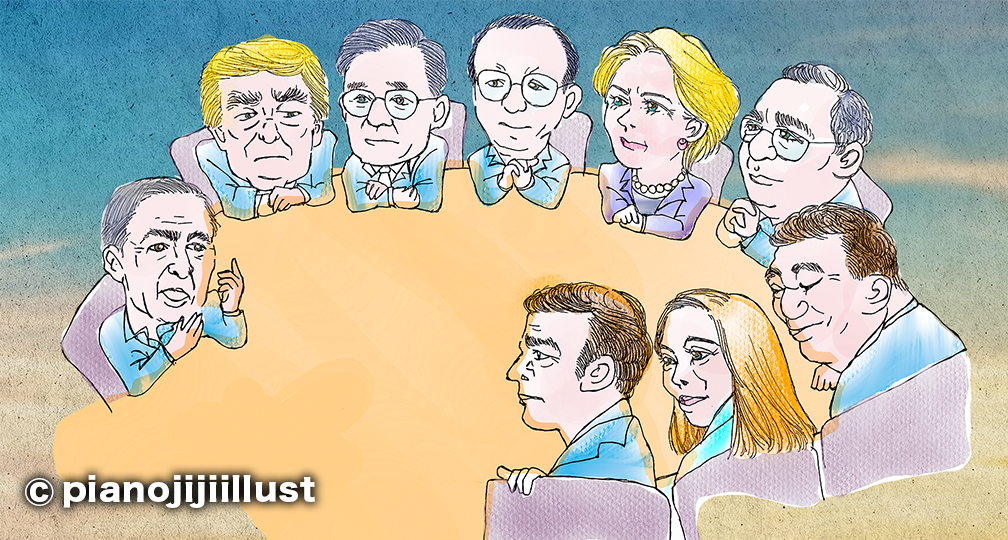
G7カナナスキス・サミット
G7サミット(主要国首脳会議)が6月15日から17日に、カナダのカナナスキスで開催された。1975年11月、フランスのパリ郊外、ランブイエ城で6か国(議長国順:仏米英独日伊)が集まった第1回以来、今年で50周年を迎えた。だがその内容は「50年の集大成」と言うにはほど遠く、むしろ50年間のひずみを露呈しているように見える。
毎年輪番の議長国をカナダが最後に務めたのが2018年6月、G7シャルルボワ・サミットであり、奇しくも1期目のトランプ米大統領(2017年1月~2021年1月)が「G7荒らし」のごとく振舞い、コンセンサスを重視してグローバルな課題に取り組む先進国間の政策協調を真っ向から否定したサミットと記憶された。トランプは「クリミアはロシア領」と持論を展開し、ロシアも含めたG8に戻るよう求め、サミット終了時に発出する首脳コミュニケに一旦は署名しながら、カナダからの帰途で突然撤回をツイートした。
2025年に再びG7議長国となったカナダは、先回の教訓をいかし、終了時に全体を包括する共同声明の発出にこだわらず、①イスラエル・イラン情勢、②カナナスキス山火事憲章、③G7重要鉱物行動計画、④繁栄のためのAI、⑤量子の未来のためのカナナスキス共通ビジョン、⑥国境を越えた抑圧、⑦移民の密入国への対抗という、7分野について共同声明を発出して終了した。
G7サミットは、民主主義、自由、人権尊重、法の支配など、価値を共有する先進7か国(1976年からカナダが参加)が毎年1回、非公式・非公開で集まり、政策合意を形成してきた。その中で経済的に最も重要なアジェンダの一つは、グローバルな自由貿易秩序の維持と強化だった。だが米国のトランプ政権がこれに大きく反する一方的な関税を矢継ぎ早に打ち出し、マルチラテラル(多国間主義)なG7サミットは機能不全に陥っているように見える。G7改革論はこれまでにも幾度となく出てきては消えた。
米国シンクタンク「異例の」G7サミット拡大論
G7カナナスキス・サミットに先立ち、トランプはかねてから主張してきたロシアの参加を再度持ち出し、中国の参加も「悪くない」とコメントを発出した。だがこれでは、G7諸国に加えアルゼンチン、オーストラリア、ブラジル、中国、インド、インドネシア、韓国、メキシコ、ロシア、サウジアラビア、南アフリカ、トルコ、欧州連合(EU)が参加する20か国・地域からなるG20と変わらない。G20は新興国グループBRICS諸国も包括するが、参加国間の立場の違いが大きく、G7のような政策合意は困難である。
このような現状に対し、米国のシンクタンクCSIS(米戦略国際問題研究所)からはカナナスキス・サミット直前にG7拡大論が米「フォーリン・アフェアーズ」誌に投稿された。東アジアの安全保障を専門とするビクター・チャ、CSISプレジデントのジョン・ハムレ、米国リベラル派の旗手ジョン・アイケンベリーは「グローバル・ガバナンスはどうしたら生き延びられるか―G7がルールベースの国際秩序を守るための改革案―」と題する共著論考において、G7に韓国、オーストラリア、欧州からは「大国」スペインの加入を提唱する。これにより、G7合計の経済規模と政策合意への参加国の範囲が広がり、自由貿易などグローバル・ガバナンスの根幹から乖離する米国に対し、同志国間の連携が強化できると説く。
アイケンベリーらは拡大論に加え、G7サミットがより組織化され、アジェンダ設定能力が強化されるべきだと主張する。毎年、議長国が輪番で回っていたが、EUのようなトロイカ、つまり前年議長国と次年議長国が共にホストとなる議長国を支える構造を勧める。同時に提案されているのが、常設事務局の開設である。トランプ大統領が同盟国・同志国との連携を破棄するかのような政策を打ち出すに及び、G7の制度化が必要になってきた、との主張だ。
G7拡大に慎重だった日本
これまでG7拡大論を打ち出してきたのは、特にフランスやイギリスであり、ロシアのG7参加を後押ししたのも欧州諸国だった。米ソが冷戦の終結を宣言し、1990年10月に東西ドイツが統合され、サミット会合直後にG7首脳たちが当時のゴルバチョフ・ソ連大統領と会談したのは、1991年のG7ロンドン・サミットだった。翌92年のG7ミュンヘン・サミットの直後には後継のエリツィン大統領との会談がもたれた。こうしてエリツィン大統領のG7会合初出席が97年6月、米国で開催されたG7デンヴァー・サミットで実現し、翌98年5月の英バーミンガム・サミット以降はG8主要国首脳会議となった。2014年以降はロシアのクリミア併合を理由にG7に戻り、ロシアは議長国から招待が届かず「クビ」になった。
日本はG7拡大に慎重であり、アジア唯一の参加国として、韓国やオーストラリア、東南アジア諸国を議長国として都度招待する役割を重視してきた。日本企業が多く進出するアジア太平洋諸国の利益を代弁し、途上国支援や環境対策などを盛り上げることに徹してきた。1970年代にオーストラリアの加入が議論された際、オーストラリアはG7加入によって責任と負担が増すことを嫌い、招待を辞退した経緯があった。
オーストラリアの例が示すように、G7という「クラブ」に入ることで自明に求められる責任と負担がある。条約や協定で縛られないものの、左右どちらの政権であろうと、参加国は政策の方向性に一定の緩やかなガードレールをはめられる。それは普遍的価値の共有と同時に、持続可能な経済成長、企業活動に必須の環境を維持・強化する政策のセットである。民主主義は国内政治のアカウンタビリティ(説明責任)の担保、つまり企業にとっての予見可能性を高め、朝令暮改を戒める。法の支配は最恵国待遇・内国民待遇、つまり海外拠点で差別的な扱いを受けないことと密接不可分だ。人権尊重は現地駐在員・家族の安全に直結し、多様性の尊重は、人種差別や組織への差別的措置、ボイコット、破壊的行動への抑止につながる。価値の共有は、普遍的価値だからこそ擁護してきたと同時に、日本の国益に合致するからこそ主張してきた。
G7への参加を各国首脳が国内向けのアピールに使う場面はこれまで多々あった。一方で、こうした外交政策上の足かせ、権威主義国にすり寄ろうとする首脳に制約をかける作用も重要であり、加入後の韓国やオーストラリアをはじめ、参加国の左右政権に対して有効であろう。こうした価値の共有は、特にグローバル・サウスと呼ばれる途上国には不評である。日本をはじめG7諸国は押し付けるべきではないが、同時に、これら価値は企業にとっての予見可能性を上げ、イノベーションに必須であることをリマインドし続ける必要がある。風向きが悪いからと引っ込めることは、日本の国益にならない。
拡大はG7の機能を強化するのか
G6は1975年の発足時、変動相場制への移行と石油危機への共同対応がアジェンダだった。G7の2つの機能のうちのひとつは、米国の衰退への対応、経済力も軍事力も陰りが見えはじめた米国が提供する国際公共財(経済のけん引役・世界の警察官)の役割を、先進国による共同ドナーに変換することだ。
もう一つの機能は、参加国の「教育」だ。米欧の目線でいえば、日本の集中豪雨的な輸出を内需主導経済に転換させ、先進国に相応しい互恵的な経済関係に脱皮させることだった。日本の目線で言えば、日本だけを狙い撃ちにした差別的な保護措置を撤廃に追い込み、自由貿易のルールを徹底することだった。
現在の文脈に置き換えたG7の機能は、何か。2つ目の「教育」の潜在的な対象は、インドと中国であろう。後者は国家資本主義ともいえる構造を放棄しない限り修正はほぼ不可能であり、安全保障上の脅威国でもあるため、現実的な解決は見当たらない。高い輸入関税や国内規制の手続きなど、国内産業の育成を名目に保護主義的な政策が目立つインドは、国内の民主主義にも課題を抱えるものの、加入によりG7の経済規模が拡大する。G7の合計人口は、2023年に世界の1割まで低下している。
インドはWTO(世界貿易機関)ドーハ・ラウンドを膠着状態に追い込んだ新興国の一つであり、G7に入れてもすぐには保護主義を修正しない、という見立てもある。だが日本と米欧諸国の通商摩擦も、1970年代から20年近くかけて緩和された。時間がかかるプロセスとして臨む必要がある。
インド以上に深刻な問題は、米国の衰退マネージ、もといG7自体の衰退マネージである。G7が世界経済に占める大きさの縮小は、インドの加入によって幾分持ち直す。だが現在の米国の衰退は、経済・軍事の物質面の後退ではなく、グローバルなリーダーシップをとる意思の後退であり、これまでG7が取り組んだことがない課題である。
トランプ政権はイランの核施設空爆のようにユニラテラル(一方的)な力の行使を厭わず、G7の会場で署名した米英貿易合意(米英経済繁栄協定)のように、2国間のディールを好む。それでもなお、グローバルな7つの課題について、トランプ大統領の「早退」にもかかわらず米国も含め共同声明を発出できたことは、G7カナナスキス・サミットがもたらした明るい兆候と受け止めることができる。
これまでは、米国が価値の共有のために率先して行動することが、空気や水のように「当然、手に入るもの」と想定できた。これが自明ではなくなった現在こそ、日本は同盟国・同志国の範囲を広げ、結束を率先して強化するメンタリティに変わっていかなければならない。そのことが、G7における「アジア代表」というこれまでの蓄積を、一層、強化することにつながろう。日本が「アジア唯一の参加国」という自意識を卒業し、G7における「グローバル・サウス唯一の代表」を自認するであろうインドに道を開くのか、G7拡大の是非について議論するべきだ。

地経学ブリーフィング
コロナウイルス後の国際政治と世界経済の新たな潮流の兆しをいち早く見つけ、その地政学的かつ地経学的重要性を考察し、日本の国益と戦略にとっての意味合いを精査することを目指し、アジア・パシフィック・イニシアティブ(API)のシニアフェロー・研究員を中心とする執筆陣が、週次で発信するブリーフィング・ノートです(編集長:鈴木一人 地経学研究所長、東京大学公共政策大学院教授)。
おことわり:地経学ブリーフィングに記された内容や意見は、著者の個人的見解であり、公益財団法人国際文化会館及び地経学研究所(IOG)等、著者の所属する組織の公式見解を必ずしも示すものではないことをご留意ください。


Senior Research Fellow,
COO, LLC future mobiliTy research
Hitoshi Suzuki (PhD) was Associate Professor at the Graduate School of International Studies and Regional Development, University of Niigata Prefecture, Japan. He received his Ph.D. in History and Civilization from the European University Institute in December 2007 and has focused on Japan’s relations with the EC/EU, as well as Japan’s auto and aero-space industry in Europe. He was visiting fellow at the Monash European and EU Centre, the London School of Economics and Political Science. After serving as Deputy Director at the Economic Partnership Division, Economic Affairs Bureau of the Ministry of Foreign Affairs of Japan, and as a Research Committee Member of the Europe Study Group at the 21st Century Policy Institute of Keidanren (Japan Business Federation), he founded Mirai Mobility Research LLC in 2021. He currently serves as a Visiting Senior Research Fellow at the Makihara Laboratory, Research Center for Advanced Science and Technology (RCAST), the University of Tokyo, and as an Adjunct Lecturer at Ferris University. As of December 2021, he serves as a Visiting Fellow & Staff Director, CPTPP Project, Asia Pacific Initiative. His publications include "Thatcher and Nissan Revisited in the Wake of Brexit" (Palgrave Macmillan), “The New Politics of Trade: EU-Japan” Journal of European Integration 39(7), “Post-Brexit Britain, the EU and Japan” Europe and the World 4(1), and Suzuki et.al. “Japan and the European Union,” Oxford Encyclopedia of European Union Politics.
View Profile-
 Orbán in the Public Eye: Anti-Ukraine Argument for Delegitimising Brussels2026.02.04
Orbán in the Public Eye: Anti-Ukraine Argument for Delegitimising Brussels2026.02.04 -
 Trump, Takaichi and Japan’s Strategic Crossroads2026.02.03
Trump, Takaichi and Japan’s Strategic Crossroads2026.02.03 -
 Analysis: When Is a Tariff Threat Not a Tariff Threat?2026.01.29
Analysis: When Is a Tariff Threat Not a Tariff Threat?2026.01.29 -
 Takaichi’s Strengths and the Need for ‘Strategic Signaling’2026.01.23
Takaichi’s Strengths and the Need for ‘Strategic Signaling’2026.01.23 -
 Takaichi’s Twin Challenges: Economic Growth and Security2026.01.13
Takaichi’s Twin Challenges: Economic Growth and Security2026.01.13
 Oil, Debt, and Dollars: The Geoeconomics of Venezuela2026.01.07
Oil, Debt, and Dollars: The Geoeconomics of Venezuela2026.01.07 It’s Now or Never: India’s Ambitious Reform Push2026.01.09
It’s Now or Never: India’s Ambitious Reform Push2026.01.09 Analysis: When Is a Tariff Threat Not a Tariff Threat?2026.01.29
Analysis: When Is a Tariff Threat Not a Tariff Threat?2026.01.29 Navigating Uncertainty in U.S. Space Policy: Decoding Elon Musk’s Influence2025.04.09
Navigating Uncertainty in U.S. Space Policy: Decoding Elon Musk’s Influence2025.04.09 Analysis: Ready for a (Tariff) Refund?2025.12.24
Analysis: Ready for a (Tariff) Refund?2025.12.24












