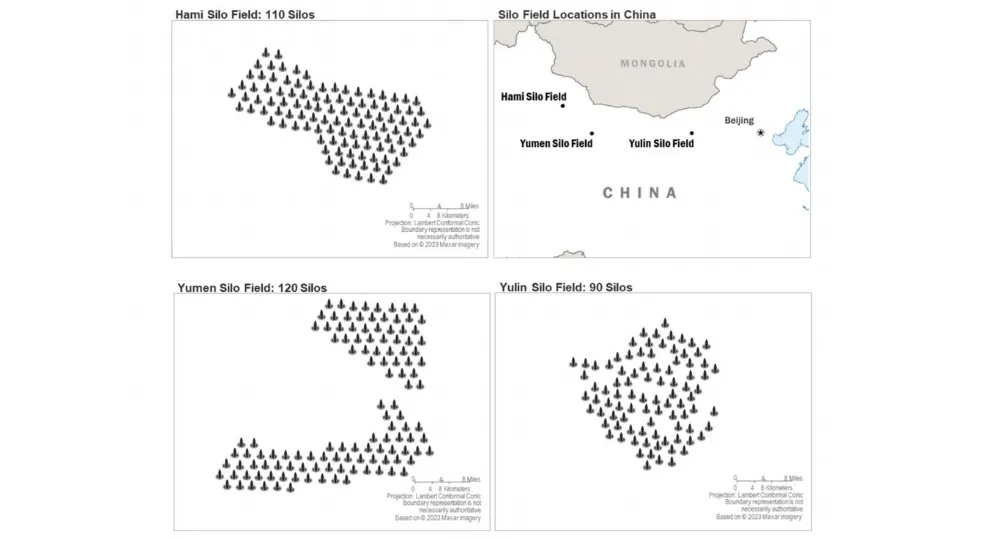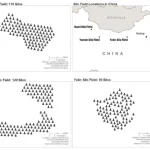日本は「G7の結束」を強化することができるのか

2023年、日本は議長国として7回目のG7広島サミットを開催することになる。
G7サミットのこれまでの歴史を回顧すると、日本が何度か重要な貢献を行った機会があった。そのひとつが、今から40年前の1983年5月にアメリカで開催されたウィリアムズバーグ・サミットであった。このとき、西側諸国はソ連の挑戦を前に動揺し、米仏間では亀裂が広がっていた。そのようななかで、G7の結束の強化に貢献したのが日本であった。
このときの日本の首相は、中曽根康弘であった。中曽根はそれまでの多くの前任者と異なり「大統領型」の政治指導を目指し、外交においても自らが先頭に立って指導する姿勢を示していた。同時期に首相を務めて中曽根とも親しい関係にあったイギリスのマーガレット・サッチャー首相は、「私が首相を務めていた間に出会った日本の指導者のなかで、おそらく一番、いいたいことをはっきりという『西洋的な』人だったと思う」と回顧している。
米仏間で広がっていた亀裂
ウィリアムズバーグ・サミットでは、アメリカのロナルド・レーガン大統領と、フランスのフランソワ・ミッテラン大統領が激しく衝突し、米仏間の亀裂が広がっていた。軍備増強を進め、ヨーロッパ大陸に中距離核戦力(SS20)を配備しようとしていたソ連に対して、どのように対峙するかが大きな争点となっていた。
このときソ連は、西側同盟に亀裂をもたらし、アメリカを孤立させることを試みていた。西側同盟諸国が結束を強化して、ソ連を包囲することを回避することが重要な戦略目標とされていたのであろう。ここで西側同盟内部では2つの亀裂が広がっていた。
1つは米欧間での亀裂であり、もう1つはヨーロッパとアジアが分断されることであった。ソ連は欧州諸国を宥和する一方で、対ソ強硬姿勢が顕著なアメリカのレーガン大統領を孤立させようとしていた。
同時に、ヨーロッパとアジアを分断させることで西側諸国に揺さぶりをかけ、ソ連のグロムイコ外相はその前年に「SS20の一部を、ソ連の欧州部からアジア部に移転させることができる」と発言していた。この問題にG7としてどのように対応するかが問われていたのである。
このときに、NATOの軍事機構に参加していなかったフランスは、経済問題を扱うG7の枠組みの中で、軍事問題を議題に含めることには否定的であった。フランスは自律的な外交を展開することで、ソ連に対してもアメリカとは異なる姿勢を示していた。
さらには、多くの軍事基地をアジアに擁するアメリカがヨーロッパとアジアの安全保障を一体として捉えていたのに対して、フランスはそうではなかった。ヨーロッパで緊張が緩和される一方で、ソ連のSS20のミサイルの一部がアジアに配備される懸念に対して、米仏両国が歩調を揃えることが重要だった。
中曽根首相は、国際舞台で日本が積極的な役割を担うべきだという信念を有していた。中曽根は、フランス語を用いてミッテラン大統領を説得して、アメリカに歩み寄って西側諸国の結束を強化するべきだと説いた。
中曽根首相は米欧間の亀裂回避に貢献
このサミットで、次のように中曽根はミッテラン大統領へ向けて語った。「今は西側の結束をソ連に示す時である。日本はアジアの一国であっていわゆる『西側』の一員ではないが、自分は世界の安全保障はグローバルに考えるべきであると思う」。
そのような中曽根の熱意を受けて、ミッテラン大統領は譲歩をして、サミットの政治声明のなかで「西側同盟の一体性」についての言及がなされた。
このように中曽根首相は、ウィリアムズバーグ・サミットにおいて米欧間の亀裂を回避することに貢献し、またヨーロッパの安全保障問題とアジアの安全保障問題が不可分であることを強調した。米欧間と、ヨーロッパとアジアの間と、2つの亀裂を回避して、G7としての結束を深めることに貢献した。
ウィリアムズバーグ・サミットの政治声明文書では、最終的に、「われわれサミット参加国の安全は不可分であり、グローバルな観点から取り組まなければならない」という文言が含まれることになった。
その後、西側同盟はその結束を維持しながら、ソ連に対する圧力をかけることで、冷戦終結とソ連の解体に帰結する。日本がG7の枠組みの中で、経済問題だけではなく、安全保障問題でも重要な主導的な役割を担えることを、中曽根は証明した。このウィリアムズバーグ・サミット以降、G7で安全保障問題も議題に含められるようになっていく。
このような中曽根外交の軌跡は、現在の岸田文雄政権の外交を考えるうえで示唆的である。現在においても、1980年代の新冷戦の時代と同様に、G7はロシアの軍事的脅威に向き合いながら、その結束が試されている。
だが、現在G7が直面する課題は、よりいっそう深刻だ。というのも、ソ連の脅威に中国と提携して立ち向かっていた1980年代とは異なり、現在は中国とロシアが提携し、さらには「グローバル・サウス」の諸国の多くも、その両国との関係を強化しているからだ。
さらに、G7諸国はウクライナにおける現在進行しつつあるロシアの侵略と、台湾をめぐる中国の将来の武力統一の可能性と、その2つの危機に直面している。そのような複合的な危機に、米仏両国は異なる対応を示した。
対中接近を示唆するマクロン大統領
今年の4月5日から7日まで訪中したフランスのエマニュエル・マクロン大統領は、仏レゼコー紙とのインタビューの中で、「最悪なのは、欧州がこの問題でアメリカのペースや中国の過剰反応に追随しなければならないと考えることだ」と述べて、「私たちの優先事項は他国の予定に合わせることではない」と答えた。
さらには、ヨーロッパがアメリカに「追随」するべきではないと論じて、対中接近を示唆するフランスの自主外交の姿勢を示した。加えて、台湾危機は「われわれの危機ではない」と答えて、「われわれのものではない危機にとらわれれば、ワナに陥る」と、台湾問題からヨーロッパが距離をとる必要を説いた。
フランスはこれまで、対ロシア政策をめぐっても、しばしばアメリカとは異なる独自の姿勢を示してきた。また、マクロン大統領はこれまで、停戦のためにはウクライナがロシアに対して一定の譲歩をする必要性があることを示唆し、ロシアをヨーロッパの大国として尊重する必要性を示唆してきた。
このようなフランスの独自のアプローチが、G7の結束を乱すようなことがあってはならない。
そのような不協和音が広がる中で、4月16日から18日までの3日間、日本の軽井沢でG7外相会合が開催されることになった。そこでは、ウクライナ情勢について時間をかけて意見交換を行うと同時に、対中国およびインド太平洋地域に関するセッションに多くの時間を割くことになった。
対中認識や、台湾危機の可能性についての危機意識など、G7諸国の間での認識の乖離が広がらないように、議長国である日本はそれらの問題に多くの時間を割くように配慮した。さらには、インド太平洋の議題については、今後、G7の枠組みの中で定例協議を行うことが合意された。
英語が流暢で、日本の政界の中でも例外的に国際派であり社交的である林芳正外相は、軽井沢のG7外相会合のさなかに誕生日を迎えたアメリカのブリンケン国務長官と、フランスのコロナ外相の2人に、ビートルズのジョン・レノンが好んだというアップル・パイをプレゼントした。
和やかな雰囲気の中で行われた軽井沢G7外相会合は、日本外交の努力によって、台湾問題をめぐる米仏間の認識の乖離を埋めるうえで大きな貢献をなした。まさに、40年前に中曽根首相が行った米仏間の対ソ政策をめぐる亀裂を回避する外交を、現在、林外相、さらには岸田首相が行っていると見ることもできる。
岸田首相は中国の軍事行動の可能性に警鐘
岸田首相はG7諸国が結束して中国やロシアに向かうこと、さらにはヨーロッパの問題とアジアの問題を一体性のあるものとして考えることの重要性を、しばしば指摘している。
たとえば、今年の1月13日のワシントンDCで行った演説の中で、岸田首相は次のように論じる。「日本はG7で唯一のアジアの国です。その日本が対露措置に加わったことで、ロシアによるウクライナ侵略との戦いは、大西洋世界のものからグローバルな性格のものに変わりました」。
岸田首相はそこで、「この力による一方的な現状変更を許せば、アジアをはじめ世界のほかの場所でもこのようなことが行われてしまう」と言及し、台湾や尖閣諸島をめぐる中国の軍事行動の可能性に警鐘を鳴らしたのであろう。
このように、1983年に中曽根総理が試みた米欧間、およびヨーロッパとアジアの間の亀裂の拡大を回避するという試みは、40年間の時代を経て岸田首相に継承されている。
ウィリアムズバーグ・サミットで中曽根首相は、世界における日本のプレゼンスを誇示することに成功した。
これから岸田首相もまたG7広島サミットを契機として、同様に、国際社会の結束を強化して、「法の支配に基づく自由で開かれた国際秩序」を回復するための努力が求められるのだ。
(Photo Credit: Ministry of Foreign Affairs / Reuters / Aflo)

地経学ブリーフィング
コロナウイルス後の国際政治と世界経済の新たな潮流の兆しをいち早く見つけ、その地政学的かつ地経学的重要性を考察し、日本の国益と戦略にとっての意味合いを精査することを目指し、アジア・パシフィック・イニシアティブ(API)のシニアフェロー・研究員を中心とする執筆陣が、週次で発信するブリーフィング・ノートです(編集長:鈴木一人 地経学研究所長、東京大学公共政策大学院教授)。
おことわり:地経学ブリーフィングに記された内容や意見は、著者の個人的見解であり、公益財団法人国際文化会館及び地経学研究所(IOG)等、著者の所属する組織の公式見解を必ずしも示すものではないことをご留意ください。