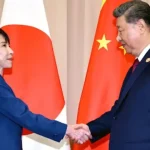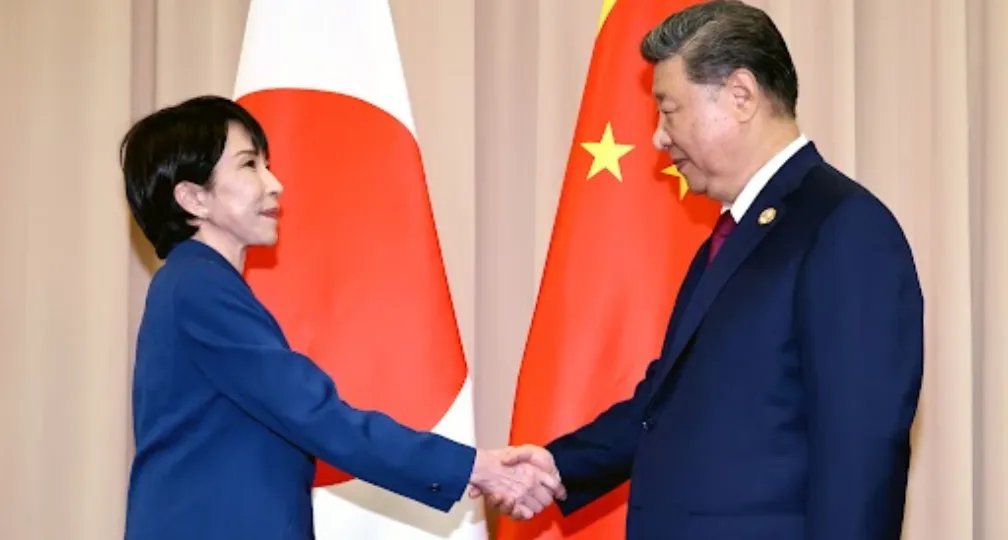広島から核の国際秩序再構築に向けた行動を

【連載第3回:G7広島サミットの焦点】
G7広島サミットは、ロシアのウクライナ侵略によって国際秩序が根幹から揺らぐ中、「力による一方的な現状変更の試みや核兵器による威嚇、その使用を断固として拒否し、法の支配に基づく国際秩序を守り抜くというG7の強い意志を力強く世界に示す」歴史的な機会となる。
最初の被爆地である広島に、招待国のインドを含め、核保有国7カ国の内の4カ国(米英仏印)が会し、核兵器のない世界に向けた取り組みと現実的な核抑止の両立について意見が交わされる。ゼレンスキー大統領も岸田文雄首相の要請を受けオンラインで参加する。
ロシアによる核兵器の恫喝に屈せず、ロシアの侵略と戦っているウクライナを全面的に支持し、プーチン大統領にいかなる形であれ核兵器の発射ボタンを押させないことが必要だ。岸田首相は議長として、「ヒロシマ・アクション・プラン」をG7共通プランに位置づけ、核の国際秩序の回復に向けた新たな一歩を踏み出さなければならない。
核抑止の正念場
冷戦後の核兵器への関心が低下した「核の忘却」の時代は、北朝鮮の度重なる核実験やミサイル開発、中距離核戦力全廃条約(INF条約)の破棄に象徴される米ロ間の軍備管理制度の緩み、中国の急速かつ大規模な核戦力増強など、核の国際秩序の不安定化をもたらした。
2014年に一方的にクリミアを併合したロシアは、「エスカレーション抑止(escalate to de-escalate)」という戦略(核兵器の使用を含め、紛争を意図的にエスカレートさせることにより相手を萎縮させ、ロシア側が望む条件を強いる戦略)を導入し、昨年2月24日のウクライナ侵攻以降、実際にこの戦略を遂行しており、核使用の可能性は現在も否定できない。
これに対し、早々にアメリカの軍事介入を否定し、ロシアの軍事侵攻を抑止できなかったバイデン大統領だが、核使用に関しては「ウクライナで核兵器を使えば壊滅的な結果を招くぞと、極めて高いレベルでロシア側に直接、内々に伝えてある」(ジェイク・サリバン国家安全保障問題担当大統領補佐官、2022年9月25日)。
ウクライナがNATO加盟国ではないにもかかわらず、アメリカが報復意思を公表するのは、実際に核が使用された場合、核拡散防止条約(NPT)体制はもちろん、アメリカの核戦略・拡大抑止戦略が崩れてしまうからだ。
アメリカの報復には、ロシアからの戦略核兵器による反撃を招き、全面核戦争に拡大するリスクが伴う。しかし、アメリカが躊躇し、ロシアの「エスカレーション抑止戦略」が機能するとなれば、核ミサイルの運用能力向上を進める北朝鮮や武力による台湾統一を否定しない中国が同じ戦略を使うことが予想され、同盟国に対するアメリカの拡大抑止も重大な挑戦を受けることになる。ウクライナはまさにアメリカの核抑止が実戦で試されている正念場なのだ。
核を使用させないことの意義
核抑止の戦略は、冷戦時代から現在に至るまで戦略環境の変化や技術の発展に伴い、精緻に理論化されてきた。
核兵器の破壊力の大きさ故、存在自体が抑止力となるとする「最小限抑止」戦略から、抑止力の担保には核の使用を前提として損害限定による勝利の体制構築が必要とする「柔軟反応」戦略、さらに、お互いの脆弱性(ABM条約)を前提に核兵器を使えない絶対兵器とする「相互確証破壊(MAD)」戦略、そして「エスカレーション抑止」戦略へと至っている。
いずれの戦略もパラドックスとジレンマを包含するため、その戦略の「正しさ」は実際に核兵器が使用されていない事実の積み重ねによってしか証明できない。逆に言えば、抑止は、客観的な評価がほぼ不可能な、相手との相互的な心理作用の結果であり、いずれの理論も破綻しなければ(核が使用されなければ)、通用する机上の理論でもある。
仮にウクライナで核が使用されれば、これら机上の理論は一掃され、その後の戦争の展開も戦後の抑止理論の展開も予想がつかない事態となる。これはロシアにとっても同様だ。
ロシアの「核抑止の分野におけるロシア連邦国家政策の基礎」(2020年6月2日全文公表)は、核抑止の目的を「国家の主権及び領土的一体性、ロシア連邦及び(又は)その同盟国に対する仮想敵の侵略の抑止、軍事紛争が発生した場合の軍事活動のエスカレーション阻止並びにロシア連邦及び(又は)その同盟国に受け入れ可能な条件での停止を保障する」と規定している。
この政策に従えば、ロシアの核恫喝は、ウクライナ反攻のエスカレーション阻止とロシアが受け入れ可能な条件での停戦を目的とすると読めるが、これは「核抑止」の目的なので、使用すると逆にその目的達成は難しくなる(アメリカの報復を招く)。
プーチン大統領にこの矛盾を理解させ、歴史的な一線を超えさせないことが、核抑止の有効性を今後も維持するうえで死活的に重要なのである。そのためには、地経学研究所主任研究員の小木洋人が「ロシアによる核恫喝を拒否するために必要なこと」で指摘するように、戦術核兵器の使用が軍事的には効果があまりないことを明らかにすることも重要である。
ウクライナで核兵器がなぜ使用されなかったのかという要因分析が、ウクライナ戦争後の核戦略と拡大抑止体制構築の基礎となるからだ。
NPT体制を巡る新たな展開
ロシアの核の脅威は、フィンランドとスウェーデンが中立政策を捨てNATOの核の傘を選択したように、敵対的な核保有国からの安全をいかに保障するかという厳しい選択を非核保有国に迫っている。
ウクライナは、旧ソ連時代に配備され、そのまま国内に残されていた大量の核兵器を放棄することに合意し、1994年、NPTに加盟したが、米英ロの「ブダペスト覚書」(核兵器の放棄と引き換えに安全を保障)の約束は守られなかった。
また、米ロ英仏中の5大国は、NPT条約を締結している非核国に対しては核を使用しないとする「消極的安全保証」に関する一方的宣言を行ってきた。しかしこの宣言もロシアが自ら破り、非核国のNPT体制への信頼は危機に瀕している。元々不平等なNPT体制の存続には、核保有国の非核国に対する共同責任を改めて明確にする必要があろう。
韓国の尹錫悦大統領は、独自の核保有を志向する根強い国内世論を押さえ、アメリカの拡大抑止を強化する選択をした(ワシントン宣言、4月26日)が、戦術核の運用能力の向上を進める北朝鮮が7回目の核実験を断行した時に耐えられるだろうか。
言うまでもなく、北朝鮮の核は日本にも向けられている。また、中国は従来の「最小限抑止」を転換し、2035年にはアメリカと均衡する約1500発の戦略核戦力を保有すると見積もられている。
仮に、米ロ中という核の三極体制に移行すると、各国がそれぞれの国に対して同時にパリティを追求することは不可能になる。各国が同じ数の核兵器を持っていても、そのうちの2カ国が協調してしまえば、残りの1国が一方的に不利な状態に置かれてしまうからだ。
三極体制の下でいかに軍拡競争を防ぎ、戦略的不安定のリスクを低減させるか、軍備管理の新たな課題である。核大国となる中国は、少なくとも核の透明性を高め、核大国の責任を果たさねばならない。
中国の核軍拡はインドの核戦略にも影響を及ぼす。インドはNPTに加わらず、1998年にパキスタンと前後して核実験を成功させて以降、核兵器の「軍事作戦に勝利するための戦術的手段」としての役割(限定核使用オプション)を否定し、一貫して「抑止のための政治的手段」と位置づけてきた。
その結果、パキスタンとの地域的な戦略的安定を維持し、「安定・不安定の逆説」の効果をも抑え込んだと評価されている(栗田真広、『「核の忘却」の終わり』第5章)。
習近平主席は、4月26日のゼレンスキー大統領との電話会談で、「核戦争に勝者はいない。各国は冷静さと自制を保つべきだ」と語り、ロシアを念頭に核使用に反対する姿勢を示している。
これに対し、モディ首相は、今後のインドの核抑止・対中戦略をどう構想するのであろうか。また、米英仏の核保有国は、日独伊加等の拡大抑止提供国さらにはすべての非核保有国に対する核の脅威からの安全をいかに保障するのか。G7広島サミットで採択される宣言には、その決意と具体的な行動を盛り込む必要があろう。
原点・ヒロシマからの再出発
伊勢志摩サミット後の2016年5月27日、現職として初めてオバマ大統領が広島を訪問し、高齢の被爆者と抱擁した光景は、「核なき世界」への前進を予感させた。同大統領の2009年のプラハ演説は世界の核軍縮への機運を高め、2017年7月の国連総会における核兵器禁止条約(TPNW)の採択(122カ国の賛成)につながった。
TPNWは、核保有国や日本を含むその同盟国が参加しておらず、国際規範にはなっていない。そもそも国際社会には、秩序を強制的に形成するだけの自律した権力の裏付けは存在しない。従って、核兵器の使用を規制する国際法的規範の確立は、それが可能であったとしても遠い将来のことであろう。
それでも、核兵器の非人道性を国際社会の共通認識にすることは、核のハードルを高め、核使用をタブーとする王道である。その先の核廃絶という理想の達成には、まず核の抑止と管理という現実に立脚した方策が不可欠であることも事実だ。
G7広島サミットに結集する首脳たちは、ヒロシマの非人道性を実感するであろう。核兵器廃絶という理想は諦めず、目前の核使用の危機を回避し、核の国際秩序の回復に向けた新たな一歩を広島から踏み出してもらいたい。
そして、歴史的に特別な責任を有する日米両国は、ロシアの核兵器による恫喝や攻撃を拒否し、揺ぎない相互信頼によって国の安全を保障する拡大抑止の模範となって、その先頭に立つ必要がある。
(Photo Credit: ZUMA Press / Aflo)

地経学ブリーフィング
コロナウイルス後の国際政治と世界経済の新たな潮流の兆しをいち早く見つけ、その地政学的かつ地経学的重要性を考察し、日本の国益と戦略にとっての意味合いを精査することを目指し、アジア・パシフィック・イニシアティブ(API)のシニアフェロー・研究員を中心とする執筆陣が、週次で発信するブリーフィング・ノートです(編集長:鈴木一人 地経学研究所長、東京大学公共政策大学院教授)。
おことわり:地経学ブリーフィングに記された内容や意見は、著者の個人的見解であり、公益財団法人国際文化会館及び地経学研究所(IOG)等、著者の所属する組織の公式見解を必ずしも示すものではないことをご留意ください。