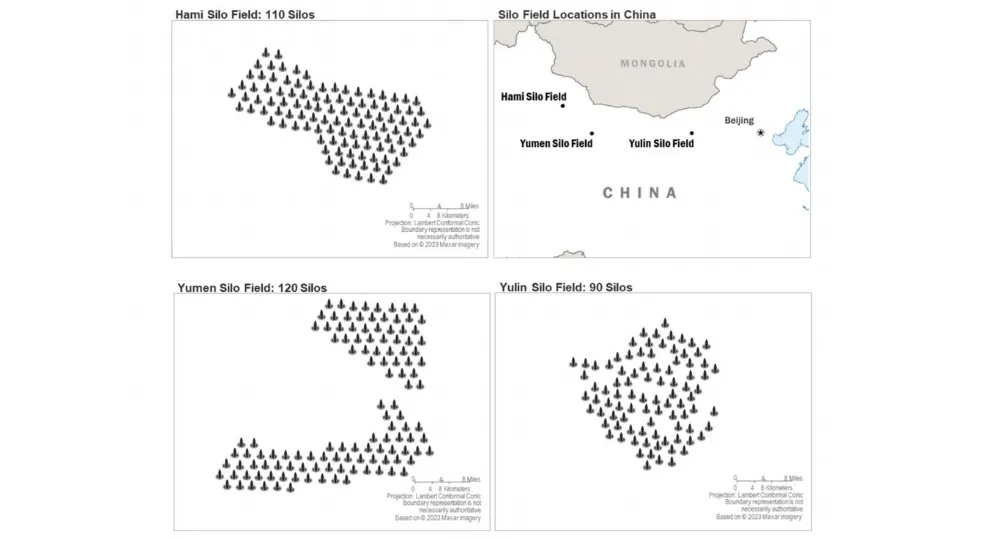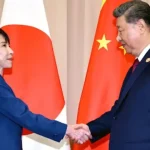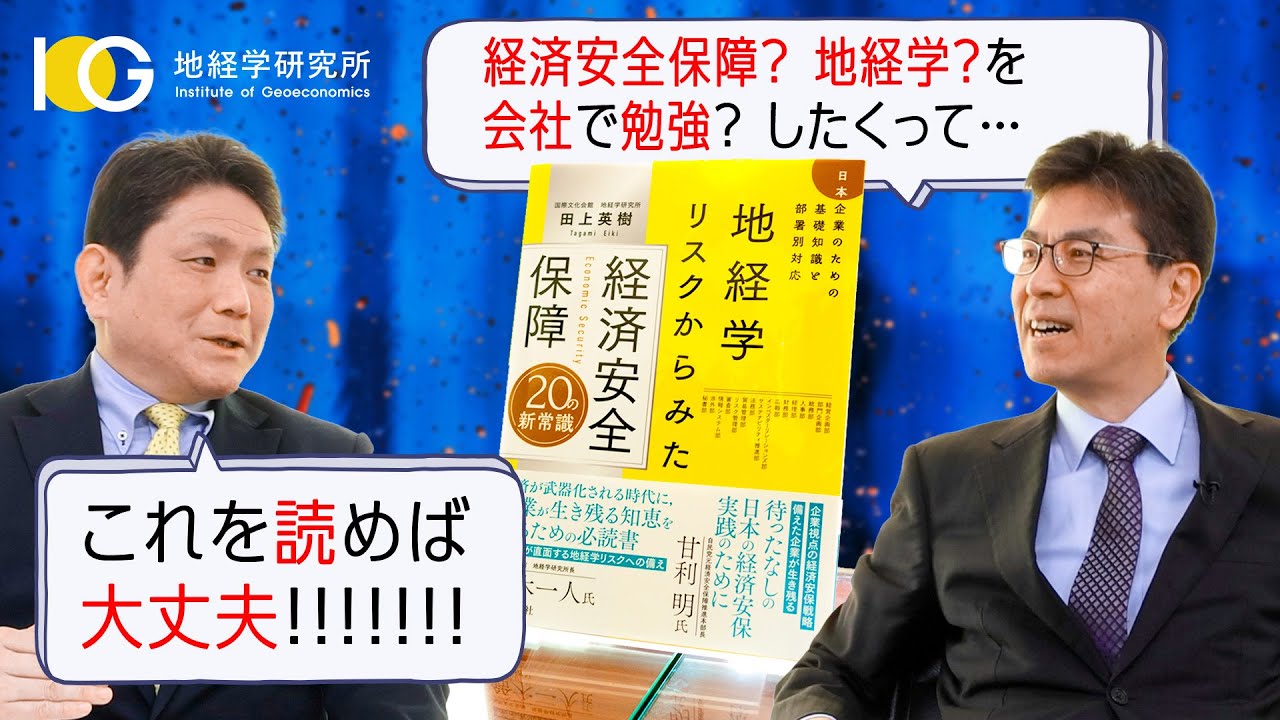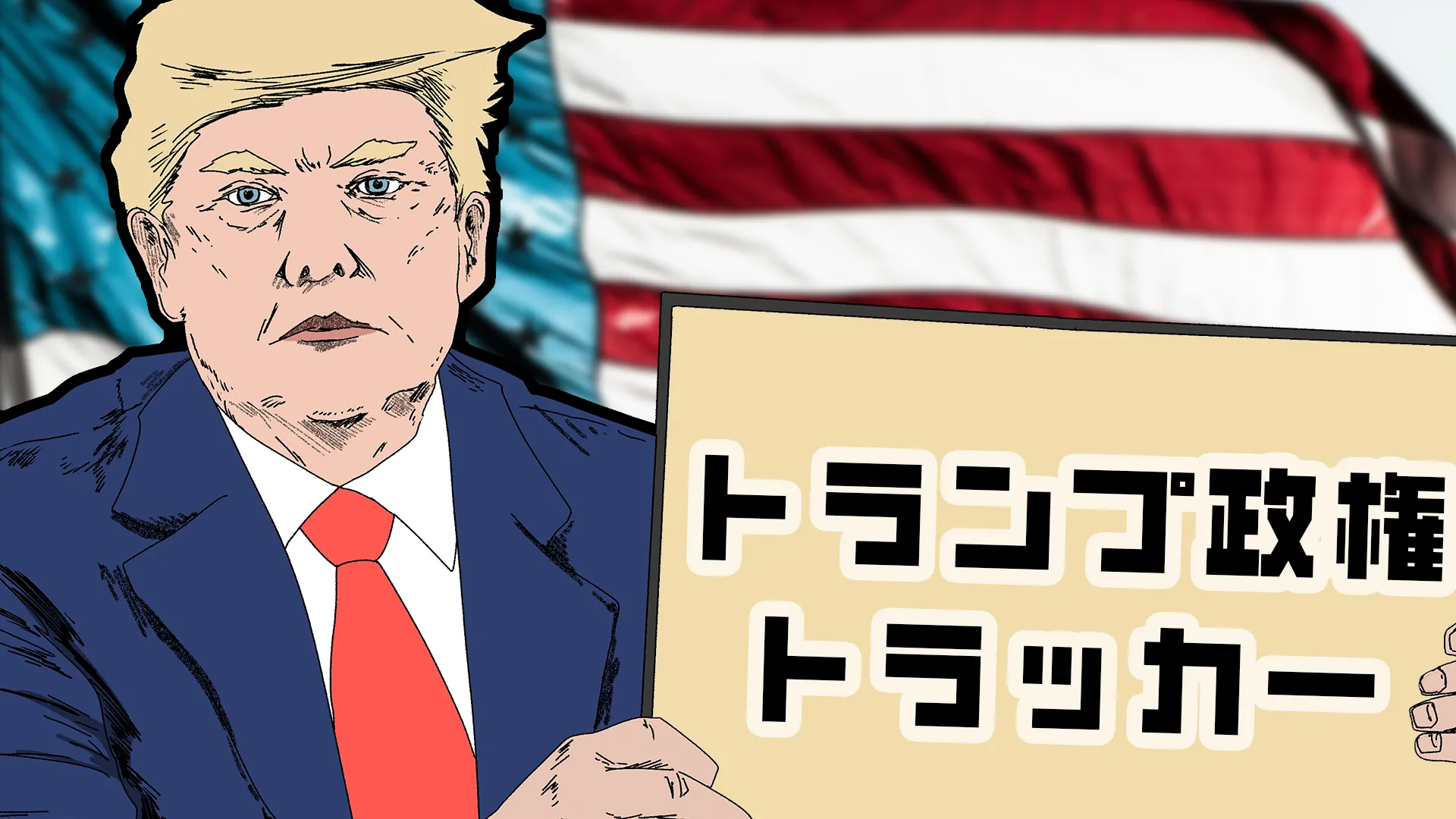シリコンバレーと移民政策:テクノロジーの未来を決める「ディール」

なぜシリコンバレーにはアジア系エンジニアが多いのか
シリコンバレーのグーグル本社のオフィスに足を踏み入れると、アジア系のエンジニアが多いことに気づく。同社の報告書を覗くと、従業員のおよそ半分がアジア系だと記される。これはグーグルに限らず、偶然でもない。メタ(旧フェイスブック)などIT企業の本社が置かれるシリコンバレーの住民の人種別マジョリティは、アジア系である。同地域の住民の人種構成の変化は、1990年以降、急激に変化し、1990年は白人が59%とマジョリティを占め、アジア人は17%だったが、2010年には白人が37%へと減少する一方、アジア人は30%まで増え、2023年には白人が30%と減少を続ける中、アジア人は37%と増加を続け、マジョリティとなった[1] 。この住民の人種別構成の変化は、1990年代以降のシリコンバレーのハイテク企業の台頭と足並みが揃う[2] 。IT企業を中心としたハイテク企業の成長に伴い、エンジニアなどの雇用が増大する中、アジア出身、とりわけインドと中国出身のエンジニアが増えていった。彼らの多くがH-1Bビザという就労ビザにより、働くことが可能になったからである。つまり、アメリカ政府はビザ制度を通じて、シリコンバレーの人材供給網をコントロールできる立場にあり、企業にとってはまさに「生殺与奪の権」を握られている状態である。そのため、第一次トランプ政権の制限的な移民政策に対し、シリコンバレーのIT企業は対抗姿勢を見せてきた。だが、第二次に入ると、彼らは政権への歩み寄りを模索している。なぜシリコンバレーは抵抗から歩み寄りへと戦略転換したのだろうか。
第一次トランプ政権 抵抗のフロントラインに立ったシリコンバレー
第一次トランプ政権では、トランプ大統領から出される制限的な移民政策をめぐり、シリコンバレーのIT企業は次々と対抗姿勢を表した。2017年1月にトランプ氏が大統領就任直後に出した大統領令(いわゆる「入国禁止令」)では、イスラム圏7カ国からの入国を制限した。これに対し、グーグル、メタ(当時のフェイスブック)、アップルなど127社のシリコンバレーのIT企業が連名で「アミカス・ブリーフ(法定助言書)」を裁判所に提出した[3] 。シリコンバレーの企業は、高度人材の流入がシリコンバレーの人材供給に不可欠であり、このような突然の大統領令による入国制限がもたらす不安定さと不確実性が、優秀な人材の採用を困難にし、グローバル市場での競争を妨げると主張し、大統領令の差し止めを求めた。こういった法廷での抵抗は、「入国禁止令」に留まらない。トランプ政権がDACAプログラム(若年の非正規移民への救済措置)を廃止しようとした動きにも、グーグルやアップルなど約140社がDACAの維持を求めて、最高裁に意見書を提出した。さらに、高度人材に対する就労ビザH-1B制限への反発として、シリコンバレーのIT企業のリーダー達が設立したロビー団体FWD.usを通じて、H-1Bビザを含む移民政策の改革を積極的に推進してきた。シリコンバレーのIT企業の最高経営責任者(CEO)は、「移民制限に反対する」という声明も出した。当時のシリコンバレーのIT企業にとって、最大の課題は、突発的に現れる政策の不確実性をいかに抑え、人材の供給網の安定化を図るかということであった。そのため、法廷、議会、世論をフル活用し、トランプ政権の移民政策に抵抗してきたのである。
第二次トランプ政権 歩み寄りへ戦略の修正
ところが、二期目に入ると、グーグルやメタ(旧フェイスブック)などシリコンバレーの大手IT企業のCEOによるトランプ大統領への歩み寄りが目立つ。この戦略転換の背景には、次の三つの「不確実性」がある。
第一に、先述した、シリコンバレーのIT企業が第一次トランプ政権に経験した政策の不確実性である。就労ビザH-1Bといった外国人を雇用する上で不可欠なビザ制度は、政府が運営する。トランプ以前の政権では、高度外国人材に対する就労ビザH-1Bの却下率が顕著に上がることなどなかった。だが、第一次トランプ政権では、その却下率が著しく高まった [4]。それに加えて、「入国制限令」など制限的な移民政策が次々と実施され、企業の人材供給網に予測不可能な状況が生じた。シリコンバレーのIT企業は、こういった突発的な政策という政策の不確実性に真っ向からの対抗では限界があると学び、政権への歩み寄りを図っているのである。
第二に、中国やインドをはじめとした新興国のIT企業の急成長である。中国やインドは、シリコンバレーのIT企業にとって高度人材の供給元である。とりわけ、その中国におけるIT企業が急成長し、その人材確保上のライバルとなってきた。中国の大手のIT企業であり、AI分野の開発も著しいテンセントやアリババ、バイトダンス(TikTokの運営会社)といったIT企業の従業員は、2017年のそれと比較すると、顕著に増加している[5] 。これらの会社の雇用の拡大は、アメリカへの留学・就労経験の中国出身の高度人材の就労先の選択肢を増やし、帰還を促進させる。さらに、中国のAI企業が、こういった企業から投資を受け、アメリカからの帰国組が起業している [6]。すなわち、高度外国人材の就労先として、これまでシリコンバレーのIT企業が独占的な地位にあったが、これまでシリコンバレーのIT企業にとっての高度人材の供給国のIT企業の成長が、優秀な人材を自国に引き留める動きが強まっている。
第三に、高度外国人材のアメリカ離れである。この動きは、第一次トランプ政権以前から進んでおり、先述した出身国におけるIT企業などの成長による経済的な機会の増加に、出身国側の人材への呼び戻し政策が相まった形での出身国側の肯定的な環境変化による。だが、最近では、アメリカ側の政策の不透明性などが重なり、出身国に留まる人材が増えている。例えば、アメリカのIT企業への従事者も含めた上位AI研究者を中国が最多で輩出しており、その数は2019年の29%から2022年の47%へ増加しており、これらの人材が国内で働く割合は増加傾向にある[7] 。同じくインドもトップクラスのAI研究者の輩出国の一つであるが、2019年はAI人材のほぼ全てが海外での雇用機会を選択したが、2022年ではその割合は減少し、20%のAI人材が国内に留まることを選んだ [8]。つまり、トップクラスのAI人材が国内に留まる傾向が強まっており、これは中国やインド発のライバル企業の更なる出現や台頭へと繋がり、シリコンバレーのIT企業にとっては自社の競争力と人材確保上の脅威となる。中国のディープシークの創業者の梁文峰とその開発組には留学・海外就労経験者がいないとされるが、これはAI人材の国際移動の最近の傾向を表している。
これら三つの不確実性のうち、企業が自らの行動である程度コントロールできるのは、一つ目の国内要因の政策の不確実性である。一期目には、抵抗によって、政策の不確実性を抑えようとした。二期目は、国外の不確実性が増える中、シリコンバレーのIT企業は歩み寄りによって政策の不確実性を管理しようと模索しているのである。
トランプとの駆け引きが未来を決める
シリコンバレーの歩み寄りの戦略転換は成功したのか。答えはイエスでもノーでもある。トランプ政権はシリコンバレーのIT企業に有利なH-1Bビザの運営方針の転換という「アメ」を渡した一方で、留学生や研究者といった大学へ供給される人材にビザ厳格化という「ムチ」を与えている。シリコンバレーにとって、大学は人材供給網の川上にあたり、留学生や研究者の減少へと繋がるビザの厳格化は、シリコンバレーへの人材供給にも影響を及ぼしかねない。一方、シリコンバレーはしたたかである。政策の不確実性ショックを人材供給元インドでの雇用拡大の契機とし、戦略転換を図っているようである。同国はコスト抑制先として位置付けられてきたが、昨今は政策リスクの回避先として、安定的に人材供給が確保できる開発拠点へと変容させている。
ビザ制度の厳格化は、トランプ政権にとっては、人材供給元である中国などへの技術流出に対する安全保障政策の一環であるため、企業の要望に沿って緩和することはできない。他方、海外からの人材供給は、シリコンバレーにとっては、自社の競争力の維持とコスト抑制に欠かせない。こういったトランプ政権とシリコンバレーのせめぎ合いが、テクノロジーの未来を決めるのである
(The Washington Post / Getty Images)

手塚 沙織 南山大学外国語学部英米学科准教授
専門は、人の国際移動、移民政策、国際政治経済学。同志社大学経済学部卒業、同志社大学大学院経済学研究科応用経済学博士前期課程修了、カリフォルニア大学ロサンゼルス校(UCLA)留学を経て、同志社大学大学院グローバル・スタディーズ研究科グローバル社会専攻博士後期課程修了、博士(グローバル社会研究)。
書籍等出版物
・米中間の人の流れの再構築:米中の求心力とディープシークの衝撃」『CISTECJournal』218号, 安全保障貿易情報センター, 2025年7月, 77-87頁.
・「米中間の高度人材をめぐる攻防と技術覇権の行方」『CISTEC Journal』200号, 安全保障貿易情報センター, 2022年7月, 166-174頁.
・「米印間の高度人材の移動をめぐる齟齬とせめぎあい―WTOへの訴訟から」明石純一編著『移 住労働とディアスポラ政策―国境を越える人の移動をめぐる送出国のパースペクティブ』筑波大 学出版会, 2022 年, 120-145頁.

地経学ブリーフィング
コロナウイルス後の国際政治と世界経済の新たな潮流の兆しをいち早く見つけ、その地政学的かつ地経学的重要性を考察し、日本の国益と戦略にとっての意味合いを精査することを目指し、アジア・パシフィック・イニシアティブ(API)のシニアフェロー・研究員を中心とする執筆陣が、週次で発信するブリーフィング・ノートです(編集長:鈴木一人 地経学研究所長、東京大学公共政策大学院教授)。
おことわり:地経学ブリーフィングに記された内容や意見は、著者の個人的見解であり、公益財団法人国際文化会館及び地経学研究所(IOG)等、著者の所属する組織の公式見解を必ずしも示すものではないことをご留意ください。