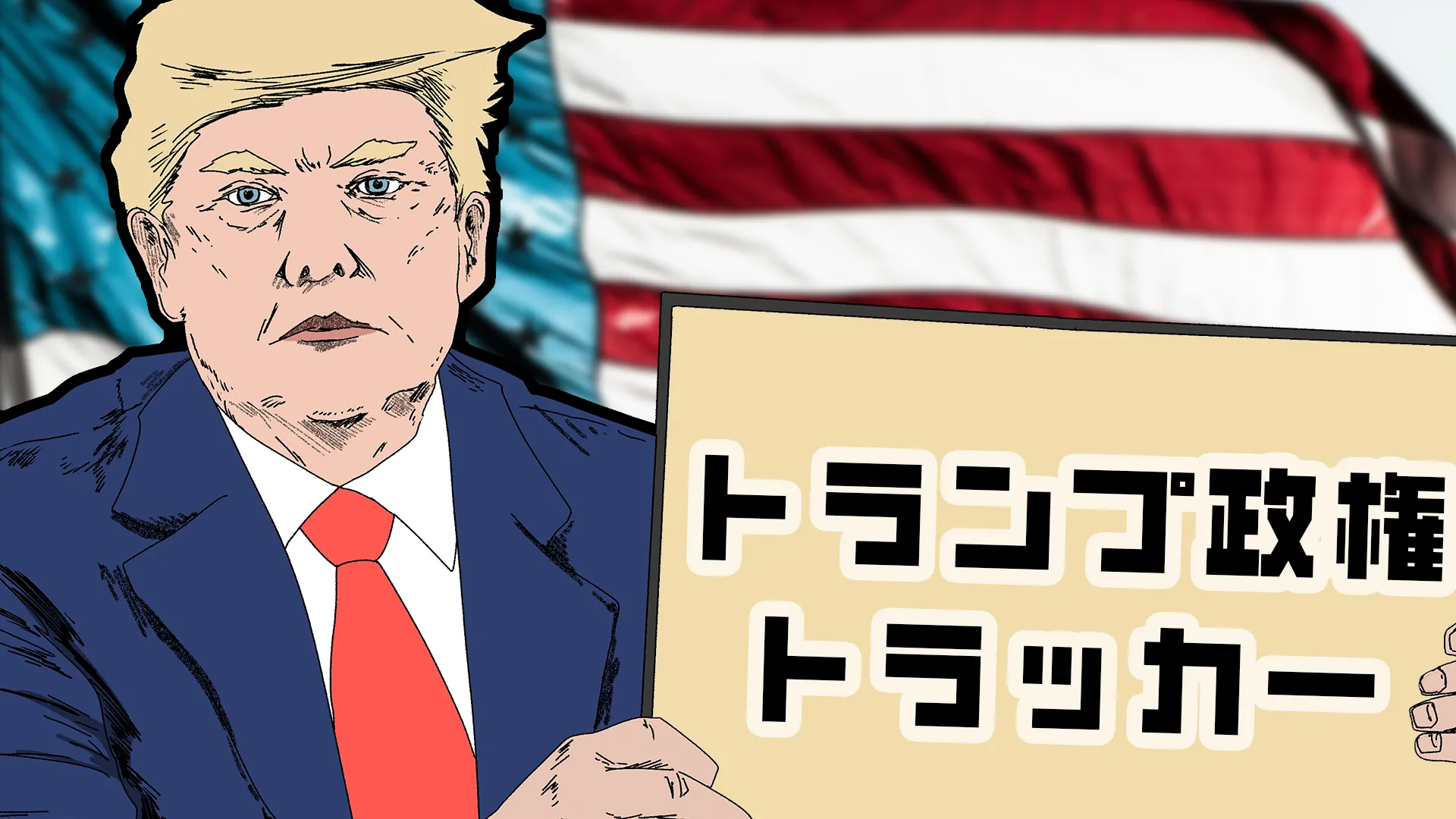中国は国際分業をどう変えようとしているのか -レアアース輸出規制から見る中国の方向性-

このような中国企業の躍進を可能にしたのは、自由貿易とそれを支える世界貿易機関(WTO)を中心とする多国間主義という、第二次大戦後の国際経済秩序であった。モノや資本は、政治体制の相違とは関係なく国境を越えて移動することができ、多国籍企業はより安価な材料や労働力を求めて世界各地に拠点を設け、各地が役割分担する国際的な分業体制が生まれた。中国は、世界中の大企業を引きつけて「世界の工場」となり、産業の集積により技術力を向上させ、世界の付加価値の3割を生み出す製造大国になった。
したがって、第二次トランプ政権が「相互関税」を課し、中国企業を排除し始めれば、中国が「自由貿易の擁護者」を主張して対抗するのは当然の流れである。だが、別稿で指摘したとおり、中国は新しい経済秩序を構築する意図はあっても、能力はまだない。では、中国は自国経済をどう導き、世界経済とどう関わろうとしているのか。最近の中国によるレアアース輸出規制を切り口に考えてみたい。
レアアースを武器にする中国
中国は自他共に認めるレアアース大国である。1992年1月に鄧小平氏が「中東に石油があり、中国にレアアースがある」と述べたように、中国は、以前からレアアースを独占的に供給していることの戦略的意義を理解し、時に外交上の武器として使ってきた。2010年の尖閣諸島沖漁船衝突事件における対応を不満として、日本向けに輸出を止めたのがよい例である。
中国をレアアース大国にしたのも国際的な分業体制であった。レアアースは、銅や亜鉛といったベースメタルに比べて国際的な需要は極めて少なく、需給の変化を受けやすい不安定な産業である。また、精錬過程で放射性物質が排出される等、レアアース産業は環境への負荷が大きい。さらに、レアアースは採掘・精錬段階よりも、それをモーターや磁石などに製品化することで付加価値が大きくなる。先進国経済は、環境基準の緩い中国に採掘や精錬過程を移し、そこからレアアースを輸入して製品に加工する体制を構築してきた。
一方、中国政府は2000年前後から輸出量を段階的に制限するなど、重要鉱物の輸出管理を強化してきた。2010年7月、温家宝国務院総理(当時)は訪問先のドイツで、「中国はレアアースの輸出を停止することは決してないが、レアアースの取引は適正な価格、適正な数量で行われるべきである」と述べている。2014年に当時の輸出管理制度がWTO違反と認定されると、中国は、それを廃止して輸出許可制を開始しており、一貫してレアアース供給を制限してきた。また、2010年代からレアアース企業の整理統合を進め、2021年には国内のレアアース産業を大手4社に集約するなど、国内生産への統制も強めてきた。
中国は、2023年8月からガリウムや黒鉛などを輸出管理対象に追加し、昨年12月にはこれら鉱物の対米輸出審査を厳格化した。また、今年2月にはタングステンなどの重要鉱物を、4月にレアアース7種類を、10月には5種類のレアアースとレアアース精錬技術等を規制対象に追加した。これら輸出管理強化が、米国の対中規制への対抗措置であることは言うまでもない。ただし、これらは従来からの輸出管理強化の延長にあり、発動するタイミングを利用して、米国への対抗措置として使っただけだろう。だからこそ、中国は、10月末の米中首脳会談において、輸出管理強化の一部延期などに同意している。
規制強化の狙い
では、何故中国はこの数年、レアアースの輸出規制を強化するのだろうか。中国当局は、過去の経験から、輸出規制はいわば諸刃の剣であり、それにより自国産業が痛むことを理解しているはずである。2010年の日本への輸出規制によって、中国産レアアースへの日本の依存度は大きく下がり、代替材料の使用も進んだため、多くの中国レアアース企業が倒産に追い込まれた。実際、今回も、中国以外での採掘やリサイクルの推進、代替技術の研究といった中国依存脱却の動きが見られる。
それでも輸出規制を強化するのは、中国が産業の高度化を真剣に進めようとしているからであろう。中国当局は、輸出管理を強化することで、レアアース産業のような付加価値が低く、環境汚染をもたらす「汚い」産業はもはや支援しない、付加価値のより高い産業に従事せよ、というメッセージを国内に出している。また、レアアースの輸出規制により、先進国産業界のサプライチェーンは混乱するが、中国としては、この機会に、中国産レアアース製品を世界に売り込み、国内の製品化技術を向上させたいとも考えている。さらに、レアアースへのアクセスをテコに、ハイエンド製造業を中国国内に呼び込みたいという思惑もあるだろう。
レアアースは引き続き戦略的に重要であり、中国はレアアース産業を放棄するつもりはない。だが、中国は2000年代から産業構造の高度化を進めており、対外輸出製品の中心も衣類、家具、家電(「旧三様」)から電気自動車(EV)、リチウムイオン電池、太陽光発電(「新三様」)へと先進化した。産業構造の変革に自信をつけ、中国指導部はいまや、レエアース産業のような自国が国際的優位性を持つ産業にも更なる高度化を迫っている。
自信をつける中国
また、中国の最近の輸出規制は全世界を対象としている。米国への対抗措置であれば、昨年12月のように、米国のみを対象にした方がシグナル効果は大きい。中国による経済の武器化は今に始まったものではないが、これまでは二国間の措置として使ってきた。経済成長と産業の高度化に自信をつけ、中国は、世界全体に対して経済を武器として使い始めている。レアアース輸出規制を強化し、世界経済に影響を及ぼすことで、「付加価値が低く、環境汚染だけ負わされる国際分業はもうしない」と分業体制の変更を迫っている。特に、レアアース精錬による環境汚染はひどいので、「他国で出来るものであればやってみろ」とも思っているだろう。
今年10月の輸出管理強化では、中国国外で製造された製品でも中国の輸出管理対象レアアースを含む場合には、輸出に中国の許可が必要だとして域外適用を行った。この規制の実施は延期されたが、中国は、自国のレアアースを使うのであれば中国の安全保障に配慮し、中国と良好な関係を維持することを求めている。中国は、自国に有利な国際分業体制を築こうとするだけでなく、経済を武器として各国に中国との関係の見直しを求めている。
日本に求められる対応
米国は、行き過ぎた国際分業による国内製造業の没落に危機感を覚え、関税を使って各国に対米投資や米国製品の購入を迫り、分業の見直しを求め始めた。日本は巨額の対米投資を約束することで、この米国の変化についていくことにコミットした。米国との関係を安定化させた日本は、次は、中国の変化に対応することが求められる。
中国は経済の武器化に自信を深めている。日本は、中国に依存している物資の調達を多様化し、代替物資の利用を推進していくことが急務であり、南鳥島周辺でのレアアース開発やレアアースフリー技術の開発、同志国との連携強化などを進めていく必要がある。また、中国は産業の高度化を進めているが、拡大しない内需や一部技術を外国に依存するといった課題も抱えている。日本は、これまでの国際分業体制を当然とせず、中国をどう利用するかを考え、対応していく必要がある。中国を上手く活用することは、米国との関係を進める上でも有利になる。
(出典: CFOTO/Getty Images)

地経学ブリーフィング
コロナウイルス後の国際政治と世界経済の新たな潮流の兆しをいち早く見つけ、その地政学的かつ地経学的重要性を考察し、日本の国益と戦略にとっての意味合いを精査することを目指し、アジア・パシフィック・イニシアティブ(API)のシニアフェロー・研究員を中心とする執筆陣が、週次で発信するブリーフィング・ノートです(編集長:鈴木一人 地経学研究所長、東京大学公共政策大学院教授)。
おことわり:地経学ブリーフィングに記された内容や意見は、著者の個人的見解であり、公益財団法人国際文化会館及び地経学研究所(IOG)等、著者の所属する組織の公式見解を必ずしも示すものではないことをご留意ください。
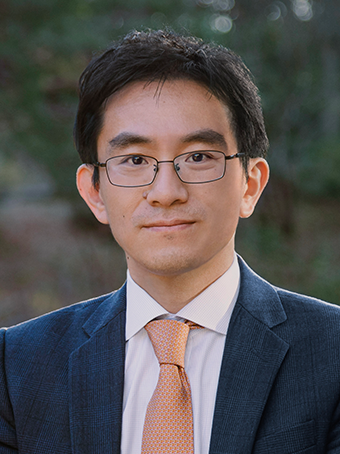
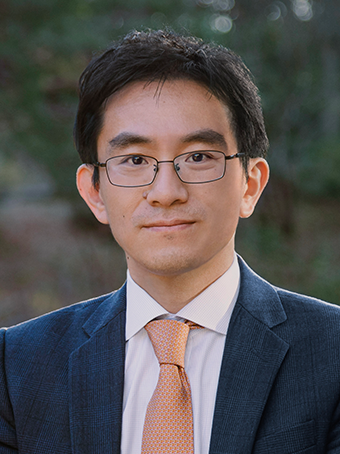
主任客員研究員
東京大学法学部卒業後、2001年4月に外務省入省。中国・南京大学及び米国・ハーバード大学(修士号取得)を経て、在中国大使館において勤務。その後、中国・モンゴル課において、4年間に10回の首脳会談、12回の外相会談などのハイレベル会談の準備に従事した他、「日中高級事務レベル海洋協議」の立上げや「日中海上捜索・救助(SAR)協定」の原則合意に関する交渉を担当・主導した。また、日米地位協定室首席事務官として、「軍属補足協定」の締結や沖縄の負担軽減政策に関する日米交渉を総括した。在外勤務では、国連代表部において、安保理改革に関する各国との調整や世界的な働きかけを担当した他、在中国大使館において、中国経済や米中経済対立に関する情報収集・分析に従事。その他、二度の人事課勤務において、組織マネージメントも経験。2022年4月に外務省を退職。
プロフィールを見る