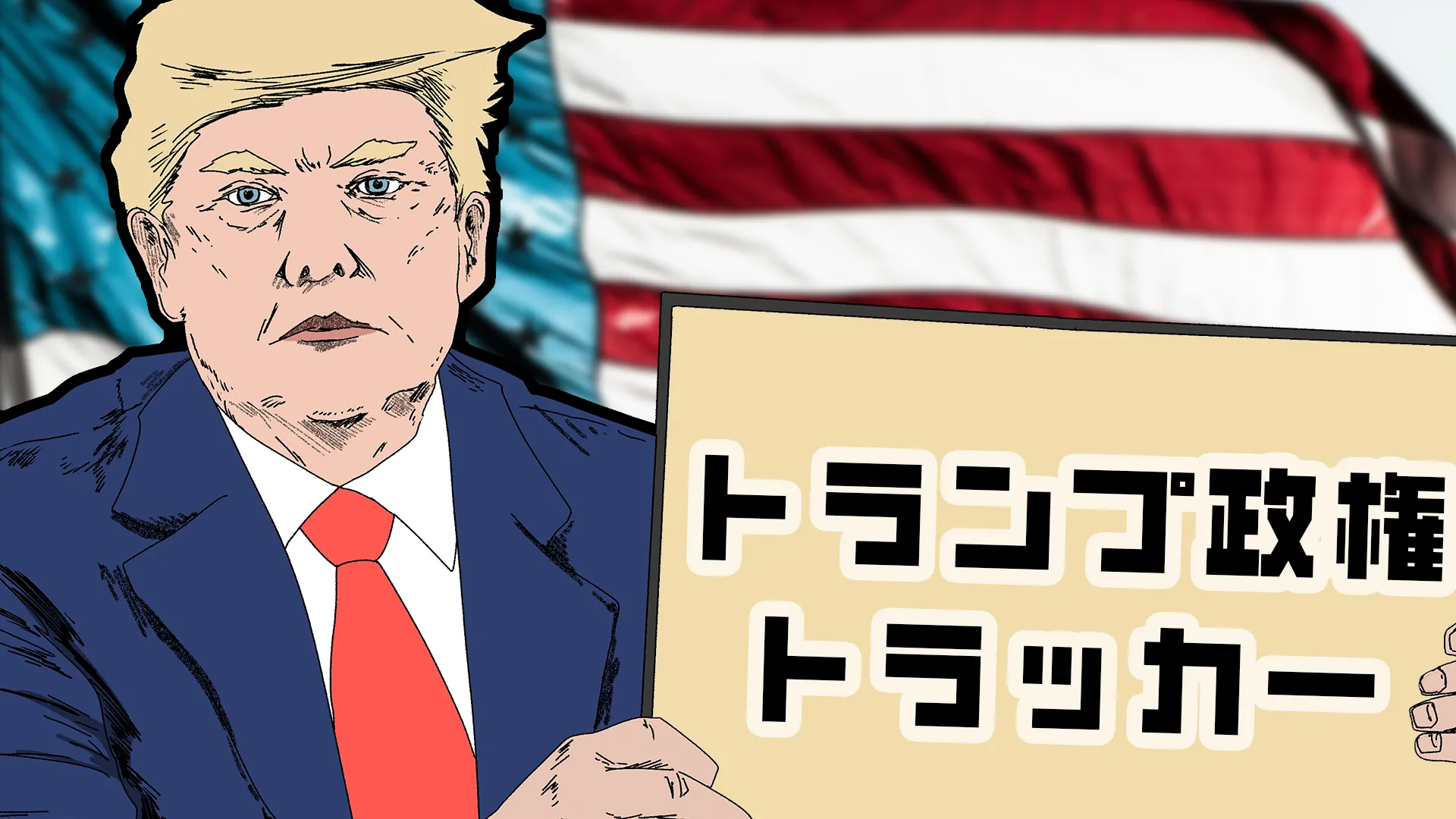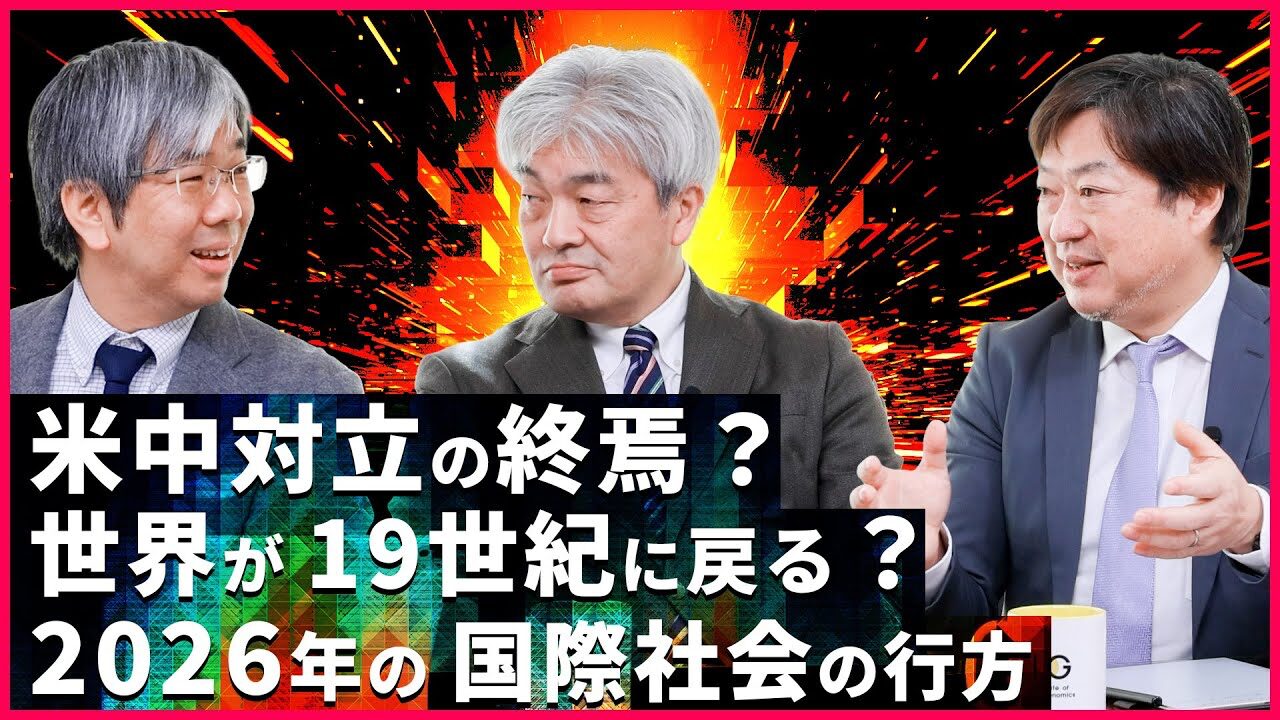だれが「戦後国際秩序」の担い手か -第二次大戦をめぐる中国の戦略的ナラティブ-

2025年5月、ロシアの「大祖国戦争勝利80周年」にあたり、習近平・中華人民共和国国家主席は、ロシア政府機関紙『ロシースカヤ・ガゼータ』に寄稿した。「歴史を鑑とし、ともに未来を創ろう」と題した文章のなかで習主席は、「正しい第二次世界大戦史観を堅持せねばならない」こと、「戦後の国際秩序を断固として守らなくてはならない」ことを述べた。では、習主席のいう「正しい第二次大戦史観」とは何か。「戦後国際秩序を守る」ことで中国は何を達せようとしているのか。
本稿は、第二次大戦の史的解釈をめぐり習近平政権が国際的に展開する言説・ナラティブの特徴と意図を整理し、それが既存の秩序や日中関係に与えうる影響を考える。
「戦後国際秩序」の創設者を主張する中国
習政権の日中戦争および第二次大戦をめぐる語りは、江沢民・胡錦濤政権期から、漸進的ではあるが大きく変化していることが指摘されている。そのひとつに、侵略を受けた被害者としての物語から、連合国の主要国として勝利し、戦後国際秩序の創設者となった物語への変化が加速度的に進んでいることがあげられる。2014年9月の戦勝69周年記念座談会において習主席は、日本の満洲侵攻(1931年)に対する中国共産党の抵抗に始まる抗日戦争は「世界反ファシズム戦争」においてもっとも早く始まり長く戦われた「東方主戦場」であり、その「重要な構成部分であった」との見方を示した。さらに「抗日戦争と世界反ファシズム戦争の勝利の成果を断固守り、戦後国際秩序を断固維持すべき」と強調した。中国(共産党)は、連合国を第二次大戦勝利に導いた主要アクターの一角であり、現在へと連なる「戦後国際秩序」の創設者なのであり、ゆえに、それを守る立場と責任を有する。これが、習主席が述べる「正しい第二次大戦史観」である。
この歴史観は、中国を既存秩序に対する挑戦者と位置づける「リベラルな国際秩序」への「カウンター・ナラティブ」として提唱されたものと考えられる。そして、2025年に入って中国は、この国際秩序をめぐる言説上の対抗においてさらなる攻勢を仕掛けている。第一に、戦後80周年のタイミングで中国は「戦後国際秩序を維持する」というタームをより頻繁に用いている。周知のごとく米国のトランプ政権は、数々の国連機関からの脱退を表明し、WTO(世界貿易機関)の理念に背くような高関税を諸外国に課している。中国はどうやらこの状況を利用(exploit)している。5月に発表された中央党校国際戦略研究院院長の論説によれば、「戦後国際秩序」は、国連を中心とする政治体系、IMF(国際通貨基金)・WTOを中心とする経済体系、「多国間主義」の理念、「カイロ宣言」「ポツダム宣言」の法理根拠、を中核とするという。習政権がこれらを強調する意図は、中国でなく米国こそが既存秩序への挑戦者であることを示唆することにあろう。5月の「中露共同声明」は、あきらかに米国を念頭において「個別の国は…自身の覇権や私利を追求し、第二次大戦勝利の成果を改ざんすることを企図し、戦後国際秩序の原則を転覆し、国連の世界の平和と安全を維持する核心作用を弱めている」と非難した。
第二に中国は、「台湾が中国に帰属することは戦後国際秩序の重要構成部分である」との主張を、とりわけ2025年3月の王毅・外交部長の発言以降、より強く打ち出している。「カイロ宣言」(1943年)は台湾および澎湖諸島の中国への返還を明言しており、「ポツダム宣言」(45年)はその履行を命じている。それらの最終帰属先を明示していない「サンフランシスコ平和条約」(1951年)は中国が署名しておらず違法かつ無効。だから、中国によって台湾が統一されていることが、本来「戦後国際秩序」の正しい状態であるとの主張だ。
この言説は南シナ海にも拡張されている。新華社研究院が2025年8月に中国語と英語で発表したレポートは、飛躍的にも、「カイロ」と「ポツダム」により南シナ海島嶼が法的に中国に帰属することは明確と述べ、これを否認することはすなわち「戦後国際秩序の否定、国際法に対する公然たる違背である」などと主張する。このように、戦後80周年に際して中国は、「戦後国際秩序」というタームのなかに自らの領土主張を落とし込む「認知戦」「法律戦」を強化している。
習近平政権のナラティブの国際的伝播と日本
中国は、9月3日の戦勝記念日に前後して、在外公館の主催ないし現地組織との共催による、シンポジウム、研究会、座談会、晩餐会、パネル展示、映画上映会、音楽会など各種形式の「抗日戦争および世界反ファシズム戦争勝利80周年記念活動」を活発に行っている。外交部や各大使館のウェブページでは、ほぼすべての国で複数の関連イベントが開催されていることを確認できる。各地の大使や総領事は、このような場を、自国のナラティブを披露し、共有する場として利用している。また、公表されている限りで計88ヵ国の複数のメディアで、戦後80周年に関する大使署名の寄稿文が掲載されている。その内容は総じて、①中国が国連中心の「戦後国際秩序」の創設者にして一貫した守り手であったこと、②台湾の中国への帰属は戦後国際秩序の重要構成部分であること、および③戦後80周年にして「個別の国」が一国主義や強権いじめ行為を強めるなか、これに反対し、中国とともに「人類運命共同体」を構築すべきことを主張するものだ。
他方、抗日戦争勝利80周年のタイミングにもかかわらず、尖閣諸島の支配をめぐり日本を「戦後国際秩序」への挑戦者と位置づける、2012~14年頃に活発に展開された言説は、現在鳴りを潜めている。しかし、中国の主張は、尖閣は台湾の付属島嶼の一部で、「下関条約」により日本に「割譲」されたというものであるから、台湾の法的地位に関する言説は日本に直接関わる。なにより、中国は東シナ海における法執行機関の活動を段階的に強化し、2023年頃からは沖縄への影響工作も活発化させている。中国はこうして、「認知戦」、「法律戦」、あるいは「歴史戦」と、力を用いた威圧の両方を強めている。それは言い換えれば、「戦後国際秩序を守る」ことを主張し、国際社会からの反発を可能な限り抑えながら、現行の国際秩序(status-quo)を変更しようとする試みである。
これに日本としてどのように対処すべきだろうか。日本単独での反論は空中戦となりかねず、望ましくは、広く国際社会の同調を得ることで言説空間における優位を確保したい。第一に、戦後の国際秩序の根幹が「武力による威嚇又は武力の行使」を禁ずることによる平和の希求にあることを、諸外国とともにあらためて強調すべきだ。ウクライナ侵攻を続けるロシアはもちろん、それとの蜜月関係を維持し、南シナ海や東シナ海において力を用いた威圧を強化する中国の行動は、既存の秩序に背馳する。そのことを可視化し続けることは、習政権の言説の浸透を防ぐうえで有効なことのひとつだろう。第二に、中国が2012年より強く打ち出している「サンフランシスコ平和条約」は「違法かつ無効」という主張に対して、条約に署名・批准した40以上の国々とともに、あらためてその意義を確認することも必要だろう。すでに頼清徳政権下の台湾は中国の言説に抗して「サンフランシスコ」の有効性を強調する主張に転じており、米国(在台協会)もこれに同調している。中国が署名していないことを理由に、この条約を起点・基盤に戦後アジア太平洋の国際秩序を維持してきた諸国家・地域の営みが否定されるべきではない。
中国は、国連中心や多国間主義といった、広く共有されている価値の一部をプレイアップして「戦後国際秩序」を定位し、そのなかに台湾や南シナ海の主権といったきわめて論争的な問題を組み込んでいる。習政権はどうやら、欧米諸国が主導し構築してきた言説を覆すのではなく、いくつかの要素を選択的に取り入れながら自国に有利な言説空間を造り上げようとしている。その巧妙さに加え、米国の規範的な力が低下し、中国の経済的影響力が増しているなか、習政権の言説を取るに足らない妄言として座視することは許されない。だれが戦後国際秩序の担い手で、だれがそれに対する挑戦者なのか。そのナラティブをめぐる競争はすでに始まっているのだ。
(出典: 朝日新聞 / Getty Images)

角崎信也 霞山会主任研究員
2011年慶應義塾大学大学院法学研究科後期博士課程単位取得退学。日本国際問題研究所研究員、人間文化研究機構総合人間文化研究推進センター研究員などを経て24年4月より現職。共著に小嶋華津子・磯部靖編『中国共産党の統治と基層幹部』慶應義塾大学出版会、2023年、蔡東傑・韓碩熙・青山瑠妙編『中國周邊外交 : 台日韓三方比較新視野』五南圖書出版、2023年、国分良成・小嶋華津子編『現代中国政治外交の原点』慶應義塾大学出版会、2013年など。

地経学ブリーフィング
コロナウイルス後の国際政治と世界経済の新たな潮流の兆しをいち早く見つけ、その地政学的かつ地経学的重要性を考察し、日本の国益と戦略にとっての意味合いを精査することを目指し、アジア・パシフィック・イニシアティブ(API)のシニアフェロー・研究員を中心とする執筆陣が、週次で発信するブリーフィング・ノートです(編集長:鈴木一人 地経学研究所長、東京大学公共政策大学院教授)。
おことわり:地経学ブリーフィングに記された内容や意見は、著者の個人的見解であり、公益財団法人国際文化会館及び地経学研究所(IOG)等、著者の所属する組織の公式見解を必ずしも示すものではないことをご留意ください。