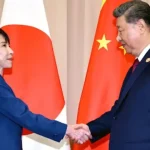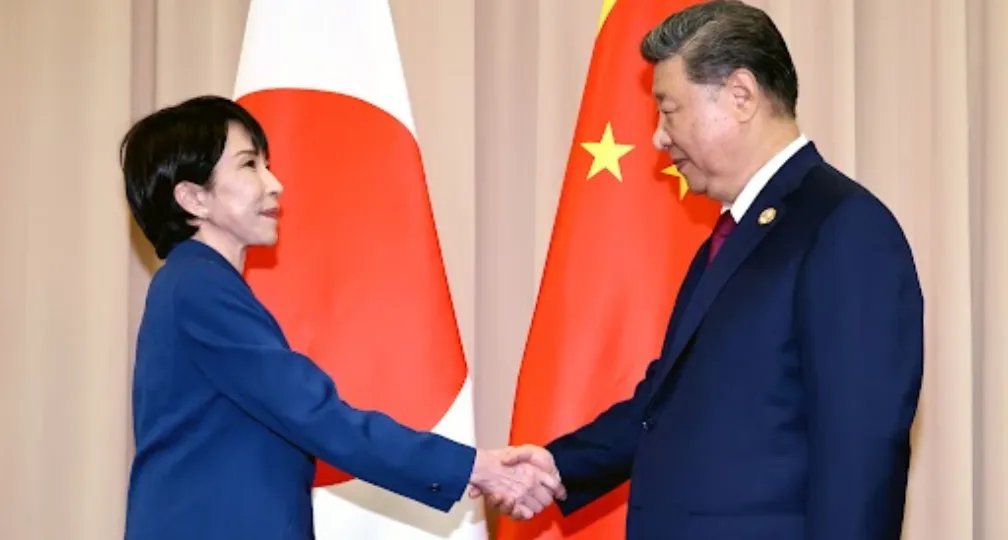地球儀を回さない対外政策言説 ードンロー主義と共和党外交の展望ー

地球儀を回さない対外政策
ここ最近、トランプ政権下の西半球政策を論じる際に「ドンロー主義(Donroe Doctrine)」という造語が専門家の間で用いられるようになっている。この言葉は、モンロー主義(Monroe Doctrine)をもじりつつ、「ドン」(ドナルドの愛称)の名を冠することで、歴史的な西半球政策との連続性と非連続性を同時に示唆する表現である。CNNのまとめによると、この用語は第2次トランプ政権発足直前の2025年1月8日付の保守系タブロイド紙「ニューヨーク・ポスト」が一面に掲載したのが初出であり、2025年秋ごろから主要メディアで一般化したとされる。また、マドゥロ拘束作戦(アブソリュート・リゾルブ作戦)後の記者会見では、トランプが自ら「ドンロー主義」に言及した。
このドンロー主義は、2025年版国家安全保障戦略(NSS2025)に見られる「モンロー主義のトランプ・コロラリー(補遺)」という表現をそのまま言い換えたものではない。ドンロー主義とはむしろ、国内秩序の問題との関連で世界を見るMAGA的空間認識を、外部の観察者が後付けで戦略的地理区分の系譜に接続することで概念化したものである。従って、モンロー主義のトランプ・コロラリーの意味内容としてNSS2025が挙げる西半球からの域外競争国の排除は、後で見るように、ドンロー主義の枠内で肯定されるものの、論理必然的に導かれる方針ではない。
トランプ以前の米国の西半球政策は、常に地球儀を俯瞰する統治エリートの視点を前提に形成されてきた。原義モンロー主義は旧大陸と新大陸の地理的・統治体制的分離を基礎に、欧州列強の干渉を排除する防御的原則を定立した。セオドア・ローズヴェルトのコロラリーは、マハンのシーパワー論から影響を受けつつ、「東(欧州)に干渉しないことの反対解釈として、南(中南米)と西(太平洋)には介入してよい」という地理的拡張を試みたものである。冷戦期のレーガン主義的保守派は、地球儀をぐるぐる回しながら、世界各地の社会主義勢力を率いるソ連との大国間・体制間競争の文脈で西半球を戦略的後背地と定義し、中南米の社会主義政権・左翼勢力の打倒に注力した。
これに対し、ドンロー主義の最大の特徴は、その地球儀をテーブルから払い除ける点にある。その思考の起点は、書斎や会議室の地球儀ではなく、米国内の一般市民、特にエリート層から見捨てられたと感じているMAGA支持層の玄関先の風景にある。彼らにとっての脅威とは、国際秩序に対する挑戦や、遠く離れたユーラシア大陸外縁における抑止の破綻ではなく、自らの生活圏に流れ込む不法移民であり、コミュニティを破壊する麻薬であり、国境を越えて浸透する犯罪組織である。ドンロー主義において、西半球は国際戦略上の後背地である以前に、「米国社会の安定を蝕む問題の震源地」として把握されるのである。
この認識を裏付けるのが、2026年1月に発表された国家防衛戦略(NDS2026)の記載ぶりである。同文書の「本土と西半球」に関するセクションは、冷戦後のワシントンの意思決定者に対する痛烈な批判から始まり、核兵器やサイバー、電磁波攻撃といったアメリカ本土に向けられる直接的な軍事的脅威への言及よりも先に、不法移民や麻薬組織への対応が国防上の最優先課題として列挙される。NSSを軍事的観点から具体化すべきNDSにおけるこのような記述順序は、同文書の主要執筆者と目され、対中優先論者(プライオリタイザー)として知られるコルビー国防次官の従前の戦略観からは導かれないものであり、政権内におけるMAGA的言説の卓越と、それに対するコルビーの適応を示唆している。
介入の内在論理とベネズエラの矛盾
トランプ的世界観においては、対外政策と国内政策の境界線が消失し、西半球への介入は国際主義的対外関与ではなく、国内の治安維持の地続きと捉えられる。そこで貫徹されるのが、スティーヴン・ミラー次席補佐官らが主導する、不法移民と麻薬に対する「軍事化された法執行」の論理である。ここでは、不法移民や麻薬犯罪は「米国の血を毒する存在」と定義され、その社会秩序攪乱的性格が強調される。また、州の管轄権や適正手続きなどの法執行を拘束してきた規範の遵守よりも、結果としての秩序回復を最優先する評価基準が前景化し、法執行と軍事力行使のあいだに引かれてきた規範的・組織的境界が曖昧化している。このような傾向は、連邦化された州兵の支援を受けたICE(移民・関税執行局)による強硬な不法移民の摘発として前景化し、ミネソタ州での相次ぐ市民射殺事案に至った。トランプがICEへの抗議活動に対して反乱法の適用を示唆していることは、かかる評価基準の転換が大統領自身によって公然と承認されていることを象徴している。
ミネアポリスの街頭で行使されるこの法執行のロジックは、そのままカリブ海を越えてカラカスへと延長される。MAGA的認識において、米国内の不法移民と、「麻薬テロリスト」としてのマドゥロは、いずれも米国の社会秩序を攪乱する要因として同一の脅威カテゴリーに属する。従って、マドゥロ拘束作戦は、主権国家への軍事侵攻としてではなく、秩序回復を目的とする法執行の域外適用として正当化される。同作戦にDEA(麻薬取締局)職員が随行したことはその証左である。
ところが、国内社会問題の原因排除という視点だけでは、移民対策と麻薬対策の両面で、ベネズエラに対する軍事行動を説明できない。トランプ政権の関心は、経済崩壊と弾圧により多数の逃亡者を生むチャビスタ体制の是非ではなく、米国への流入阻止という結果のみにある。こうした考え方の表れが、政権発足後半年間の対ベネズエラ政策であった。かつてのレーガン主義は、社会主義体制から逃れる者を自由の希求者として保護の対象としたが、ドンロー主義はそうしたイデオロギー的色分けを認めない。自由を求める亡命者であれ、経済難民であれ、トランプ政権によって国際テロ組織(FTO)に指定されたベネズエラ系国際犯罪組織トレン・デ・アラグアの構成員であれ、ベネズエラ人は「不法越境者」という等質なカテゴリーへ還元される。第2次トランプ政権は発足後まもなく、ベネズエラ系不法移民の一時保護ステータス(TPS)を取り消した。さらに、不法移民送還便を受け入れさせる代わりに石油大手シェブロンのベネズエラでの操業ライセンス再発行を認めるとする交渉が、リック・グレネル特使によって主導された。グレネルは、ルビオをタカ派すぎるとみなすMAGA派から国務長官への指名を待望されたように、従来のエスタブリッシュメント的外交路線の否定を象徴する人物である。ベネズエラ系有権者が多く住むフロリダ州南部選出の共和党議員ら(マリオ・ディアス=バラート、マリア・エルビラ・サラザール、カルロス・ヒメネス、いずれもキューバ系)はこの交渉に強く反対したが、彼らが2025年財政調整法への賛成投票留保というレバレッジを失った7月末にこの「ディール」は成立している。
麻薬対策の観点でも、チャビスタ体制幹部(いわゆる「太陽のカルテル」)の関与によってベネズエラを経由するコカインの密輸は米国の麻薬問題のごく小さな部分に過ぎず、マドゥロ個人の拘束が抜本的解決策とはならない。最も米国人の命を奪っているのはメキシコ経由のフェンタニルであり、コカイン流入の最大経路は主要産地コロンビアから直接太平洋を経由してカリフォルニアに至るルートである。
ルビオとヴァンスが奪い合うドンロー主義
この論理的空白を埋め、夏以降の対ベネズエラ政策の急激な軍事化を導いたのが、ドンロー主義の、いわば「ルビオ・コロラリー」である。ルビオ国務長官は、ドンロー主義の枠内に留まりながら、大国間競争の視点を西半球限定的に再導入しようとする。彼は中国、ロシア、イランがベネズエラを通じて西半球に足場を築くことを、米国本土防衛上の死活的問題として位置づける。この補遺によって、ベネズエラは麻薬と移民の震源地であるばかりでなく、敵対勢力が米国の背後に築いた橋頭堡であるという視点が追加され、マドゥロ排除の軍事作戦の正当化が補強される。NDS2026が「19世紀の先人たちは米国の安全のために西半球でより強力な主導権を握る必要性を認識していた」とモンロー主義を引用する部分は、まさにこのルビオ的補遺を戦略文書として定式化したものといえる。この意味で、NSS2025で提示される「モンロー主義のトランプ・コロラリー」は、「ドンロー主義のルビオ・コロラリー」と機能的に等価である。
ここで重要なのは、ルビオには「ルビオ・ドクトリン」を独自に定義する自由がないという点である。2024年大統領選の共和党予備選において、レーガン主義の正嫡を継ぐ保守国際主義を掲げたニッキー・ヘイリーがトランプによって一蹴され、副大統領候補にMAGAの筆頭であるヴァンスが据えられた時点で党内の勝負は決している。MAGAの言葉を叫びつつそこにレーガン主義的語彙を補遺として滑り込ませる、いわば翻訳者としての役割は、2028年の大統領選を窺う未来ある政治家としてのルビオの生存戦略といえよう。ドンロー主義のルビオ・コロラリーとは、国際主義の復権ではなく、むしろ国際主義がMAGAの軍門に降り、その実装形態の一つとして従属的立場に追いやられたことの表現といってよい。ベネズエラ沖の「麻薬密輸ボート」攻撃(サザン・スピア作戦)を主導したのがミラーの国土安全保障会議であったことに鑑みても、政策転換はルビオ独自の成果というよりも、彼がミラーの掲げる「軍事化された法執行」の論理との間に従属的な提携関係を結んだゆえに実現したと考えるのが妥当である。
他方で、ルビオの「翻訳」に冷ややかな視線を送るのが、ヴァンスに代表される、より孤立主義的な勢力である。2025年3月のいわゆる「シグナル・ゲート」事件で明らかになったように、ヴァンスは国内労働者層の負担を重視する反介入主義的ポピュリズムを体現しており、その関心は一貫して対外関与のコストに向けられている。アトランティック誌に漏洩したやり取りによれば、彼はスエズ運河を通過する取引が米国の貿易の3%に過ぎないのに対し欧州は40%に上ることを指摘し、フーシ派空爆を欧州のための肩代わりとして批判した。ドンロー主義の「ヴァンス・コロラリー」においては、対外軍事行動はそれが国内の安全や雇用に短期的に直結しない限り、原則として拒絶すべきものである。彼にとって、ベネズエラへの深入りは、かつての中東での失敗の再来を予感させる危うい試みに映る。ヴァンスが介入を擁護する場合でも、それは役職上の責務であり、思想的な一致を意味しない。ドンロー主義の下では、この「伝統的な戦略的観点を援用して介入を正当化するルビオ」と、「コストと実利を冷徹に計算して介入を抑制しようとするヴァンス」という二つの補遺が恒常的に競合し、トランプの気まぐれな決断を奪い合うことになる。
ドンロー主義的介入の帰結と共和党外交の展望
この文脈において、トランプ政権がベネズエラの民主化に対して冷淡であるのは、極めて正当な帰結である。ドンロー主義において、民主化や制度改革は、米国の社会秩序攪乱要因の除去という目的に対する手段的価値を持たない。ベネズエラで求められるのは民主的な大統領ではなく、米国への移民と麻薬を物理的に遮断し、石油を中国やキューバに渡さない「管理能力」である。WSJが報じたCIAの分析では、マドゥロ排除後の統治主体として、エドムンド・ゴンザレスやマリア・コリーナ・マチャドといった民主的右派は最適解とはみなされなかった。彼らは道徳的正当性こそ備えているが、チャビスタが浸透している軍や情報機関を掌握し、国内の混乱を即座に収拾する物理的な強制力を欠いていると判断された。他方、現体制内の実力者であるディオスタド・カベージョやウラジーミル・パドリーノといった強硬左派も、その権力基盤が反米感情の喚起に依存しているため、米国の国内秩序回復に向けた協力相手としては不適格であった。この消去法の果てに浮かび上がったのが、デルシー・ロドリゲスという実務能力と体制掌握力を兼ね備えた人物を通じた「間接統治」である。
イデオロギー的価値判断を排した非情ともいえる帰結主義は、国家建設を否定するMAGA的世界観と整合的である。2028年の大統領選挙は、このドンロー主義がどこまで純化されるかの試金石となるだろう。もはや争点は国際主義かアメリカ・ファーストか否かではない。ルビオのように伝統的論理を補遺として接合し続けるのか、それともヴァンスのように戦略的・イデオロギー的レトリックを排した純粋な国内論理へと突き進むのか。共和党の指名争いは、地球儀を捨て去った後に残る対外政策言説を競う場へと変質している。
ドンロー主義とは、新たな国際戦略ではなく、国内政治の論理の対外的投射である。同盟国にとって重要なのは、いま前景化しているルビオ・コロラリーが、ドンロー主義の枠内で、既存の外交言説との摩擦が相対的に小さい実装形態であるという点である。ドンロー主義の基底にあるのは会議室で地球儀を回すことを拒否するMAGA的感情である。将来、ヴァンス・コロラリーが前面に出ることがあれば、同盟関係は米国とりわけMAGA支持層に実利をもたらさない単なるコストとしてさらに厳しく切り捨てられていくだろう。
(出典:アフロ)


リサーチ・アシスタント
東京大学法学部卒業、同法学政治学研究科総合法政専攻修士課程修了。2020年4月より博士課程。専門は現代アメリカの政治と外交。中曾根康弘世界平和研究所米国政治外交研究会支援研究員(2022年度)を経て現職。地経学研究所にて、政治・外交についての米国の論壇の動向調査に従事。
プロフィールを見る