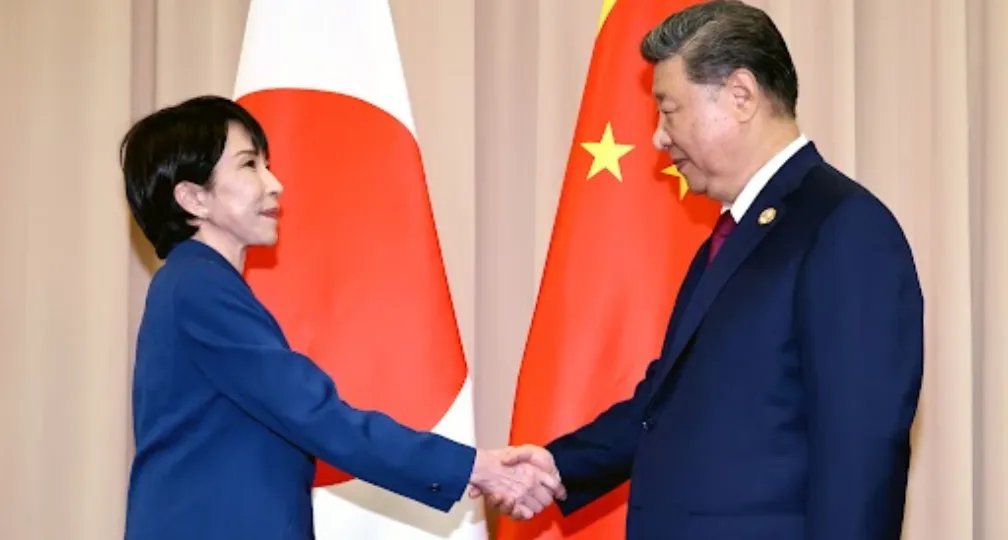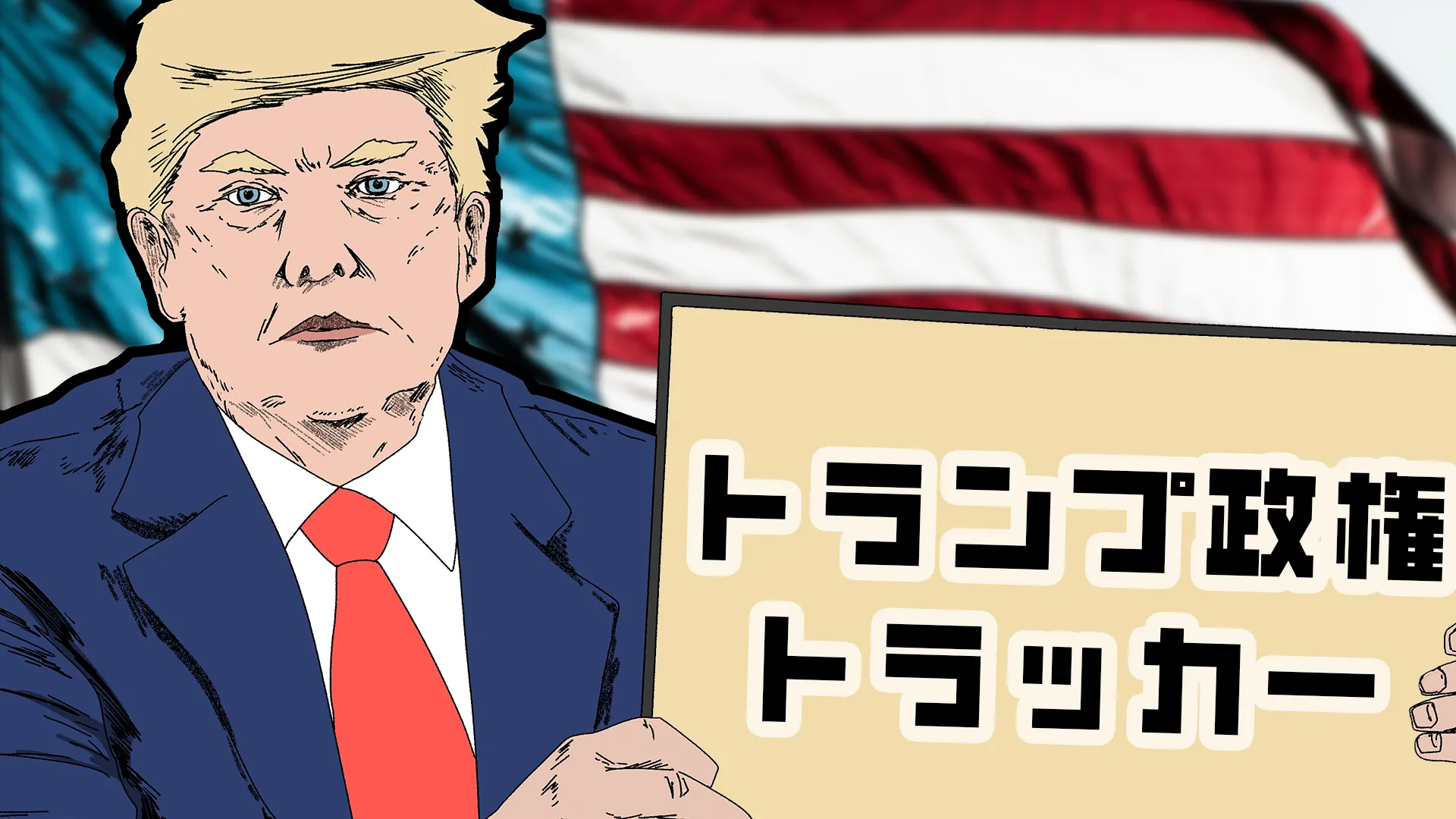セキュリティ・クリアランス導入の議論に必要な三つの視点
これまで、政府文書等においては、累次に渡って人的なセキュリティ・クリアランス制度(政府職員のみならず民間人を含め、秘密情報を取り扱うための資格を審査の上で付与する制度。米国でPersonnel Security Clearanceと表現されることに倣い、以下「PCL」という[1] 。)創設の必要性が述べられてきた。2022年に成立した経済安全保障推進法に当該制度は盛り込まれなかったが、同法案審議時の国会の付帯決議では「国際共同研究の円滑な推進も念頭に、我が国の技術的優位性を確保、維持するため、情報を取り扱う者の適性について、民間人も含め認証を行う制度の構築を検討した上で、法制上の措置を含めて必要な措置を講ずること」が掲げられ、新たに策定された国家安全保障戦略でも、「主要国の情報保全の在り方や産業界等のニーズも踏まえ、PCLを含む我が国の情報保全の強化に向けた検討を進める」とされた。これらも踏まえ、岸田総理は、本年2月14日に開かれた政府経済安全保障推進会議で、「経済安全保障分野におけるセキュリティ・クリアランス制度のニーズや論点等を専門的な見地から検討する有識者会議を立ち上げ、今後1年程度をめどに、可能な限り速やかに検討作業を進め」ることを高市経済安全保障担当大臣に指示した。
PCLの導入の必要性については、専ら機微な情報を含む国際共同研究や海外政府調達への日本企業の円滑な参入に資するとの観点から議論されてきた。しかし、資格付与のための身上調査と個人情報保護の関係といった審査・評価方法のみに焦点が当てられ、どのような仕組みにより、いかなる情報を対象として制度を構築すべきなのかについての議論はほぼ行われていない。本稿では、そもそもいかなる情報を秘密として守り、そのためにいかなる対象や事例を想定して実効的な制度を構築すべきなのかという観点に着目し、論点を整理してみたい。
日本にもPCLは存在するが限定的
日本でもPCL制度を創設すべきとの議論がややミスリーディングなのは、現在そのような制度が存在しないかのような誤解を与えていることだ。しかし、特定秘密保護法においては、特定秘密を取り扱う者に対するPCLである適性評価制度が既に規定されており、政府との契約に基づき物品製造・役務提供を行う「適合事業者」の従業者(民間人)も当該資格付与の対象とされている。
では問題の所在はどこにあるのか。米国における同様の制度との比較で議論を整理すると、第一に、特定秘密以外の秘密について、必ずしも同様の資格審査付与制度(PCL)が網羅的に規定されていない点が挙げられる。例えば、防衛省では、自衛隊法上の自衛隊員の守秘義務を根拠とする防衛省の秘密保全訓令に基づく「防衛省秘」の制度があるが、これを取り扱う政府職員に対する適格性付与の規定はあるものの、これを委託する者に対して厳密な調査を行う旨の規定があるのみで、特定秘密保護法のような個別の従業者に対する適性評価の具体的規定はない。加えて、防衛省秘については、特定秘密と異なり、基本的に民間人に対して義務違反時の刑事罰はなく、違約金請求等の契約条項に基づく措置のみが可能となっている[2]。
さらに、経済産業省や文部科学省といった先端技術研究に関する資金提供を行う省庁においても、特定秘密のほか、国家公務員法上の公務員の守秘義務を根拠とした秘密情報の管理に関する規則はあるものの、委託した研究成果を秘密指定して管理することを前提としたものとはなっていない。また、委託研究の契約条項において、相手方に守秘義務を課す規定は見られるが、義務違反の刑事罰はなく、適性評価の仕組みも構築されていない。機密(top secret)、極秘(secret)及び秘(confidential)に区分された秘密情報が、これを取り扱う民間事業者を含めて一様にPCLの対象となっている米国とはこの点がまず異なる(大統領令12968号、12829号及び13526号)[3]。
秘密指定の範囲に安全保障に関する委託研究を含めるか
第二に、秘密指定の対象となり得る情報の範囲も米国とは異なる。特定秘密保護法では「防衛の用に供する物」(防衛装備品)などに関する情報、外交交渉等に関する情報といった防衛・外交・テロ情報等が指定対象とされ、また、防衛省秘も同様に防衛の用に供する物に関する情報を指定対象として列挙している。一方、米国における秘密情報の指定対象には、「国家安全保障に関する科学技術又は経済的事項」も含まれており(大統領令13526号)、政府資金の提供を受けた研究に際して、PCLを得なければならない場合があり得る[4]。特定秘密保護法や防衛省秘でも防衛装備品の研究開発段階の性能や製作方法が指定対象となっているが、米国における指定対象はより広範なものとなっていると言える。
秘密を生成し得るのは政府だけか
第三に、秘密情報が政府から生成されることを前提として、民間事業者に政府が指定した秘密情報を委託して取り扱わせる制度を設計している日本とは異なり、米国では、契約事業者や委託研究者が秘密情報を自ら生成し得る場合があることを想定し、そうした情報を秘密指定する手続を明示的に規定している。大統領令13526号は、政府資金の受給者等が自ら秘密指定を要する情報を創出したと判断した場合に、当該情報を管轄する政府機関にその旨を通知すべきことを規定しており、その通知を受けて、政府は当該情報を秘密するか否かを決定することとしている[5]。
秘密指定すべき情報の範囲をどこまで広げるべきか
これらの点を踏まえると、日本における課題は、第一に、単に全ての種類の秘密制度に関し民間人も含むPCLの仕組みが存在しないことのみならず、その前段階として、そもそもPCLによって保護すべき秘密情報の範囲から、防衛装備品の研究開発や製造の契約に直接は紐付かないものの、安全保障に関わる民生技術(いわゆる汎用機微技術)が抜け落ちていることにあると言える。秘密指定すべき事項として対象になっていなければ、その漏洩を防止するために取扱者の資格を評価するPCLを適用できない。
このことが課題として明確になるのが、経済安全保障推進法の成立によって進められている重要技術育成プログラムにより、国による支援の対象となる「特定技術」の取扱いであろう。同法上、特定技術は、概略すると、外部から不当に利用されたり安定利用が妨げられた場合に国や国民の安全を損なう事態を生ずるおそれがある先端的技術であるとされており、広い意味で安全保障に関連する技術と言えるだろう。実際、同プログラムの下で掲げられた個々の研究開発構想は、AI、無人、量子、宇宙、海洋技術など、防衛用途に応用可能な汎用先端技術を含んでいる。
ところが、同プログラムの運用に係る「基本的考え方」や「運用・評価指針」といった政府文書においては、研究の段階に応じて「適切な技術流出対策」をとることが記載されるにとどまり、秘密指定の有無を含む具体的な仕組みは示されていない(ただし、現在、特定重要技術に関する「基本指針」やプログラムの「運用・評価指針」においては、研究成果は公開を「基本」とするとされている。)[6]。
したがって、PCLの仕組みを検討するに当たっては、重要技術育成プログラムを含め、国が民間に資金提供を行って委託する先端技術の研究開発で得られた情報のうち、防衛装備品の研究開発に直接結び付かないものの、防衛分野への応用可能性のある安全保障上機微なものを秘密指定すべきか否か、また、どこまで秘密指定の対象とすべきかが論点となると思われる。そのような先端的機微汎用技術が日本で秘密指定の対象とされない場合、(防衛装備品の研究開発と同一人物が行う場合を除き、)これを扱う研究者や民間事業者がPCLを保持する契機が基本的には訪れないので[7]、類似の機微技術を扱う国際共同研究等に参加する際に生じ得るとされる問題は解決されないことになるからだ。
もっとも、米国と同様の範囲で秘密指定を行うか否かは、科学技術の発展に求められる研究のオープン性と、当該技術の機微性や国際共同研究等に参加できないことによる国や企業の逸失利益とを比較考量した上で、真に必要なものに限定して判断する必要がある。限界事例の線引きは難しいが、例えば、基礎研究レベルの成果は公開を基本としつつ、実装化のレベル、防衛分野への応用可能性、製造方法の機微性、技術の優位性、技術が流出した場合の安全保障への影響などの要素を複合的に勘案して秘密指定するような基準を整理することも一案だろう。
また、秘密指定され得る情報の範囲拡大を、その情報の取扱要領や民間人も含む形でのPCLの仕組み創設と共に行うためには、新たな法整備が必要となると思われる。この点について、高市経済安全保障担当大臣は、本年2月14日の記者会見で「情報通信や宇宙などマルチユースな技術に対してアクセスできる資格を付与することになると、それらを全て特定秘密に指定することは考えにくい。そのようなことから特定秘密とは分けて考えていただきたい」と述べている。「経済安全保障分野」における制度の検討との岸田総理指示も併せて考えると、特定秘密保護法とは別の法制で検討するのではないかと思われる。
拡充したPCLの実効性をどう担保すべきか
第二に、国が研究費を提供して研究機関等が行う研究のうち、安全保障上機微なものを秘密指定の対象に含むこととした場合、これを取り扱う研究者等に適用されるPCLの制度をどのように構築するかが論点となる。特定秘密保護法においては、テロ等との関係、家族に関する情報、犯罪歴、経済的な状況等の情報について評価対象者に質問票への記入などにより調査を行う適性評価が規定されており、新たに拡充するPCLについても、ベースとしてはこれと同様の仕組みの適用が考えられる。
一方、民間の研究者等に資格を付与することを前提とした制度を検討するのであれば、当該研究者が海外を含め様々な財源から研究費を得ている可能性があることを踏まえ、専ら公務員を対象として想定する特定秘密保護法の適性評価項目に加え、追加的な調査項目が必要かもしれない。具体的には、こうした個人情報のみならず、職務として受けている外部からの資金提供の状況についても評価の対象に含めるか否かが論点となろう。
この点、政府は、外国からの不当な影響による技術流出等の懸念を踏まえ、研究の健全性・公正性(研究インテグリティ)確保のための取組として、2021年に競争的研究資金に関するガイドラインを改正し、研究資金への応募時、応募者に海外を含め外部からの支援や兼業等の情報を提出させることなどを定めている[8]。そして、この中で、秘密保持契約が取り交わされている共同研究等については、共同研究の相手方機関名など最低限の情報のみ提出させることとしている。仮に、海外からの資金提供により不当な影響を受け、技術流出につながるような事例を未然防止したいのであれば、このガイドラインと同様の項目をより実効性のある形で評価することを検討する必要があるだろう。しかし、上記のような秘密保持契約付きの資金提供を受けている場合、当該契約上の義務によりPCL付与のための調査への回答ができなければ、PCLを要する研究に参加できない場合も生じるかもしれない。PCL制度の研究者への拡充に際しては、必要十分な調査項目と技術流出防止の実効性をバランスさせる工夫が重要となる。
また、米国ではPCLの付与資格を基本的に米国市民に限っており、非米国市民による秘密情報の取扱いは例外とされているが[9]、日本でもPCL制度を民間研究者等に拡充する場合には、同様の取扱いとすることが穏当だろう。資格付与の際、質問票への回答を踏まえて個人を調査する場合、国籍国政府当局の協力が得られなければ実効的な調査を行うことができないと思われるためである。
さらに、政府において、民間人を含む資格付与の審査を行う機関をどのように構築し、専門的人材をどのように確保するのかも今後の論点となるだろう。米国では、国防省に属する国防防諜保全局(DCSA)[10]がPCLの実務、特に政府や企業職員のバックグラウンド調査を一括して担っており、実効的な産業保全の構築のため、このような保全実務の中核人材(security cadre)を擁する組織の必要性を訴える指摘もある[11]。
日本のPCLを海外でどのように通用させるべきか
第三に、もう一つ見過ごされている論点は、日本が米国等と同等と判断できるPCLを構築したとしても、それがそのままそれらの国において適用されるわけではないという点である。例えば、上記で述べたとおり、米国では、米国のPCLを取得できる対象を米国市民に限っており、日本の国内法の下でPCLを取得したとしても、それを米国で直接援用できるわけではない。日本で取得したPCLを相手国で通用させるためには、そうした取扱いを定める条約等の国際約束や相手国の国内法上の措置が必要となる。
日米間の秘密情報のやり取りについては、日米秘密軍事情報保護協定(GSOMIA)の下、互いの秘密情報を相手国において与えられる保護と「実質的に同等の保護」を与えることや、契約企業に秘密情報を提供する場合は当該情報にアクセスする個人が「秘密軍事情報取扱資格」(すなわちPCL)を有すること、秘密情報の送付は「政府間の経路を通じて」行われるべきことなどが条件として定められている。このため、防衛に関する研究開発や調達に関しては、国防当局間の共同プロジェクトとすることにより、日本におけるPCLの保持が、米国における事業参加において参加資格として意味を持つことになる。ただし、同協定の対象となる情報は「秘密軍事情報」なので、防衛に直接結び付かない安全保障関連の機微技術のやり取りを対象に含めるためには、協定の改正や解釈の整理、あるいは新たな協定の締結を選択肢の幅として、日米間で協議し、取扱いを決める必要がある。
この点、米国は、英国等との間で補足的な「産業保全協定(industrial security agreement)」を締結している場合があるようであり、内容が公開されていないので確たることは言えないが、こうした取決めの中で産業を含む秘密情報取扱いの具体的な手続を定めているとされている[12]。政府は、こうした類似例を調査しつつ最適な枠組みを協議していくべきであろう。
また、例えば、日英、日豪情報保護協定などでは、軍事に限らず国家安全保障に関する秘密情報を対象とし、PCLに関する規定もある。このため、両国政府の関与を前提とすれば、自国におけるPCLの取得が、相手国との共同研究や相手国政府の調達への参加機会を広げる可能性がある。
日本におけるPCL制度拡充の検討に当たっては、日本企業がいずれの国との共同研究や政府調達への参加において課題を感じているのかを特定した上で、当該相手国との間で必要な協定の改正や締結を行う必要がある。また、相手国国内措置の変更を要する場合には、これに関する働きかけを行っていかなければならない。重要なのは、日本国内で法制化の具体的検討を行う前に、あるはそれと並行して、共同研究等の海外展開先として想定する国における制度の調査や当該国政府との協議をしっかり行うことだろう。相手国から受領する秘密情報が日本においても相手国におけるのと「同等」の保護を受けていると判断できるような取扱要領やPCL制度はいかなるものなのか、認識をすり合わせなければならない。
将来の機会損失か獲得利益への影響か
冒頭で紹介した地経学研究所の100社アンケートでは、多くの企業が将来の国際事業参画にとって障壁となるとの懸念から制度創設の必要性を答え、実際に既に支障が生じている企業はわずかにとどまる。これには、個々の企業の状況や業種によって海外展開の度合いやその態様が異なることも影響している可能性がある。このことは、PCL創設の議論が政治的に争点化した際、産業界全体の当該制度に対する一致した強い意見が形成されにくいことを示唆しているのかもしれない。
一方、上記で触れた研究インテグリティに関する議論に見られるとおり、海外から研究資金を得ている研究者や研究機関においては、PCL制度の内容によっては実質的な影響を受け得ることを見据え、強い反対意見が生じる可能性もある。そうなった場合、将来の海外展開機会を広げるための産業界の緩やかな支持意見は、既に獲得された利益が影響を受け得ることを理由とした一部の強い反対意見を前に埋もれてしまうかもしれない。
しかし、将来の海外展開・協力が妨げられることは、国産技術の発展や経済成長にも影響を及ぼす可能性がある。また、PCLが拡充されることにより、研究者が逆に海外資金を得やすくなる場合もあるかもしれない。さらに、海外展開のニーズとは別に、PCL制度の構築により、国内において民間の資格のまま政府のプロジェクトに参画する際、PCL保持者により機微な情報を共有することが可能となり、民間の知見の取り込みが促進されることも考えられる。
PCL制度を検討するに当たっては、こうしたことを踏まえた上で、産業界や学術界を含む幅広い意見を吸い上げ、その支持が得られるような制度設計を工夫しなければならない。
注
- [1]セキュリティ・クリアランスには、ほかに、企業・施設の資格審査付与制度であるFacility Security Clearance: FCLがあり、また、産業における秘密情報の取扱い全体では、秘密情報の取扱要領や情報システムの保全を含む様々な考慮要素がある。これらについては別途の論点整理が必要だが、本稿ではPCLに絞って論点を整理する。
- [2]田村重信編『新・防衛法制』(内外出版、2018年)、740頁。これについて、防衛省は、本年(2023年)国会に提出した「防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律」案により、従来契約上の守秘義務によって担保してきた防衛装備品等に関する「防衛省秘」を「装備品等秘密」に指定し、企業等の民間人の義務違反に刑事罰を導入する規定を創設する方針である。https://www.mod.go.jp/j/presiding/houan/pdf/211_230210/03.pdf。
- [3]このうち、産業向けPCLについて特に定めているのは大統領令第12829号:国家産業保全プログラム(NISP)であり、これに基づき、国防長官が「国家産業保全プログラム運用マニュアル(NISPOM)」を発行し、手続の詳細を規定している。”Executive Order 12829—National Industrial Security Program” (January 6, 1993), Federal Register, Vol. 82, No. 7 (January 2017), 3224, https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2017-01-11/pdf/2017-00152.pdf。
- [4]“Executive Order 13526—Classified National Security Information” (December 29, 2009), Federal Register, Vol. 75, No. 2 (January 2010), 709, https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2010-01-05/pdf/E9-31418.pdf; 福田健志「米国のセキュリティ・クリアランス制度と日本における議論―研究者への適用をめぐって―」『変化する国際環境と総合安全保障 総合調査報告書』(国立国会図書館、2022年)、117-119頁。ただし、国家安全保障に明らかに関連しない基礎的科学研究は指定対象外とされる。
- [5]“Executive Order 13526”, 708-709.
- [6]内閣総理大臣決裁「経済安全保障重要技術育成プログラムの運用に係る基本的考え方について」(令和4年6月17日)、https://www8.cao.go.jp/cstp/anzen_anshin/20220617_kihonteki.pdf;内閣官房・内閣府「経済安全保障重要技術育成プログラムの運用・評価指針」(令和4年9月16日)、https://www8.cao.go.jp/cstp/anzen_anshin/unyo-hyouka.pdf。
- [7]ただし、研究内容自体ではないが、重要技術育成プログラムの実施に当たって開催され得る官民の協議会の事務に関して知り得た秘密は、経済安全保障推進法上、罰則付きで保護対象とされ、これにより機微な「関係行政機関が保有するニーズ情報」を研究者に共有することが可能となるとされている(「特定重要技術の研究開発の促進及びその成果の適切な活用に関する基本指針」(令和4年9月30日閣議決定)、https://www.cao.go.jp/keizai_anzen_hosho/doc/kihonshishin3.pdf。)。当該機微情報へのアクセスに必要な要件としてPCL制度を構築するという最小限の手法もあり得るが、その場合、技術そのものを秘密指定の対象とし得る米国の制度とは乖離が生じることになるだろう。
- [8]競争的研究費に関する関係府省連絡会申合せ「競争的研究費の適正な執行に関する指針」(2021年12月17日)、https://www8.cao.go.jp/cstp/compefund/shishin_r3_1217.pdf。
- [9]US Department of Defense, “National Industrial Security Program Operating Manual” (Change 2, May 2016), Federal Register Vol., No. 245 (December 21, 2020), 83330, https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2020-12-21/pdf/2020-27698.pdf.ただし、専門的知識等の理由から秘密情報取扱いが必要な場合は、限定的取扱資格(LAA)が非米国市民にも付与可能とされる。
- [10]2019年に国防保全局(DSS)から改組。1万の企業を監督し、年間200万件のバックグラウンド調査を行っているとされる。https://www.dcsa.mil/about/
- [11]Arthur Herman, “Closing the Defense Industrial Security Gap with Japan” (Hudson Institute, July 2018), https://s3.amazonaws.com/media.hudson.org/files/publications/HermanJapanFINAL.pdf.
- [12]US Department of Defense, “National Industrial Security Program Operating Manual”, Federal Register, 83348; Masahiro Matsumura, “Facilitating Japan’s Participation in Multinational Defense R&D: A Japanese Approach to Strategic Management of Technology Transfer and Intellectual Property Rights Issues”, (Institute for National Strategic Studies, National Defense University, February 27, 2017), 5-7, https://researchmap.jp/read0032929/published_papers/18085743/attachment_file.pdf.

地経学ブリーフィング
コロナウイルス後の国際政治と世界経済の新たな潮流の兆しをいち早く見つけ、その地政学的かつ地経学的重要性を考察し、日本の国益と戦略にとっての意味合いを精査することを目指し、アジア・パシフィック・イニシアティブ(API)のシニアフェロー・研究員を中心とする執筆陣が、週次で発信するブリーフィング・ノートです(編集長:鈴木一人 地経学研究所長、東京大学公共政策大学院教授)。
おことわり:地経学ブリーフィングに記された内容や意見は、著者の個人的見解であり、公益財団法人国際文化会館及び地経学研究所(IOG)等、著者の所属する組織の公式見解を必ずしも示すものではないことをご留意ください。


主任研究員
防衛省で16年間勤務し、2022年9月から現職。2014年から2016年まで外務省国際法局国際法課課長補佐、2016年から2019年まで防衛装備庁装備政策課戦略・制度班長、2019年から2021年まで整備計画局防衛計画課業務計画第1班長をそれぞれ務める。2021年から2022年まで防衛政策局調査課戦略情報分析室先任部員として、国際軍事情勢分析を統括。 2007年東京大学教養学部卒、2012年米国コロンビア大学国際関係公共政策大学院(SIPA)修士課程修了。
プロフィールを見る