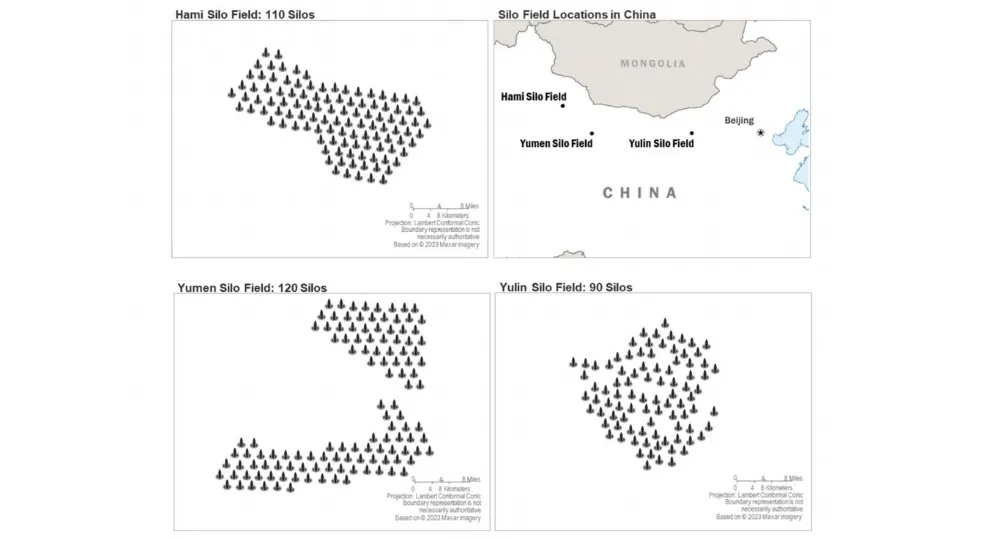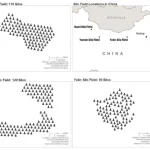トランプ政権トラッカー:大統領令の概要と解説 No.6(2025年2月19-25日)
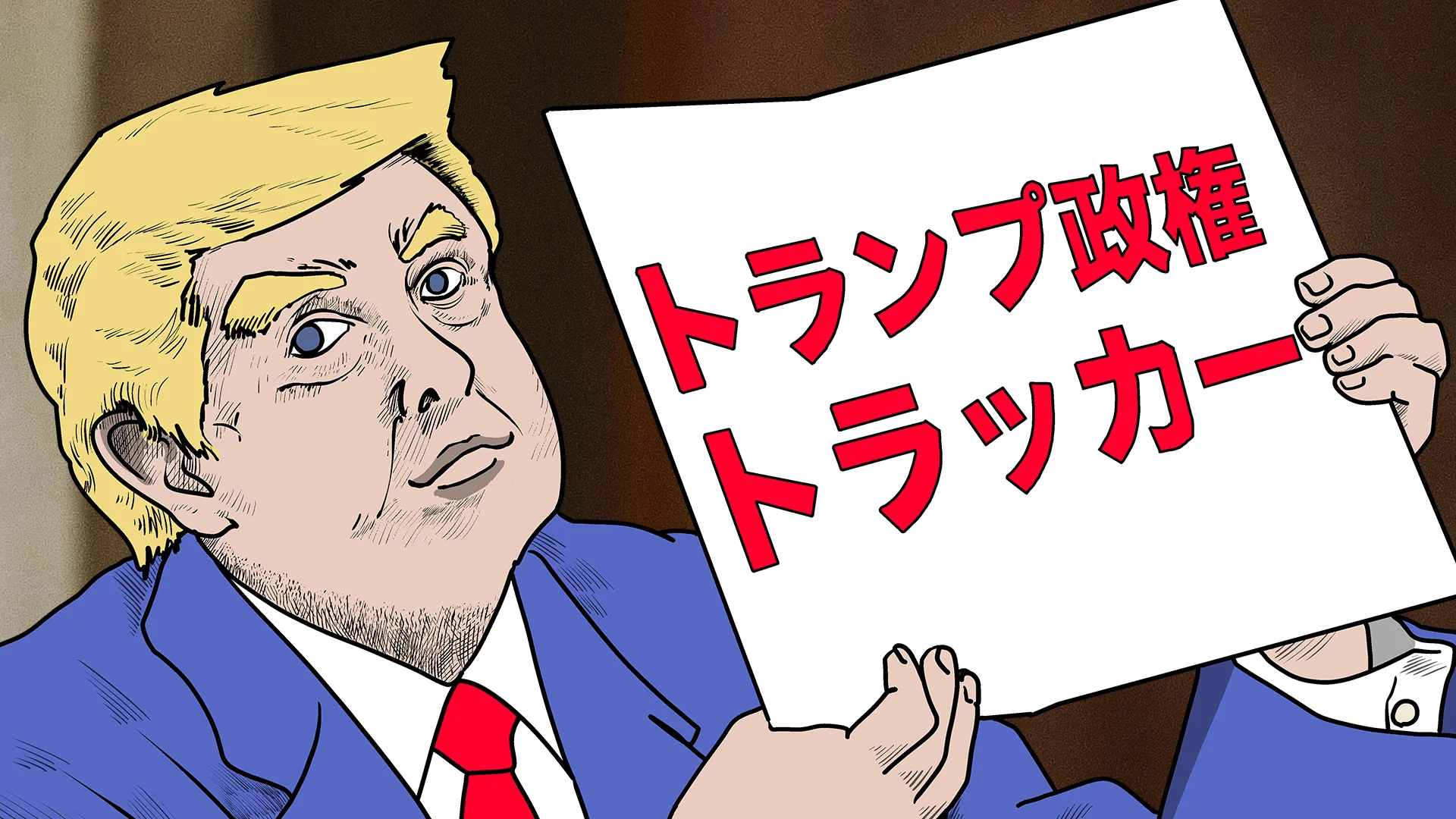
・銅資源の輸入依存が安全保障に及ぼす影響の調査に関する大統領令
・連邦官僚機構の削減を開始する大統領令
・AI分野の行動計画に関するパブリックコメント募集
・アメリカ・ファースト投資政策
・米国企業およびイノベーターを海外からの収奪や不当な罰金・制裁から守るための覚書
トランプ政権トラッカーの一覧(2025年1月20日~)
・【一覧】トランプ政権トラッカー(大統領令・布告・覚書・発表)
- 大統領令の一覧と概要
- 布告・覚書・公式発表の一覧と概要
- トランプ大統領の演説および優先政策
- エキスパートの視点
大統領令一覧
明確・正確で実用的な医療費情報を通じて「アメリカを再び健康に」する大統領令(2月25日)
この大統領令は、病院や保険会社などの「強大な組織」が医療費の説明責任を果たしてこなかったと指摘し、トランプ第一次政権に引き続き情報の透明化を推進するもの。具体的には、実際の価格の開示、情報の標準化、病院や保険プランを比較できる環境の整備、透明性のあるデータ報告を求めている。(大統領令はこちら、ファクトシートはこちら)
■解説付き■ 銅資源の輸入依存が安全保障に及ぼす影響の調査に関する大統領令(2月25日)
この大統領令は、世界の銅生産が特定の国々によって支配され、米国が輸入に依存している現状を懸念し、国内サプライチェーンの構築の必要性を強調している。これを踏まえ、商務長官に対し、銅の輸入が国家安全保障に与える影響を調査するよう命じている。(大統領令はこちら、ファクトシートはこちら)
解説
この大統領令は、「銅は米国の国家安全保障、経済力、産業の強靱性に不可欠な重要物質である」と宣言している。銅をこのように定義することで、大統領は1962年通商拡大法第232条を用いて、輸入銅への米国の依存が国家安全保障に及ぼすリスクの調査を命じた。銅のサプライチェーンの脆弱性を特定する報告書は270日以内に提出される予定である。報告書では、関税、輸出規制、戦略的投資、許可制度改革、リサイクル強化イニシアチブなどの国内生産増加のインセンティブなどの措置を勧告する予定である。ファクトシートでは、防衛用途、インフラ、新興技術における銅の「極めて重要な役割」を認めている。また、米国には「十分な銅埋蔵量」があるものの、その製錬・精製能力は他国、特に世界の製錬能力の50%を占める中国に遅れをとっていると指摘している。その結果、米国の銅輸入依存度は「1991年の消費量の実質0%から2024年には45%に急増」した。トランプ大統領は鉄鋼とアルミニウムに対しても同様のアプローチを取っており、経済依存を国家安全保障の観点から捉え、関税を課したり、その他の報復措置を講じてこれらの必須金属に対する国内産業競争力を高めようとしている。(アンドリュー・カピストラノ)
■解説付き■ 連邦官僚機構の削減を開始する大統領令(2月19日)
この大統領令は、連邦政府の規模を劇的に縮小するため、不要と見なされる機関や機能の削減を開始し、それらの機関の予算要求を見直すよう命じている。(大統領令はこちら、ファクトシートはこちら)
解説
大統領令14217は、トランプ政権が掲げる「連邦政府の大幅な縮小」と「官僚機構の効率化」を実現するために発布された命令である。本命令は、連邦官僚機構の不要な構成要素や機能を廃止し、政府の無駄を削減することを目的としている。特に、プレシディオ・トラストや米州基金、アフリカ開発基金、米国平和研究所(USIP)などの非必須機能を削減する方針が示されている。また、諮問委員会やプログラムの廃止を通じて、既存の行政構造を大幅に見直す意図が明確である。しかし、USIPを巡る混乱が象徴するように、政権側の「権限移行」と「法的正当性」を巡るトラブルが続発している点は問題である。連邦官僚機構の削減自体には一定の合理性があるものの、政治的意図が強く反映された人事介入や行政権限の濫用が疑問視されている。官僚機構改革は、効果的かつ合法的な手続きの確保が求められるが、本命令がもたらす混乱と政治的対立は今後も継続する可能性が高い。(神保謙)
合法的な統治の確保と大統領の「政府効率化省」規制緩和イニシアティブの実施に関する大統領令(2月19日)
この大統領令は、連邦政府の過剰な権限行使を是正するため、各機関の長に対し、政府効率化省(DOGE)と連携し、合憲性に疑問のある規制や国益を損なう規制の見直しを命じている。(大統領令はこちら、ファクトシートはこちら)
納税者によるオープンボーダー(開かれた国境)への補助金の廃止に関する大統領令(2月19日)
この大統領令は、米国民の納税に支えられている公的給付が不法滞在者に渡るのを防ぐため、不法移民が受給可能なプログラムの特定や、不正受給の取り締まり強化を命じている。(大統領令はこちら、ファクトシートはこちら)
布告・覚書・公式発表一覧
(特定の法律事務所に対する)セキュリティクリアランスの一時剥奪と政府契約の精査についての覚書(2月25日)
この覚書は、トランプ氏の起訴に携わったジャック・スミス元特別検察官を支援したCovington & Burling法律事務所を、「司法手続きの武器化」の疑いがあると名指しし、疑いが晴れるまで同事務所の全従業員のセキュリティクリアランスを一時停止し、政府契約の終了または精査を命じている。(覚書はこちら)
■解説付き■ AI分野の行動計画に関するパブリックコメント募集(2月25日)
2025年1月23日の大統領令に基づき、人工知能(AI)分野の行動計画策定に向けて、学術界、業界団体、民間企業、地方政府など幅広い関係者からの意見が募集されている。期限は同年3月15日まで。(発表はこちら、募集はこちら)
解説
1月23日に発出された大統領令では、AI分野におけるアメリカの優位性を維持・強化するために、180日以内に「AI行動計画」を策定する指示が出ていたところ、今回ホワイトハウスから、当該行動計画に策定のためのパブリック・コメントの募集が発表された。(回答締切は3月15日まで)パブコメのトピックとして例示されているのは、AI開発のためのハードウェア、エネルギー消費、基盤モデル開発、教育、知財などのほかにも、AIモデルの出力結果の説明可能性、データプライバシー、AIシステム開発利用のライフサイクルでの安全性、リスク、規制、国際協力、輸出規制なども含まれている。上記の「AI行動計画」がどのような内容となるかは依然として不明である。ただし、パブコメでは幅広いトピックが例示されており、そこから読み取れる範囲では、AI行動計画も単にAIの競争力強化を推進するだけではなく、安全性や規制を完全に排除するものではない可能性も出てきたと推察される。いずれにしても、第2次トランプ政権のAI政策においては、「AI開発促進・支援」と「リスクへの対応」のバランスが前者に傾く方向性が示されているが、その程度がどうなるかが一つの焦点となる。また、広島AIプロセスなど、これまでAIのリスクに対する国際的なルール形成の議論がなされてきたところ、そのリスクへの対応を巡って、米国と欧州、日本などでの国内の対応の差が広がれば、国際的なルール形成にも大きな影響が出てくる可能性がある。(梅田耕太)
■解説付き■ アメリカ・ファースト投資政策:財務長官、国務長官、国防長官、司法長官、商務長官、労働長官、エネルギー長官、国土安全保障長官、環境保護庁長官、行政管理予算局長、国家情報長官、米国通商代表、経済諮問委員会委員長、科学技術政策局長、大統領補佐官(国家安全保障担当)、連邦捜査局(FBI)長官宛て(2月21日)
この覚書は、アメリカの国家安全保障・経済安全保障を強化するため、同盟国や友好国からの投資を促進する一方で、中国をはじめとする敵対国からの投資を制限する方針を示している。(覚書はこちら、ファクトシートはこちら)
解説
この覚書は、「経済安全保障は国家安全保障である」と宣言している。この大統領令には2つの主要な要素がある。第一に、同盟国や同志国からの米国経済への投資が国益に資することを認識し、これらの投資源からの投資拡大を促進するため、高度な技術分野に重点を置いた迅速な「ファストトラック」プロセスを作成するよう行政機関に命じている。しかし、投資は安全保障条項の対象となり、投資家は米国の外国の敵対国と提携しないよう求められる。第二に、中国、キューバ、イラン、北朝鮮、ロシア、ベネズエラを外国の敵対国と定義し、特に中国が米国の重要インフラを「乗っ取る」ことを試み、米国の投資を利用して最先端の技術、知的財産、戦略的産業における影響力を獲得しようとしていると指摘している。このような投資はさまざまな法的権限に基づいて制限され、「米国の利益にかなう」と判断された場合にのみ許可される。これら2つの要素を組み合わせることで、欧州とアジアの同盟国が投資を中国から米国に移し、その資金を使って米国の主要部門における中国資本を置き換え、米国の経済と国家安全保障の利益を同時に推進するよう促すことが目的である。(アンドリュー・カピストラノ)
■解説付き■ 米国企業およびイノベーターを海外からの収奪や不当な罰金・制裁から守るための覚書:財務長官、商務長官、米国通商代表、 大統領上級顧問(貿易・製造業担当)宛て(2月21日)
この覚書は、欧州やカナダが米国企業に対して一方的なデジタルサービス税(DST)や規制を導入し、米国企業の収益に不当な負担を課しているとして、関係機関の長に対し、各国によるDSTや規制の実態を調査し、具体的な対応措置を検討するよう指示している。(覚書はこちら、ファクトシートはこちら)
解説
この覚書は、外国政府が米国のハイテク企業に課しているデジタルサービス税(DST)、規制、法的体制に対する報復的対応策を策定するものである。この覚書は、外国政府が「外国市場で事業を展開している米国企業が、通常は外国の管轄権の対象となっていないにもかかわらず、外国政府によって徴税されている」のは不公平であると主張している。トランプ政権の最初の任期中、USTRの調査により、特に欧州連合諸国におけるDSTは、1974年通商法第301条に基づく不公正な貿易慣行に該当すると判断された。2021年に米国は135カ国とDSTを撤回するに合意したが、大部分はまだ施行されている。トランプは、アメリカ第一主義の貿易政策報告書(4月1日提出予定)に新たなDSTのレビューを含めるよう命じており、関税やその他の報復措置を勧告する可能性がある。この覚書は、DST を規制の削減やイノベーションの奨励によって自国のテクノロジー企業を成功に導くのではなく、外国政府が米国企業に徴税して国家歳出計画を支援するための手段であると位置づけており、その結果、米国のテック企業の競争力を損なうと見なされる。覚書によると、「米国企業は、法外な罰金や税金によって破綻した外国経済を支えることはもうしない」という。このレビューでは、欧州連合や英国が、米国のテクノロジー企業に「言論の自由や政治関与を損なう、あるいはコンテンツを抑制」する行動への参加を要求または奨励しているかどうかを調査することも任務としている。これは、2 月のミュンヘン安全保障会議でJD ヴァンス副大統領が示した立場と似ている。(アンドリュー・カピストラノ)
「アメリカが帰ってきた-そしてこれはトランプ政権の始まりに過ぎない」(2月20日)
ホワイトハウスは、トランプ政権1ヶ月の節目にその成果をまとめた声明を公表した。「通常ならば任期全体を使って得られる成果を僅か1ヶ月で達成した」とし、移民対策・関税と投資・インフレ対策・外交・エネルギー再転換・反多様性・連邦政府改革・その他に分けてまとめている。(詳細はこちら)
硫黄島の戦い80周年に関する布告(2月19日)
この布告は、2025年2月19日を「硫黄島の戦い80周年」と宣言し、この戦いで犠牲となった全ての愛国者に敬意を表するために発表されたもの。また、現在の日米同盟が、インド・太平洋地域の平和と繁栄の礎になっていることにも触れている。(布告はこちら)