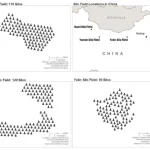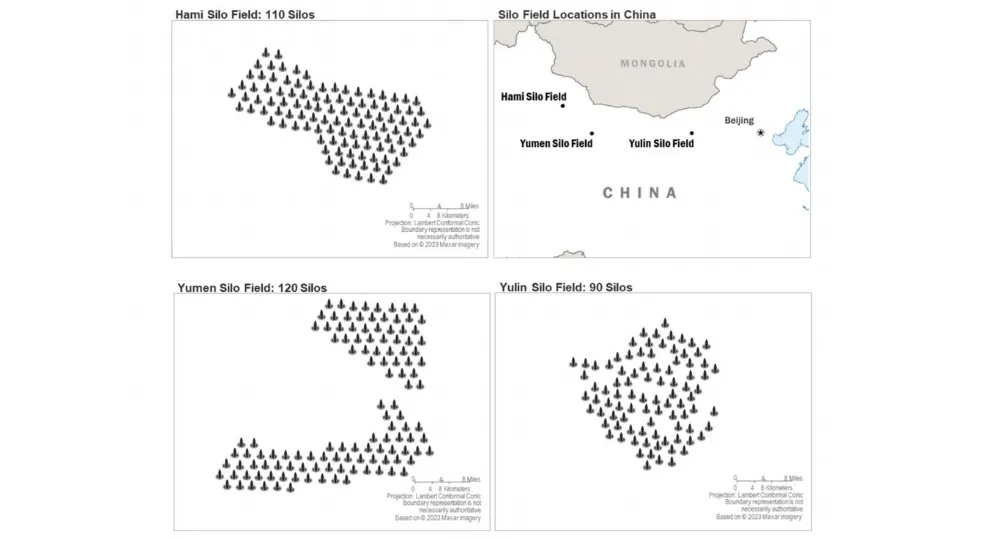ロシアによる核恫喝を拒否するために必要なこと

ウクライナ戦争が国際秩序に与える影響は多岐にわたるが、今後最も懸念すべき論点の一つは、ロシアがいずれかの段階で核兵器を使用するリスクであろう。核保有国ロシアが非核国ウクライナを侵略したうえに、公然と核恫喝をしているという現状は、核不拡散体制に深刻な影響を及ぼしている。
これまで、米露英仏中の5大国は、非核国が核保有国と協力して自国への侵略を行う場合を例外として、核兵器不拡散条約(NPT)を締結している非核国に対しては核を使用しないとする「消極的安全保証」に関する一方的宣言を行ってきている(うち中国の宣言は例外への言及なし)。これらの宣言は、法的拘束力を有していないが、核保有国と非核国の地位を固定するというNPTが有する不平等性を和らげる意図表明である。
ロシアによるウクライナに対する核使用の威嚇には、NPT体制を支えているこの自制の信頼性を低下させる重大な意味がある。本稿では、これまでの核抑止論が必ずしも前提としてこなかった核保有国による非核国への核使用という危険に焦点を当てる。これを論じることは、非核国日本の安全保障を考えるうえでも、とりわけ不可欠な視点となるためだ。
本稿は、東洋経済オンラインにも掲載されています。
https://toyokeizai.net/articles/-/667561
限定核使用の可能性とその限界
ウクライナ戦争の過程で、ロシアは核使用の可能性を累次にわたって示唆してきた。ロシアでは、プーチン大統領が2022年2月、北大西洋条約機構(NATO)諸国の姿勢等を理由として抑止力部隊の警戒態勢を上げる方針を表明したほか、同年秋には、ウクライナ軍の反転攻勢を阻止するため、戦場で戦術核(非戦略核)を使用する方針について、ロシア軍内部で議論がなされた旨報道されている。
さらに、プーチン大統領は、本年3月末、アメリカが欧州に戦術核を配備していることなどに言及しつつ、ベラルーシ軍への戦術核運搬能力支援やベラルーシにおける戦術核保管施設建設の意向を示した。これらの動きをどう捉えるべきか。
ロシアによる核使用の威嚇には、反転攻勢を行うウクライナに対して向けられたものと、武器援助を通じた介入の阻止を目的としてNATO諸国に向けられたものという2つの側面がある。しかし、ロシアにとって、NATO諸国への直接の核使用は、核報復を含むNATOの参戦を招き得るものであり、第1の選択肢となるかは疑わしい。
一方、ウクライナの前線における反転攻勢がNATO諸国による武器援助の効果の発露としてロシアに受け止められていることを踏まえれば、NATO諸国に対する威嚇の意味を含め、その核攻撃がウクライナに対して行われる可能性は考慮すべきだ。
しかし、現在の状況において、ロシアが戦術核を戦場で使った場合の有効性は、それほど高いものとは言えない。
第1に、侵攻段階における戦術核の使用は、ロシア軍自らにも不利益をもたらす可能性のある手法である。限定的とはいえ核を投射した地域を乗り越えて領土確保のため侵攻作戦を継続すれば、自軍にも大きな被害が生じる可能性があるからだ。
核爆発による地形の変化等の影響で自軍の機動力が低下し、戦域における形勢を有利なものにできない可能性もある。
第2に、現在の陸上戦闘で主流となっている地理的に分散した戦い方の中で、戦術核投射の効果がどれほど出るかも疑問が残る。すなわち、精密誘導兵器や情報収集に関する技術の進歩により、通常兵器による火力の効率性が向上した現代戦においては、精密火力の標的とならないよう、部隊の生存性を向上させるための取り組みが不可欠となってきた。
その一環として、部隊の1カ所への集中をなるべく避けた、地理的に分散した戦い方が顕著になっている。例えば、ウクライナ軍の戦い方として、伝統的な陸軍で数千人規模の旅団が担当する広さの地域の戦闘を、数百人程度の大隊が担っているとの指摘もある。このように分散展開した敵を戦術核によりピンポイントで無力化するのは、集中して殺到する戦力を撃退するのと比較して容易ではない。
もっとも、仮にロシアが国境線付近まで後退して追い詰められた場合、ウクライナ軍の阻止のため戦術核を使用する可能性はある。しかし、消耗戦により追い詰められた状況で核を使用したとしても、それを攻勢に転じる契機として活用できるだけの体力がロシア侵攻部隊に残っているかは疑わしい。
「戦略抑止力」としての戦術核
しかし、これらはあくまで戦術核を、戦場で相手の軍事力を削ぐために使用する「拒否的抑止力」の延長線で位置付けた場合の分析である。一方、戦術核を、高威力の戦略核使用の前段階において、対価値(カウンター・バリュー)、対都市(カウンター・シティ)攻撃の手段として用い、相手に耐えがたい損害を与えることを予測させる「懲罰的抑止力」の延長線上で位置付けるとしたら、結論は少し異なり得る。
ロシアが2014年に発表した軍事ドクトリンでは、ロシアが直面する軍事リスクの一つとして、外国の精密誘導兵器による「戦略的非核システム」の配備が掲げられるとともに、ロシア自身も精密誘導兵器の使用を戦略抑止の手段として想定する旨規定された。このことは、ロシアが通常弾頭のミサイルを、戦場における軍事的効果のみならず、政治的脅威を与えるための手段としても位置付けていることを示唆している。
また、ウクライナ戦争においては、ウクライナ東部や南部の前線における戦闘とは無関係な形で、断続的にウクライナの主要都市、特に、民間施設を標的としたミサイル攻撃が行われている。これは、攻撃対象を軍事目標に限るべきとする軍事目標主義の原則を意図的に逸脱することにより、戦場で軍事的には挫けないウクライナの戦争継続意思を、政治的に挫こうとする意図の表れとも捉えられる。
仮にこのような対都市ミサイル攻撃がロシアの「戦略的非核抑止」の発露であるとすれば、その延長線上に、低出力の戦術核の対都市・対重要拠点使用という選択肢が控えている可能性も排除できない。
この点、戦術核の搭載手段の一つとして想定されるイスカンデル地対地ミサイルは、その射程が500km弱にとどまるため、ベラルーシに配備した場合、東部や南部の主要な前線にはほぼ届かず、戦場への核投射手段としては期待できない。しかし、そうした手段も、首都キーウやNATO諸国からの武器援助の輸送経路への政治的脅威の手段として捉えれば、一定の合理性を持ち得る。
そして、そのような核使用の脅威を与えることは、核抑止力の目的として、軍事活動のエスカレーション阻止や受け入れ可能な条件での停止を掲げるロシアの核ドクトリン(2020年に発表)の記述とも整合的である。
ロシアの核使用を拒否するために必要な取り組み
非核国ウクライナは、ロシアの核恫喝を核によって抑止することができない。このような状況で、ロシアの核使用にどう対処すべきか。
直接的な手段は、アメリカが核を含む戦力により報復する意思を示すことである。しかし、同盟国でないウクライナを支援するため通常戦力のレベルでも武力介入を行ってこなかったアメリカが、核のレベルに至って介入できるのか、そして、NATO欧州同盟国への核反撃のリスクを冒してまでそれを行う判断が可能かといった観点を踏まえると、そのハードルは極めて高い。
そして、そのハードルの高さは、抑止の信憑性を低下させ得る。また、1900発にも及ぶ非戦略核と多様な搭載手段を有するロシアに対し、アメリカの非戦略核は、核・非核両用航空機(DCA)搭載核爆弾と潜水艦発射弾道ミサイル(SLBM)搭載低出力核に限られる。
DCAはロシア防空ミサイルの脅威や地上駐機時の攻撃に対して脆弱となる可能性があり、SLBM搭載低出力核は数に限りがあるとされる。非戦略核のレベルで米露の能力が必ずしも均衡していない状況においては、ロシアの核エスカレーションを抑止する効果にも疑問が生じ得る。
このため、現下のアメリカの核に関する発信や態勢のみでロシアの核使用を抑止し続けることは、現実的には不十分かもしれない。そうであれば、ロシアの核恫喝に抗し得るウクライナ自身の戦いと、それを支える武器援助という通常戦力のレベルにおける努力との組み合せが不可欠となる。
そのためには第1に、万一戦場で核が使用された場合にもその容易な標的とならないよう、ウクライナ軍は、これまで以上に地理的に分散した戦力配置と機動的な戦い方を重視しなければならない。また、現在断続的に行われているロシアによる対都市ミサイル攻撃が軍事的はおろか政治的にも効果を与えないことを、前線の反転攻勢によって示し続ける必要がある。
第2に、西側諸国は、ウクライナの戦場における戦いを支えるための武器援助に加え、対都市限定核使用の可能性も見据え、首都キーウなどの戦略要衝へのペトリオット地対空ミサイルの集中配備を進め、損害限定の態勢を築くべきである。
中国に対する抑止力にもなる
加えて、将来への示唆として、アメリカの非戦略核の態勢がDCA搭載核爆弾とSLBM搭載低出力核のみで十分なのか、議論を本格化させるべきであろう。そのような中間的な核戦力の充実は、核も搭載可能とされる中距離ミサイルを充実させ、今後その核弾頭の低出力化を進める可能性のある中国に対する抑止力にもなる。
アメリカ等の核保有国による武器援助および核抑止についての取り組みの強化は、単にウクライナを支援するためのみならず、自らが特権的地位を有するNPT体制の擁護にも貢献する。ロシアの核使用を拒否できなければ、それを目の当たりにした非核国において、核保有の議論が高まる可能性もあるからだ。
そして、日本政府がNPT体制の維持・強化を掲げるのであれば、G7広島サミットにおいて、核廃絶に至っていない現状を踏まえ、ウクライナ援助やアメリカの核抑止力の切れ目ない保持が、NPT体制の維持にとって重要な意味を持つことを想起させるべきである。
日本は、G7の一員としてウクライナ援助を行う主体であると同時に、ウクライナと同じ非核国として、冒頭で触れた消極的安全保証に対する核保有国の責務を改めて問う立場にもある。
(Photo Credit: AP / Aflo)

地経学ブリーフィング
コロナウイルス後の国際政治と世界経済の新たな潮流の兆しをいち早く見つけ、その地政学的かつ地経学的重要性を考察し、日本の国益と戦略にとっての意味合いを精査することを目指し、アジア・パシフィック・イニシアティブ(API)のシニアフェロー・研究員を中心とする執筆陣が、週次で発信するブリーフィング・ノートです(編集長:鈴木一人 地経学研究所長、東京大学公共政策大学院教授)。
おことわり:地経学ブリーフィングに記された内容や意見は、著者の個人的見解であり、公益財団法人国際文化会館及び地経学研究所(IOG)等、著者の所属する組織の公式見解を必ずしも示すものではないことをご留意ください。


主任研究員
防衛省で16年間勤務し、2022年9月から現職。2014年から2016年まで外務省国際法局国際法課課長補佐、2016年から2019年まで防衛装備庁装備政策課戦略・制度班長、2019年から2021年まで整備計画局防衛計画課業務計画第1班長をそれぞれ務める。2021年から2022年まで防衛政策局調査課戦略情報分析室先任部員として、国際軍事情勢分析を統括。 2007年東京大学教養学部卒、2012年米国コロンビア大学国際関係公共政策大学院(SIPA)修士課程修了。
プロフィールを見る