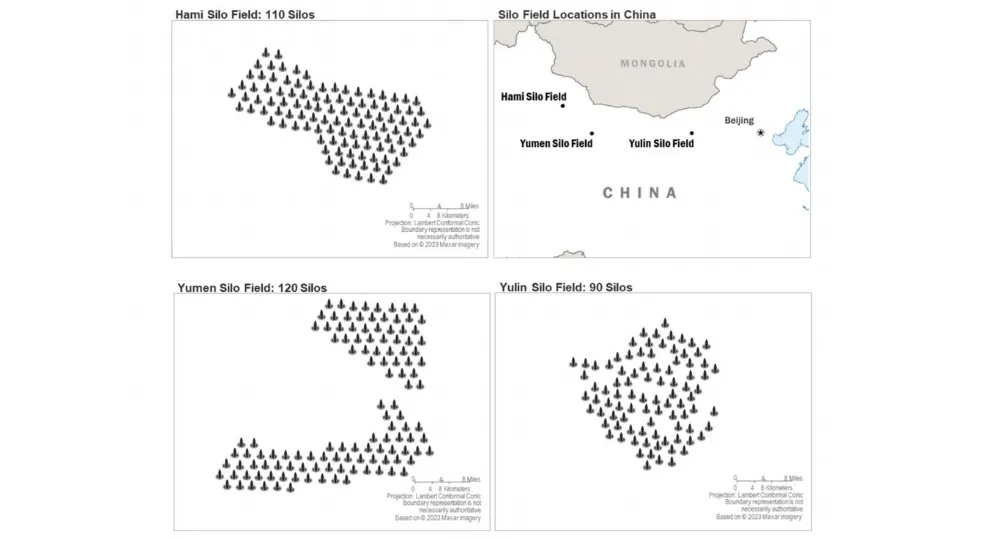変質しつつあるアメリカのリベラリズム

本稿では、アメリカの民主主義の現状とその国際秩序への影響について、リベラリズムの再考を通じて分析する。リベラリズムに注目する理由は、アメリカの民主主義の後退の背景にあるアメリカ社会の分断の底流には、リベラリズムの変質、いわば原理的な二極化が存在するためである。そしてアメリカのリベラリズムの変質は、 国際的にはアメリカの自国中心主義傾向、国際協調からの後退、権威主義諸国の増長につながり、リベラルな国際秩序を危機に陥れている。
本稿では、リベラリズムを、フランシス・フクヤマが説くように、個人の尊厳と自律性は普遍的で平等であり、寛容性の原則の下に尊重されるという考え方として捉える。「リベラル」というと、特に日本では、政府の社会への積極的介入を支持する「大きな政府」を説く中道左派というニュアンスで理解されるかもしれない。しかし、ここでは、政策スタンスとしてではなく、人間の在り方についての思想としてのリベラリズムを検討する。
リベラリズムとアメリカにおけるその変質―分断と対立
今日のアメリカのリベラリズムは、個人の自律性の過度な拡大の結果、利己主義を生む一方で、共同体や伝統的道徳への回帰の傾向を高めている。これは、複雑に絡み合い、リベラリズムの二極化を生じさせている。まず、ジェンダーや人種に基づく社会的少数者の集団としての権利主張が、アイデンティティ政治となり急進化した結果、 社会正義に目覚めたと自認するウォークによるキャンセルカルチャーに代表される左派ポピュリズムの現象となっている。そして、これに対する反動として、反移民や反多文化主義を主張する保守派の白人層を中心とした右派ポピュリズムが台頭しつつある。両者はともに、 程度の差はあれ理性ではなく感情にかられ、 不十分な自己省察で排他性を帯びつつ、分断を深めている。
この分断の遠因として、冷戦の終焉とグローバリズムがある。冷戦後、イデオロギー対立に代わり、様々な社会的少数者の人権向上の機運が高まった。また、グローバリズムが生んだ経済格差は、左派では特に若者の、右派では中間層の不満を招いた。さらに、増加する移民とその他社会的少数派の権利運動、そして国際社会における中国の台頭とアメリカの覇権の揺らぎへの反動が、白人とキリスト教を中心としていた戦後の「古き良きアメリカ」への郷愁となった。
確かにアメリカのリベラリズムには、その自己批判と寛容の力をもって、人種差別問題を徐々に改善する回復力もあった。しかし、昨今のリベラリズムの二極化によって、各社会集団の過度な被害者意識と独善性の片鱗が見られた。一つの事例として、白人警官による黒人男性暴行殺害事件への抗議運動であるブラック・ライブズ・マター(BLM)運動がある。BLM運動の一部は暴徒化し、さらに史実をイデオロギー的に解釈する様相も帯びた。リンカーン大統領の前に跪く黒人という構図の「解放記念碑」が、解放奴隷によって建てられたものであるにもかかわらず、撤去されるべきという議論まで起こった。他方で、BLM運動への反動として、白人ナショナリズムの意識が高まった。
分断は、党派対立の先鋭化と大衆迎合主義としても現れている。民主党と共和党ではそれぞれの主流派が求心力を失い、ともに急進派が台頭しつつある。特に共和党では、アメリカ政界のアウトサイダーであったトランプ氏が、大統領にまでなった。前トランプ大統領は、人種やジェンダーをめぐる差別的な発言を行い、南部国境の壁の建設に象徴される移民排斥の政策をとった。 さらに「アメリカを再び偉大な国にする」というスローガンの下に、アイデンティティ政治に疲弊した白人層の支持を得た。
分断の中で増幅する不寛容性は、民主主義を麻痺させる。民主主義に重要な熟議と妥協を通じた合意形成に耐えられない左右急進派は、選挙勝利へ執心する。一番象徴的なのは、トランプ氏の大統領選敗北を受け入れない親トランプ派の暴徒による2021年の連邦議会議事堂襲撃である。トランプ氏は、暴徒を扇動した責任を認めていない。そのトランプ氏は、次回大統領選挙の共和党候補者氏名を獲得している。
アメリカの変質したリベラリズムの国際秩序への影響
このアメリカの変質したリベラリズムは、 自由、民主主義、人権の拡大がアメリカそして国際社会の平和と繁栄につながるという考えに基づくリベラルな国際秩序の脆弱化につながっている。アメリカの自国第一主義と国際協調の後退は、アメリカの「善意の覇権国」としての意欲の低下でもある。トランプ前大統領は、 アメリカの産業と雇用を守るためとしてTPPを脱退し、パリ協定から離脱した。さらにはコロナ禍においてWHOからの脱退を通知し、NATOにも攻撃的であった。バイデン政権でもアメリカの自国第一主義が垣間見られる。バイデン大統領はUNESCOやパリ協定へは復帰し、WHOからの脱退通知を撤回したが、「中間層のための外交」を唱え、TPPには復帰していない。
与党民主党への反対を主眼に置く共和党は、長引くウクライナ戦争においてウクライナへの軍事支援への不満と疲れを抱き始めた有権者の意向をとりこみながら、バイデン政権の追加支援案に執拗に反対した。結局、追加支援は半年遅れ、侵略側のロシア軍の優位性を高めた。
共和党強硬派による債務上限問題の政争化により、バイデン大統領のG7広島サミット出席が一時危ぶまれるという事態にもなった。権威主義国も参加するG20やBRICSの台頭の中で、G7はリベラリズムを掲げるその構成国の結束こそが強みであるにもかかわらずである。結局バイデン大統領は、サミットには出席した。しかし、サミット後に予定されていたパプアニューギニアへの米大統領としての初訪問や、またポートモレスビーでの太平洋島嶼国の首脳との会談の機会を、 債務不履行危機打開協議のために断念せざるを得なかった。これは権威主義体制の中国の支配が拡大しつつある西太平洋で、アメリカの存在感を増すための機会の逸失であった。
イスラエルのガザ侵攻に対するバイデン政権の容認姿勢は、 国連でのアメリカの孤立、世界での反米主義を生んでいる。容認姿勢の背景には、共和党との選挙競合が激化する中で、強力なユダヤロビーの支持の重要性が増していることもある。ただ、国際社会の中でのアメリカの権威は、 長期的には失墜する恐れもある。
加熱する党派対立の中で、超党派の支持があるのが対中強硬論である。この状況は、かえって熟慮に欠けた前のめりの意思決定、結果として中国と軍事衝突を招きかねない。アメリカ自身の覇権の地位が脅かされるという不安と恐怖に煽られた拙速さもこの危険性を高め得る。
さらに、アメリカのリベラリズムが解決しきれていない人種問題は、特にBLM運動を契機に、中国が自国内の人権問題に対するアメリカからの批判かわす材料となった。また、中国政府は、議会襲撃事件をアメリカ式民主主義の破綻と断じ、個人の自律性を実質尊重しない中国式民主の主張の妥当性を主張した。
リベラリズムに依拠する国際秩序のために
アメリカには自国のためにも、そしてリベラリズムに依拠する国際秩序の維持のためにも、寛容性を伴う本来のリベラリズムを取り戻すことが期待される。リベラリズムは、各個人が他者に干渉されずに自己の価値を追求するという普遍的な平等と自律性を前提とする。ただ、自由と平等のバランスは、具体的政治状況による妥協の結果であり、多様である。よってリベラリズムは、多様な政治的見解を包含し、価値の多元性を保障する。
ただこれは、価値相対主義とは異なる。リベラリズムにおける価値の多元性においては、人間が最低限満たす基準として、秩序、保護、安全、信頼、協力があるといわれている。 安全という基準については、昨今の経済格差拡大に鑑みれば、 経済福祉も含まれるであろう。
特に、国際社会においては、アメリカの国際協調主義の維持回復のみならず、世界の文明文化のもつ自由と平等の間の多様なバランスを尊重することが重要であろう。権威主義国に対しては、 排他的なナショナリズムや人権抑圧へは警鐘を鳴らしつつも、互いの安全や安定した関係を維持しつつ、政治的に賢明な妥協を模索した対話と協力を継続することが重要である。リベラリズムの寛容性こそが、価値の対立をまたぐための自由な言論と対話を継続させ、亀裂を修復させる。アメリカの価値観をもって他国を道義的に批判しても、中国はおろか、植民地被支配の経験と記憶を抱えるグローバルサウスの多くの国々の理解を得ることは難しい。さらに、今世紀後半には、アジアとアフリカの人口が世界の8割を占めると予想されており、寛容性に基づく価値多元性は現実的な目標でもある。
昨今のアメリカの対中政策としての「デカップリング」から「デリスキング」、そして半導体の輸出管理という対立分野とその他の協力分野という貿易上の区別は、価値の多元性の中での政治的妥協の実現といえる。
今日、日本をはじめリベラリズムを掲げる諸国には、原因や程度の差はあれど、国内社会の分断と対立が現れつつある。各国がアメリカの教訓から学んでこそ、リベラルな国際秩序の維持は一層強固なものになると期待される。
(Photo Credit: Keiko Hiromi / Aflo)

地経学ブリーフィング
コロナウイルス後の国際政治と世界経済の新たな潮流の兆しをいち早く見つけ、その地政学的かつ地経学的重要性を考察し、日本の国益と戦略にとっての意味合いを精査することを目指し、アジア・パシフィック・イニシアティブ(API)のシニアフェロー・研究員を中心とする執筆陣が、週次で発信するブリーフィング・ノートです(編集長:鈴木一人 地経学研究所長、東京大学公共政策大学院教授)。
おことわり:地経学ブリーフィングに記された内容や意見は、著者の個人的見解であり、公益財団法人国際文化会館及び地経学研究所(IOG)等、著者の所属する組織の公式見解を必ずしも示すものではないことをご留意ください。