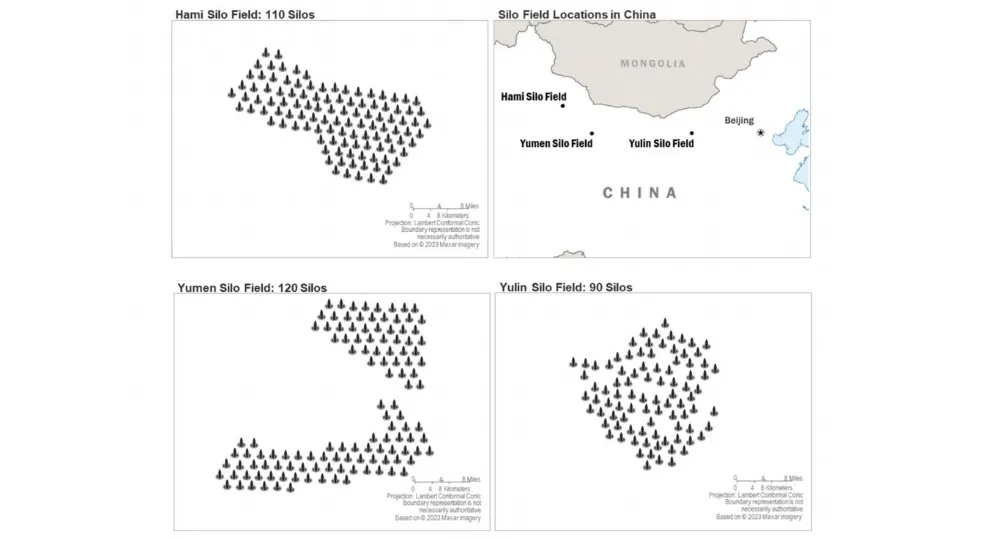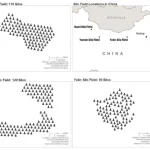トランプ政権トラッカー:大統領令の概要と解説 No.4(2025年2月5-2月11日)
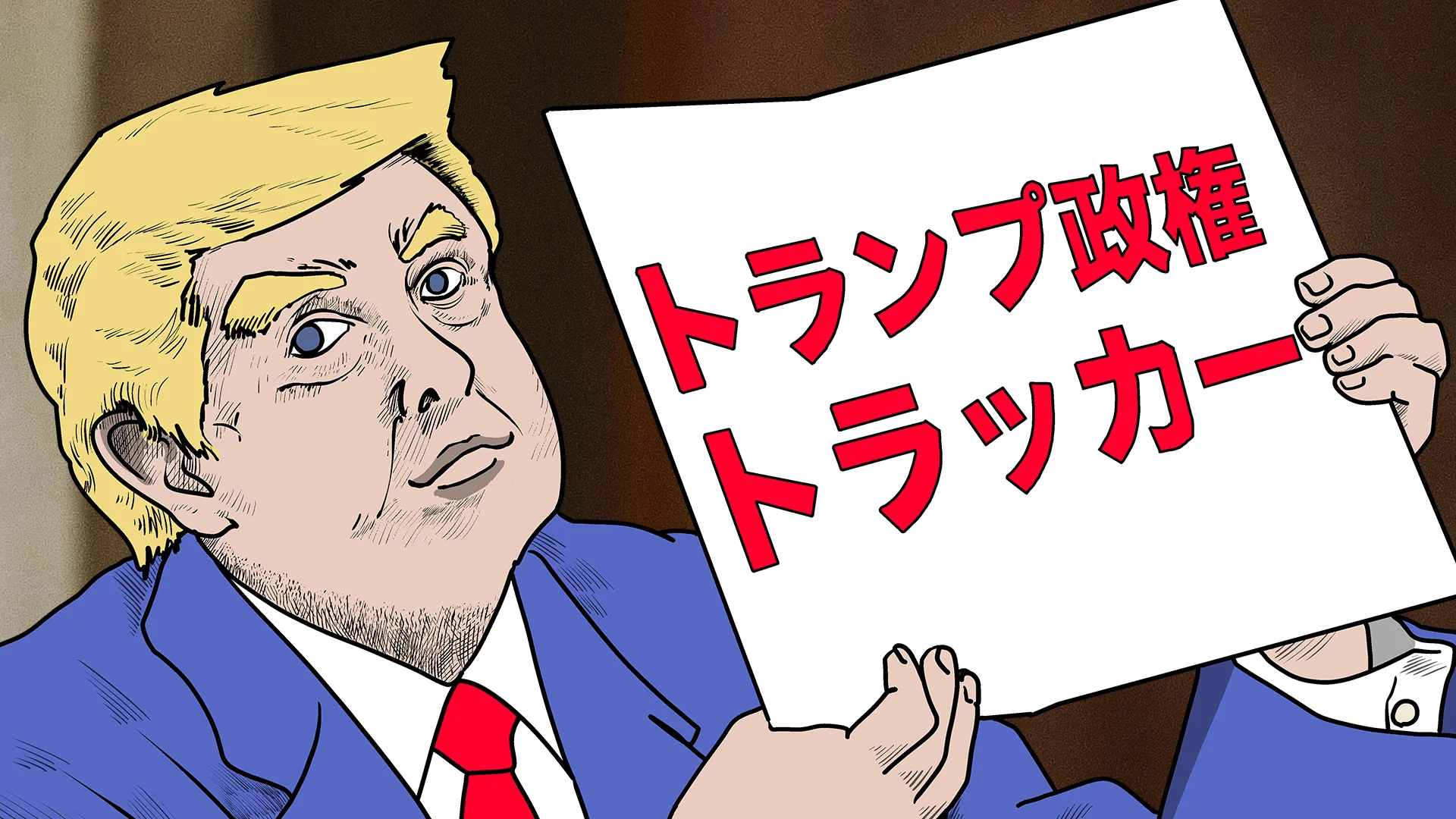
・「DOGE」による人員最適化の取り組み実施に関する大統領令
・米国の経済・国家安全保障の強化に向けた海外腐敗行為防止法(FCPA)の執行停止に関する大統領令
・紙ストローの調達や強制的な使用の終了を指示する大統領令
・南アフリカ共和国の悪質な行動に対処する大統領令
・アルミニウム輸入の調整に関する布告
・鉄鋼輸入の調整に関する布告
トランプ政権トラッカーの一覧(2025年1月20日~)
・【一覧】トランプ政権トラッカー(大統領令・布告・覚書・発表)
- 大統領令の一覧と概要
- 布告・覚書・公式発表の一覧と概要
- トランプ大統領の演説および優先政策
- エキスパートの視点
大統領令一覧
■解説付き■ 「DOGE」による人員最適化の取り組み実施に関する大統領令(2月11日)
この大統領令は、政府効率化省(DOGE)による連邦政府の人員削減を進めるための施策を実施するもの。各連邦機関に対し、4人の退職につき1人の新規採用に制限する計画(治安維持など重要職務を除く)や、DOGEと協力した採用計画の策定、職務の適格基準の見直しと非優先分野の縮小を指示している。(大統領令はこちら)
解説
1月20日の大統領令に基づいて設立(実際のところはオバマ政権時代に作られたデジタルサービス局の改編)された「政府効率化省(DOGE)」が実質的に動き始め、USAIDの予算の削減を筆頭に、行政府の支出に大ナタを振るっている。予算の削減に次いで、人件費の削減を目指すDOGEを後押しすべく、4人の退職に対して1人の新規雇用を認めるとしている。またDOGEチームがその採用を許可するだけでなく、財務省の会計システムにDOGEチームがアクセスできるようにしたことで、給与水準などもDOGEチームが決めることが出来るような体制がつくられている。これに基づき、多くの職員が早期退職するようになり、行政府の機能が失われつつある状況にある。中でも核セキュリティなどを担当するエネルギー省の人員が削減されたことで核物質の管理などが十分に行われなくなるといったことも懸念されている。(鈴木一人)
■解説付き■ 米国の経済・国家安全保障の強化に向けた海外腐敗行為防止法(FCPA)の執行停止に関する大統領令(2月10日)
この大統領令は、海外腐敗行為防止法(FCPA)の適用を180日間停止し、司法長官に対して既存の調査や措置の見直しを指示するもの。その背景には、FCPAの過度な適用が米国企業の国際競争力を損ない、国家安全保障にも悪影響を及ぼしているとの判断がある。(大統領令はこちら、ファクトシートはこちら)
解説
海外腐敗行為防止法(FCPA)は、ウォーターゲート事件や田中角栄元首相が逮捕されたロッキード事件などを契機として1977年に制定された外国公務員への贈賄行為を禁止する法律である。その適用範囲は広く、外国企業であっても米国内の子会社や銀行を介した場合にはFCPAの適用を受ける可能性がある。米国企業の公正さを確保するため、1988年の法改正以降は国際枠組みの締結や各国の規制強化を求める規定が設けられているが、トランプ大統領は第一次政権の時からFCPAの米国企業への「過剰かつ予測不可能」な適用を批判しており、今回の大統領令はトランプ大統領のFCPA観が反映された形といえる。今回の措置はFCPAの適用を一時的に停止するものに過ぎないが、2月5日にパム・ボンディ司法長官が発行した覚書には、カルテルや国際犯罪組織に関するFCPA捜査を優先すると記されており、FCPA停止が解除された後にFCPAが「米国第一主義」に基づく適用となる可能性、つまり米国以外の企業の国際犯罪に関連する事案が優先的に捜査される可能性を指摘する声もある。(石川雄介)
連邦行政研修所の廃止に関する大統領令(2月10日)
この大統領令は、国民や国家の利益にならないとの判断に基づき、連邦行政研修所(Federal Executive Institute)の廃止を指示するもの。同研修所は1968年に設立され、連邦政府幹部向けの研修プログラムを提供してきた。(大統領令はこちら、ファクトシートはこちら)
■解説付き■ 紙ストローの調達や強制的な使用の終了を指示する大統領令(2月10日)
この大統領令は、連邦機関の施設内における紙ストローの調達や提供の停止を指示するほか、全米での紙ストロー使用を廃止するための計画を45日以内に策定することを命じ、プラスチックストローより紙ストローを優先する政策の見直しを目指している。(大統領令はこちら、ファクトシートはこちら)
解説
海洋プラスチックごみ問題に対処すべく、プラスチックのストローを廃止するという社会的な動きがあったが、それをバイデン政権が2021年の大統領令で紙のストローを使用することを義務化した。その決定を廃止する大統領令だが、元々のプラスチックストローの問題は、メディアやSNSで広く拡散されたカメの鼻にストローが刺さった画像がきっかけであり、海洋プラスチックごみの問題を啓発することが目的だったにも関わらず、問題がストローに矮小化されたこともあって、リベラル派を自称する人たちの間でも、紙ストローは不評であった。そのため、トランプ政権が発する様々な大統領令の中で、意外な人気を博している大統領令となっている。(鈴木一人)
■解説付き■ 南アフリカ共和国の悪質な行動に対処する大統領令(2月7日)
この大統領令は、南アフリカ政府が少数派民族であるアフリカーナ人(主にオランダ系の子孫)の農地を補償なしに収容する方針を定めていることや、イスラエルを国際司法裁判所に提訴するなどの姿勢を取っていることに加え、イランとの関係強化も踏まえ、南アフリカへの資金援助を停止し、アフリカーナ人難民の再定住を支援するよう指示している。(大統領令はこちら、ファクトシートはこちら)
解説
1990年にアパルトヘイトが終了した南アフリカで、長らく黒人が多数派となり、政権もアフリカ民族会議(ANC)が担ってきた。その結果、黒人の社会的地位を向上する様々な政策が取られたことに対して、一部の白人(アフリカーナ)の人たちは反発をしていた。その1人がトランプ政権で強い影響力を持つイーロン・マスク氏である。彼はアフリカーナが迫害され、権利を奪われていると言うが、実際には過去の支配層であったアフリカーナの人たちは現在でも経済的に裕福な層をなしており、黒人の社会的地位の向上は道半ばといった状態である。しかし、そうした実情とは関係なく、イーロン・マスク氏が主張する議論を踏まえて発せられた大統領令。ファクトシートは「南アフリカの少数民族であるアフリカーナが迫害されている人権問題」という位置づけで大統領令の正当化がなされている点は、トランプ政権における人権概念の使われ方として興味深い。(鈴木一人)
ホワイトハウス信仰局の設立に関する大統領令(2月7日)
この大統領令は、宗教団体や地域組織、礼拝所における家族やコミュニティへの支援能力の強化や、宗教の自由の保護などを目的として、ホワイトハウス内に「信仰局」を設置することを指示している。(大統領令はこちら、ファクトシートはこちら、幹部指名に関する発表はこちら)
第二条修正条項の権利を保護する大統領令(2月7日)
この大統領令は、武器を保有し携帯する権利を定めた米国憲法修正第二条を保護するため、全ての命令、規制、国際協定などを30日以内に精査し、修正第二条の権利を侵害しているものを特定して是正案を提案するように命じている。(大統領令はこちら、ファクトシートはこちら)
国際刑事裁判所に制裁を課す大統領令(2月6日)
この大統領令は、国際刑事裁判所(ICC)が米国やイスラエルを含む同盟国に対して、不当かつ根拠のない行為を行っているとして、米国内におけるICC関係者の資産凍結や米国への渡航制限などの制裁を可能にするもの。なお、イスラエルも米国もICCの加盟国ではない。また、ICCは2024年11月にイスラエルのネタニヤフ首相らに対する逮捕状を発行していた。(大統領令はこちら)
反キリスト教的偏見を根絶する大統領令(2月6日)
この大統領令は、バイデン前政権がキリスト教徒を不当に取り締まったと批判し、「反キリスト教的な政府の武器化」を終わらせることを目的として、反キリスト教的偏見の撲滅を担うタスクフォースの設立を命じている。(大統領令はこちら、ファクトシートはこちら)
男性を女子スポーツから排除する大統領令(2月5日)
この大統領令は、教育機関やスポーツ団体が男性の女子スポーツ参加を認めることは「屈辱的で不公平かつ危険」であり、女子選手の機会を奪っているとして、男性の女子スポーツへの参加を禁止し、それに違反した教育機関へ連邦資金を停止する方針を定めている。(大統領令はこちら、ファクトシートはこちら)
中国からの合成オピオイド供給網に対処するために関税の修正に関する大統領令(2月5日)
この大統領令は、2月1日に発令された「中国からの合成オピオイド供給網に対処するために関税を課税する大統領令」を一部修正するものである。元の大統領令では、中国から輸入される全ての製品に対する関税について「de minimis制度」による関税免除が適用されないと明記されていたが、本大統領令ではde minimis制度の適用を一時的に認めつつ、商務長官の判断により適用が停止される可能性があるとしている。(大統領令はこちら)
布告・覚書・公式発表一覧
■解説付き■ アルミニウム輸入の調整に関する布告(2月11日)
この布告では、アルミニウム製品の輸入に関する関税率を従来の10%から25%に引き上げることを指示している。また、これまで適用されていた関税免除措置を終了し、2025年3月12日以降、すべての国からのアルミニウム製品の輸入に対して新しい関税率を適用する。(布告はこちら、ファクトシートはこちら、関連記事はこちら)
解説
2018年に「1962年の通商拡大法」の第232条に基づいてアルミニウムの輸入に10%の関税をかけていたが、アルゼンチン、豪州、ブラジル、カナダ、日本、メキシコ、韓国、EU、ウクライナ、英国はその適用を除外されていた。しかし、こうした除外国を通じて中国はアルミをアメリカに輸出しているという認識の元、「抜け穴」を防ぐことを目的とし、さらにアメリカのアルミ産業を保護するために、25%に関税を引き上げる決定をした。これにより、日本が享受していた適用除外も失われ、日本からの輸出も難しくなることは確実となった。(鈴木一人)
■解説付き■ 鉄鋼輸入の調整に関する布告(2月10日)
この布告は、これまで関税免除や代替措置が適用されていた国々に対する鉄鋼および派生鉄鋼製品の特例措置を終了し、2025年3月12日から一律25%の追加関税を適用することを指示する。これまで日本は関税割当(一定の輸入量までの関税免除)を受けていたが、今回の措置により同様の例外措置は認められなくなる。(布告はこちら、ファクトシートはこちら、関連記事はこちら)
解説
アルミニウムと同様、鉄鋼に関しても、2018年に設定した25%の関税の適用除外となった国、特にメキシコやカナダを経由した鉄鋼の輸入が米国産業にとって不利な状況となっているとして、適用除外を排し、全ての国を対象に25%の関税をかけることとなった。日本製鉄によるUSスチール買収の際にも明らかにされた「鉄鋼は安全保障上、死活的な産業である」という認識の元、国際競争から米国産業を保護し、国内での生産を維持することを目指した布告。(鈴木一人)
「アメリカ湾の日」を制定する布告(2月9日)
「アメリカの偉大さを称える名称を復活させる大統領令」(EO14172)によってメキシコ湾を「アメリカ湾」とするよう指示したトランプ大統領は、2025年2月9日、「アメリカ湾」を訪問し、同日を「アメリカ湾の日」として制定する布告を発した。(詳細はこちら、アメリカの偉大さを称える名称を復活させる大統領令はこちら)
日米首脳会談(2月7日)
石破茂首相とトランプ大統領は米国現地時間2月7日、ホワイトハウスで初の首脳会談を行った。会談後に公表された共同声明では、日米同盟を新たな高みに引き上げる決意を確認するとともに、同盟の抑止力と対処力の強化、エネルギー安全保障の強化や日本へのLNG輸出増加、日米豪印・日米韓・日米比といった多国間枠組みによる協力の重要性が確認された。また、石破首相はトランプ大統領に対し、早期の日本公式訪問を招待した。(共同声明はこちら、日本外務省公式発表はこちら)
非政府組織への資金提供に際した米国の利益促進:各行政機関および省庁の長官への覚書(2月6)
この覚書は、アメリカの国益を損なう活動を行っている非政府組織(NGO)への資金提供を防ぐため、各行政機関の長に対し、NGOへの全ての資金提供を精査し、今後は米国の国益に沿った支出を行うよう指示している。(覚書はこちら)