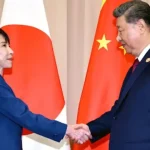対中抑止強化の逆説的アプローチ:米陸軍の新たな中東配備を検討すべき理由

第一次トランプ政権およびバイデン政権におけるアメリカの軍事戦略は、中東での軍事的関与を縮小し、西太平洋に戦力を集中させることで対中抑止力の強化を目指すものであった。しかし、この試みは実質的に失敗したと言わざるを得ない。因果関係は必ずしも明確ではないが中東情勢は米軍のプレゼンス縮小後、2023年10月のハマスによるイスラエルへの攻撃によって一変した。その結果、米軍はイスラエルへの防空ミサイルシステムの展開や複数の空母打撃群の中東派遣を余儀なくされた。
イスラエルとハマスが停戦した今、表面的には、中東情勢は安定すると見られているが、構造的には、イランが代理勢力の多くを失ったことで、核開発に向かう可能性が高まってしまったとも指摘されている。仮にイランが本格的に核保有を試み、情勢が緊迫した場合、トランプ政権は同地域の安定化を図るため、多くの部隊を派遣することになるだろう。そのため、トランプ政権がイランに対し従来よりも譲歩した政策を追求したとしても、依然として情勢悪化に備えなければならない。一方で、中国が台湾侵攻の能力を獲得すると米軍が懸念している2027年まで、すでに二年を切っていることから、このタイミングで西太平洋に対するコミットメントの意志の強さを示すプレゼンスと有事における対処能力を犠牲にして他地域に戦力を振り向ける余裕はない。米軍は、いかにして限られた戦力を複数の戦略正面において効果的に配置し、抑止力を構築していくべきか。鍵は米陸軍が握っていると思われる。
西太平洋における抑止態勢の課題
米軍はオバマ政権後期から、対中抑止の強化を目指してきた。しかし、その中核となる空母を11隻しか保有しておらず、さらにその約三分の一しか即応態勢を維持できないため、対中抑止の強化は二つの相反する戦略的要請が引き起こすジレンマに阻まれてきた。第一に、西太平洋におけるプレゼンスと有事対処能力の維持による抑止力の維持・強化であり、これを達成するには、他のアセットと共に複数の空母打撃群を同地域に常時展開させることが重要である。中国が通常戦力で優位に立つ中、西太平洋における空母打撃群を中核とする海空戦力を弱める余裕はない。第二の戦略的要請は、危機や紛争は地域を跨いで影響をもたらす性格を持つため、インド太平洋以外の地域でも同様に抑止力や対処力を維持しなければならない点である。このため、米軍は西太平洋に集中すべき戦力を、他地域への対応のために分散させ続けざるを得ない問題に直面している。
この二つの要請が対立したとき、ほとんど決まって西太平洋における抑止力が犠牲にされ、日本に前方展開する空母打撃群が中東に緊急派遣される事態が繰り返されてきた。これは、空母打撃群が短時間で大規模な海空戦力を世界各地に展開可能な高い機動力を持ち、受け入れ国との調整が不要であるため、陸上戦力よりも派遣しやすいという特性に起因している。横須賀を拠点とする空母は、2021年にアフガニスタン撤退支援、2024年にはイランやその代理勢力を打撃するために中東に派遣され、西太平洋に一隻も原子力空母が存在しない状況が度々生じた。このように、西太平洋地域における抑止態勢は他地域での危機や紛争に引き抜かれやすい空母打撃群に依存しているため、構造的に非対称的な課題を抱えている。
特にバイデン政権は、このジレンマを適切に調整することに失敗した。中東での米軍のプレゼンス縮小後、地域の不安定化は加速し、さらに西太平洋における持続的な抑止力維持も困難なものにしてしまった。台湾有事の可能性が高まるにつれて、以前と同様な地域を超えた戦力配備のトレードオフを繰り返すことはリスクが高すぎるため、異なる戦略が求められる。
米陸軍の長距離精密打撃能力
第二次トランプ政権は、西太平洋における抑止力を高めつつ、他地域も安定させるというジレンマに効果的な答えを打ち出さなければならない。米陸軍が、中東に強力な有事対処能力を恒常的に配備すれば、仮に中東情勢が不安定化しても、米海軍が西太平洋地域以外への空母打撃群の展開する頻度を減らし、二つの戦略的要請を同時に満たすことが可能になる。
米陸軍が現在整備を進めているマルチドメイン任務部隊(MDTF)は、長射程精密打撃能力を保有しているため、中東に配備された場合、対処能力の増強に貢献する可能性を秘めている。同部隊は、主に戦略火力大隊と防空大隊によって構成されている。前者は移動可能な発射機に搭載されている短距離(HIMARS)・中距離(MRCタイフォン)・長距離(LRHW)ミサイルと電子戦・サイバー能力・情報戦能力を組み合わせたものであり、後者は、無人機等の新たな経空脅威にも対応可能な防空能力を保有している。
中東に展開したMDTFの精密打撃能力がイランやその代理勢力を抑止できるかは明らかではない。過去の事例を見ても、精密打撃能力が抑止力向上に寄与した明確なエビデンスは乏しい。そもそも、これまで中東に派遣されていた空母がイランなどに対する抑止力あるいはフーシ派のミサイル能力の破壊に十分な効果を発揮したかは不透明である。さらに、MDTFは隠れて敵の隙を突くという非対称能力の性格を持つため、平時プレゼンスを示威する空母の役割を代替することはできない。しかし、ある程度の火力を投射できるため、空母打撃群が中東において求められてきた有事対処能力は代替できるだろう。
マルチドメイン任務部隊中東配備の意義と課題
米陸軍のMDTFが対中抑止に貢献する方法は、西太平洋だけでなく中東への配備も急ぐことが重要だ。一見矛盾しているようだが、中東でMDTFが十分な有事対処能力を発揮すれば、対中抑止の要である空母打撃群の中東派遣を減らせる。情勢が大幅に悪化すれば、西太平洋から中東に派遣せざるを得ないが、MDTFが展開していればその頻度と規模を抑えられ、中東対応と対中抑止のバランスを維持できる。米陸軍は2028会計年度までに五つのMDTFを運用開始し、そのうち3部隊を米太平洋陸軍、1部隊を米欧州陸軍の隷下に配備し、残る1部隊を米中央軍の担任地域に配備する計画を進めている。しかし、中東への1部隊の配備で十分な有事対処能力が得られるかは議論の余地があり、地域情勢を踏まえた再検討が求められる。
一方で、MDTFにはいくつかの課題も存在する。同部隊は、新たに空母打撃群を編成するよりも圧倒的に安価かつ短時間で整備できるが、トマホーク巡航ミサイル(射程約1,800㎞)や長距離極超音速ミサイル(射程約2,800㎞)といった高価なミサイルを運用するため、作戦遂行時のコストが空母打撃群と比較して高額になると思われる。MDTFが中東で効果的かつ効率的な火力を発揮するためには、新興防衛企業が開発する安価なミサイルや無人アセットの導入を積極的に検討する必要がある。
また、MDTFの配備には受け入れ国との調整が不可欠であり、地域情勢や国民感情を理由に配備を拒否される可能性もある。例えば、MDTFの日本配備が見送られたのは、日本政府が国内世論の反発を懸念したためである。同盟国等との信頼を維持しつつ、部隊配備を円滑に進めるためには、慎重な外交が求められる。しかし、中東情勢は現在大きく動いており、イランやその代理勢力を抑止する新たなフレームワークを検討する政策の窓が開きつつあるため、地域におけるアメリカの友好国がMDTFの受け入れなどの負担増を買って出る可能性は十分に考えられる。
次期グローバル・ポスチャー・レビューに求められる戦略眼
トランプ政権が新たに国家防衛戦略を策定するにあたり、米軍の戦力態勢を見直すグローバル・ポスチャー・レビューに取り組むと予想されるが、1期目およびバイデン政権が犯した過ちを繰り返すべきではない。限られた資源の中で、米軍は多正面で同時に紛争を抑止するためには、その基盤となる十分な有事対処能力を維持することが求められる。そのため、中東での突発的な事態に対処しつつ、対中抑止の態勢を維持するアプローチが不可欠である。中東における空母打撃群の役割を部分的に補完する手段として、MDTFの配備を加速することは、有効な選択肢の一つといえる。中東配備に伴う費用を、引き続きアメリカにイランを抑止してもらいたいと考える地域諸国に負わせれば、アメリカ・ファーストのアプローチとも符合させることもできる。
陸軍と同じく陸上兵力を基盤とする米海兵隊は、近年、海軍の支援を受けて戦う組織から、戦域レベルで海軍を支援し、海上戦での優位性を確保するための組織へとその役割を転換してきた。同様に、米陸軍も他地域において海空軍を補完することで西太平洋での対中戦力バランスを改善し、その存在感を示すことが可能だろう。
(Photo Credit: Darrell Ames / Program Executive Office Missiles and Space)

地経学ブリーフィング
コロナウイルス後の国際政治と世界経済の新たな潮流の兆しをいち早く見つけ、その地政学的かつ地経学的重要性を考察し、日本の国益と戦略にとっての意味合いを精査することを目指し、アジア・パシフィック・イニシアティブ(API)のシニアフェロー・研究員を中心とする執筆陣が、週次で発信するブリーフィング・ノートです(編集長:鈴木一人 地経学研究所長、東京大学公共政策大学院教授)。
おことわり:地経学ブリーフィングに記された内容や意見は、著者の個人的見解であり、公益財団法人国際文化会館及び地経学研究所(IOG)等、著者の所属する組織の公式見解を必ずしも示すものではないことをご留意ください。


研究員
慶應義塾大学法学部政治学科卒業、同法学研究科政治学専攻修士課程修了。2023年4月より博士課程。専門は、米豪同盟、防衛・安全保障政策、防衛産業政策。アジア・パシフィック・イニシアティブ(API)でのインターン(日米軍人ステーツマンフォーラム(MSF))を経て現職。
プロフィールを見る