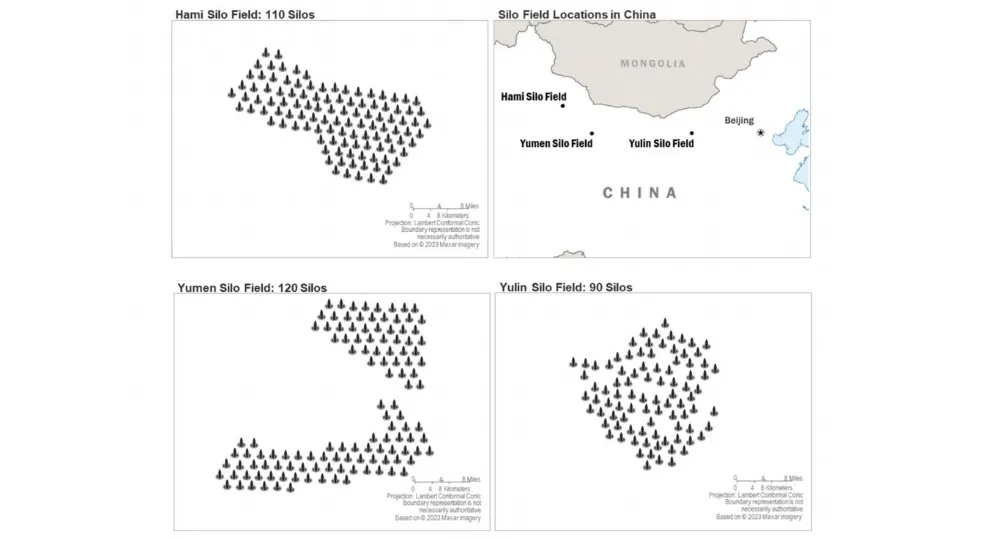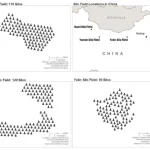視界不良の米空軍はどこへ向かうのか:湾岸戦争から対中戦争への転換?

「ドローンの時代に有人戦闘機なんて時代遅れ」
第二次トランプ政権で「政府効率化省(DOGE)」を率いるイーロン・マスクはこうXへ投稿した[1]。彼はまた、小型ドローン(無人機)の大群が編隊飛行する動画に「一方で、いまだにF-35のような有人戦闘機をつくっているマヌケもいる」とコメントし、最悪のコスパだとF-35をやり玉に挙げている[2]。
確かに、ロシア・ウクライナ(露・ウ)戦争で、ロシアは最新のSu-35戦闘機やA-50早期警戒管制機を含む350機以上の有人機を喪失し[3]、2022年2月24日の侵攻以来、一度も航空優勢を獲得できていない。今や作戦の主役は戦闘機からドローンやミサイルに移ったように見える。ウクライナ軍は、防空システムやMANPADS(携帯式防空ミサイル)によるロシア機の撃墜、また無人機による地上での破壊が功を奏し、航空戦力の圧倒的な劣勢にもかかわらず、地上戦を膠着状態に持ち込み、長期抗戦を続けている。
このような作戦推移の評価をめぐって米国の空軍戦略家の間では、「航空優勢派(Air Superiority)」対「航空拒否派(Air Denial)」の激しい論争が起きている。米空軍は長年に亘る予算等の制約のため、質量ともに危機的な状況に瀕しているとされる[4]。台湾有事を視野に、強敵となった中国軍の挑戦に米空軍はどう対抗するのか。単純化を恐れずに言えば、この戦略論争は空軍力の攻防の主軸をどちらにおくかであり、米空軍の今後の資源配分の優先順位だけでなく、日米同盟の「盾と矛」の役割分担にもその帰結が影響を及ぼす。
航空優勢の獲得が勝利のカギ?
航空優勢派の代表格のデヴィッド・デプトゥラ(David Deptula)元空軍中将は、露・ウ戦争の教訓として、開戦当初に航空優勢を獲得できなかったことがロシアから決定的勝利を奪った、また、十分な資源と能力がなければ航空優勢の獲得は困難でありウクライナのように自国領域への攻撃による被害に曝され続ける、という二点を挙げている[5]。彼は1991年湾岸戦争の「砂漠の嵐」作戦に従事し、その航空作戦を「20世紀に米国が戦った中で最も成功した戦争(米会計検査院報告)」と自負しており、最大の成功要因が航空優勢だとしている。米空軍はその後のコソボ紛争(1998-99)においても勝利の中心的な役割を果たし、この「航空優勢」思想は米空軍だけでなく、航空自衛隊を含む世界の空軍において今でも支配的となっている。
2001年の9.11同時多発テロ以降の米空軍は、対テロ作戦(Counter-Insurgency)が主任務となり、イラク戦争(2003-11)やアフガン戦争(2001-21)に従事したが、対象脅威はまともな空軍戦力を持っていなかった。このため、空軍長官と空軍参謀長が毎年度連名で議会に報告する「米空軍態勢報告(USAF Posture Statement)」においても、テロとの戦いの長期化による作戦テンポの問題や即応体制(Readiness)の低下、また長年の国防予算の抑制による主要装備品等の近代化の遅れや戦力規模の縮小について強い危機感が示されているものの、中国に対抗する体制については将来のレディネスへの懸念を示唆するに留まっていた。
この状況を劇的に転換したのが第一次トランプ政権の国家安全保障戦略・国家防衛戦略(2017NSS/2018NDS)である。米空軍もその後の態勢報告では、同等の敵(中国)とのハイエンドの戦いを前提とした新たな戦い方(Joint All Domain Command and Control: JADC2)を実現するため、資源投資の優先分野として、①統合戦力のネットワーク化、②宇宙の圧倒的支配、③戦闘力の創出、④被攻撃下での兵站を挙げた。これらは、その後の宇宙軍の創設やA2/AD(接近阻止・領域拒否)脅威下での航空戦力の分散・機動による「俊敏な戦力運用(Agile Combat Employment: ACE)」構想へと繋がっている。
さらに2021年7月に就任したフランク・ケンドール(Frank Kendall)空軍長官は、通常戦力における対中優位を維持するために必要な7つの運用要求(Operational Imperatives: OI)を示し、資源投資の優先順位を明確にした。7つのOIとは、①宇宙能力の強化、②先進戦闘指揮統制システム/JADC2の構築、③次世代航空支配(NGAD)の明確化、④脅威下での移動目標対処能力の強化、⑤脅威下での基地・兵站強化、⑥B-21長距離攻撃機開発、⑦空軍省の有事移行体制である[6]。当時のチャールズ・ブラウン(Charles Brown)空軍参謀長(2020.8-2023.9)も「Accelerate Change Or Lose: ACOL(変化を加速せよ、しなければ負ける)」を合言葉に変革を奨励した。これらの体制改革は、凄まじい勢いでA2/AD態勢を強化し、対等もしくは対等以上の能力を有する強敵となった中国軍に対し、いかに航空優勢を獲得するかという思考が前提にある。
航空拒否戦略(Air Denial Strategy)とは何か
露・ウ戦争はお互いに航空優勢を取れないまま、ドローンやミサイルによる攻撃の応酬が続いており、ロシアは決定的な勝利を達成できていない。航空拒否戦略を提唱するマキシミリアン・ブレマー(MaximilianBremer)とケリー・グレコ(Kelly Grieco)は、「攻撃は最大の防御であり、空軍力は本質的に攻撃力である」という伝統的な前提に対し、「防御こそ本質的に航空戦の中でより強力な形態であり、新たな技術や戦術の登場が防御側の優位性をさらに強化している」とし、お互いに航空優勢が取れない状況こそ、中国の台湾侵攻を抑止すると主張する[7]。彼らの主張を要約すると、
・中国との戦争は常に核戦争への拡大を念頭に置かねばならない。航空優勢を獲得する為には、中国軍の海上配備防空システムや本土の航空基地等を無力化する必要があり、このような本格的航空進攻(攻撃)は核戦争のリスクを著しく高めるので、戦略として不適切だ。
・中国が構築したA2/AD態勢は航空優勢派も認めるように堅牢強固であり、これを突破するのは極めて困難、仮に突破できても多大な損害は不可避。一方、中国が台湾海峡を越えて本格洋上侵攻するには航空優勢の獲得が不可欠。我が方が重層的かつ重厚な防空システムを展開(防御)すれば、航空優勢獲得の重荷は中国が担うことになる。核エスカレーションのリスクも低い。
・技術的に大きく進化したミサイル・防空システムが中国の航空優勢獲得を拒否できることを中国に理解させられれば、拒否的抑止(相手の戦争遂行手段を無効にして戦争による目的達成を断念させる戦略)は機能する。米空軍は航空拒否を主任務に規定し、空軍自ら防空任務を担うべきだ(空自と異なり、PatriotやTHAADの防空任務は米陸軍が担当)。
第一次トランプ政権で国家安全保障担当大統領副補佐官を務めたポッティンジャーは、近著The Boiling Moat(邦題『煮えたぎる海峡』)で、台湾海峡を「煮え立たせ」、本格的な洋上侵攻の重心となる中国海軍を撃沈する拒否的抑止戦略を提唱している。同書は航空拒否について言及していないが、洋上侵攻の必要条件である中国の航空優勢獲得を拒否できれば、洋上侵攻拒否と合わせた二段構えの拒否的抑止力の強化となる。
資源の最適配分に必要な戦略構想
クラウゼヴィッツは「政治家や司令官がなすべき最初の、そして最も広範囲に及ぶ究極的な判断行為は、乗り出そうとしている戦争がどのようなものなのかを明らかにすることだ」と指摘した。米国は中国との戦争を、何を目的にどの手段でどのように戦い、勝利しようとしているのか。中国のA2/AD戦略に対抗する構想は、2010年の「QDR(四年毎の国防見直し)」で提示された統合エアシー・バトル構想(JASBC)に遡るが、今に至るも明確な作戦戦略いわゆる勝利の方程式は確立されていない。
航空拒否戦略による防御態勢構築は中国との戦争に勝利し、抑止する方程式の一つの解となり得る。米インド太平洋軍はグアムのミサイル防衛体制を強化し、同空軍はACEの拠点となる前進基地等の拡張や抗堪性の強化に取組んできており、中国の侵攻を「拒否」するための資源投資を既に行っている。この拒否態勢、即ち統合防空ミサイル防衛能力や航空戦力の機動運用体制を、第一列島線において日本・台湾・フィリピンと共同で強化することは有効な選択肢だ。
同時に、航空優勢が勝利の必要条件であることも当面、不変である。課題は、無人機等の新たな手段を含む最適な組合せによって、必要な時に必要な空域でいかに航空優勢を確保するかだ。マスクの指摘するとおり、兵器の費用対効果は資源配分の重要な指標である。最新戦闘機の単価は暴騰しており、ドローン等の安価で消耗可能な装備の活用は当然必要だ。しかし、装備品の効用は適切な戦略に裏付けられた明確な運用構想に基づいて計らねばならない。ケンドール長官は離任に当たり、米空軍の最大の開発プロジェクトであり、OIの一つのNGAD(次世代航空支配)を一時中断し、継続の是非をトランプ政権に委ねた[8]。第二次トランプ政権の対中戦略策定及びNGADを含む空軍戦力構築の判断は、航空優勢と航空拒否、即ち攻防のバランスをどう保つかがカギとなろう。
日米同盟に期待される相乗効果
石破・トランプ政権で初の日米首脳会談では、自衛隊と米軍の指揮統制の枠組みや南西諸島での両国軍の存在感向上等によって日米同盟の抑止力・対処力をさらに強化することが表明された。GDP比3%以上の防衛費増額要求はなかったが、日米共同態勢の強化は第二次トランプ政権にとっても最重要課題である。日米同盟の基本的な「盾と矛」の役割分担を、航空優勢と航空拒否をめぐる自衛隊と米軍の戦略的連携に進化させ、対中抑止の相乗効果を上げるべきだ。日米は相互の政権イメージにとらわれず、引き続き実務的な戦略協議を深化させ、共同態勢の具体化を推進する必要がある。
脚注
- [1] https://x.com/elonmusk/status/1861070432377737269
- [2] https://forbesjapan.com/articles/detail/75495
- [3] https://www.newsweek.com/russia-air-force-losses-ukraine-christopher-cavoli-1890228
- [4] https://www.forbes.com/sites/davedeptula/2025/01/29/president-trump-reverse-the-air-force-nosedive–boost-the-space-force/
- [5] https://www.airandspaceforces.com/article/air-superiority-and-russias-war-on-ukraine/
- [6] https://www.af.mil/news/article-display/article/2953552/kendall-details-seven-operational-imperatives-how-they-forge-the-future-force/
- [7] https://warontherocks.com/2023/04/in-defense-of-denial-why-deterring-china-requires-new-airpower-thinking/
- [8] https://defensescoop.com/2024/12/05/air-force-punts-ngad-fighter-decision-to-trump-administration/
(Photo Credit: US Air Force)

地経学ブリーフィング
コロナウイルス後の国際政治と世界経済の新たな潮流の兆しをいち早く見つけ、その地政学的かつ地経学的重要性を考察し、日本の国益と戦略にとっての意味合いを精査することを目指し、アジア・パシフィック・イニシアティブ(API)のシニアフェロー・研究員を中心とする執筆陣が、週次で発信するブリーフィング・ノートです(編集長:鈴木一人 地経学研究所長、東京大学公共政策大学院教授)。
おことわり:地経学ブリーフィングに記された内容や意見は、著者の個人的見解であり、公益財団法人国際文化会館及び地経学研究所(IOG)等、著者の所属する組織の公式見解を必ずしも示すものではないことをご留意ください。


シニアフェロー,
第24代航空自衛隊補給本部長;空将(退役)
奈良県出身、1982年防衛大学校卒業(管理学専攻)。1997年米国ハーバード大学ケネディ大学院修士課程修了、2002年米国防総合大学戦略修士課程修了。統合幕僚監部報道官、第2航空団司令兼千歳基地司令、統合幕僚監部防衛計画部長(2013年空将昇任)、航空自衛隊幹部学校長、北部航空方面隊司令官を経て、2017年航空自衛隊補給本部長を最後に退官。2019年7月~2021年6月、ハーバード大学アジアセンター上席研究員。現在、企業アドバイザー及び安全保障研究フェロー。
プロフィールを見る