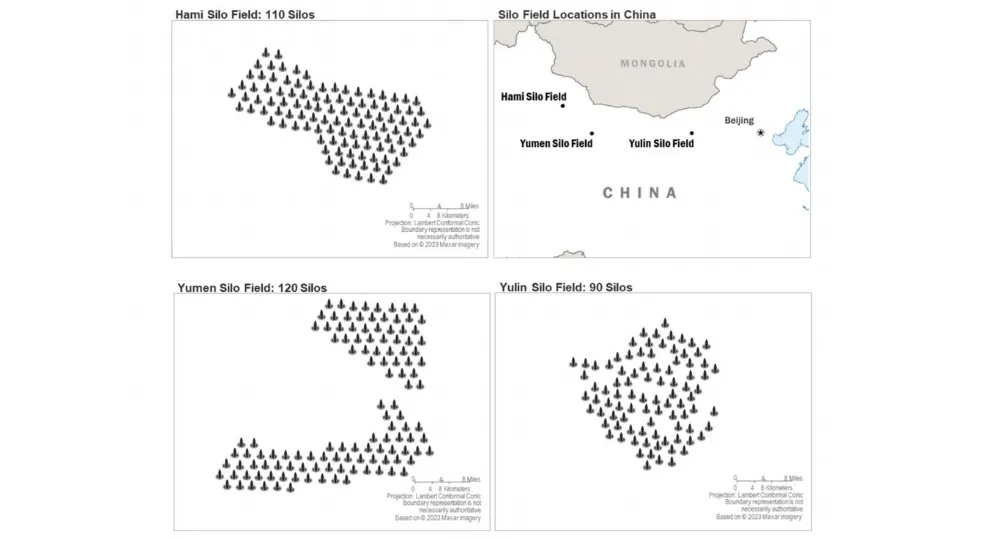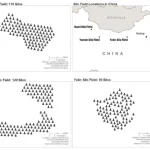世界はトランプ政権をどう見るか No.3
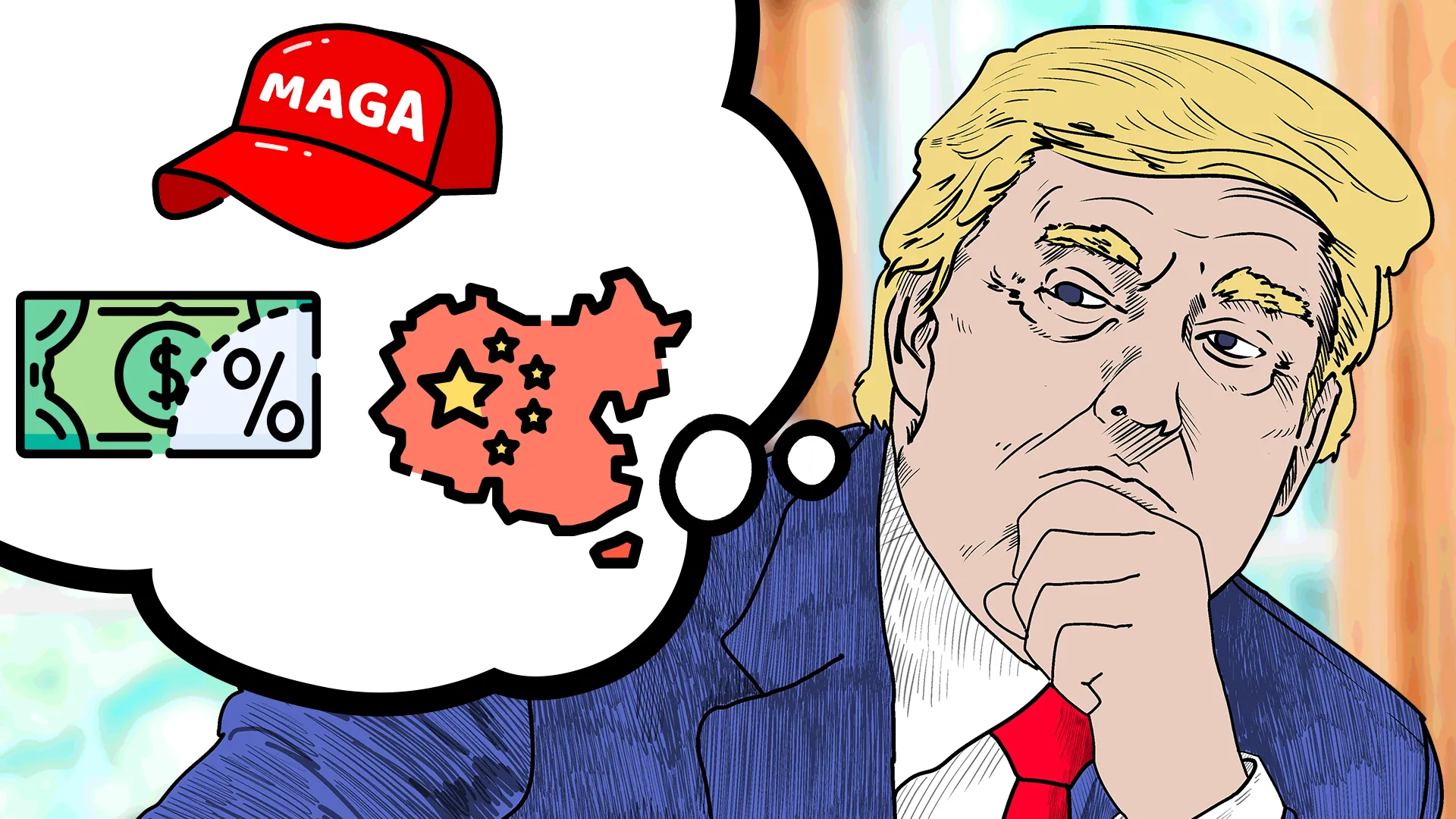
世界はトランプ政権をどう見るか(主要論考の紹介)

特集「2025年 トランプ政権は世界をどう変えるか」
トランプ第二次政権の動向がグローバル経済や国際秩序にどのような変化をもたらすのか、そして他国はどのように対応するのかが注目されます。本特集では、2025年のトランプ政権の政策動向とその影響を分析し、国際社会に与えるインパクトについて考察します。
①「米国権威主義への道」
Steven Levitsky and Lucan A. Way, “The Path to American Authoritarianism,” Foreign Affairs, February 11, 2025
ベストセラーとなった『民主主義の死に方』の著者で、近年にはその実質的な続編である『少数派の横暴』を著すなど米国における民主主義の後退の危険性に警鐘を鳴らしてきたハーバード大学教授のスティーブン・レビツキーと、彼と共同で政治体制の研究を行っているトロント大学教授のルーカン・ウェイによる論考である。現在の米国が、彼らの提唱する政治体制である「競争的権威主義」への移行の危機に瀕していると論じており、比較政治学の大御所による、理論的知見を生かした第2次トランプ政権論の決定版と言える。
レビツキーとウェイによると、第2次トランプ政権は司法省、FBI(連邦捜査局)、IRS(内国歳入庁)等の職業公務員を自らに忠誠を誓う人物に入れ替えることによる政敵を標的とした訴追や税務調査、政治的に友好なビジネスリーダーに報いるための規制の決定、支持者による政治的暴力の黙認、政府批判を行う政治家、市民、メディアへの圧力等を駆使した「国家機構の武器化」を行っている。共和党が民主主義の基本的な原則へコミットする意志と能力を失った今日において、その危機は極めて深刻だという。第2次トランプ政権下で米国の政治環境が激変する中、同盟国である日本には様々な可能性を念頭に置いた知的・政策的な備えが求められる。
②「USAIDの解体は世界中の独裁者にとっての勝利である」
Samantha Power, “Killing U.S.A.I.D. Is a Win for Autocrats Everywhere,” The New York Times, February 6, 2025
トランプ政権による米国国際開発庁(USAID)の解体の決定を受け、バイデン政権下でUSAID前長官を務めたサマンサ・パワーが寄せた論考である。この決定は「残酷かつ逆効果」だとして、人道的・戦略的観点の双方から厳しく批判している。
USAIDが世界各国で児童への医薬品や栄養食品の供与、疾病対策、紛争地域への緊急人道援助等に貢献してきたのは言わずもがな、ケネディ大統領による創設以降米国の超党派の支持を受け、冷戦期には共産主義に対抗する世界戦略において枢要な役割を果たしてきた点が重要である。パワーが指摘する通り、中国による高金利の債務の再交渉やサプライチェーンの多元化による重要鉱物の輸入拡大など、USAIDの米国の国家安全保障上の重要性は増していた。世界各国で米国が撤退した空白を埋めるのは中国やロシア等の権威主義国家に他ならず、今回の決定は賢明とは言い難い。トランプ政権下の米国の国際的な関与からの離脱を象徴する事例である。
③「中国の対トランプ戦略」
Yun Sun, “China’s Trump Strategy,” Foreign Affairs, February 6, 2025
トランプ政権が連日ニュースのヘッドラインを賑わせる中、中国の動きは比較的静かだ。それもそのはず、第二次トランプ政権期における中国の最優先課題は「嵐を乗り切る」ことであり、長期的には世界の超大国としての地位を確立することにある。こう論じるのは、軍備管理やインド太平洋研究に強みを持つ米国のシンクタンク、スティムソン研究所で中国・東アジア研究を統括するユン・ソンだ。彼女の論考は、米国の有識者が中国の対トランプ戦略をどう捉えているかを知る上で重要であり、大きな注目を集めている。
中国は、トランプによって引き起こされた混乱にただ揺さぶられるつもりはない。むしろ、トランプが主導する貿易戦争を利用し、国内改革を推進し、米国との関係が悪化した国々との結びつきを強め、新たな国際貿易秩序の中で優位に立とうとしている。トランプによる米国の信頼性と国際的影響力の低下は、中国の台頭を加速させる好機だと見ているのだ。
④「すべての大統領には外交政策がある。トランプには5つある。」
Hal Brands, ““Every President Has a Foreign Policy. Trump Has Five.,” Bloomberg, February 3, 2025
ジョンズ・ホプキンス大学高等国際問題研究所(SAIS)特別教授で、政策にも強い影響力を持つ国際関係史家であるハル・ブランズが、第2次トランプ政権の対外政策を形作る派閥について整理・分析した論考である。トランプ政権の対外政策を理解するための基本的な枠組みを極めて明快に提示している点で、この論考は傑出している。
ブランズによると、トランプ政権の外交政策は、米国の優位性の維持による国際秩序の安定を重視する「グローバル・ホーク派」、西太平洋における軍事バランスの強化を追求する「アジア・ファースト派」、中東をはじめとする対外的な関与からの撤退と軍事支出の削減を目指す「米国よ、帰って来い派」、外交政策を商業の問題と捉えて外国からの投資の呼び込みや不公正な貿易慣行の是正を目指す「経済ナショナリスト派」、外交政策を国内政策の延長とみなし、対外援助の削減や強硬な移民政策を推進する「MAGA強硬派」の5つの派閥の合従連衡によって形成される。政策アジェンダごとに各派は一致点と相違点の双方を有するため、どの派閥の意見が重視されるかによってトランプ政権の外交政策は大きく変動し得る。各派閥の主要人物と各政策アジェンダに対する見解を認識しておくことが、トランプ政権の外交政策を占う上で重要である。
⑤「トランプ政権が引き起こした中国経済の津波に対するASEANの対応」
Mari Pangestu, Shiro Armstrong, “ASEAN response to a Trump-generated Chinese economic tsunami,” East Asia Forum, February 2, 2025.
トランプの対中関税により、安価な中国製品が津波のように東南アジアへ流れ込むと予測されている。これに対抗するため、東南アジア諸国はASEAN内で連携し、貿易ツールや制度を活用しながら、中国との対話を通じて正当な防衛策と持続的な解決策を講じ、保護主義の激化を防ぐ必要がある。こうした警鐘を鳴らしたのは、2023年まで世界銀行専務理事を務め、インドネシアの貿易相や観光・創造経済相を歴任したマリ・パンゲストゥと、オーストラリア国立大学の経済学教授シロ・アームストロングだ。トランプの関税政策は中国を標的にしているものの、その余波は世界各国に及ぶ。パンゲストゥらの「津波警報」を受けた東南アジア諸国がどのように対応するのかが注目される。対米輸出黒字を維持するASEAN諸国にとって、トランプの関税だけでなく、すでに発動されている関税措置による過剰生産の影響で、中国製品が域内に流入するリスクにも備えなければならない。
⑥「史上最も愚かな貿易戦争」
The Editorial Board, “The Dumbest Trade War in History,” Wall Street Journal, January 31, 2025.
カナダとメキシコからの輸入品に対して25%の関税を課すとしたトランプ大統領の決定を受け(※2月3日、この追加関税の発動を1ヶ月後まで一時停止することを発表)、米国保守系の主要紙である『ウォール・ストリート・ジャーナル』紙が発表した社説である。これまでトランプ政権に対して肯定的な立場を表明することが多かった同紙が、トランプ大統領の経済政策を「史上最も愚かな貿易戦争」という強い表現で批判したことは衝撃を与え、注目を集めた。
社説によると、違法薬物の流入を止めるために高関税を課すという正当化は意味不明であり、北米3カ国のサプライチェーンが高度に統合されている自動車産業への影響が特に深刻であるほか、報復関税の可能性も懸念される。自らを「タリフ・マン」と称するトランプ大統領であるが、今回の決定は自身が1期目に交渉・署名した米国・メキシコ・カナダ協定(USMCA)に違反するものであり、同盟国であるカナダや近隣のメキシコに対して、戦略的競争相手である中国よりも高い関税を課すのは合理的ではない。このような経済的威圧の事例は、今後も増えてくると予測される。
⑦「トランプ2.0とベトナムがすべき3つのこと」
Pham Quang Vinh, Duy Linh, “Trump 2.0 và 3 việc Việt Nam cần làm,” Tuoi Tre Online, January 22, 2025.
ベトナムの元外務副大臣であり、第1期トランプ政権下の米国で駐米特命全権大使も務めたファム・クアン・ヴィンが、ベトナムを代表する有力な日刊新聞の電子版TuoiTreOnlineに寄せた論考。
最大の懸案は、ベトナムの対米貿易黒字が膨らんでいることだが、トランプは関税によってベトナムに本当に制裁を加えたいわけではなく、対話と交渉を通じて、米国とベトナムがなんらかの合意に達することを望んでいると理解しておくべき。
その観点で、ベトナムが取り組むべき課題が三つある。第一に米国売りたがっているもの、ベトナムが必要としているものの輸入を増やすこと、第二に輸出製品の原材料や部品の国内生産比率を高め、米国が懸念している中国原材料への依存率を減じること、そして第三に米国企業の投資及びビジネスの障壁を下げることである。
トランプが関税を課す場合、事前に何らかの警告があり、段階的に関税が実施されると考えられる。日本において我々も、それを待つだけではなく、先手を打って課題に取り組むことで問題解決の余地がうまれるであろう。