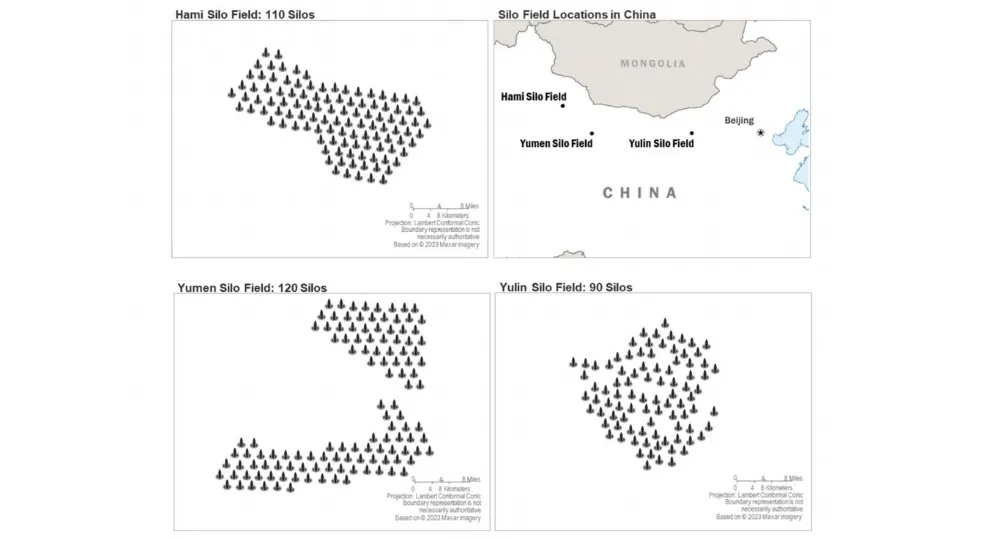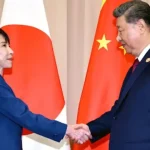中国は自由貿易の擁護者になれるのか
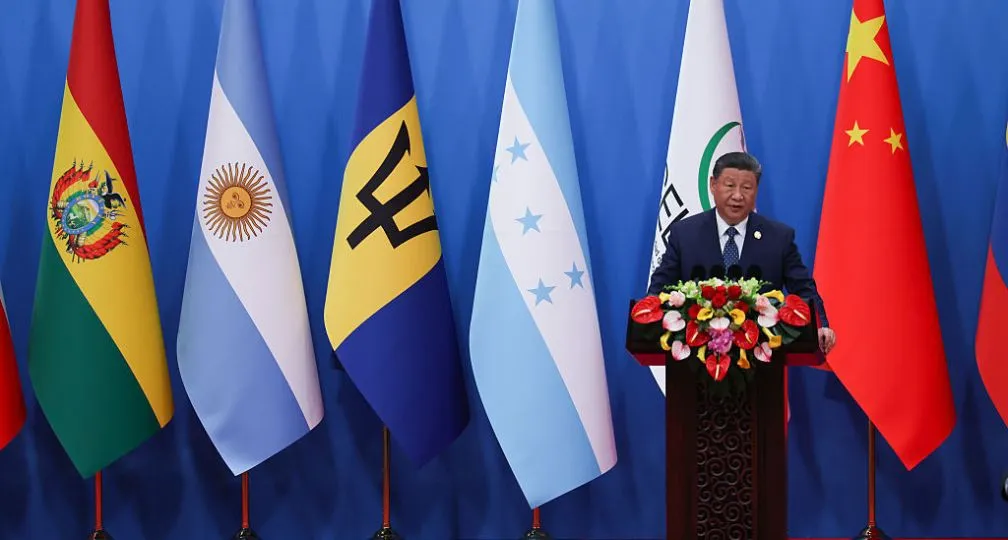
これに対して、中国は、米国による相互関税を保護主義として批判し、100%を超える対中関税には「最後までお付き合いする」として、自由貿易や多国間貿易体制の維持を主張した。米国によるパリ議定書からの離脱に対して、中国外交部報道官は、気候変動は全人類の共通課題であって、個別の国による一方的行為は許されないと批判した。中国は、自らが自由貿易や多国間主義の擁護者であるかのように振る舞い始めている。
中国は、国際秩序の擁護者になれるのだろうか。自由貿易の擁護者と主張する中国に、我々はどう向き合うべきだろうか。
キンドルバーガーの罠か
第一次トランプ政権が始まる直前の2017年1月、米国の国際政治学者であるジョセフ・ナイ教授は、強すぎる中国は、現在の覇権国(米国)が新興国(中国)を脅威に感じて戦争になる「トゥキディデスの罠」に陥るが、弱すぎる中国も、国際公共財を提供する大国がなくなり国際秩序が揺らぐ「キンドルバーガーの罠」を起こすので避ける必要があると主張した。ナイ教授は、金融の安定性や航行の自由といった各国が利用して利益を受ける国際公共財は大国によって提供されるのであり、中国が弱すぎて国際公共財にただ乗りすれば、国際公共財が提供されなくなり、国際社会が不安定になると警告した。
それから8年が経過しているが、中国は国連などの国際組織での活動を活発化させ、発展・安全保障・文明に関するグローバルイニシアティブを発表するなどしており、国際公共財を提供する意思はありそうである。実際、中国は「一帯一路」やアジアインフラ投資銀行(AIIB)、「人類運命共同体」などをもって国際公共財を提供していると主張してきた。
ただ、中国は自由貿易や多国間主義といった国際公共財を利用して経済成長を実現し、国際的地位を向上させてきたが、利用しているだけで維持に必要な費用を負担しておらず、ただ乗りとの批判も強い。自由貿易による弊害とも言える、過剰生産による他国産業の破壊に対して何も手を打っていないし、自国の市場規模を使って先進技術の移転を迫ったり、他国に圧力をかけたりするなど、自由貿易を悪用した「自国第一」も目につく。
また、多国間主義についても、国連安保理常任理事国という特権的地位や一国一票の多国間システムを利用し、自国利益を追求する姿勢が目立つ。2018年前後から、中国は国連や国連人権理事会などで決議案を積極的に提出するなど活動を活発化させているが、その中心は「人類運命共同体」や「発展の権利」といった中国の重視する用語を決議案に入れ込み、新疆やチベットといった人権問題への批判を数で潰すことである。
習近平政権は、新興国の台頭と欧米の影響力低下という「百年に一度のチャンス」を利用し、欧米主導の国際的なルールやシステムを修正し、自らに有利な国際秩序を作り出したい。中国には、国際公共財を提供する意思はあるのだろう。だが、現在の中国には、それを提供できるだけの能力はまだ十分にはない。2022年に中国は「安全保障に関するグローバルイニシアティブ」を発表し、新興国・途上国からの支持を取り付け、これは国際公共財だと主張している。だが、ウクライナ危機やイスラエル・ハマス戦争において、中国は自国の立場を表明するだけで、解決にむけた具体的な行動を取っている訳ではない。
また、トランプ政権の対中高関税に対して、中国は自由貿易や多国間貿易体制の堅持を訴え、報復関税などの対抗措置を取っただけである。中国は、自由貿易を推進するために市場を開放することも、米国が距離を置き始めた秩序に代わって新しい通商貿易の国際枠組みを提案することもなかった。
既存秩序から離脱する米国と抵抗する中国
これに対して、戦後の国際秩序を主導してきた米国は、国際公共財を提供する能力はあるが、既存の自由貿易や多国間主義を続ける意思をなくしつつある。中国やロシアといった権威主義国家が経済を武器化して他国に脅威を与え、また、科学技術の進展により軍民両用技術が拡大したことで、経済活動にも安全保障上の考慮が必要となっている。自由貿易だけでは国益が守れず、経済安全保障の観点から制限する必要が出てきている。
そして、米国としては、中国には国際公共財を提供する意思だけでなく、能力もあると見ている。米国は、「一帯一路」や「人類運命共同体」などにより、中国が国際秩序を修正しようとしていると警戒する。また、中国による自由貿易の悪用など、既存の国際秩序へのただ乗りを許さない。
だが、中国は国内に多くの問題を抱えていて経済発展で精一杯であり、国際社会のために自国の利益を犠牲にすることも、新しい国際的なルール・枠組みを提供することもできていない。中国は自由貿易や多国間主義の下で経済発展しており、米国がこれらを不便に感じて離脱しようとすれば、中国は米国を批判し、抵抗してこれら秩序を擁護すると主張する。5月上旬の習近平国家主席によるロシア訪問の際、中露両国は国際社会の安全性や国際法の維持に関する共同声明を作成した。ロシアも、第二次世界大戦の勝者という地位を使い、戦後秩序へのただ乗りを続けている。
中国にどう向き合うか
戦後国際社会では、米国が自由貿易や多国間主義といった国際公共財の提供にコミットし、維持に必要な費用を負担してきた。国際秩序は、各国が維持すると主張すれば維持されるものではない。中国は自らが国際秩序の擁護者だというのであれば、国際秩序を使って自国の利益だけを優先したり、不利なルールを排除したりするのを止め、秩序維持のために必要な費用を負担すべきである。
例えば、中国が自由貿易の擁護を主張するのであれば、過剰生産の問題を放置せずに他国に影響を与えないように取り組み、市場規模を使った圧力をやめるなど、相応の貢献を行うべきである。また、中国はCPTPP(環太平洋パートナーシップ協定)への加盟意欲を示しているが、自由貿易の高い水準を満たす覚悟があるのであれば、政府調達へのアクセスや国有企業改革において、先に実際の行動を示せばよい。そして、中国が多国間主義を維持したいのであれば、「真の多国間主義」といった米国批判を繰り返すだけでなく、国際組織が出した不利な判決であっても受け止めて南シナ海での威圧を止め、人権問題などに関する批判に耳を傾けるなど、具体的な行動を取る必要がある。
日本は資源に乏しく、軍事大国に囲まれており、自由貿易や多国間主義、法の支配といった価値が国際社会で維持されることが国益である。これら戦後秩序を主導した米国が、不満を感じて単独主義を強めるなかで、日本としては米国の不満に可能な限りの対応をしつつ、国際社会が自由貿易や多国間主義を維持できなくなることは避けなければならない。中国が国際公共財の提供に積極的な関与をしないままに、米国が国際秩序のあり方に不満を強めて身を引けば、「キンドルバーガーの罠」に陥り国際社会は不安定化しかねない。
ナイ教授は、冒頭で紹介した論考において、トランプ政権に対して、中国の国力について誤解や判断ミスをしないように戒めた。中国が言っていることは勇ましいが、実際の行動が伴っていないところも多い。日本としては、欧州などとも連携して、米国と中国それぞれに対して、国際社会の安定と発展のために言うべきことを言っていく必要がある。
(Photo Credit: Florence Lo-Pool/Getty Images)

地経学ブリーフィング
コロナウイルス後の国際政治と世界経済の新たな潮流の兆しをいち早く見つけ、その地政学的かつ地経学的重要性を考察し、日本の国益と戦略にとっての意味合いを精査することを目指し、アジア・パシフィック・イニシアティブ(API)のシニアフェロー・研究員を中心とする執筆陣が、週次で発信するブリーフィング・ノートです(編集長:鈴木一人 地経学研究所長、東京大学公共政策大学院教授)。
おことわり:地経学ブリーフィングに記された内容や意見は、著者の個人的見解であり、公益財団法人国際文化会館及び地経学研究所(IOG)等、著者の所属する組織の公式見解を必ずしも示すものではないことをご留意ください。
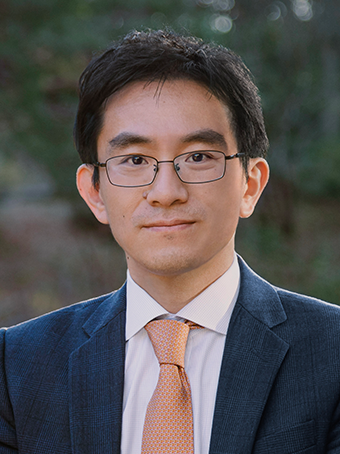
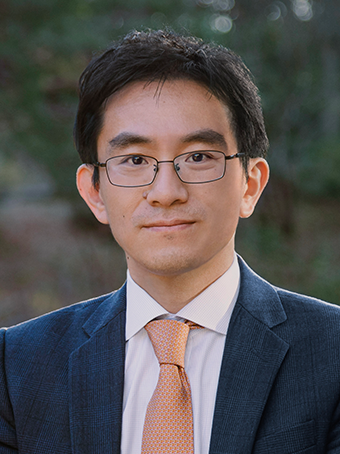
主任客員研究員
東京大学法学部卒業後、2001年4月に外務省入省。中国・南京大学及び米国・ハーバード大学(修士号取得)を経て、在中国大使館において勤務。その後、中国・モンゴル課において、4年間に10回の首脳会談、12回の外相会談などのハイレベル会談の準備に従事した他、「日中高級事務レベル海洋協議」の立上げや「日中海上捜索・救助(SAR)協定」の原則合意に関する交渉を担当・主導した。また、日米地位協定室首席事務官として、「軍属補足協定」の締結や沖縄の負担軽減政策に関する日米交渉を総括した。在外勤務では、国連代表部において、安保理改革に関する各国との調整や世界的な働きかけを担当した他、在中国大使館において、中国経済や米中経済対立に関する情報収集・分析に従事。その他、二度の人事課勤務において、組織マネージメントも経験。2022年4月に外務省を退職。
プロフィールを見る