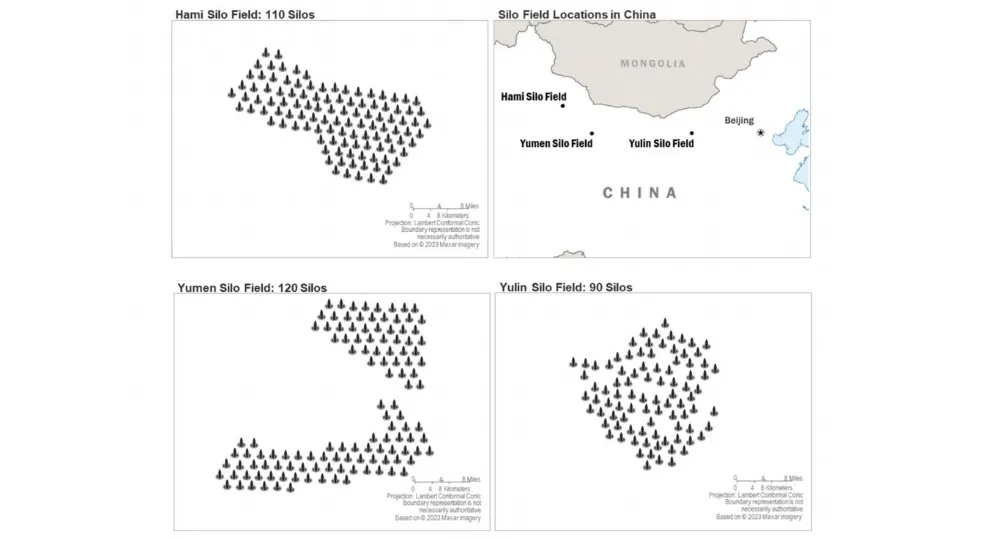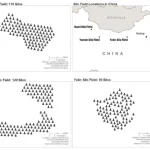イタリアのメローニ首相は分裂する米欧間の橋渡しが可能か

EUの米国との間の「相互関税」に関する最近の動向では、イタリア政府が積極的な動きを示しており、メローニ首相が米欧間の橋渡しを行うような役割を果たそうとしている。まだEUと米国との間の交渉は妥結しておらず、先行きは不透明であるがここでは米欧間の橋渡しを行おうとするメローニ首相がどのような動機において行動を取っており、どのような役割を果たしているのかを論じることにしたい。
メローニ政権誕生に至る国内政治事情
メローニ首相がはたして米欧間で橋渡しの役割を担えるかどうかという問題は、現在のイタリアの国内事情とも深く結びついている。ここで少しイタリアの政治事情についても触れることにしたい。
イタリアは選挙において比例代表制を採用しており、通常、複数政党による連立内閣が組まれることもあり、非常に不安定な政治が続いている。それゆえ、歴代政府の平均存続期間はわずか1年2か月に過ぎない。このような政治的な流動性が制度的な不安定性と結びつき、1990年代以降、イタリアでは危機が発生した際に政治的中立性を重視した「テクノクラート内閣(技術官僚内閣)」が成立することがしばしばであった。たとえば、2011年の欧州債務危機の際にはモンティ政権が、2021年のコロナ危機の際にはドラギ政権が発足し、そのようなテクノクラート内閣が危機の回避に努めることになった。
しかし、このようなテクノクラート政権は、当然ながらも、民主的正統性に大きな疑問を生じさせた。とりわけ、ポピュリズム的な性質を有するベルルスコーニ政権の後を継いだモンティ政権は、「EUの圧力で成立した」と国民世論からは受け止められたことで、とりわけ右派層の有権者の間での反EU感情の高まりを招くことになった。このような背景からも、右派からの政治批判が強まり、保守的なメローニ氏率いる「イタリアの同胞(Fratelli d’Italia)」が政権を獲得したとも言うことができる。
財政事情に関しても、イタリアはユーロ圏20か国の中で、ギリシャに次いでGDP比債務残高が2番目に高く(約135%)、EUで遵守が定められている財政規律が問われる状況にある。EUの「安定・成長協定」によって、単年度の財政赤字はGDP比3%以内に収める必要があるが、2024年は3.8%となることが予測されていたため、欧州理事会はイタリアに対して「過剰財政赤字是正手続き(Excessive Debt Procedure)」を開始した。
こうした事情からも、メローニ政権は財政支出に関しては極めて慎重な姿勢をとっており、トランプ政権が要求するようなGDP比での5.0%の防衛支出を実現できるような体力に乏しい。イタリア自らの利益という観点からも、EUと米国との間での摩擦を回避して、橋渡しの役割を担うことは重要な機会となっている。他方で、上に示したようなイタリアが抱える国内事情を考慮すれば、EUと米国の間での最適な均衡点を見出すことは簡単ではない。
それでは、メローニ氏ははたしてどのような政治家なのであろうか。次にメローニ首相個人の役割を観ていきたい。
EUにおけるイタリアの指導力の限界
政治家ジョルジャ・メローニは、EUのなかではいわゆる「新世代の欧州保守政治家」の中心的な存在としてみなされている。2017年の「イタリアの同胞党」のマニフェストでは、EUの官僚主義や、加盟国の主権が制限されることに対して、きわめて批判的な立場が明確にされていた。反移民政策も、そのような「主権主義」という主張の延長線上に位置づけられる意味では、米国におけるトランプ氏の政治的主張との共通点が大きい。
しかし政権獲得後のメローニ首相は、EUに対してそれまで予想されていたよりも穏健な姿勢を見せている。欧州委員会のフォンデアライエン委員長とも、これまで協力的な関係を築いている。他方で、深刻な財政赤字の問題を抱え、軍備拡張への慎重な姿勢などからも、イタリアはEU内での指導的立場を担うにはあまりにも課題が多い。
とはいえ、米欧関係においてメローニ首相が重要な役割を担う可能性も考えられる。というのも、EU加盟国首脳の多くがイデオロギー的に大きく立場が異なるトランプ政権との友好的な関係構築に苦悩する中で、メローニ首相はより容易に連携することが可能だ。したがって欧州委員会は、「相互関税」交渉において、メローニ氏に一定の役割を委ねたとも考えられる。フォンデアライエン委員長のそのような意向は、おそらくイタリア政府の立場を支持しているからというよりも、交渉の成果を実現することを優先するための決定とも考えられる。他方で、メローニ首相にしてみれば、米欧間の不可欠な仲介者として見られることによって、国内外での自らの存在感を強調することができる。
メローニ首相とトランプ大統領
経済的な視点から見ると、イタリアはEU加盟国の中で対米貿易黒字が2番目に大きく(390億ユーロ)、米国にとっては関税引き上げの対象となりやすい。そのように考えると、橋渡し役としてはやや不利な立場にあるといえる。
さらには、第二次トランプ政権において強調されるNATOへの防衛費支出の拡大の要求に関して、メローニ首相は2025年4月の訪米時にGDP比2%への増額を約束したが、経済財政大臣の説明によるとそれは現在の防衛費1.49%から増額するのは支出の増加の結果ではなく、あくまでも算定方法の変更に基づくものである可能性がある。このメローニ首相の訪米時に約束したトランプ大統領のイタリア訪問に関しても、まだ実現していない。あくまでもヴァンス副大統領の訪問にとどまっている。このイタリア訪問の際の記者会見で、ヴァンス副大統領はメローニ首相の橋渡し役を高く評価しながらも、具体的な交渉成果が得られたわけではなかった。
このヴァンス副大統領のイタリア訪問の際も、4月のメローニ首相の訪米の際も、必ずしもメローニ首相の指導力が評価されたわけではなく、イタリア国内の反移民的な政策や、イタリアの文化への評価が強調されるにとどまっていた。このようにメローニ首相とトランプ政権の米国との関係においては、実質的な成果は必ずしも明らかではなく、良好な首脳間の個人的な関係や、イメージのレベルにとどまったものだというべきである。同じく、メローニ首相の1月20日のトランプ大統領就任式への出席は象徴的な行為であったと言える。
個人的な交友関係という限界
確かに、実質的な政策面での成果が見られないとしても、メローニ首相とトランプ大統領の友好的な個人的関係は注目に値する。この両首脳は、新しい保守主義的なイデオロギーを掲げ、さらなる移民の反対や、国家主権の重視、規制緩和といった、数多くの領域で政治的な立場を共有する。
トランプ大統領は、首脳間の個人的な関係を重視することで知られ、表向きにはメローニ氏に対して好意的な態度を示している。しかし、かつての安倍晋三首相とトランプ大統領の関係を振り返ると、安倍首相の下で日本は東アジアにおける米国の最も重要な同盟国として、より大きなパワーを行使できる環境にあった。他方で、メローニ首相はそれと同等のパワーを持っているわけではない。関税交渉は、トランプ氏本人のそのような個人的な人間関係とは関係なく進められており、そこでメローニ首相のトランプ大統領との良好な関係がどれほど意味を持っているかは、不透明である。例えば日本や韓国などでは、そのような首脳間の個人的な関係とはあまり関係なく相互関税をめぐる対米交渉が進められている。この視点からしても、メローニ首相の橋渡し的な役割がどの程度重要な位置を占めているのか、見えにくい。
最近のオランダのハーグでのNATO首脳会議の後に、イタリアは英米関税協定と同様の水準の、基本関税10%程度の関税で合意することを提案し、ドイツのメルツ首相も「手っ取り早いディール」を求めているようであった。だが、もしもイギリスの交渉結果と同様の内容になるのであれば、イタリアの橋渡し役としての存在感は小さくなる。これらのことから見えてくるのは、米欧関係を改善していく上でのメローニ氏のトランプ大統領との友好的な人間関係には、限界があるということだ。
イタリアは、経済面や政治面において多様な制約の下にあり、EUにおいて指導的な役割を担うことは容易ではない。米国からも、EUからも、財政支出を拡大することを要請されても、それへと対応する余地は限られている。だが、現代の政治の世界では、政策の実質的な内容のみならず、リーダー間の人間関係や、シンボリックな役割もまた重要な要素であり、メローニ首相の存在はその意味で一定の効果を持つことが考えられる。
EU加盟国の中ではトランプ政権との交渉の果実を得るための橋渡し役を期待され、他方で米国の側からはトランプ大統領との良好な人間関係に基づき同じ欧州側の窓口としての役割が任されている。メローニ首相がはたしてどの程度、効果的な橋渡し役の役割を果たせるのか明らかではないが、それによって自国の世論に向けて、そのような信頼できる不可欠な指導者だというイメージをうまく創り出すことができたのは、確かであろう。
(Photo Credit: Win McNamee / Getty Images)

地経学ブリーフィング
コロナウイルス後の国際政治と世界経済の新たな潮流の兆しをいち早く見つけ、その地政学的かつ地経学的重要性を考察し、日本の国益と戦略にとっての意味合いを精査することを目指し、アジア・パシフィック・イニシアティブ(API)のシニアフェロー・研究員を中心とする執筆陣が、週次で発信するブリーフィング・ノートです(編集長:鈴木一人 地経学研究所長、東京大学公共政策大学院教授)。
おことわり:地経学ブリーフィングに記された内容や意見は、著者の個人的見解であり、公益財団法人国際文化会館及び地経学研究所(IOG)等、著者の所属する組織の公式見解を必ずしも示すものではないことをご留意ください。


リサーチ・アシスタント
2025年慶應義塾大学のメディア・政策研究科大学院卒業後、地経学研究所に入団。 2019年にロンドン・スクール・オブ・エコノミックス大学院(LSE・ロンドン大学)を卒業し、EUの防衛庁(EDA)で勤務。LSE在学中にロンドンの英国のジャパン・ソサイエティにて勤務経験あり。 専門は日欧外交関係、EU安全保障、外交と防衛政策。
プロフィールを見る