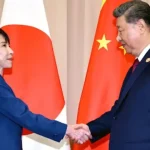同盟戦略から見たトランプ構想:NATO結束の試練

第二次トランプ政権が登場し、北大西洋条約機構(NATO)は新たな危機に直面している。ロシアの「特別軍事作戦」で始まったウクライナ戦争は、3年以上が経過しても終息の方向性はまだ見えない。こうしたロシアの動きを背景としてトランプ(Donald Trump)米大統領は、同盟国による「役割分担」への圧力を強め、「GDP比5%」というかつてない水準の国防支出を数値目標として掲げた。2025年6月、トランプ氏自ら出席したNATO首脳会合で原則合意を取り付け、世界を驚かせたことは記憶に新しい。
戦略的サプライズを求めるトランプ氏の手法は、ビジネス分野における「競争戦略」を想起させる。ベストセラーとなったリチャード・P・ルメルト著『良い戦略、悪い戦略』を例にとれば、優位にある分野で主導権を発揮し、自ら議題を設定し、ゲームチェンジャーになることが「良い戦略」とされる。こうしたトランプ流の「ディール」が再浮上したことにより、世界最大の同盟であるNATOにどう影響するであろうか。
トランプ政権第二期は、第一期よりも厳しい戦略環境に直面している。逆説的であるが、こうした競争激化によってトランプ氏の政策オプションは広がっている。2022年2月24日に始まるロシアのウクライナ侵攻によって、欧州では「抑止の失敗」が現実となった。そのため欧州諸国では同盟としての抑止と防衛の再構築が喫緊の課題となった。そうした中で登場した第二次トランプ政権は、大国間の「ディール」による紛争解決を求めつつ、地経学上の競争を再定義し続けている。
まずここでは、米国の国家安全保障戦略を検討する際に用いられている「外交・情報・軍事・経済(DIME)」という4分類を用い、NATOに関するトランプ氏の構想を分析したい。
トランプ構想の外交・情報・軍事・経済(DIME)分析
第1の「外交」分野において、第二次トランプ政権は、地域紛争はその地域で主体的に取り組むべきとの姿勢を崩さない。一見、孤立主義的とも見える動きであるが、こうした姿勢は決して新しいものではない。民主党のオバマ(Barack Obama)政権もリビア内戦については英仏主導を期待し、米国は「後方から指導する」とした。逆に、米国の戦略的利益が直接関与しない場合は、米国の役割を見直す可能性がある。第一次政権の時点で、トランプ大統領は対アフガニスタン支援を見直すためにタリバーンと秘密裏に交渉し、これが2021年8月末の外国軍全面撤退の布石となった。そして第二次トランプ政権では、ロシアとの「ディール」による和平合意を公言し、ウクライナからの要求が副次的なものであるとの印象を与えてきた。NATOのこれまでの取り組みと比較すれば、トランプ政権はパートナー国を軽視し、歴史的なしがらみもゼロベースから再検討していると言える。
第2の「情報」の分野では「戦略的コミュニケーション」が注目される。トランプ政権は「中国共産党」との表現を多用しながら、「体制上の脅威」である中国との競争がグローバルな脅威であると警鐘を鳴らす。またアフガニスタンの「陥落」とウクライナでの「抑止の失敗」は、米国の前政権の失策とも解釈できるため、トランプ政権では、これを繰り返さないための「力による平和」が打ち出される。
第3の「軍事」の分野ではウクライナ戦争で動揺した抑止の再構築が必須であるが、これは米軍の一方的な関与をもたらすとは予想できない。むしろ冷戦終結後の約30年間を通じて、在欧米軍は縮小の一途であったことを想起するべきであろう。在欧米軍が約45万人の最大規模を誇ったのは1950年代であるが、冷戦が終結する1980年代末の時点でも約30万人の規模を維持した。しかし1991年末にソ連邦が消滅し、2003年のイラク戦争後には米軍再編が進み、在欧米軍は6万人規模へと大幅に縮小された。その主たる任務は中東、中央アジア、アフリカ等への後方支援に限定され、欧州防衛の任務は忘却された。そうした構図がウクライナ危機で一変したのである。皮肉にも、2022年のロシアによるウクライナ侵攻という「抑止の失敗」は、目に見える形での米軍のプレゼンスを必須とした。そして2022年以降、約2万2千人の追加派遣を含め、米軍の駐留規模は10万人規模へと強化された。
近年の在欧米軍の動きで注目されるのは、陸軍の配置変更であろう。米陸軍第5軍団の司令部がポーランドへ設置され、冷戦後初めて欧州前線へと復帰した。陸軍部隊はロシアとの合意を踏まえて「ローテーション配備」方式を続けているが、NATOの東欧における前方展開部隊の拠点となっている点は無視できない。
DIMEの最後の「経済」の視点では、トランプ政権が「数値目標」によるゲームチェンジャーを目指している点が特徴的である。ヘグセス米国防長官はNATOを再び偉大にする出発点が国防費と語り、2025年2月の時点で同盟の優先事項を示した。それは「大西洋横断の防衛産業基盤の復活、新興技術の迅速な導入、即応態勢と殺傷能力の優先、そして真の抑止力の確立」であった。そして6月のハーグ首脳会議で「国防費GDP比5%」がNATOとしての目標として合意された。但し、その内訳を見ると国防に直結する支出は3.5%に留まり、これまでの「3%目標」との差はわずかである。残りの1.5%はサイバー防衛やインフラ整備といった項目も含んでおり、各国の長期目標としての柔軟性もある。
経済分野では欧州連合(EU)の動きも注視すべきである。2025年3月、EU初の『防衛白書』が刊行され、防空ミサイル、ドローン、サイバー戦争における能力格差を埋めることが謳われた。特筆すべきは、「最大150億ユーロ(約2.6兆円)規模の防衛融資」という予算規模である。また喫緊の課題であるウクライナ支援のために武器弾薬の供給確保を最優先とする点で、NATOと共同歩調をとるよう変化した。
同盟戦略からみたトランプ構想:インド太平洋地域への意味
それでは最後に、トランプ氏のNATO構想がインド太平洋地域の同盟戦略にどう影響するか。DIMEの枠組みを用いつつ、今後の動きを展望したい。まず外交と情報の分野でトランプ氏は、大国間の戦略的競争を最優先課題とし、そこでのディールを加速するであろう。とりわけ「体制上の脅威」である中国の動きに注目し、台湾海峡の平和と安定に向けた動きが加速化する。この文脈では地域内の同盟国の具体的な協力が重視され、グローバルな連携は後退する可能性がある。この点、米国のバイデン(Joseph Biden)前民主党政権の取り組みと好対照をなすであろう。バイデン氏は2024年7月、NATO創設75周年を記念する首脳会議をワシントンで主催し、日本、韓国、オーストラリア、ニュージーランドというインド太平洋4か国(IP-4)、およびウクライナとEUも招待した。トランプ政権下ではこうしたグローバル化は後退する可能性がある。
軍事分野では、トランプ政権によるディールが同盟戦略を揺るがす可能性がある。トランプ大統領は、第一次政権では北朝鮮に対して「すべてのオプションはテーブル上にある」と強調し、核戦争をも辞さないエスカレーション戦略を前面に押し出した。その狙いは、敵の心理に「不確実性」を生み、侵略的な行為を抑止することにある。2022年以降、ウクライナ侵攻を続けるロシアは、戦術核の使用にしばしば言及しており、第二次トランプ政権にとり欧州正面での核拡大抑止の強化は現実的な課題となっている。トランプ大統領はロシアとのディールの可能性を模索しつつ、これと同時にエスカレーション戦略も保持するであろう。そして、米国の一方的なエスカレーションは同盟国への「安心感」を低下させる危険をはらむことは忘れてはならない。
最後に経済では、トランプ大統領がNATO諸国から国防費の「GDP比5%」という原則合意を取り付けたことは、インド太平洋地域にも影響を及ぼさざるを得ない。昨年のNATOワシントン首脳会議において、日本を含むIP-4は「防衛費のGDP比2%」を目標としたが、トランプ政権下ではさらなる負担増を求められていることは避けられない。
こうしたグローバルな同盟がエスカレーションのリスクとコストをどのように管理するのか。「トランプ構想」に直面した同盟結束の試練はここにある。
(Photo Credit: NurPhoto / Getty Images)
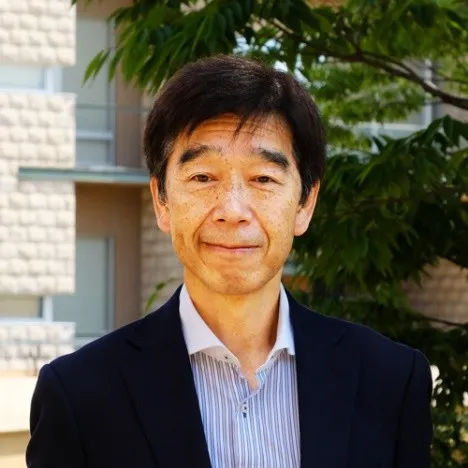
吉崎 知典
東京外国語大学大学院総合国際学研究院特任教授
東京外国語大学大学院総合国際学研究院特任教授、および、政策研究大学院大学(GRIPS)大学院政策研究科客員教授(International Security Studies担当)。専門はNATO(北大西洋条約機構)を含む同盟関係とヨーロッパ国際政治。慶應義塾大学法学部政治学科、同大学修士課程修了後、現在の防衛省防衛研究所に入所。その後、理論研究部長、政策シミュレーション特別研究官、研究幹事を歴任し、2023年4月に東京外国語大学に着任。大学の新企画であるJV-Campus講座でPeace and Conflict in the Indo-Pacificおよび Re-designing Japan’s Future VisionのWeb配信を担当。ロンドン大学キングズ校(KCL)と米ハドソン研究所の客員研究員も務めた。近著としてThe Impacts of the Russo-Ukrainian War(共著、2025年、Springer)、『自衛隊最高幹部が明かす国防の地政学』(共著、2025年、PHP研究所)がある。

地経学ブリーフィング
コロナウイルス後の国際政治と世界経済の新たな潮流の兆しをいち早く見つけ、その地政学的かつ地経学的重要性を考察し、日本の国益と戦略にとっての意味合いを精査することを目指し、アジア・パシフィック・イニシアティブ(API)のシニアフェロー・研究員を中心とする執筆陣が、週次で発信するブリーフィング・ノートです(編集長:鈴木一人 地経学研究所長、東京大学公共政策大学院教授)。
おことわり:地経学ブリーフィングに記された内容や意見は、著者の個人的見解であり、公益財団法人国際文化会館及び地経学研究所(IOG)等、著者の所属する組織の公式見解を必ずしも示すものではないことをご留意ください。