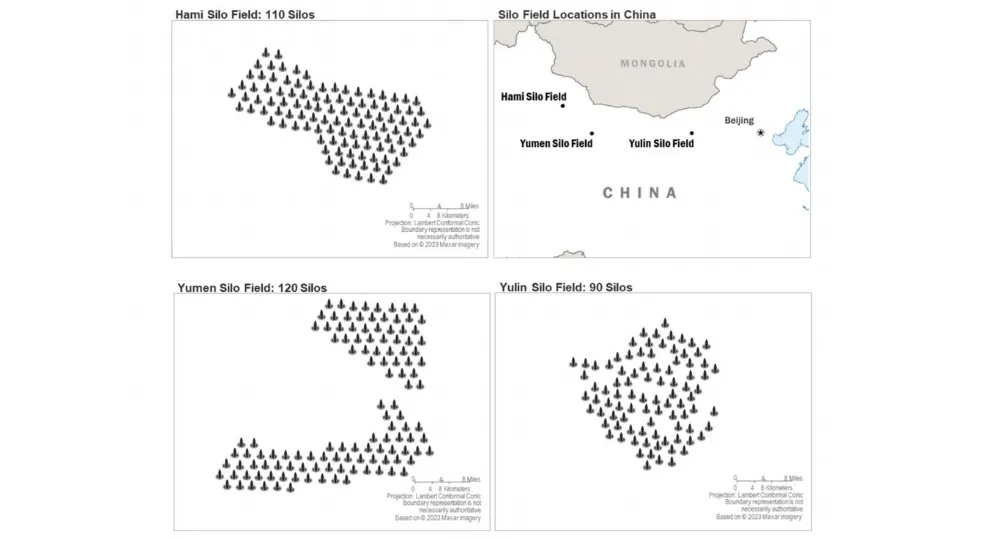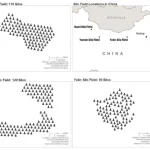韓国の政権交代と米韓同盟の「現代化」をどう見るか

第二次トランプ政権の発足以来、韓国国内では今後の米韓同盟に関する議論が活発化している。昨年12月3日に起きた…(以下、本文に続きます)
米韓同盟の今後をめぐる発言と憶測
第二次トランプ政権の発足以来、韓国国内では今後の米韓同盟に関する議論が活発化している。昨年12月3日に起きた「非常戒厳」によって、尹錫悦(ユン・ソンニョル)前大統領の弾劾、大統領選挙、新政権発足に至る一連の韓国内政の混乱に多少の落ち着きが見え始めた一方で、米韓両国の間で首脳会談が開催されない状況が依然として続いている。この間、米国側による在韓米軍(USFK)に関する従来にはない踏み込んだ発言の数々が、韓国側で様々な憶測を呼ぶ状況を招いている。トランプ政権はインド太平洋地域の米軍戦力を対中抑止のために再配置することを公言しているが、在韓米軍には実際に兵力削減だけではなく、どのような影響が及ぶことが考えられるだろうか。
本年3月に米国防総省内と議会の一部に配布された「暫定国防戦略指針(Interim National Defense Strategic Guidance)」の中で「中国による台湾の軍事統一は他のいかなる脅威よりも優先的に備えるべき唯一の差し迫った脅威」と認定したとされる。4月には米軍のケイン(Jonh Daniel Caine)統合参謀本部議長は日本と韓国内の米軍駐屯現況を評価して国防長官と大統領に勧告することを明らかにした。そして、5月に米紙ウォールストリート・ジャーナル(WSJ)は複数の米国防当局者の発言を引用して、トランプ政権は在韓米軍から約4,500名の兵士を撤退させ、グアムなどに再配置されると報じた。同月にはブランソン(Xavier T. Brunson)在韓米軍司令官は「韓国は日本と中国の間に浮かぶ島、または固定された航空母艦」、「在韓米軍は北朝鮮を撃退することだけに焦点を合わせない。我々はより大きなインド太平洋戦略の小さな部分として域内作戦にも焦点を合わせている」と発言して、韓国に部隊が駐留することの意義を強調しつつも、在韓米軍の戦力が半島以外にも展開する「戦略的柔軟性」の必要性についても言及した。
韓国保守勢力が懸念するシナリオ
こうした従来にはなかった米国側の一連の発言に加え、先月発足した革新系の李在明(イ・ジェミョン)政権が目指す戦時作戦統制権の返還(OPCON Transfer)に強い警戒感を示しているのが韓国の保守勢力である。歴史を振り返ると、1994年に平時における韓国軍の作戦統制権が返還された。戦時における作戦統制権返還は2006年に米側と合意した盧武鉉(ノ・ムヒョン)政権以来、2012年とされていた返還時期が李明博(イ・ミョンバク)政権によって延長され、朴槿恵(パク・クネ)政権は「韓国軍が米韓連合軍を指揮する能力を持った際に返還される」とする条件を設定した。文在寅(ムン・ジェイン)政権は米韓首脳が「条件に基づく戦時作戦統制権の転換が『早期』に行われるよう協力する」との合意を引き出して、韓国軍の能力評価を開始したものの時間的な制約により完了できなかった。尹錫悦政権は返還のための能力評価よりも、韓国軍に必要とされる能力を持つことを優先させた。
李在明大統領は選挙公約で「戦時作戦統制権の返還」を掲げた。トランプ政権によるインド太平洋地域の戦力再配置の動きに加えて、現在行われている関税交渉において、安保議題も含むパッケージ・ディールにより、在韓米軍を縮小したい米国側と独自の指揮権確保に拘る韓国側の利害が一致して返還が早期に実現してしまうことを保守勢力は懸念する。仮に返還が実現すると、在韓米軍の弱体化に相対して在日米軍(USFJ)の強化をもたらし、在韓米軍からの主要部隊撤退にとどまらず、在日米軍司令官が4つ星の将軍に昇格して、在韓米軍司令官が3つ星将軍に降格することで、北東アジア地域の米軍兵力が韓国から日本などに移転し、朝鮮半島における軍事バランスに変化が生じることを最も恐れている。
また、最近米国側から韓国側に提起されたとされる米韓同盟の再定義、すなわち対中牽制も見据えた「同盟の現代化」が今後どう具体化するかが焦点である。李在明大統領自身は大統領選で台湾問題への関与をしないことを明言してきた一方で、米国は自国のインド太平洋戦略において米韓同盟を太平洋地域に拡大適用させ韓国の関与を求めている。
在韓米軍の現状と今後の展開
現時点での在韓米軍の兵力は、2008年4月に当時の李明博・ブッシュ(George W. Bush)両大統領が首脳会談で合意した約28,500名で維持されている。その内約20,000名の兵力を有する陸軍は主力部隊であるストライカー旅団戦闘団(SBCT: Stryker Brigade Combat Team)が米本土から9ヶ月の間隔でローテーション配備される体制になっている。同旅団は4,400名の兵力で構成されており、前述のWSJ報道が示した約4,500名が同部隊のことを指すと推測された所以である。以前は戦車部隊が主力であった機甲旅団戦闘団(ABCT:Armored Brigade Combat Team)が2022年のローテーションからSBCTに置き換わり、その際、エイブラムス戦車(Abrams tank)やブラッドレー戦闘車(Bradley Fighting Vehicle)といった装備は、有事に備えた陸軍事前備蓄(APS:Army Prepositioned Stock)として在韓米軍基地に保管されている。
かつては重装備の在韓米陸軍部隊が北との軍事境界線付近に展開・駐留することで、有事における主力部隊を担うのと同時に、「トリップワイヤー」と呼ばれる米韓同盟が持つ抑止力の根源となっていた。つまり、北の軍事攻撃に対して米国が自動的に巻き込まれることが北に対して軍事行動を思いとどまらせる効果があったのである。
しかしながら、2000年代に入って以降、世界的な米軍再編の波が韓国に及ぶと、2004年に当時の盧武鉉政権下において、ソウル南方の平澤市に在韓米陸軍部隊を集約する巨大基地の建設が決定した。「キャンプ・ハンフリーズ(Camp Humphreys)」と名付けられた米陸軍海外駐屯基地の中で最大規模の基地に大部分の兵力が集約された一方で、韓国軍の火力不足を補うという名目で、多連装ロケットシステム(MLRS)などを有する第210野戦砲兵旅団は前線近くの東豆川(ドンドゥチョン)市に残っている。また、世界でも類を見ない米韓連合師団がソウル北方の議政府(ウィジョンブ)市にあるキャンプ・レッドクラウド(Camp Red Cloud)に所在している。これら2つの米軍部隊が前線地域に駐留することでトリップワイヤーの仕組みを残し、韓国側の「見捨てられる懸念」を払拭する役割を果たしてきた。
在韓米空軍は韓国中部の烏山(オサン)基地と南部の群山(クンサン)基地にF-16戦闘機部隊が配備されている。このほかに烏山にはU-2高高度偵察機に加え、A-10対地攻撃機が海外では唯一配備されている。A-10は本年1月から段階的に退役することが発表されていて、在韓米空軍のF-16が代替戦力となって烏山に集約され、群山には対中牽制の役割も含めてF-35Aが新たに配備されるとの報道もある。これ以外の撤退可能性が予測されているアセットは陸軍のアパッチ(AH-64 Apache)部隊である。米韓の間では長年に渡って同部隊の訓練場確保に関して摩擦が絶えなかった中、ヘグセス(Pete Hegseth)国防長官が主導する陸軍改革の一環で戦闘ヘリが削減される可能性が高く撤退が予測されている。もっとも、代わりに最新のドローンなど無人・省人化兵器が充当されるようであれば、兵力削減ではあっても戦力削減にはならないことに留意が必要である。
トランプ政権の韓国に対する揺さぶりをどう見るべきか
WSJが報じた在韓米軍兵力がグアムなどに再配置されるという報道内容は米当局によって即座に否定されたが、米国による韓国に対する揺さぶりとも受け取れる動きは第一次トランプ政権にも見られた現象だ。当時、駐留米軍の費用負担をめぐって米韓両国政府が交渉していた際、米軍はローテーションで米本土から韓国へ向けて大移動するエイブラムス戦車の動きをメディアに詳細に公開してみせた。
最近では在韓米軍のパトリオット(Patriot)部隊の一部が、米軍によるイランの核関連施設に対する空爆後、同国からの報復攻撃に備えるため中東・カタールにある米軍基地に派遣された。実際に同基地に対してイランによる弾道ミサイル等の攻撃が行われた際は、ケイン統合参謀本部議長が、在韓米軍から派遣された部隊がどのように現地で活躍したかを詳細に説明する場面があった。今後も米国は、パトリオットのように韓国軍が保有する戦力、あるいはそれに類する戦力が韓国から撤退することをちらつかせる可能性がある。
我が国では最近の米韓同盟の動きに関して、トランプ政権が要求する国防費増額と在韓米軍の兵力削減に注目が集まりがちである。今後の注目点は実際に「在韓米軍の兵力が増減するのかどうか」、「どのように再配置されるのか」にとどまらず、たとえ部隊の再配置で常設兵力が削減されたとしても、平時における陸海空・海兵隊に加え、サイバー・宇宙・特殊戦にわたる多様な領域を対象とした米韓両軍による共同訓練および共同演習の規模と種類、そして頻度がどう変化するかについても的確に把握する必要がある。さらに、米韓同盟の現代化が日米同盟にどのような影響をもたらすのか、詳細な分析と備えが必要となるだろう。
(Photo Credit: SOPA Images / Getty Images)

伊藤 弘太郎
キヤノングローバル戦略研究所 主任研究員
2001年中央大学総合政策学部卒業、2004年同大学大学院総合政策研究科博士前期課程修了、2017年同大学大学院法学研究科博士後期課程単位取得満期退学。2022年同大学大学院より博士(政治学)取得。衆議院議員事務所、公益財団法人日本国際交流センター等での勤務を経て、2015年1月より内閣官房国家安全保障局にて、参事官補佐として韓国を中心とする東アジア地域の政策実務に携わった後、2017年7月より現職。法政大学人間環境学部特任准教授、立命館大学共通教育推進機構客員准教授も務める。著書に『韓国の国防政策 「強軍化」を支える防衛産業と国防外交 』(単著、勁草書房、2023年)、『ドローンが変える戦争』(共編著、勁草書房、2024年)などがある。

地経学ブリーフィング
コロナウイルス後の国際政治と世界経済の新たな潮流の兆しをいち早く見つけ、その地政学的かつ地経学的重要性を考察し、日本の国益と戦略にとっての意味合いを精査することを目指し、アジア・パシフィック・イニシアティブ(API)のシニアフェロー・研究員を中心とする執筆陣が、週次で発信するブリーフィング・ノートです(編集長:鈴木一人 地経学研究所長、東京大学公共政策大学院教授)。
おことわり:地経学ブリーフィングに記された内容や意見は、著者の個人的見解であり、公益財団法人国際文化会館及び地経学研究所(IOG)等、著者の所属する組織の公式見解を必ずしも示すものではないことをご留意ください。