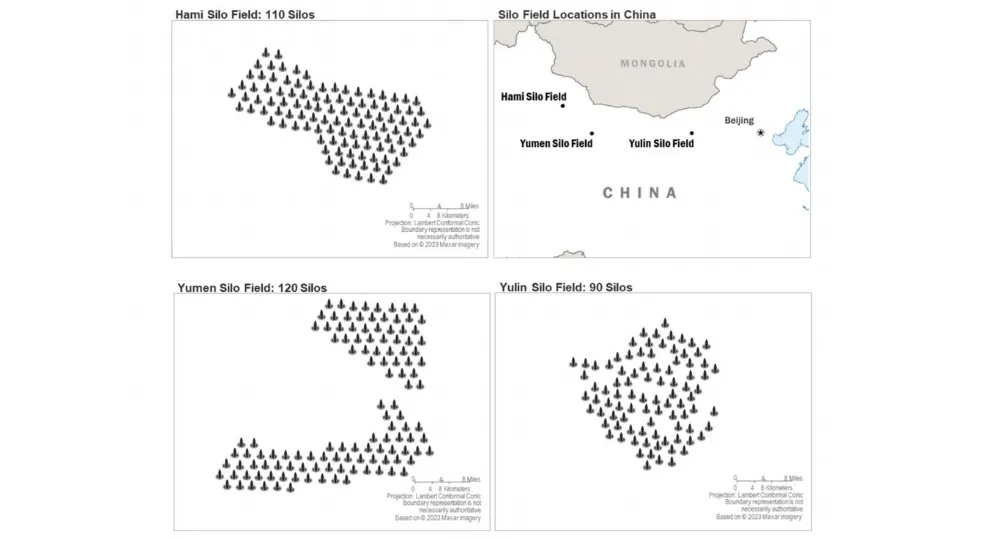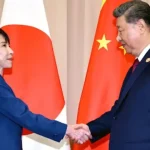日米防衛分担をめぐるゼロサム的発想を超えて

一方、欧州や韓国とは対照的に、凪の状態なのが在日米軍である。ピート・ヘグセス米国防長官が発出した「暫定国家防衛戦略指針」(概要が公開)では、同指針が対応すべき優先順位として、米本土防衛、対中抑止、そして同盟国等により大きな役割を果たさせることが順に列挙された。この点、第二の優先順位である対中抑止の中核となるのは在日米軍であり、これを縮小するのはいわば語義矛盾と言える。
しかし、だからと言って懸念要素がないわけではない。米国は自らの対中抑止力を強化するとともに、上記の第三の優先順位に従い、日本のより大きな貢献も求めている。これら二つの力学は、互いにどのように作用するのだろうか。そして日本はどう対応すべきか。
「凪」の在日米軍
ヘグセス国防長官は2025年5月、トランプ政権における新たな国家防衛戦略(NDS)の策定を指示し、その後、国防省内で新たな戦略の検討が進められた。米軍の前方展開兵力の見直しも、NDSの策定と密接に関係しながら検討されている。
その中で、徐々に見直しの傾向が見えてきた。国防省は2026年度国防予算要求を公表したが、前年度から1,000億ドル以上の増額を見込む中で、海軍(海兵隊含む)と空軍(宇宙軍含む)の予算の伸びが圧倒的なものとなっている。中でも、核戦力や爆撃機、戦闘機、水上艦、潜水艦、ミサイルなどの大型装備の開発取得が目に付く。一方、陸軍予算は大きく伸びず、ドローンやミサイルなど装備の近代化は重視されているものの、4月の長官指示では、陸上車両や攻撃ヘリ等のレガシー装備の縮小や各司令部の統合・合理化が求められていた。これらを踏まえると、トランプ政権は、インド太平洋における対中抑止を念頭に、陸上戦力を合理化する一方、海空戦力やミサイル・ドローンを増強する方向性を目指していることが分かる。もちろん、これに加えて米本土防衛に万全を期すため、核戦力やミサイル防衛を強化し、戦略抑止力を高めることも求めている。
この方向性を前方展開態勢に当てはめると、欧州や韓国に駐留する陸軍を縮小する方向性とは整合性が高い。一方、在日米軍において陸軍は少数派で、海空軍と海兵隊が中心の兵力となっている。このため、米軍の戦力増強や戦力構成の見直しが在日米軍の規模に与える影響は大きいとは言えず、少なくとも兵力縮小の方向に動く可能性はない。むしろ、2006年及び2012年の日米外務・防衛担当閣僚会合「2+2」で合意した在沖縄海兵隊要員約9,000人のグアム移転に対し、エリック・スミス海兵隊総司令官は、対中抑止力・対処力の低下を懸念する発言を行っており、駐留規模は微増に動くかもしれない。
現状維持の慣性
一方、海空軍と海兵隊を中心とする在日米軍は、有事にはインド太平洋司令官又はその委任を受けた指揮官が直接指揮をとり、朝鮮半島や台湾有事で活動することが想定されているため、日本所在部隊のみが自己完結的に作戦を行う構造にはなっていない。場合によってはハワイ、グアムや米本土から派出される増援部隊や自衛隊と共に、柔軟に部隊編制を組み替えて運用することが適しているとも言える。
このようなことから、在日米軍の指揮系統はハワイに直接連なる形で維持され、長らく日本所在軍種間で統合されてこなかったが、バイデン前政権下で在日米軍司令官を部分的に統合司令官化する方向性が決まった。そしてトランプ政権もこの方針を継承している。
この決定は、在日米軍の即応性向上と日本との連携強化を念頭に置いたものだが、インド太平洋軍は基本的に海軍とこれを支援する海兵隊が主体の兵力であり、日本に余計な中間結節を作り出すことをハワイの司令部はあまり歓迎していないように思える。このため、こうした海軍・海兵隊の立場とトランプ政権による主要司令部・高位司令官合理化方針が奇妙な一致を見た結果、指揮系統の改編は小規模なものにとどまる可能性が高い。在日米軍の兵力態勢には、各軍種の思惑もあり、現状を維持する強い慣性が働いている。その慣性は同盟関係の安定にとって好ましい側面もある。
対中抑止強化と負担分担要求を両立させる無理
このため、今後の日米間の主要な論点は、在日米軍の兵力態勢見直しというよりは、いかに日本に負担分担を求めるかという点に集中することが予想される。しかしこの議論は以下の理由から必ずしも容易には進まないだろう。
第一に、自ら対中抑止態勢強化のため戦力増強を目指しているにもかかわらず、日本にその負担分担を「要求」するのは交渉の手法として無理がある。すなわち、現在の米国における国防戦略上の優先順位ではない欧州や韓国に対しては、駐留兵力縮小・撤退をカードとして防衛努力強化を求めることが効果的だが、駐留兵力を撤退させる気のない日本に対してその戦術はあまり意味がない。もっとも、台湾有事ではなく日本有事における防衛コミットメントの有無をちらつかせて日本に「見捨てられ」の恐怖を抱かせる方法もないわけではないが、これが説得力を持つためには「対中抑止」の看板を取り下げる必要があるだろう。しかし今のところ米国においてその予定はない。暫定国家防衛戦略指針は、以下のように述べる。「同盟国に他の脅威への対処を主導するよう求めつつ、米本土防衛強化とインド太平洋における中国の侵略抑止のため直ちに行動する」。中国抑止のための米軍の軍事行動には作戦基盤が必要であり、それを効果的に提供できるのは日本のみである。本土からの爆撃機やミサイルだけで台湾有事は阻止できない。
第二に、米国がこだわる台湾有事において、米国自らが軍事介入の方針を明確化していない以上、負担分担協議の発射台が定まらない。米軍介入を前提としたとしても、それが海空からの台湾防衛支援にとどまるのか、地上部隊まで派遣するのか、あるいは核使用まで見込むのかによって、想定すべき作戦の形態は異なる。同盟国が果たす役割も当然変わる。
もちろん、日米間で共同作戦を踏まえた公にならない協議を行うことは可能だし、中国の軍事力増強ペースを踏まえれば、両国がより多くの防衛資源を持つべきことは明らかである。しかし、それはゼロサムの「ディール」で進む話合いではなく、あるべきトータルの戦力像を共有しながら、それを達成するため少しでも多くの資源を持ち寄るという「ポジティブ・サム」の発想が不可欠である。対中抑止という同盟諸国側にとっての「ポジティブ・サム」の目標を、負担分担という「ゼロサム」の協議によって達成しようというミスマッチに、米政権はなぜ気付かないのだろうか。その結果、防衛支出の数値目標的な要求が独り歩きし、結果として幅広い説得力を欠いてしまっている。
「ポジティブ・サム」の協力に向けて
だからと言って、日本が何もしなくてよいわけではない。言うまでもなく日本は中国、北朝鮮、ロシアという軍事的脅威に囲まれた最前線に位置しており、米国からの要求の有無にかかわらず防衛努力を自ら加速しなければならない。
他方、今日の戦争が消耗戦によって特徴付けられる中でも、日本にとって防衛に使える資源は青天井ではない。国民負担の更なる増加を伴う防衛費増額は、社会保障費の自然増と厳しいトレードオフの関係にある。また予算が増えても人が増えなければ戦力の量的拡大はできないが、少子化や募集環境の悪化、防衛産業における人手不足はこれに構造的制約を課している。その対処には、国民的支持と強い政治決断が必要となる。
問題は、エルブリッジ・コルビー(米国防次官)流のゼロサム交渉は、そのような国民的支持にとって必ずしも説得的な助けにならないという点である。また日米防衛当局が負担分担協議にエネルギーを費消してしまえば、戦力増強や共同作戦の在り方に割くべき建設的な議論の時間が奪われてしまう。日米の戦略目標は本来一致しているはずだ。そうであれば、その目標達成には「ポジティブ・サム」の発想が不可欠である。
その発想転換には、危機対処のシナリオ共有が助けとなる。かかるシナリオ共有により日米の運用構想を明確化する中で、特に、中国による事態生起時の既成事実化を防ぐため、日本が初動対処においてより大きな役割を見込む必要がある。そしてそれに基づき、海空戦力、ミサイル、ドローン、それらを支える情報収集(ISR)の増強など、戦略三文書で置き去りにされた自衛隊の兵力構成見直しを推進しなければならない。
日米「2+2」の延期も報道されたが、日本にとって必要なのはリスク回避ではなく、提案を積極的に行う姿勢である。2015年以降改訂されていない日米防衛協力のための指針(ガイドライン)見直しを日本から提起することも一案だ。安全保障環境が激変する中、日米間における役割分担の方向性を示した同文書は更新が必要となっているからだ。特に、台湾情勢を含むインド太平洋における脅威への対処を念頭に置きつつ、日米間の役割をより相互補完性の強いものに見直していく必要がある。そして日米両政府は、この見直しと在日米軍の指揮統制見直しを、一体的に検討し両者を整合させることが必要だ。両国は、政治的機運に頼ったパッチワーク的な対応からそろそろ脱却すべきだろう。
(Photo Credit: Chip Somodevilla / Getty Images )

地経学ブリーフィング
コロナウイルス後の国際政治と世界経済の新たな潮流の兆しをいち早く見つけ、その地政学的かつ地経学的重要性を考察し、日本の国益と戦略にとっての意味合いを精査することを目指し、アジア・パシフィック・イニシアティブ(API)のシニアフェロー・研究員を中心とする執筆陣が、週次で発信するブリーフィング・ノートです(編集長:鈴木一人 地経学研究所長、東京大学公共政策大学院教授)。
おことわり:地経学ブリーフィングに記された内容や意見は、著者の個人的見解であり、公益財団法人国際文化会館及び地経学研究所(IOG)等、著者の所属する組織の公式見解を必ずしも示すものではないことをご留意ください。


主任研究員
防衛省で16年間勤務し、2022年9月から現職。2014年から2016年まで外務省国際法局国際法課課長補佐、2016年から2019年まで防衛装備庁装備政策課戦略・制度班長、2019年から2021年まで整備計画局防衛計画課業務計画第1班長をそれぞれ務める。2021年から2022年まで防衛政策局調査課戦略情報分析室先任部員として、国際軍事情勢分析を統括。 2007年東京大学教養学部卒、2012年米国コロンビア大学国際関係公共政策大学院(SIPA)修士課程修了。
プロフィールを見る