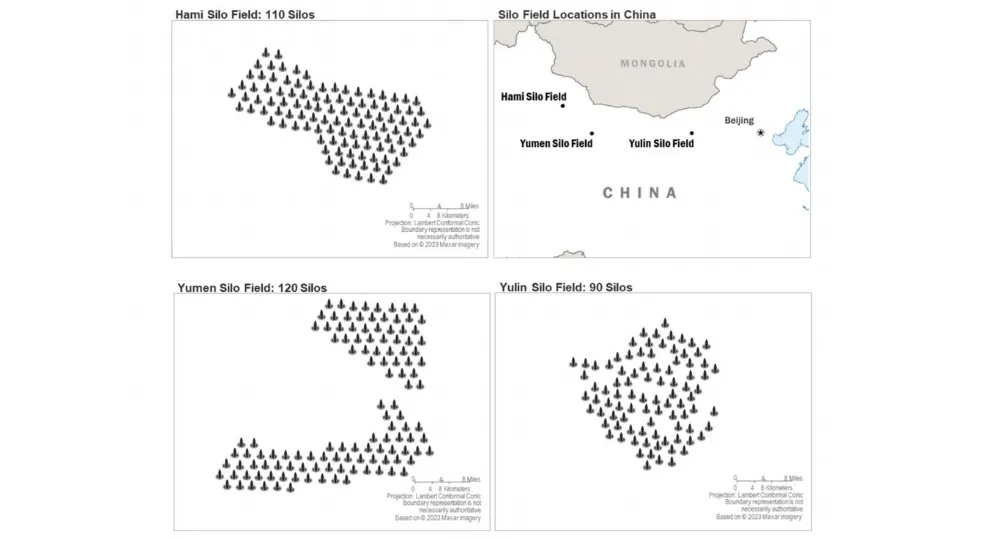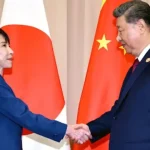オーストラリアへの新型FFM移転 ③防衛装備移転政策へのインプリケーション

では、この成功体験から何を学び、どのように次の案件へとつなげるべきか。移転事例が増えるにつれて、何に注意を払わなければならないのか。初の大型装備移転が決まった今こそ、次の装備移転に向けた教訓を抽出するための検証が求められている。本稿では、移転先のニーズを考慮せずに戦略関係を強調した売り込みは政治的リスクを招く恐れがあること、また、運用者である自衛隊の積極的な関与と官民連携が有効であることを確認する。さらに、移転案件の増加を見据え、長期的に機能するビジネスモデルや雛形となるような枠組みの整備が求められるという点を指摘する。
戦略関係重視の長所と短所
日本政府は、オーストラリアへの新型FFM売り込みにあたり、日豪戦略関係の深化を最重視する方針を当初から取っていた。2024年6月の国家安全保障会議(局長級会合)では、「対中国を念頭に置いた戦略的意義がある」との判断が示され、オーストラリア国防省への新型FFMの前型であるもがみ型護衛艦の技術情報開示が決定された。さらに同年11月末の国家安全保障会議では、相互運用性の向上や、インド太平洋地域における艦艇建造・維持整備基盤の強化に資するとして、政府一丸となって移転を推進する方針が正式に確認された。こうした姿勢はオーストラリアの戦略コミュニティにも好意的に受け止められ、同国の多くの論考で、日本との戦略関係が新型FFM導入の主要理由として言及された。
対称的に、韓国の売り込みは戦略関係よりも企業利益を前面に出したと受け止められ、反発を招いた。韓国案のテグ級を設計・建造するハンファ社は、フリゲートの売り込みと並行して、オーストラリア国内建造を担うオースタル社の買収を試みた。しかし、オーストラリア国防省の反発があったため上手くはいかず、延期するに至った。その背景には、国防省がオーストラリア国内に防衛プライム企業を持たない現状を懸念し、オースタル社を「戦略造船パートナー」として育成する意図を持っていたからだとみられる。
もっとも、戦略関係への過度な依存と期待は諸刃の剣となり得る。「①日本の勝因」で論じたように、新型FFM選定の決定的要因は、納期を守れる見通しとオーストラリア海軍の運用構想との適合性であり、戦略関係そのものが直接の決め手ではなかった。仮に新型FFMが要求性能を満たさなかった場合、戦略関係を前面に押し出していた日本側は、2016年のそうりゅう型潜水艦移転失敗に続き、再び移転に失敗したことへの強い失望を抱く可能性が高かった。その場合、二国間関係は停滞に向かい、日豪防衛協力全般にも深刻な影響が及び得る。実際、潜水艦移転の失敗後には、日豪防衛相会談は長らく成果を上げられず、防衛装備・技術協力も長期的な停滞期に入った前例がある。
装備移転においては、戦略関係に胡坐をかかず、相手国のニーズを精確に把握することが不可欠である。先方のニーズに対し最適ではない装備品を提案する場合には、過大な期待を抱かずに交渉を進めるべきである。特に日本の国産装備品は戦後長らく日本独自の背景に適合する自衛隊の要求性能のみに基づいて開発されてきており、いわゆるガラパゴス化していることが多いとされるため、海外の運用構想に必ずしもマッチしないものも多々あるということを改めて認識するべきである。
積極的な売り込みと緊密な官民連携
新型FFMの売り込みにおいて特筆すべきは、日本政府の極めて積極的な姿勢と、緊密な官民連携である。防衛省・自衛隊は積極的な売り込みを展開し、とりわけ海上自衛隊の熱意は際立っていた。2024年8月末に実施された初の海軍種レベルの日豪戦略対話では、平田利幸海幕防衛部長がオーストラリア海軍能力開発部長ステファン・ヒューズ少将と、部隊運用、技術・装備、ロジスティックスなど多岐にわたる分野で意見交換を行った。さらに、その2日後には自衛艦隊司令部が同少将を招き、もがみ型の多様な任務対応能力や、省人化・無人化・ステルス化の取組を説明し、海上自衛隊の装備品や運用構想への理解促進を図った。また、海上自衛隊は、オーストラリア国防省の選定プロセスが始まって以降、もがみ型護衛艦を少なくとも2度オーストラリアに寄港させている。
こうした積極姿勢は、防衛省・自衛隊全体としての前向きな方針に加え、担当者個人の熱意にも支えられていた。防衛装備庁のある担当者は、「装備移転は戦であり、攻めの姿勢が重要だ」と語っていた。
官民連携の面では、防衛省が「ワンチーム」を掲げ、関係省庁と企業による官民合同推進委員会を設置し、移転に伴うさまざまな課題を調整したとされる。三菱重工も2025年2月にキャンベラにオフィスを開設し、選定直前には泉澤清次会長がオーストラリアを訪れ、アルバニージ政権の閣僚らに直接働きかけるなど防衛装備庁と連携していた。装備移転にはさまざまなアクターが関与するが、最終的に設計・建造し、運用を支える企業は不可欠な存在である。彼らの前向きな姿勢がオーストラリア側に伝わったことは、選定された重要な要素であったいえるだろう。
大型防衛装備品の移転は日本にとって初の試みであったため、当初オーストラリア側には、日本の経験不足から納期遅延が生じるのではないかとの懸念があった。しかし、日本政府が企業への全面的なバックアップ姿勢を明確に示したことで、この懸念は徐々に和らいだ。特に、吉田圭秀統合幕僚長がオーストラリア公共放送ABCのインタビューで「オーストラリアが新型FFMを選定すれば、海上自衛隊の配備計画を延期してでもオーストラリア向けを優先する」と明言したことは、オーストラリアの戦略コミュニティ内で繰り返し引用され、日本側の官民連携の力強さを裏付ける言説として受け止められた。結果として、日本は移転事業においてオーストラリア国防省と海軍から高い信頼を獲得したと考えられる。
更なる海外需要を見越して
装備移転の流れは、今後さらに加速する可能性が高い。新造の護衛艦であれば、インドネシアが引き続きもがみ型を検討していると報じられている。また、オーストラリア海軍が新型FFMを選定した以上、同海軍との相互運用性を重視するニュージーランド海軍が同型採用に傾く可能性もある。実際、クリストファー・ラクソン首相は2024年6月、横須賀基地でもがみ型を視察しており、その関心度の高さがうかがえる。他装備に目を向ければ、日本の装備移転に信頼を得たオーストラリア国防軍が、自衛隊が運用または計画中の衛星コンステレーションへの協力や、目標観測弾、地対艦・地対空ミサイルなどの導入を検討する展開も考えられる。では、今後海外需要が増えた際に、防衛省と防衛産業はどう対応すべきか。
第一に、海外需要への供給については、国内生産よりも現地生産を促進するべきである。日本の防衛産業は、自衛隊との間で比較的頻繁に意見交換や認識を共有することが可能であるため、ある程度需要を予測できるが、海外の顧客の場合、そういった場が非常に限られており、突発的な需要が発生しがちである。小規模の需要であれば日本国内で対応することも可能である。実際、オーストラリア海軍向け新型FFMのうち日本国内で建造される3隻については、大規模な追加設備投資を必要としていない。しかし、海外からまとまった需要が発生した際、人手不足にあえぎ、需要の予測不可能性から設備投資に総じて消極的な日本の防衛産業にとって、必ずしも迅速に対応できるわけではない。そのため、海外需要への対応は国内生産よりも移転先のパートナー企業へのライセンス供与を軸とするビジネスモデルを本格的に採用するべきであろう。
現地生産は、日本の防衛が抱える構造的な脆弱性の緩和にも資する。対中抑止の要となる海上自衛隊の艦艇の多くは、中国本土に地理的に近い西日本や九州の造船所で建造されており、有事には打撃されるリスクが高い。現地生産であれば、移転先が日本に代わって装備品や部品を製造・供給することが可能となり、継戦能力の強化にもつながる。こうした意味でも現地生産方式は有望である。
もっとも、ライセンスビジネスには技術情報漏洩といったリスクが伴うため、情報セキュリティや第三国移転に関する取り決めなど、制度的な対応を予め整備しておくことが不可欠である。オーストラリアは比較的低リスクと評価されたが、他国については国別事情に応じた慎重な検討が求められる。
第二に、装備移転にあたっては、案件ごとにアドホックに枠組みを構築するのではなく、標準化された「雛形」を整備すべきである。現状、日本の装備移転は案件ごとに官民連携などの形態が若干異なっている。たとえば、フィリピンへの警戒監視レーダー移転とオーストラリアへの新型FFM移転では、官給品の取り扱いが異なっている。官給品とは、防衛企業が防衛省に納入する護衛艦の主機やレーダー等であり、防衛省は一度これらを製造する企業から個別に直接調達したうえで、システム統合を担うプライム企業に支給し、組み込ませる仕組みである。大型・複雑な装備品ほど官給品の点数は増える傾向にあり、官給品が増えれば増えるほど、特に海外移転の場合は調整コストが増大する。フィリピン案件では問題が顕在化しなかったが、もがみ型護衛艦に官給品が多数存在することを踏まえれば、新型FFM移転では調整が複雑化する恐れがある。このように、案件ごとに官民連携の在り方や移転方法が異なる状況は、現時点では大きな問題となっていないかもしれないが、今後、移転事例が増えれば、そのたびに関係企業や移転先政府の負担が増えることになり、装備移転の動きを抑制してしまう可能性がある。調整コストの低減には、装備移転全体のプロセスを統一化する必要がある。官給品の扱いに加え、アフターサービス、教育・訓練、シミュレーション、情報管理、技術供与などの付随要素も含めた包括的な標準化が求められる。その際、価格競争力低下の懸念はあるものの、米国が装備輸出に活用する対外有償軍事援助(FMS)のような枠組みは、有力な参考事例となるだろう。
おわりに
オーストラリアへの新型FFM移転の成功体験からどういった教訓を学ぶかによって、今後の装備品移転の成否が左右される。したがって、その内容を注意深く検証し、今後の案件に反映していくことが不可欠だ。日本が装備移転事業で実績を積み重ねれば、さらなる引き合いが増え、複数案件を並行して進める局面が確実に増えるだろう。しかし、現行の防衛産業基盤や制度面では、人員不足やアドホックな運用形態が足かせとなり、海外需要に安定的に対応できるかは心もとない。こうした状況を踏まえ、本件で得られた知見を活かし、成功した取組の継続に加えて、新たなビジネスモデルの採用と標準化された装備移転のあり方を早急に整備すべきである。
(Photo Credit: 縄手英樹/アフロ )


研究員
慶應義塾大学法学部政治学科卒業、同法学研究科政治学専攻修士課程修了。2023年4月より博士課程。専門は、米豪同盟、防衛・安全保障政策、防衛産業政策。アジア・パシフィック・イニシアティブ(API)でのインターン(日米軍人ステーツマンフォーラム(MSF))を経て現職。
プロフィールを見る