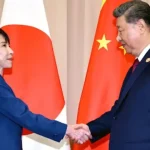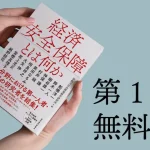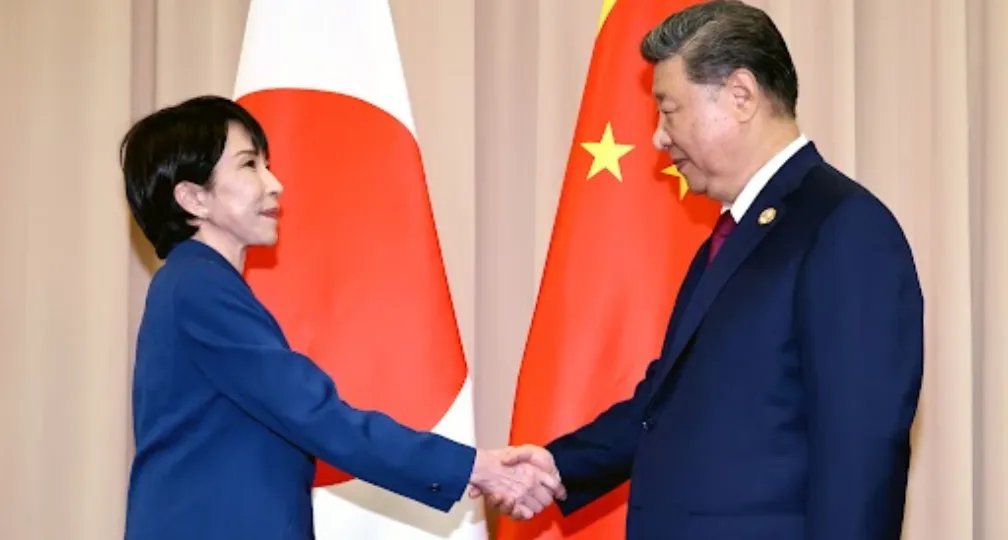トランプ関税とEU:ブリュッセル効果の限界と「市場の不可欠性」獲得への道

トランプ大統領は米国の貿易赤字を相殺することを意図する相互関税を、EUを含む世界各国に課した。2025年8月21日に署名された欧米合意は、先に発表された日米合意と様々な共通点があり、当初30%とされた関税率は相互関税15%、自動車や半導体、医薬品なども15%とされた。日本は政府系金融機関が最大5,500億ドル規模の出資・融資・融資保証を米国に提供することで合意したのに対し、EUは天然ガスや石油、AI半導体や防衛装備など年間2,500億ドル相当、3年間で総額7,500億ドル相当を米国から輸入し、6,000億ドル相当の民間投資を米国で追加実施する。
「通商パワー」EUの源泉、市場の大きさとブリュッセル効果
1990年代に入って冷戦が終結し、EU域内では貿易障壁が低減され、安定と繁栄が訪れたとの楽観が広がった。1993年に欧州共同体(EC)を改めEUとなり、市場の統合が加速し、統一通貨ユーロの発行(2002年)へ向かった。2003年に中・東欧諸国が加盟してEUの市場規模が拡大し、市場の不可欠性が高まった。2003年にEUのGDPは世界の19%を占め 、2023年も16%(加盟27か国)を維持している 。
加盟国を増やし、市場を大きくしたEUは、新規加盟国にこれまでの共通政策、EU法を全て受け入れさせ、民主主義、人権尊重や法の支配など、価値を共有することも求める。価値や規範はEU市場の大きさと表裏一体となり、市場の不可欠性をテコとして、EUのグローバルな影響力行使に使われる。こうした影響力行使のあり方は、EUの首都にちなみ、ブリュッセル効果と呼ばれる。
命名者であるアニュ・ブラッドフォード氏は、ブリュッセル効果を5要素で説明する。①EUの単一市場の大きさと豊かな消費者、これらの富の合計値、②EUの規制執行力、③EUによる規制する意思の存在、規制効果の持続性、規制内容の正統性、④製品の生産地ではなく消費地にEU規制が適用されるため、規制の適用範囲が広く、遵守される蓋然性が高いこと、そして、⑤企業による自主的適応を生むことである。EUは市場の大きさに基づいて域外国に対して影響力を行使する「通商パワー」となっている。
経済相互依存が進み、ルール・ベースの国際秩序が維持される環境では、こうしたブリュッセル効果が発揮されることをEUは期待できた。だがこれに重大な疑義を突き付けるゲームチェンジャーとして登場した第二次トランプ政権は、EUが獲得した「市場の不可欠性」に対して深刻な影響を及ぼしている。米中が経済相互依存を武器化する情勢において、「通商パワー」であるEUはどのように対米交渉に臨んだのか。
不可欠性を梃子にEUの自律性の弱さを突く第二次トランプ政権
2025年1月から始まったトランプ政権は、通商パワーであるEUに対する破壊的な交渉方針を選択し、バイデン政権まで続いた米欧間の信頼関係に断絶を生んだ。米国は関税を通商以外のアジェンダに対する梃子に使い、欧州委員会に完全な交渉権限がない安全保障問題をセットで交渉し、EU加盟国間で交渉立場がまとまらない弱さを前面に引き出した。このような交渉態度に対してEUは脆弱であり、トランプ大統領の提案に合意する他なくなった。
EUの「戦略的自律性」を損なう深刻な対米依存が二つある。安全保障と、エネルギーだ。トランプは当初、ウクライナを支援し続けてきた民主党バイデン政権を徹底的に批判し、ロシアが実効占領するウクライナの領土をロシアに割譲する和平案を繰り返し提案した。NATO(北大西洋条約機構)の同盟国に対する裏切りのような、こうした米国による前例のない提案を受け、NATOとEU双方に加盟する加盟国は、国防予算の大幅増を急ぐと同時に、米国から自立して欧州を守る将来に備えなければならなくなった。結果として、欧州諸国はこれまで米国の支出によってウクライナに供給してきた兵器を、(EUではなく)加盟国の予算によって米国から買い、ウクライナに供給することとなった。特に依存が深刻な装備品は、ウクライナに供与されたHIMARS(ハイマース)を含めロケット砲システム(86%が米製)、榴弾砲弾薬(同82%)、パトリオットを含め長距離対空射撃システム(同70%)である。欧州諸国の安全保障は、集団的自衛権を規定するNATOに頼っており、安全保障アクターになりきれていないEUには、対米交渉を取り仕切った欧州委員会に充分な交渉権限もレバレッジも用意できなかった。
エネルギーに関しては、EU域内の需要の58%を域外から輸入している 。2022年、ロシアのウクライナ侵攻を受け、ロシアへのエネルギー依存を無くすためリパワーEU(REpowerEU)政策が打ち出され、天然ガスの対ロ依存をカタールと米国からの供給に置き換えた。EUは世界第二位の消費国・地域であり、輸入率90%のうち44%(2022年)は米国から輸入された 。ウクライナ侵攻によってエネルギーの対ロ依存を減らしたものの、これが対米依存を生んだことは、米EU交渉にとって皮肉であった。EUは米国に対し、エネルギー調達において不可欠性を与えてしまい、これが米欧交渉で米側のレバレッジとなった。EUのこうした「戦略的自律性」の欠如は、交渉におけるEUの弱点になり、関税率を言われるままに呑む原因の一つになった。
クラウドサービスをはじめとするビジネスに不可欠な技術においてもEUは対米依存である。依存率はフランスが66%、ドイツ58%、イタリア69%、最高はアイルランドの93%であり、代替が効かない「モノの不可欠性」を米国に与えている。逆に米国もEUに依存しており、3,100品目においてEUへの輸入依存がある。
EU加盟国それぞれの国益と、欧州委員会が持つカードの「不行使」
EUが域内市場の大きさを活かした「市場の不可欠性」を充分に発揮できなかった背景は、二つある。一つ目は、EUの交渉権限と意思決定過程の問題だ。欧州委員会が域外通商交渉の排他的権限を持つが、相手国と達した合意を履行するためには、EU理事会(閣僚理事会:全加盟国の代表が参加する意思決定機関)および欧州議会の承認が必要である。8月21日に合意された米欧枠組み合意の施行に向け、二つの規制案(COM(2025)471およびCOM(2025)472)が、EU理事会(担当大臣が参加する意思決定機関)および欧州議会での審議に付されているが、EU理事会では27加盟国がそれぞれの国益をかけて交渉するため、難航が予想される。
米EU交渉に臨むにあたり、米国による経済的威圧に対抗するための反威圧措置(ACI)を発動することが検討されたが、その決定に必要な加盟国の過半数の賛成票すら集められなかった。EU加盟国は、①輸出における対米依存度が低く、発動に賛成するフランスの他、②NATOにおける米国の関与を重視する国、③米市場への輸出依存が高いドイツやイタリアの慎重姿勢という、三つ巴の構図になった。政治学者ジョージ・ツェべリス氏によれば、特定多数決で意思決定できる場合でも、拒否権を行使する加盟国が多い場合、意思決定過程の安定が損なわれ、コンセンサスを得ることが難しくなる。
もう一つは、欧州委員会をはじめEU諸機関が持つ政策オプションの制約である。欧州委員会にはそもそも、6,000億ドル相当の対米民間投資を決定する権限がない。欧州委員会の支出項目には、贈与(grant)と融資(loan)があるが、EU全体の投資政策の方向性を決定する権限を持つに過ぎない。欧州委員会と連携して域外支援を行う欧州投資銀行(EIB)には「グローバル・ゲートウェイ」という支援プロジェクトがあるが、途上国支援が中心である上に、米国が提示した金額よりも一桁少ない融資が主体だ。
EUは「地経学パワー」となるのか?
ここまで見てきたように、市場の大きさだけで「市場の不可欠性」が自動的に発揮されるわけではなく、EUには域内の意思決定上の構造問題、加盟国同士の死活的な国益をめぐる対立、米国との関係において米国に不可欠性を握られている経済構造など、足かせと課題が多かったのである。脆弱性を抱えた「戦略的自律」と「モノの不可欠性」に拠って立ち、政治的なアクターが多く「船頭多くて船、山を登る」EUは、トランプ政権が示した交渉内容に対して強い姿勢で反論できず、ACIや報復関税など「切れるカード」も切れなかった。EUは今後、どのような地経学アクターになるのか。
元イタリア首相であり欧州中央銀行総裁でもあったマリオ・ドラギ氏は2024年9月、『ドラギ・レポート』を発表し、EUが競争力を強化するための提案を列挙した。競争力、脱炭素、国際貿易、エネルギー価格、行政の効率化、防衛産業など幅広く問題を指摘し、ドラギ氏はEUの改革を提唱する。だがそれは域外国に握られた「モノの不可欠性」について善処する一覧表であり、欧州委員会の権限の限界、加盟国間の意思決定の迅速化など、EUの「市場の不可欠性」を充分に発揮するための「厄介な」改革を避けた議論である。第二次トランプ政権との交渉で、まさに突かれた点だ。これらに取り組まない限り、「地経学パワー」としてのEUの戦略的自律の達成も、不可欠性の獲得も、絵に描いた餅に終わろう。
(Photo Source: Andrew Harnik / Getty Images)

地経学ブリーフィング
コロナウイルス後の国際政治と世界経済の新たな潮流の兆しをいち早く見つけ、その地政学的かつ地経学的重要性を考察し、日本の国益と戦略にとっての意味合いを精査することを目指し、アジア・パシフィック・イニシアティブ(API)のシニアフェロー・研究員を中心とする執筆陣が、週次で発信するブリーフィング・ノートです(編集長:鈴木一人 地経学研究所長、東京大学公共政策大学院教授)。
おことわり:地経学ブリーフィングに記された内容や意見は、著者の個人的見解であり、公益財団法人国際文化会館及び地経学研究所(IOG)等、著者の所属する組織の公式見解を必ずしも示すものではないことをご留意ください。



主任研究員
慶應義塾大学大学院法学研究科修士、European University Institute歴史文明学博士。新潟県立大学国際地域学部および大学院国際地域学研究科准教授、モナシュ大学訪問研究員、LSE訪問研究員、外務省経済局経済連携課、日本経済団体連合会21世紀政策研究所欧州研究会研究委員を経て、2021年に合同会社未来モビリT研究を設立。現在、東京大学先端科学技術研究センター牧原研究室客員上級研究員、フェリス女学院大学非常勤講師。2021年12月にAPI客員研究員兼CPTPPプロジェクト・スタッフディレクター就任。 【兼職】 合同会社未来モビリT研究 代表
プロフィールを見る
リサーチ・アシスタント
2025年慶應義塾大学のメディア・政策研究科大学院卒業後、地経学研究所に入団。 2019年にロンドン・スクール・オブ・エコノミックス大学院(LSE・ロンドン大学)を卒業し、EUの防衛庁(EDA)で勤務。LSE在学中にロンドンの英国のジャパン・ソサイエティにて勤務経験あり。 専門は日欧外交関係、EU安全保障、外交と防衛政策。
プロフィールを見る