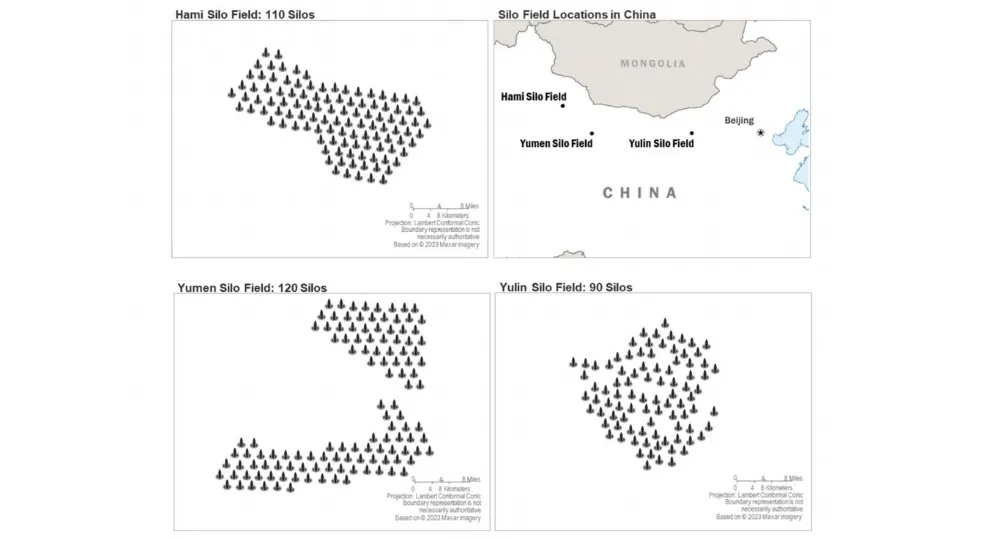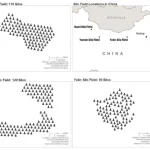衰退から拡大へ:「需要超過」時代の防衛産業

全文PDFはこちらからダウンロードいただけます。
要約は下記よりご覧いただけます。
要約
2000年代以降、日本の防衛産業は低成長を続けてきた。小泉純一郎内閣以降、民主党政権に至るまで、財政緊縮の波は内政分野にとどまらず、防衛分野にも及んだ。この10年連続で漸減し続けた防衛費を再拡大させたのが、第二次安倍晋三内閣以降の自公連立政権であった。しかし、2013年以降防衛費が増え続ける中でも、米国からの高性能の輸入装備品の割合が増し、国内産業は必ずしもその予算増から大きく裨益しなかった。その状況を一変させたのが、2022年の戦略三文書(「国家安全保障戦略」、「国家防衛戦略」及び「防衛力整備計画」)である。引き続き輸入額は大きく伸びているが、装備品調達に充てられる全体の予算の増加に伴い、国内企業との契約額も相応に増えた。長年の産業界からの要望に対応した防衛調達契約における利益率の改善や、2023年に成立した防衛生産基盤強化法によるサプライチェーン強化のための財政支援も、防衛企業に対する社内外からの期待を高めている。
しかし、防衛費の伸びにより国内防衛需要が高まるに従い、これまで見られなかった新たな課題が浮き彫りとなり、深刻化してきている。それが余剰生産能力(キャパシティ)の不足である。過去20年間にわたり低成長を続けたために、需要の急増に対応した生産拡大の準備ができていない。これに加えて、ウクライナ戦争の長期化や米中競争の激化により、国際的な防衛需要も、同時に高まりを見せている。その結果、米国を始めとする日本の同盟国・友好国が、日本の防衛生産力に期待を寄せるようになってきた。
こうした「需要超過」の時代において、日本の防衛産業はどのように対応し、また今後どのように対応すべきなのか。政府はその生産能力の拡大を促すため何ができるのか。
これらの問題意識に基づき、本報告書は、日本の安全保障研究において見過ごされがちな余剰生産能力の問題に焦点を当てる。特に、本報告書は、日本の防衛産業を構成する主要企業等への匿名インタビューとその分析を通じ、防衛企業が抱える課題を浮き彫りにする。加えて、類似の課題を抱える欧米の防衛産業における状況と、それに応じた各国政府の取組を調査する。その上で、それらの課題に対処するため直ちに着手できる具体的な政策提言を行うことを目的としている。
本報告書の中核的な発見と主張は、過去20年間にわたる衰退基調に順応した防衛企業の経営慣行が、国際安全保障環境の悪化を受けた「防衛需要超過」の時代に適合し切れておらず、今後の日本の防衛力強化にとって主要なボトルネックとなる可能性が高いとの危機感である。特に、需要の急速な拡大を受けた人材不足と生産設備の不足は明らかであり、将来の需要に迅速かつ円滑に対応するための先行投資を躊躇している企業が依然として多い。また、欧米の防衛企業が力を入れる、政府との契約を獲得していない段階での先行的な社内研究にも積極的になれない企業もある。これらの従前の事業慣行は、日本の戦略文化の一部を形成していると評することができ、結果として防衛産業の供給力とそれを取り巻く安全保障環境の変化との間にギャップを拡大させてしまっている。この強力な慣性を打破するためには、政府は今後の防衛需要の中期的な見通しを示すとともに、防衛企業の先行投資を促すインセンティブを提供する必要がある。また、企業における社内独自研究を促し、先端技術を活用した防衛イノベーションにつなげていくことも欠かせない。
このような課題を踏まえ、本報告書は、以下のとおり10の政策提言を行った。これらはいずれも課題との関連性と、政策ツールとしての具体性が高いものだと考えている。このため筆者としては、政府及び防衛産業における速やかな検討着手を期待するものである。
1. 政府は、防衛企業における将来事業の予測可能性を高め、中期的投資計画を促進するため、2028年度以降の防衛力整備計画の見直しに早期に着手すべきである。
2. 防衛省は、企業の先行投資判断を促し、その生産基盤を拡充するため、以下のとおり防衛生産基盤強化法を改正すべきである。
(1)生産基盤拡充のための防衛企業に対する財政支援を規定するとともに、当該拡充に要する資金調達を支援するため、市場調達より有利な融資や株式会社産業革新投資機構などによる出資を可能とする規定を盛り込む。また、外国等による買収を防ぐための政府等による防衛企業の「黄金株」保有制度についても、諸外国の例を参照しながら、そのメリット・デメリットを踏まえつつ検討すべきである。
(2)防衛企業の海外展開を促進するため、防衛装備移転円滑化支援基金による支援を得られる対象を拡大し、移転のために必要な生産設備等の費用の一部を負担できるようにする。また、採算性の強い事業への支援は、国際協力銀行の活用などにより、市場での資金調達より有利な政策金融(低利長期融資・政府保証)で対応する。
3. 防衛省は、企業における余剰生産能力強化を促すため、防衛調達契約における利益率算定の基礎となる企業評価の対象に、設備投資や人材確保に係る取組を加え、利益率向上を通じた金銭的インセンティブを付与すべきである。
4. 防衛省は、企業における先行的な社内研究を促すため、①防衛調達契約における価格算定の見積りに、当該契約履行を間接的に可能とした社内研究に要する費用の一部を計上することを認める、②難易度の高い研究開発に係る契約の利益率を、現行の上限10%を超えて設定する、といった契約制度の見直しを検討すべきである。
5. 内閣府、文部科学省、経済産業省及び防衛省は、先端的なデュアル・ユース技術の研究開発への資金提供プログラムと、本格的な装備品の研究開発事業の中間に位置付けられる事業を予算措置により増やしていくべきである。
6. 防衛省は、経済産業省やJOGMECと連携しつつ、サプライチェーン上のリスク低減のため、自ら装備品製造に不可欠な特定の材料や部品の備蓄を行うべきである。また、世界的に需要が集中する材料が組み込まれた部品についても、経済安全保障上の取組に防衛企業のニーズが十分反映されるよう、防衛省と経済産業省等との間で緊密に連携すべきである。
7. 防衛企業は、社内民生部門からの人材・設備の融通や、自動車産業など他業種との対話を通じ、他分野・他業種において余剰となった生産基盤や人材を防衛産業に転用することを検討すべきである。その際、防衛省は、閉鎖される他業種の工場施設を取得し、政府保有・企業委託施設(GOCO)として防衛企業に委託するなど、企業の取組を側面から支援すべきである。また、防衛企業は、製造における省人化のため、防衛生産基盤強化法による製造工程効率化の財政支援を活用しつつ、製造における自動化・ロボティクス技術の導入を進めるべきである。設計・開発において、量産段階での自動化を念頭に設計・開発の発想も欠かせない。
8. 防衛企業は、それでもなお残る人材不足に対応するため、技術を有する人材を中心として、外国人の活用を検討すべきである。その際、防衛省を始めとする関係省庁は、情報保全体制の強化のための助言等を通じ、企業の取組を支援・促進すべきである。
9. 防衛省及び防衛企業は、平時における防衛事業の持続可能性の確保と有事における余剰生産能力の確保のため、自衛隊が使う装備品の海外との共同生産や海外における現地生産を積極的に進めるべきである。その際、現地生産に必要な技術移転を円滑化するため、防衛省は、当該技術に含まれる防衛省保有の知的財産や防衛省が指定した秘密情報の共有に係る判断を行うための手順を明確化して、企業に周知すべきである。さらに、防衛省は、実効的な情報保全のため、事業の特性に応じた技術・情報管理の在り方についての企業に対する助言機能を強化すべきである。
10. 外務省は、友好国への安全保障援助の有効性を向上させるため、OSAの事業規模拡大に取り組むとともに、防衛企業が行う商業的な海外輸出に付随する部品供給や維持整備に要する費用を充当することを含め、防衛装備品輸出との相乗効果もあるOSAを実施すべきである。
国際安全保障環境は、2022年に政府が戦略三文書を策定して以降も予断を許さない状況で推移している。防衛生産は、企業の取組を伴う以上、その基盤拡充に一定の時間を要する。しかし、国際安全保障環境の変化はその準備を待ってはくれない。だからこそ、政府や企業は必要な行動に直ちに着手しなければならない。そしてそこでまず求められるのは、防衛生産に対する意識や文化を変えることである。それは、衰退や現状維持を前提とした政策や事業慣行から、有事に備えた生産拡大に適合したマインドセットへの転換である。そのような戦略文化の転換が、日本の防衛産業政策には求められる。
(Photo Credit: 東阪航空サービス/アフロ)
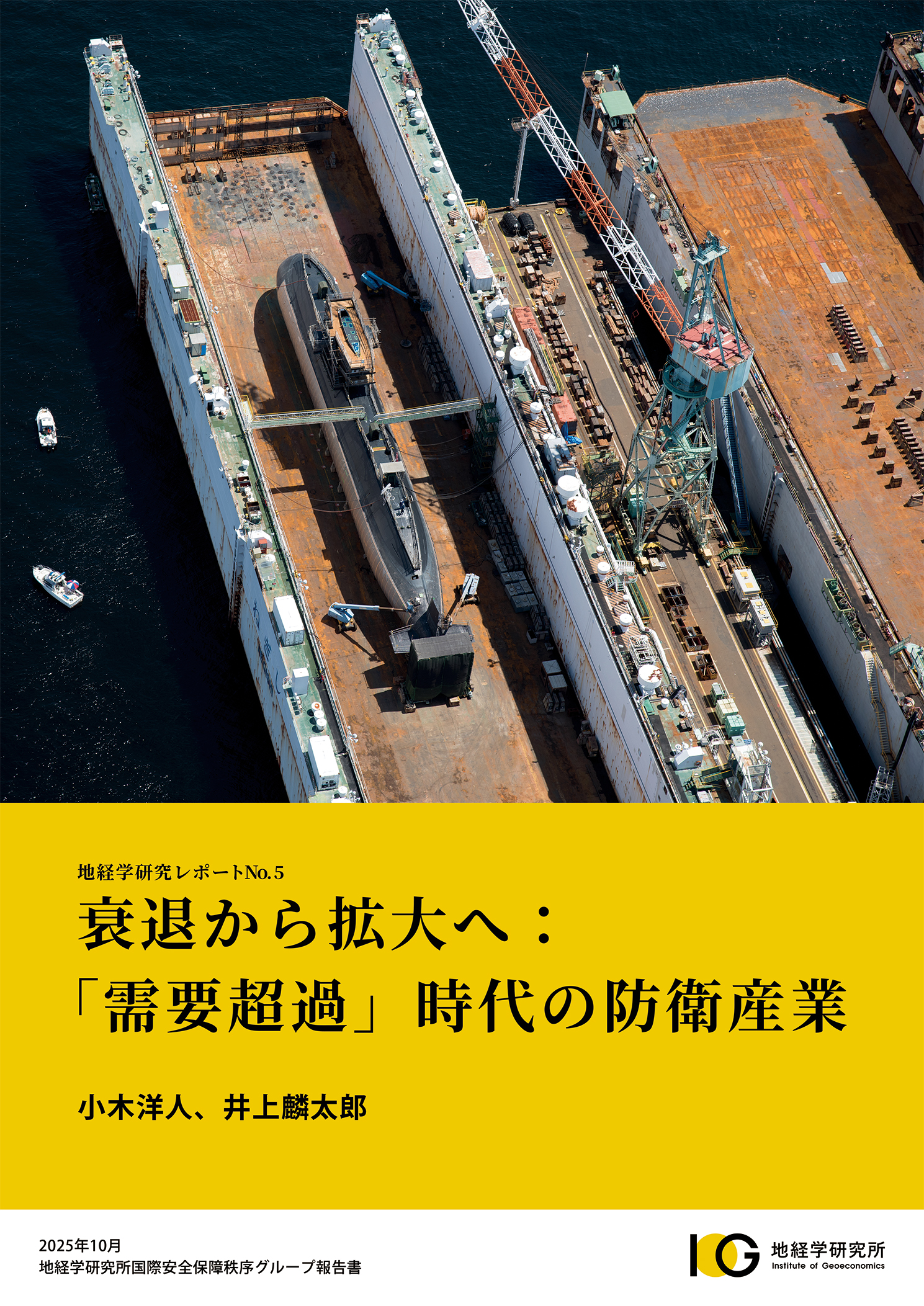
おことわり:報告書に記された内容や意見は、著者の個人的見解であり、公益財団法人国際文化会館及び地経学研究所(IOG)等、著者の所属する組織の公式見解を必ずしも示すものではないことを御留意ください。記事の無断転載・複製はお断りいたします。
執筆者(肩書は執筆当時)



主任研究員
防衛省で16年間勤務し、2022年9月から現職。2014年から2016年まで外務省国際法局国際法課課長補佐、2016年から2019年まで防衛装備庁装備政策課戦略・制度班長、2019年から2021年まで整備計画局防衛計画課業務計画第1班長をそれぞれ務める。2021年から2022年まで防衛政策局調査課戦略情報分析室先任部員として、国際軍事情勢分析を統括。 2007年東京大学教養学部卒、2012年米国コロンビア大学国際関係公共政策大学院(SIPA)修士課程修了。
プロフィールを見る
研究員
慶應義塾大学法学部政治学科卒業、同法学研究科政治学専攻修士課程修了。2023年4月より博士課程。専門は、米豪同盟、防衛・安全保障政策、防衛産業政策。アジア・パシフィック・イニシアティブ(API)でのインターン(日米軍人ステーツマンフォーラム(MSF))を経て現職。
プロフィールを見る