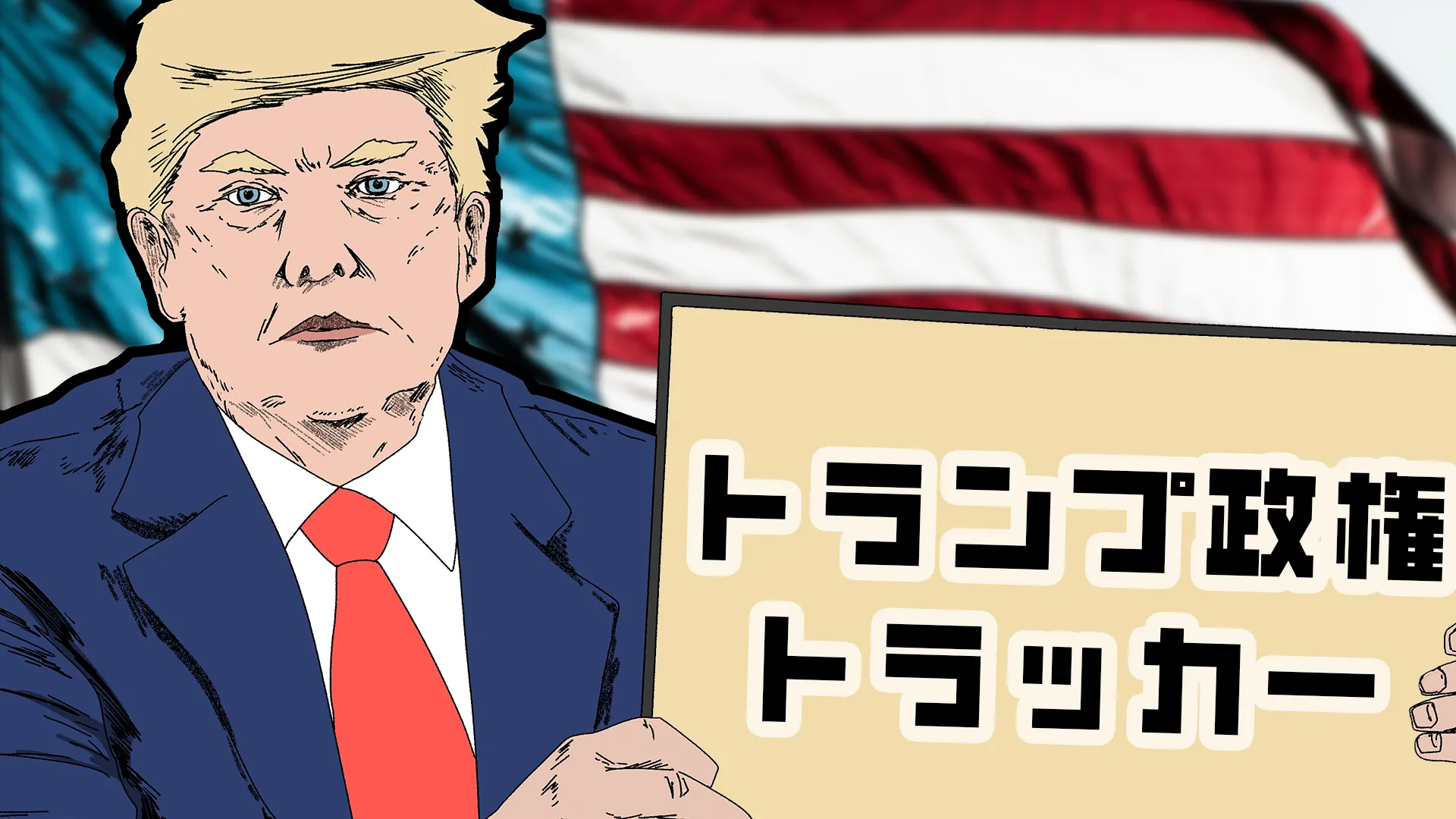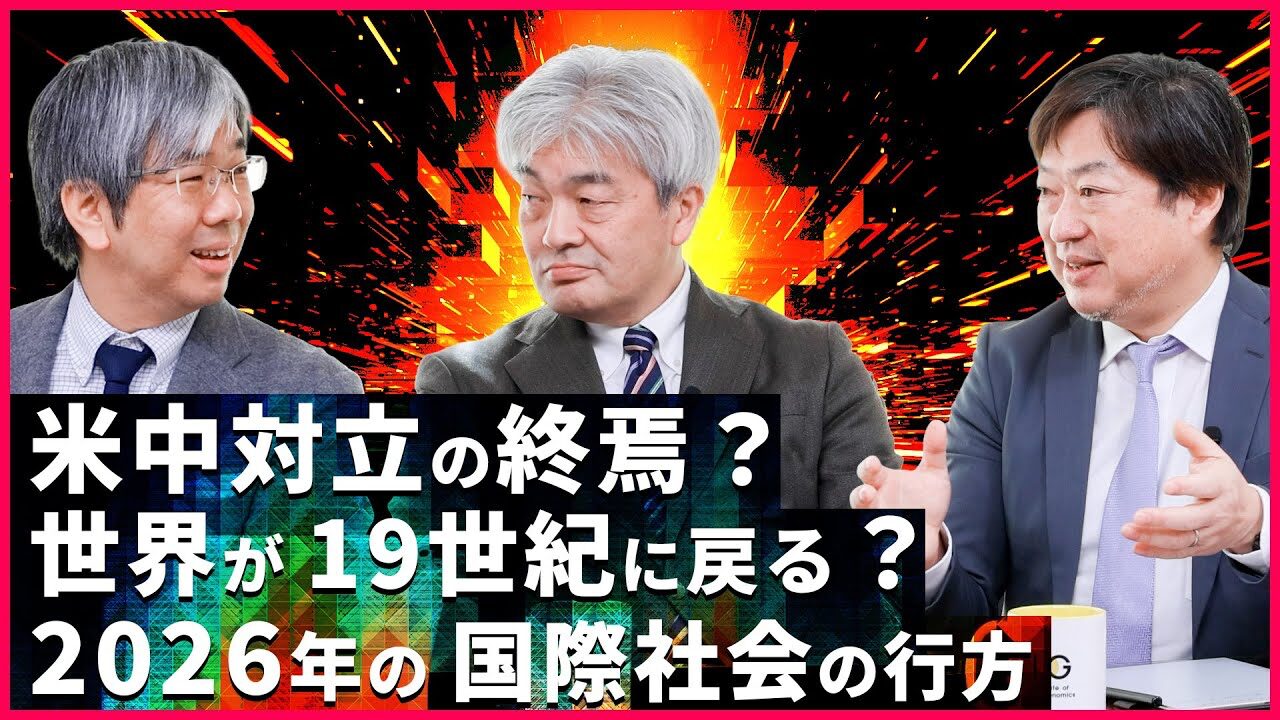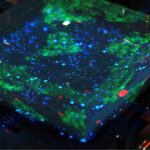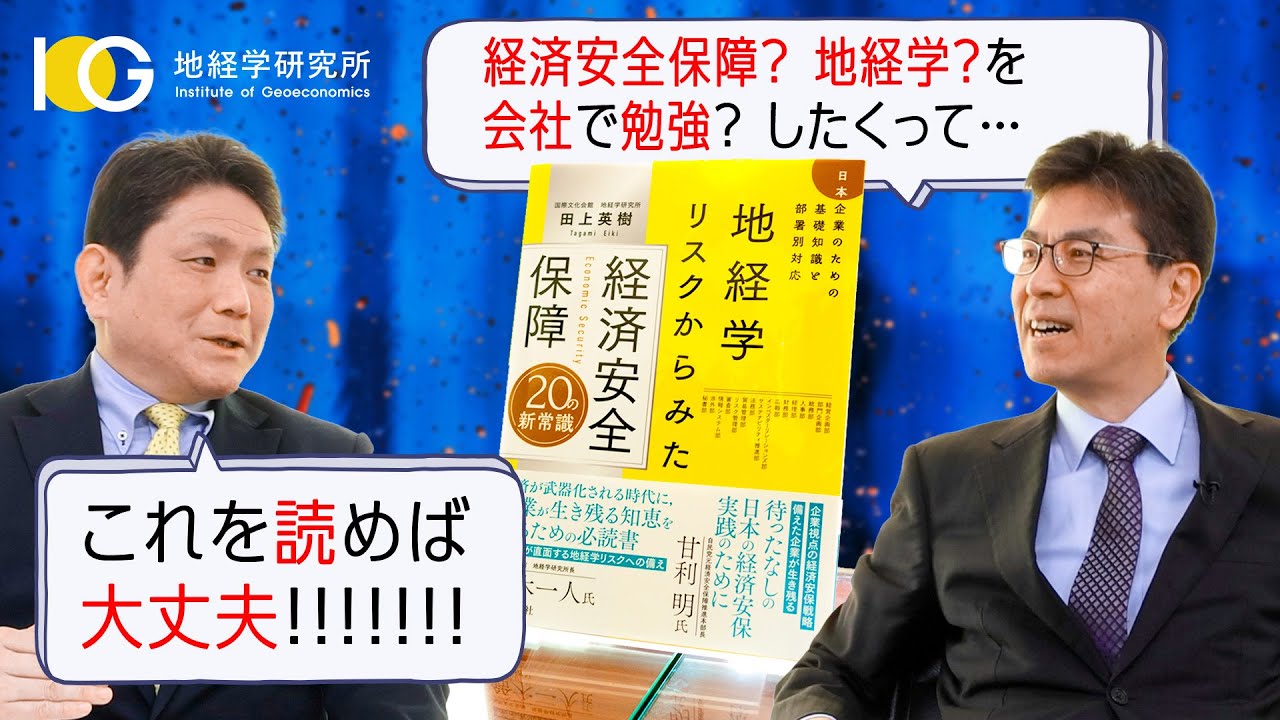タリフ・トラッカー:米国における関税の権限や行使に関するガイド
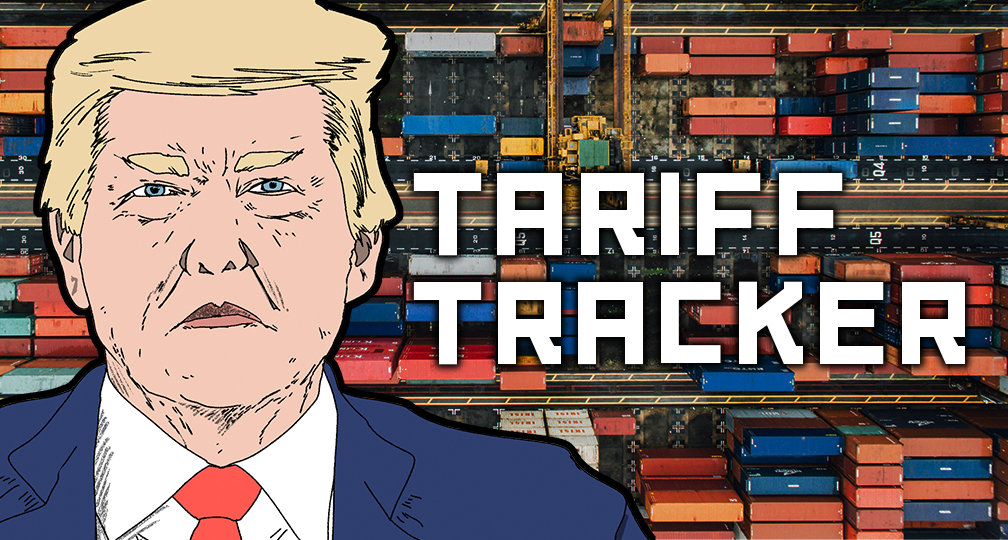
最終更新:2025年5月29日
「タリフマン(関税男)」を自称するトランプ米大統領は、これまで関税を経済政策の主要な手段として活用してきた。しかし、関税は大統領が独断で命令できるものでも、ソーシャルメディアで発表すれば自然と適用されるようなものでもない。関税政策は、合衆国憲法と法的権力のもと、特定の状況下で連邦議会が大統領に意思決定権を付与するという複雑な権限の構造によって成り立っている。
関税を実施する際、誰がどのような権限を持ち、そのプロセスがどう進むのかを理解することで、今後の米国の関税政策の動向をより予測しやすくなる。国家安全保障分野、実施までのタイムライン、関連省庁との調整といった、大統領が関税政策において独自の権限を行使できる分野を把握することで、政権に対し懸念を表明することができるポイントが明らかとなる。
以下は、過去に頻繫に使用された、または第2次トランプ政権で行使可能とされる権限の主要なものをリストアップしたものである。
この解説で使われる用語の解説:
法的根拠:米国政府の一部に関税を課す権限を与える法令または権能を指す。米国のあらゆる政策に共通して言えることだが、関税や貿易措置は大統領の正式な署名がなければ発効しない。そのため、それ以前の段階では政策というよりも、意思表明に近いものとなる。トランプ大統領が2月13日に発表した相互関税は、関税の導入を検討するよう指示は出しているが、関税を実施するための具体的な権限や、誰が何の権限のもとで検討を行うのかについて言及していないため、これを正式な政策の執行と呼ぶのは難しく、「その他」の項目にまとめている。
アクター:権限の発動および執行を担う、米国政府内の特定の役職、部署、または機関。
対象:権限が及ぶ範囲と適用される具体的な状況。
タイムライン:手続きや公式な検討が正式に開始されてから実施に移されるまでの期間。実施へ移される時点とは、個別の法律、大統領令もしくは布告により特定の発効日が定められている場合を除き、通常は大統領が法律または大統領令に署名する時点を指す。
制限:制定を遅らせる、ないしは完全に阻止する、または執行を終了させるなどの法的制限のこと。大統領令が憲法もしくは連邦議会から付与された大統領権限を逸脱している場合、裁判所に訴訟される可能性がある。例えば、国際緊急経済権限法を利用して関税を賦課することは、これまでに前例がないケースであるが、前例がないと言うだけで、その違法性・違憲性を論じることは単なる推測となるため、正式に訴訟などが開始しない限り、ここでは取り上げないこととする。
最近の使用例:トランプ政権における権限行使の具体例。ただし、バイデン政権や第1次トランプ政権の事例も含まれる場合がある。
法的根拠:1962年通商拡大法 第232条
アクター:米国大統領、米国商務省
対象:第232条においては、 国家安全保障の確保を目的とする限りにおいて、特定の品目または品目群の輸入を制限する広範な権限が大統領に付与されている。
タイムライン:最長一年。米国商務省産業安全保障局(BIS)が最長270日間かけてこの問題を調査し、その報告書の結果を受けてホワイトハウスは90日以内にどのような措置を取るか決定する。
制限:第232条の権限に関する正式な制限はない。
最近の使用例:2018年、トランプ大統領は第232条の権限を行使し、米国への鉄鋼とアルミニウムの輸入に関税を課した。2025年1月20日には、トランプ大統領が発表した「アメリカファーストの通商政策」に関する大統領覚書は、一連の調査と報告を要求したが、その際に第232条の権限は引き合いに出されなかった。
2025年3月1日、トランプ政権は商務長官に対し、国家安全保障の確保を目的とした追加措置の必要性を含め、「木材、製材やそれらの派生製品の輸入が国家安全保障に及ぼす影響を判断する」ための第232条調査を開始するよう指示する大統領令を発令。報告書の提出期限は命令発表から270日後(11月26日)である。
2025年3月12日、トランプ政権は2018年の関税における無関税枠や特定の製品除外を廃止することにより、鉄鋼とアルミニウムそして鉄鋼とアルミニウムを使用する289もの下流工程製品群に対する関税率を引き上げた。
3月26日、トランプ政権は、乗用車(セダン、SUV、クロスオーバー、ミニバン、貨物バン)およびライトトラック、主要な自動車部品(エンジン、トランスミッション、パワートレイン部品、電装部品)に対して25%の関税を課すと発表した。これは、2019年の調査において自動車の輸入が米国の国家安全保障を損なっていると結論付けられたことを受けた措置であるが、当時はその報告を受けた対応が行われていなかった。
現在進行中の第232条調査(調査終了時に関税が課される可能性のあるもの):
・銅(2025年3月10日開始)
・木材および製材(2025年3月10日開始)
・医薬品、医薬品原料、完成医薬品(2025年4月1日調査開始)
・半導体および半導体製造装置(2025年4月1日調査開始)
・重要鉱物およびその派生製品(2025年4月15日調査開始)
法的根拠:1977年国際緊急経済権限法(IEEPA)
アクター:米国大統領
対象:国家緊急事態法(NEA)が示す緊急事態への対応を目的として、大統領が行使できる権限。緊急事態が発生した際、「米国の国家安全保障、外交政策または経済に対する異例かつ重大な脅威であって、その全てまたは重要な一部が米国の国外に起因するもの」については国際緊急経済権限法を発動することができる。 国家緊急事態法において何が「国家緊急事態」かの定義についての記載はないが、どのようにして大統領が緊急事態を宣言できるかについては定められている。現在、37の緊急事態宣言が発動中であり、その中でも最も古いのはジミー・カーター政権時に発令された米国内にあるイラン政府資産の凍結である。
通商に着目すると、国際緊急経済権限法は大統領が貿易を含む様々な国際経済取引を「規制」することについて許容するが、この「規制」に関税水準が含まれているかどうかは不明確である。国際緊急経済権限法は経済制裁や金融規制実施のために使用されてきたが、これまで関税に使用した大統領はいなかった。しかし、トランプ大統領は2019年にメキシコ、2025年1月にはおそらくコロンビア(訳注:不法移民の受け入れを強要するために発動したとみられるがIEEPAが使われたことを明示する書類は存在しない)、そして2025年2月にカナダとメキシコに対して関税を課すと警告した。[1]
タイムライン:大統領は自らの意思で国家緊急事態を宣言することができるが、どの権限に基づいて発動されているのかを明確に示さなければならない。宣言が有効となる具体的な日付を含める必要がある(例えば、2025年2月1日に発表された北部国境に関する緊急事態宣言に関する大統領令では、発行予定日を2月4日と定めた)。ただし、具体的なタイムラインは大統領の裁量に拠る。
制限:米国連邦議会は、国家緊急事態法の迅速な承認制度の下、不承認の共同決議を可決することにより、緊急事態宣言を終了させることができる。
最近の使用例:2025年2月1日にカナダとメキシコに対して25%の関税賦課が宣言された。その後、違法薬物流入に対処するための関税措置として、30日間の猶予期間が設けられた。 3月4日の午前0時(米国東部標準時)には中国に対して10%の追加関税の上乗せが発表された。
2025年4月2日、IEEPAに基づく権限のもと、「貿易関係における相互主義の欠如やその他の有害な政策によって引き起こされた大規模かつ持続的な貿易赤字」を理由に、国家非常事態が宣言された。これを受け、2つの関税措置が発表された。第一の措置は、カナダ・メキシコを除くすべての米国向け輸入品に対して10%の一律関税を課すもので、2025年4月9日に発効した。
第二の措置は、「相互関税」と呼ばれるものであり、USTRによれば、「米国と各貿易相手国との間の二国間貿易赤字を均衡させるために必要な関税率」として算定される。最終的には、各国との二国間貿易赤字をゼロにすることが目指されている。関税の適用除外対象には、スマートフォン、ノートパソコンなどの民生用電子機器(2025年4月12日に別途発表された免除措置による)、通商拡大法第232条に基づきすでに関税が課されている品目、将来的に同条項の対象となる品目、ならびに米国と正常な通商関係を有していない国(例:ベラルーシ、キューバ、北朝鮮、ロシア)からの品目が含まれる。
トランプ前大統領は、各国との間で「相互関税」の税率引き下げに向けた交渉を行う時間を確保するため、これらの関税を90日間一時停止すると発表した。関税は、2025年7月8日に再発動される予定である。
1: 2025年1月27日、トランプ大統領がSNS「Truth Social」への投稿で、コロンビア政府に対する金融制裁を実施する権限として国際緊急経済権限法を引用した一方で、関税賦課については根拠となる権限に触れなかった。
法的根拠:合衆国憲法 第1条 第8項 第3節(通商条項)
アクター:米国連邦議会
対象:広範囲に渡る。合衆国憲法 第1条 第8項 第3節によると、「諸外国との通商、州をまたぐ州際通商およびインディアン部族との通商を規制する権限」が与えられている。米国連邦議会が「州際」の通商を規制する権限の意味と範囲についての議論はあったが、関税を課す権限に関する法的論争には現在に至るまで存在していない。
1930年代以降、連邦議会は、大統領が議会承認を得なくても外国政府との貿易協定交渉や、関税その他の貿易制限に関する限定的な変更の追求を進められるように、「貿易促進権限」(TPA)と呼ばれる一定の権限を大統領に委譲してきた。
タイムライン:定義なし。貿易促進権限は一定期間有効であるが、原則として連邦議会はいつでも国際貿易と関税に対処する法案を通すことができる。
制限:大統領はいかなる法案にも拒否権を行使することができる。しかし、連邦議会は両院の3分の2以上の賛成でこの拒否権を覆すことができる。
最近の使用例:2015年から2021年の間、貿易促進権限法案が有効であった。トランプ第1次政権では、この権限に基づき、日本と欧州連合との貿易協定を実施した。しかし、2021年に失効して以来、更新されておらず、バイデン前政権も、現在のトランプ政権も更新する意思を示していない。
法的根拠:1974年通商法 第301条
アクター:米国通商代表部
対象:第301条の権限に基づき、米国通商代表部は、通商協定違反行為や通商における不正行為を行っている国に対し、関税を賦課または通商協定の譲許を撤回することができる。これまでは、第301条に基づく調査は世界貿易機関(WTO)の紛争処理手続きにおける事案において発動されてきた。しかし、トランプ第1次政権において、一方的に発動されるようになり、この慣行はバイデン政権にも引き継がれた。
違反行為に対抗するため、第301条に基づき、米国の通商に対する不正行為や負担、制限を除去したり、米国の通商利益を補償することを目的として、米国通商代表部は関税やその他の輸入制限を課したり、通商協定の譲許を撤回または一時停止したり、相手政府と拘束力のある協定を結んだりすることができる。
タイムライン:約一年強。米国通商代表部は関係者から申し立てがあった場合、45日以内に調査を実施するかどうかを決定する義務がある。また、関係者との協議を経て、米国通商代表部自らが調査を提起することもできる。一般的に、調査には最長一年間を要し、調査の結果によって不正行為が発見された場合、30日以内に報復措置が実施される。調査期間は一年に満たない可能性もある。
制限: 第301条に基づく調査や救済措置に関する正式な制限はない。
最近の使用例:2018年にトランプ大統領は中国からの総額5,500億ドルもの輸入品に対し関税を課し、バイデン政権も 4年ごとに義務付けられた見直しの結果、この決定を延長した。
現在進行中の第301条調査(調査終了時に関税が課される可能性のあるもの):
・デジタルサービス税(2025年2月21日開始)
法的根拠:1974年通商法 第122条
アクター:米国大統領
対象:第122条は、米国が「大規模かつ深刻な」貿易赤字を抱えている国または複数の国々に対し、大統領が最大15%の関税を課すことを認める。米国内で入手できない品目などなどについては、除外規定も存在する。
タイムライン:第122条に基づく関税の賦課は調査結果には左右されないが、賦課期間が最長150日までとされている。それを超えて延長する場合は、米国連邦議会の承認が必要となる。
制限:国際収支赤字に関連する関税を150日以上課すには、議会の承認が必要となるため、長期的な手段や交渉手段として使用できるかは疑問が残る。
近年の使用例:第122条はこれまで一度も使用されたことがない。
法的根拠:1974年通商法 第201条
アクター:米国大統領、国際貿易委員会
対象:第201条措置は、外国企業との競争からの一時的な救済を行うことによって米国産業を保護し、対象となる米国産業が市場環境に適応して再び競争を成功させる機会を与えることを目的としている。
タイムライン:最長240日間。企業、労働組合、業界団体、または米国産業を代表する労働者グループといった関係者、米国通商代表部、下院歳入委員会、上院財政委員会、米国国際貿易委員会などは、第201条に基づき調査の開始を提起することができる。そして、米国産業が損害を受けたか、またその恐れがあるかを判断するため米国国際貿易委員会が120日間(複雑な事案の場合、最大30日間延長されることもある)の調査を行う。その上で、大統領に提案する適切な救済措置を決定するために最大60日間、さらにその提言を実施するかどうか、またはどの程度実施するかを大統領が判断するために最大60日間が与えられる。これらの判断は、連邦議会に提出する報告書に記載される。
制限:大統領の行動が米国国際貿易委員会の勧告と異なる場合、または大統領が行動を取らない場合、連邦議会は大統領の報告書を受理してから90日以内に不承認共同決議を提出することができる。不承認共同決議が採択された場合、大統領の報告にかかわらず、米国国際貿易委員会の勧告が救済措置として採用され、大統領は30日間以内に布告しなくてはならない。
近年の使用例:2018年、トランプ第1次政権は、アメリカ国際貿易委員会の調査の結果を受けて、特定の結晶シリコン製太陽光発電(CSPV)セルやモジュールの輸入に対し、4年間のセーフガード措置を発動する際に第201条救済措置を使用した。同様に、輸入される大型家庭用洗濯機に対して3年間のセーフガード措置を発動した。
法的根拠:1930年関税法第338条
アクター:米国大統領、国際貿易委員会
対象:特定の国が米国の通商を差別している証拠が見つかった場合、大統領は「新規または追加関税」を布告することができる。調査は米国政府自身が主導するか、関係者が国際貿易委員会に申し立てることで開始される。第338条に基づく関税は、対象製品の従価税を50%以上引き上げることはできない。
タイムライン:第338条は通商差別を明示する調査結果が無い限り使用できないが、調査報告書の提出、報復決定、報復措置の開始時期に関する指定もない。
制限:法的な制限ではないものの、第338条の措置は、WTOや他の貿易協定で定められた枠組みに必ずしも合致しているわけではないため、第338条が関税賦課に使用された場合、WTO加盟国が米国に対して報復措置を講じる可能性がある。
近年の使用例:1949年以降、第338条の使用例は確認されていない。
その他:
紛争解決メカニズム:WTOや個々の協定には紛争解決メカニズムがあり、交渉による解決の試みが失敗した場合、WTO加盟国は相手国に関税を含む罰則を課すことができる。
大統領の行動(Presidential Actions):憲法および法律上の権限のもと、大統領が取れる行動がいくつかある。まず、憲法および法律に基づき与えられた法的権限を利用して、大統領令や大統領覚書等を通じて各省庁の職員に直接指示を出すことが挙げられる。施行中は法的効力を持つが、削除、修正、または他の大統領令などによって取って代わられることもある。
大統領布告は、儀礼的な意味合いが強く法的効力を持たないが、既存の法律や法令を実施するために発せられる。既存の法令を調整する形でのみ活用が可能であり、1974年通商法以降、歴代の大統領は大統領布告を通じて、関税障壁に対処してきた。一方で、クォータや原産地規則のような非関税障壁への対応は議会の立法措置に任せてきた。
近年では、2015年から2021年にかけ執行された貿易推進権限(TPA)のもと、2015年超党派議会貿易優先権説明責任法第103条(a)により、大統領は布告によって既存の関税率を最大50%まで引き下げ、5%以下の関税率には制限なく調整できることとされていた。第1次トランプ政権下、日本(2019年10月)および欧州連合(2020年11月)との貿易協定締結にこの権限が使用された。いずれの協定も第103条(a)の規定とおおむね一致するように調整された。一部の議員からは、これらの協定が2015年超党派議会貿易優先権説明責任法の範囲と趣旨を逸脱しているとの批判もあった。
2021年に貿易促進権限が失効したため、関税に関する布告は2015年から2021年の貿易促進権限に基づく貿易措置にのみ適用される。例えば、輸入される鉄鋼とアルミニウムに関する関税を引き上げる契機となった2018年の通商拡大法第232条に基づき、トランプ大統領は2025年2月10日に、米国への鉄鋼とアルミニウムの輸入関税の調整を発表した。
最後に念押しするとするならば、明確な権限の根拠が示されていない限り、関税に関する意思表明は「既定の事実」ではなく、あくまで「意思の表明」に過ぎない点である。
2025年2月13日に発表された「相互貿易と関税に関する覚書(Reciprocal Trade and Tariffs)」で連邦機関に対し相互関税の可能性を調査するよう指示したことは、その中間にあるとも言える。大統領には、関係機関に対し各国の関税率を精査させ、報復的な関税措置が適用可能かを検討させる権限があり、さらにそうした関税を実際に発動する権限もある。実際の発動にあたっては、おそらく1974年通商法301条(米国に対して不公正な貿易慣行をとる国に関税を課す権限)、または、1930年関税法338条(米国の通商に差別的な扱いをする国に関税を課す権限)のいずれかが用いられると見込まれる。
2月13日の発表時点では、これらのいずれの権限にも言及されていないが、報告書が提出され次第、商務長官および通商代表が「必要なあらゆる措置」を開始する判断を下す予定である。これらの措置には、大統領の既存の法的権限を活用することが想定されており、その内容は、各貿易相手国との相互的な貿易関係の構築を目指す救済措置の提案を含む報告書において明らかにされる見通しである。
タリフトラッカー時系列表


客員研究員
テンプル大学ジャパンキャンパス客員助教授、Tokyo Review共同創業者・編集者、米国CSIS(戦略国際問題研究所)客員研究員。米国上院議員外交・貿易スタッフなどを経て現職。ジョージワシントン大学学士、タフツ大学フレッチャースクール修士、東京大学公共政策大学院博士。専門は、政治的党派性や国際貿易政策に関する国内政治と国際政治の交差。BBCニュース、ニューヨークタイムズ、日経アジアンレビュー、ジャパンタイムズなどへの寄稿も行っている。
プロフィールを見る