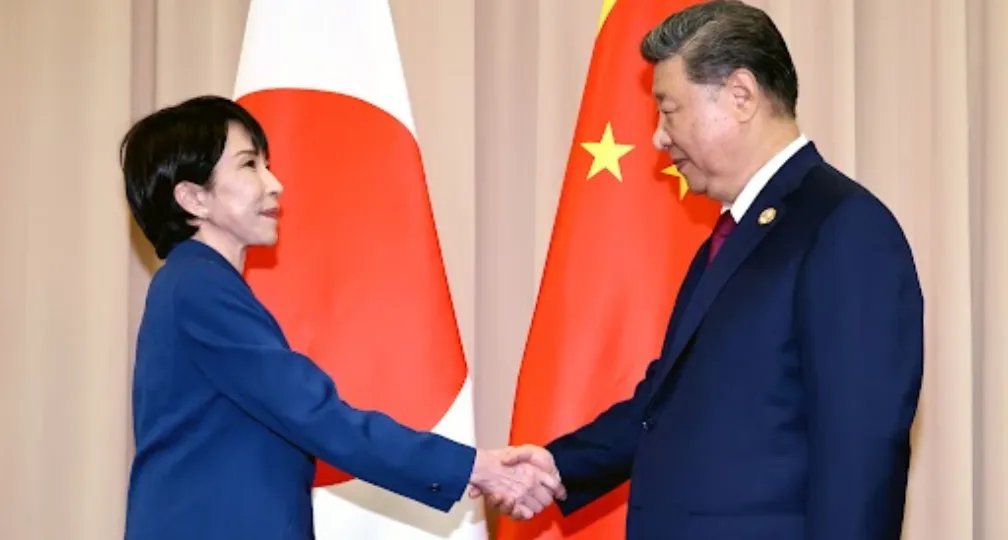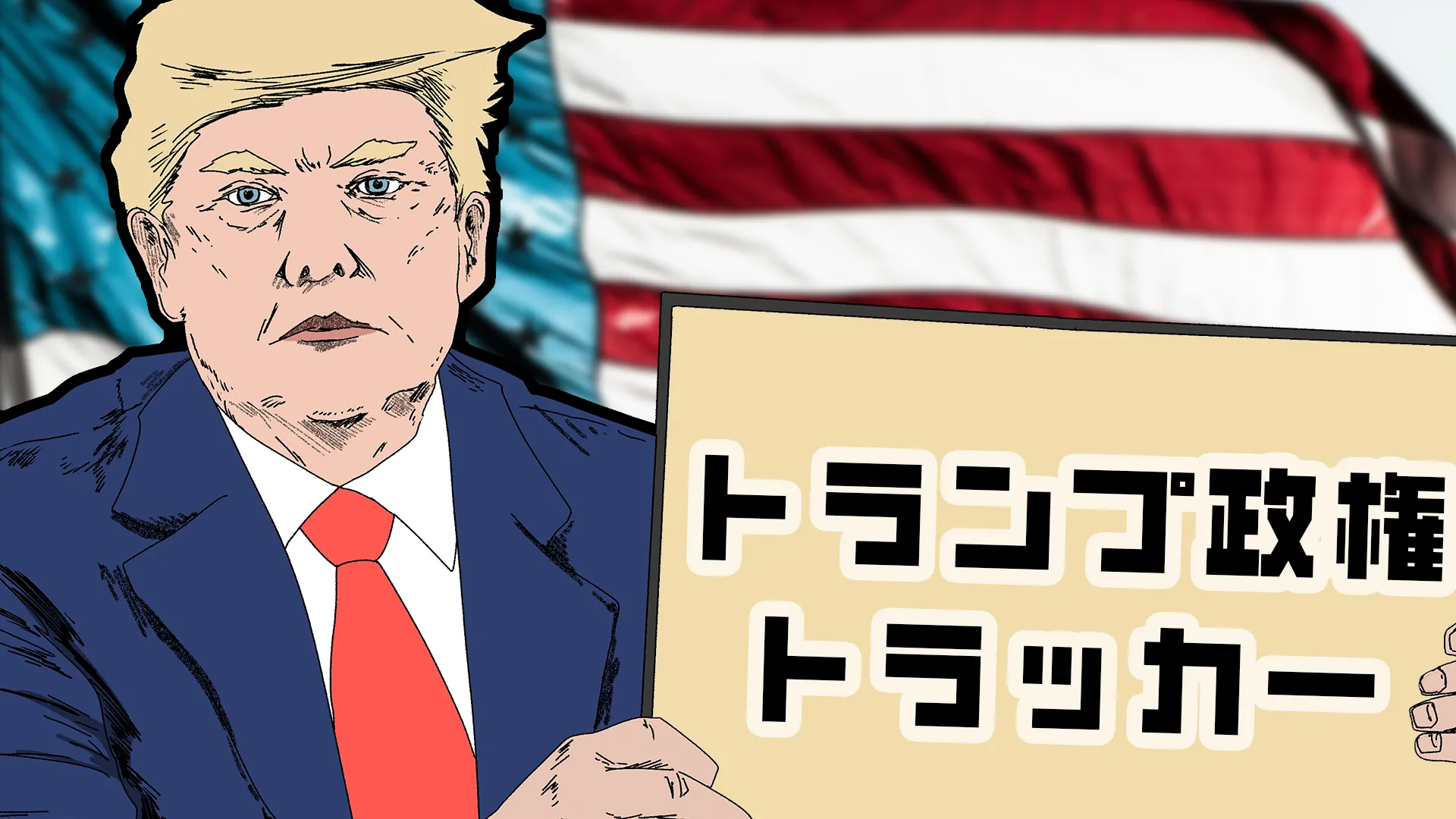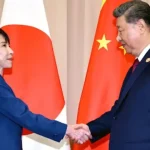石油・債務・ドル:ベネズエラをめぐる地経学

1月3日に米国が実施したベネズエラのニコラス・マドゥロ大統領の域外逮捕は、「モンロー主義に対するトランプ流の補則」、すなわちトランプ大統領自身が呼ぶところの「ドンロー主義(Donroe Doctrine)」を、これまでで最も明確に示す事例である…(以下に続きます)
1月3日に米国が実施したベネズエラのニコラス・マドゥロ大統領の域外逮捕は、「モンロー主義に対するトランプ流の補則」、すなわちトランプ大統領自身が呼ぶところの「ドンロー主義(Donroe Doctrine)」を、これまでで最も明確に示す事例である。この政策には、いくつもの正当化の論理が重なっている。地政学的には、マルコ・ルビオ国務長官が、米国は西半球が「敵対勢力、競争相手、ライバルの作戦拠点」となることを容認しないと強調してきた。法的観点では、マドゥロ氏が麻薬カルテルの指導者であり「麻薬テロリスト」に指定されたことを根拠に、正当な国家元首ではないと位置づけられた結果、この地域では「国際法」よりも米国の「国内法」が優越するとの含意を持つ。さらに経済面では、米国の石油企業がベネズエラのエネルギー・インフラを再建し、生産を拡大するとのトランプ氏の主張から、この作戦はイラク戦争と同様、実際には資源獲得を目的としたものではないかとの見方も生じている。
しかし、こうした表向きの正当化だけでは不十分である。というのも、ベネズエラ作戦の背後には、もう一つの重要な「地経学的な論理」が存在するからだ。その理由を理解するには、ベネズエラを単なる産油国としてではなく、コモディティ、通貨決済、そして西半球における敵対国の経済的影響力を結びつける、より広範な地経学システムの結節点として捉える必要がある。
ベネズエラ作戦を「石油目当て」とする説明は、表層的な見方にとどまる限り成立するように見えるが、踏み込んで検証すると説得力に欠ける。米国はすでに世界最大の産油国であり、ベネズエラの生産が短期間で急拡大するかのような最近の発言も、石油業界の専門家の間では広く否定されている。ベネズエラのエネルギー・インフラは、長年にわたる投資不足、制裁、そして経営の失敗によって深刻に傷んできた。楽観的な評価であっても、生産を意味のある水準まで拡大するには数年を要し、かつ大規模な資本投下が不可欠だとされている。歴史的に見ても、ベネズエラの原油生産量が前年から増加する場合でも、その増加幅は日量数十万バレルを超えることはまれであり、一方で、混乱期にはそれを上回る規模で急減してきた。
要するに、再建されたベネズエラの石油供給が意味を持つのは2030年代であり、短期的に世界の原油市場価格へ即座の影響を及ぼすことはない。
ここで浮かび上がるのは、重要な区別である。すなわち、新たな石油供給を立ち上げることと、既存の供給フローを支配することとの違いだ。2024年のベネズエラの原油生産量は日量約80万〜90万バレルと推定され、その大半が輸出に回っていた。輸出量のおよそ4分の3は中国向けであり、制裁の影響から割引価格で取引されることが多く、通常の商業取引というよりも、融資に対する利払いに充てられるケースが少なくなかった。したがって、米国の作戦後におけるベネズエラ産原油の重要性は、この原油が需給バランスを大きく変え、世界の原油価格を左右し得る点にあるのではない。むしろ、これまで米国の金融支配の外側で、制裁を回避するエネルギー回廊を支えてきた点にこそ、その意味がある。
この文脈において、米国がこの作戦から短期的に得る最大の利益は、将来の増産ではなく、現在の生産量および既存の輸出インフラに対する即時の影響力である。制裁の執行――12月中旬に中国向けの制裁対象原油を積んだタンカーが拿捕された事例に見られるように、ルビオ国務長官が今後も継続すると述べている措置――は、数量そのものではなく、輸送経路、取引相手、決済手段を標的としている。輸出ターミナル、海上保険、決済チャネルを誰が支配するかによって、誰がどの条件でベネズエラ産原油にアクセスできるかが決まる。たとえ世界の原油価格がほとんど動かなくとも、取引相手に及ぼす戦略的影響は大きく、最終的には将来の交渉におけるレバレッジへと転化し得る。
また、米国がベネズエラの現行の石油生産を掌握することで影響を受け得る相手は、中国だけではない。中国は潤沢な戦略備蓄を有しているからだ。カナダにとっては、ベネズエラ産の重質原油が米国寄りの流通経路に再び戻る可能性が、2026年7月に予定されるUSMCA(米国・メキシコ・カナダ協定)の更新交渉を前に、米国の製油所がカナダ産原油に依存する度合いを一定程度引き下げ、結果としてカナダの交渉上の立場を弱めることになる。さらに、キューバ経済も圧力の対象となり得る。というのも、補助金付きで供給されてきたベネズエラ産原油は、キューバの国内エネルギー需要を満たすうえで不可欠な存在となっているからである。
この焦点には、エネルギー・システム上の構造的な論理も存在する。米国のシェールオイル生産は大半が軽質原油である一方、テキサス州やルイジアナ州にある多くの製油所は、より重質な原油を処理するよう設計されている。ベネズエラ産の重質原油は、カナダのオイルサンド由来の原油と同様、これらの製油所との適合性が高い。長年にわたり、米国がカナダ産の重質原油に依存してきたことは、北米のエネルギー統合を特徴づける要素であった。しかし現在では、現行のベネズエラ産原油を吸収できる余剰の精製能力が存在している。現在の生産水準のうち、たとえ限定的な量であっても、それを米国寄りの流通経路へ振り向けることができれば、製油所の強靱性を高めると同時に、供給国と需要国の双方に対する米国の影響力を拡大することにつながる。
このように捉えると、ベネズエラ産原油は「戦利品」というよりも、「拒否(デナイアル)のための武器」として機能していることが分かる。制裁下において、中国はベネズエラ原油の最大の買い手であったが、近年の中国の原油輸入全体に占める同国産原油の比率は、およそ5%にすぎなかった。重要なのは、前述のとおり、これらの原油フローの相当部分が、過去約20年にわたる中国からベネズエラへの融資に由来する「石油と債務の交換(オイル・フォー・デット)」の枠組みに結び付いていた点である。中国の対ベネズエラ融資総額は約600億ドルと推計され、そのうち約130〜200億ドルが未返済とされている。結果として、原油生産は事実上、債務返済のための事業となり、エネルギー取引が非ドル通貨で行われる中国主導の金融エコシステムに組み込まれていった。この現状を崩すことは、中国にとって「保証された」割引供給を、国際市場での調達に置き換えることを意味し、ドル建て決済および制裁執行へのエクスポージャーを高めることになる。
この「拒否」の論理は、石油にとどまるものではない。ベネズエラは、西半球において、米国の敵対国にとって経済面と安全保障面の拠点が重なり合う、まれな結節点を提供してきた。ロシアやイランは、ベネズエラと軍事協力や防衛産業分野での取り決めを有しており、これを軽視することはできない。ただし、以下の議論では、主として中国の天然資源分野における利害に焦点を当てる。
中国企業は、炭化水素資源から重要鉱物に至るまで、採掘産業に深く関与してきた。ベネズエラには「オリノコ・アーク」として知られる、未開発のレアアース資源が集中して存在しており、そこからは電動モーター、量子センサー、AIの実装に不可欠な元素を採掘することができる。実際のところ、石油供給の拡大という誘因以上に、米国が視野に入れているのは、こうした原材料へのアクセスを確保することで、中国が支配するサプライチェーンへの依存を低減すること、あるいは少なくとも、中国が世界の鉱業分野でさらなる独占的地位を築く機会を阻むことにあると考えられる。
ルビオ国務長官は次のように述べている。「我々は、敵対国がアフリカや世界各地で資源を搾取している実態を見てきた。それを西半球で許すつもりはない」。この文脈において、石油は主たる獲得対象というよりも、より広範な影響力行使を可能にするための基盤的資産として理解するのが適切である。実際、米国の視点から見て、中国がベネズエラの天然資源を採掘していたこと以上に挑発的だったのは、それらの資源が、米国の領土に近接した地域で活動する「複数の敵対国からなるプラットフォーム」の形成を資金面で支えていた点であった。エネルギー収入、インフラ、そして国家による生産統制は、米国の安全保障上の利益に反するこうした広範な連携を支える、財政的・物流的な基盤を提供してきた。
原油フローを遮断することに加え、この体制の要石であったマドゥロ氏を排除することは、西半球における敵対国間の協力関係全体のアーキテクチャを揺るがすことにつながる。再びルビオ長官の言葉を引用すれば、「米国はベネズエラの石油を必要としていない。十分にある。我々が許さないのは、ベネズエラの石油が中国、ロシア、イランに支配されることだ」ということになる。明示されてはいないものの、この論理は、石油以上に米国の不足が大きい重要鉱物の分野において、より強く当てはまると言える。
実際のところ、米国がベネズエラの石油生産から引き出し得る経済的な見返りには、明確な限界がある。原油価格が1バレル50ドル前後の場合、現在の輸出による年間収入は、生産量にもよるが約140億〜180億ドルにとどまる。これはベネズエラにとって最大の収入源ではあるものの、そこから操業費やサービス費用、その他の輸入品購入、政府支出、さらには未払い債務の返済を賄わなければならない。こうした低水準の収入では、たとえトランプ大統領が、これらの収入が過去に国有化されたベネズエラ資産に対する補償になり得ると示唆していたとしても、米国の石油企業が巨額の財政的果実を期待してベネズエラに投資する十分な動機が生まれるとは考えにくい。加えて、政治リスクも依然として高い。インフラが再建されればされるほど、将来的な再国有化への誘因はむしろ強まる。これらの制約は、石油をめぐる米国の主要な動機が、生産拡大や利益最大化ではなく、「支配と拒否(コントロールとデナイアル)」にあるとの見方を、いっそう裏付けるものである。
米国企業がベネズエラの石油生産から巨額の利益を得られる可能性を、さらに低下させる要因として、中国がベネズエラに対する債務返済を強く求めることは確実だという点が挙げられる。中国は、バランスシート上で無視できない規模のエクスポージャーを抱えているからである。ベネズエラの銀行や国有企業は、ラテンアメリカにおける中国融資の最大級の受け手であり、石油を担保とした融資の代表的な事例でもあった。これらの未回収債権を回収できなければ、中国の「一帯一路」構想という、より大きなプロジェクト全体の持続可能性が損なわれかねない。中国にとって最悪のシナリオは、ベネズエラのデフォルトによってBRICSの結束が揺らぐことであろう。しかし、より穏健なシナリオであっても、状況は好転しない。すなわち、石油と債務の交換による返済が鈍化し、ブラジルやコロンビアが中国投資への過度な依存を見直す動きに出て、中国の中南米全体における影響力が低下するという展開である。
さらに中国にとって、ベネズエラは政治的に足並みのそろった供給国であり、ドルによる執行から部分的に隔離された存在であった。実際、ベネズエラは、人民元(RMB)などの通貨で原油を価格付け・決済したり、代替的な決済インフラを活用したりするなど、非ドル建てコモディティ決済の比較的目立つ実験の一つとなってきた。これらの試みは規模としては限定的であったものの、その象徴的な価値は大きかった。中国、ロシア、そしてBRICS諸国が掲げる「脱ドル化」という、より広範な物語を補強する役割を果たしてきたからである。しかし、ポスト・マドゥロ政権が、仮にワシントンと北京の間で均衡を取るにとどまったとしても、ましてや米国との協力に軸足を移すような事態になれば、中国のエネルギー安全保障戦略や、代替的なコモディティ金融ネットワークを構築しようとする取り組みは、大きく揺らぐことになる。
ドルの側面は極めて重要である。ベネズエラ産原油の流れを掌握すると主張することは、単に敵対国に対する供給チャネルへの影響力を誇示するにとどまらず、エネルギー決済通貨としてのドルの役割を改めて押し出す行為でもある。決済を支配することは、生産を支配することと同等、あるいはそれ以上に重要だとさえ言える。ドル建てで価格付けが行われれば、取引は米国の法的管轄下に入り、制裁の執行が可能となると同時に、世界的なドル流動性への需要を下支えするからである。この観点から見れば、今回の作戦は「石油略奪」というよりも、揺らぎが指摘され始めているペトロダラー体制の信認を立て直そうとする試みと捉えるほうが適切である。
しかし、これは1970年代型の硬直的なペトロダラー体制への回帰を意味するものではない。むしろ、その目的は「適応」にあるように見える。マドゥロ氏の逮捕後、米国防総省において国防産業基盤の再建や経済安全保障関連プロジェクトの資金供給を担う中核組織である戦略資本室(Office of Strategic Capital:OSC)のパトリック・ウィット副室長は、ベネズエラは米ドルおよびドルに裏付けられたステーブルコインを「法定通貨」として採用することを検討すべきだと述べた。同氏は、ベネズエラはすでに「事実上ドル化」されており、それを制度として正式化することで「海外投資を呼び込み、切実に必要とされている価格安定をもたらす」と主張している。この発言が示唆するのは、エネルギー取引においてドルが引き続き計算単位および担保の基軸としての役割を維持しつつ、西半球におけるドルの役割が拡大する限りにおいて、ブロックチェーンを活用した決済を含む新たな金融インフラと、ドルの優位性は共存し得るという考え方である。
ドル建てで取引される原油は、米国にとって間接的な金融上の恩恵ももたらす。ただし、その効果を過大評価すべきではない。原油価格をコントロールすることはインフレ抑制にも資する。エネルギー価格が低位かつ安定すれば、物価圧力を再燃させることなく、米連邦準備制度理事会(FRB)が利下げを行う余地を広げることができる。また、コモディティがドル建てで価格付けされることは、世界的なドル流動性およびドル建てバランスシートへの需要を押し上げる。もっとも、エネルギー取引で得られたドルが、自動的に米国債などの米国資産へ再投資されるわけではない。しかし、制度的な枠組みや市場の厚みが、その流れを後押ししているのも事実である。長期的には、この戦略の支持者の中には、ベネズエラが「西半球のサウジアラビア」となり、ドルの枠組みの下で原油を輸出し、その収益の一部を米国の金融資産に再投資する姿を思い描く者もいるだろう。仮にそれが実現すれば、海外での地経学的な執行が、国内のマクロ経済運営に直接的に寄与することになる。しかし、こうした恩恵はあくまで長期的な構想にとどまっており、短期的な現実ではない。
より具体的に言えば、今回のベネズエラ作戦は、コモディティをめぐる権力の行使のあり方が、より広い次元で転換しつつあることを示している。地経学の時代において、価格決定力はもはや生産量だけから生まれるものではなく、執行能力から生み出される比重が高まっている。サプライチェーンは「武器化」されつつある。すなわち、相互依存が前提とされてきた時代には所与と考えられていた、海上輸送、保険、金融、法的管轄権といった要素を誰が支配するかが、コモディティ価格に対してこれまで以上に大きな影響を及ぼすようになっているのである。
もっとも、生産そのものの重要性が失われたわけではない。資源をめぐる争いが激化する中で、今回のベネズエラ作戦は、この新たな時代において、米国が「資源主権」を無条件のものとは見なしていないことを示すシグナルとも受け取れる。西半球に位置する国家のうち、資源を放置したり、管理を誤ったり、あるいは敵対国に売却したりする国は、強制的な「再管理(re-stewardship)」の対象となるリスクを負う。これは露骨な略奪ではないが、米国の国家安全保障上の優先事項やドル体制に沿う形へ、力を伴って再調整されることを意味する。
こうしたシグナルは、敵対国に向けられているだけでなく、中立国や同盟国にも発せられている。西半球の国々に対するメッセージは明確であり、今後は経済面および安全保障面で足並みをそろえることが、より露骨な形で求められるということである。主権国家の元首であっても、「犯罪者」や「カルテルの指導者」と指定することで、圧力を加えるための法的経路が作り出され得る。また、港湾や運河といった物流上の要衝は、戦略的資産として扱われるようになっている。
実際、ベネズエラ作戦の後、トランプ大統領とルビオ国務長官は、コロンビアのグスタボ・ペトロ大統領を名指しし、同様の「麻薬テロリスト」指定を示唆する形で圧力をかけた。また、メキシコのクラウディア・シェインバウム大統領に対しても、カルテルの影響力を排除するためとして、米国の軍事支援を受け入れるよう改めて求めている。もっとも、麻薬供給網という観点では、コロンビアやメキシコの方がベネズエラよりもはるかに重要である。それにもかかわらず、こうした「麻薬対策」という枠組みだけで全体像を説明することはできない。米国の並行した狙いは、この地域における中国の地政学的・地経学的影響力を切り崩すことにある。同様に、パナマ運河の両側に位置する中国系企業所有の港湾をめぐる問題も、2025年初頭に見られたトランプ氏の一連の強硬な動き以降、表向きは沈静化している。しかし、この問題が解消されたと考えるのは早計である。実際、北極圏におけるロシアと中国の動きを念頭に、「米国の国家安全保障にとって必要」として、グリーンランドの併合が再び言及されるようになっている。
中国、ロシア、イラン、そしてとりわけキューバといった米国の敵対国、さらにBRICS諸国(特に西半球に位置するブラジル)にとって、このメッセージはより一層厳しいものとなる。ベネズエラは、コモディティを基盤とする脱ドル化の実験場であり、同時に、他地域における米国からの圧力に備えるための戦略的拠点でもあった。そのベネズエラが失われることは、こうした戦略に明確な上限を課すことを意味する。代替的なエネルギー決済を通じてドルに挑戦しようとするBRICSの野心は、象徴的な実験が力によって覆されたことで、信認に打撃を受けかねない。加えて、米国の本拠地とも言える地域で同盟国を育成するために投じられてきた投資も、回収がより困難になる可能性がある。
したがって、ベネズエラは狭義の「石油略奪」の物語としてではなく、現代の地経学を理解するための事例研究として捉えるのが最も適切である。米国は新たな石油供給を短期間で市場に大量投入することはできないため、その目的はむしろ、既存の供給フローを支配すること、ドル中心の決済体制を再主張すること、債務外交によるレバレッジを逆転させること、そして西半球における敵対勢力の戦略的足場を否定することにあると考えられる。
「ドンロー主義(Donroe Doctrine)」というレトリックは、「どこ」で「なぜ」この事態が起きているのかを説明する。一方で、それが「どのように」実行され、そしてなぜ「今」起きているのかを説明するのは、地経学の論理である。
(翻訳:福田 善之、客員研究員)
(出典:Photo by Molly Riley/The White House via Getty Images)


客員研究員
米国サンフランシスコ生まれ、2011年カリフォルニア大学バークレー校歴史学部卒業。専門は東アジアの外交史及び国際関係・政治経済。早稲田大学大学院政治学研究科修士修了、ロンドン・スクール・オブ・エコノミクス(LSE)国際史学部博士号。在日本米国大使館のアメリカン・センター・ジャパンを経て、2015年から2017年日本再建イニシアティブ/アジア・パシフィック・イニシアティブ研究員、元サントリー・トヨタ経済学・関係諸学科国際センター(STICERD、ロンドン)大学院生研究者。現在米国ワシントンDCの地政学リスク・コンサルタント会社PTBグローバル・アドバイザーズ研究主幹。
プロフィールを見る