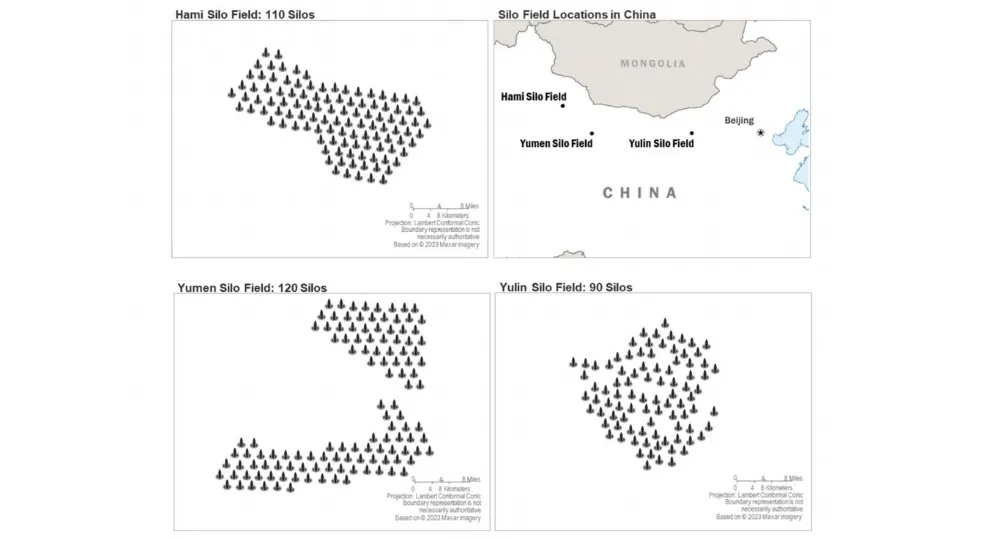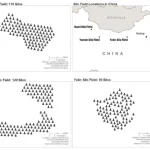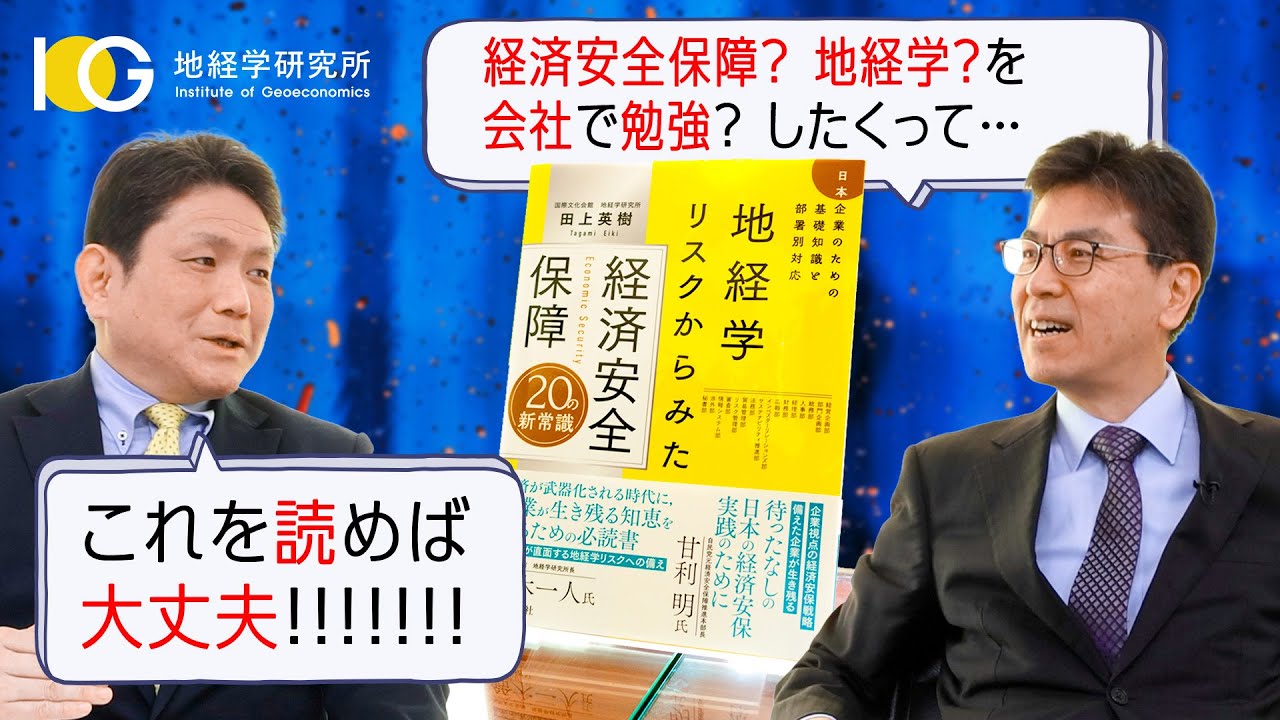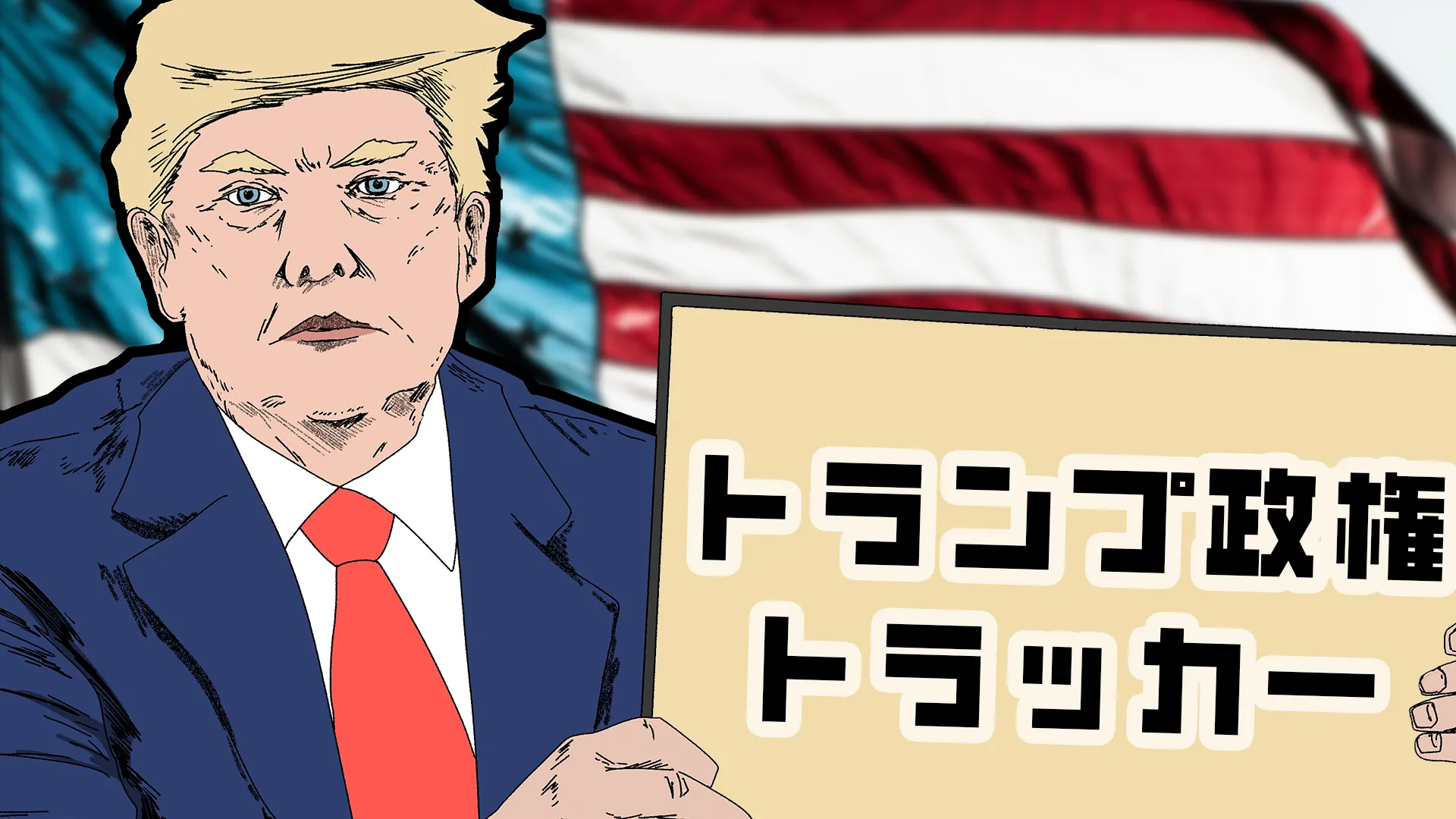揺らぐ米国の宇宙政策 -イーロン・マスクの影響力を読み解く―

もとより米国の宇宙活動は、宇宙科学から軍事宇宙利用まで、その総合力の高さで群を抜いており、文字通り世界をリードしてきた。しかし、その米国にとっても、月や火星などの有人宇宙探査計画は容易ではなく、その実現のためには政権が変わっても継続した開発が必要となる。そこで第1次トランプ政権は、まず月に行ってから火星を目指すという方針を固め、2019年にそれを「アルテミス計画」と名付けた。同計画はバイデン政権にも引き継がれた。
しかし、上述のトランプ大統領の火星探査の宣言は、これまでの方針を覆す可能性を孕んでいる。もちろん米国では政権交代のたびに政策の見直しがなされ、宇宙政策も例外ではない。だが、第2次トランプ政権の発足に際して異例なのは、トランプ大統領と非常に近い立場にある個人―イーロン・マスク―が、これまでの宇宙政策を変更しうる影響力を及ぼしている点にある。
マスクの影響力は宇宙政策全体に広がるものであり、例えばスターリンクの使用を巡ってウクライナ戦争の帰趨への関与の試みも見られる。ただし、ここでは米国の宇宙政策の中でも、特に有人宇宙探査の分野でのマスクの影響力にフォーカスをした上で、それを3つのチャンネルに整理することで、今何が起きつつあるのかを紐解いてみたい。
これまでのアルテミス計画の枠組み
第1次トランプ政権の2019年に始まった「アルテミス計画」の最大の焦点は、5年以内に米国人宇宙飛行士を再び月に送り、月面で持続的な活動を行うことであった(現在は8年以内目標に延期)。その上で、月面を火星探査のための実証場所として位置づけた。さらに今回は、国際パートナーとの協力も強調されており、日本、欧州宇宙機関(ESA)、カナダ、UAE及び豪州などがアルテミス計画への参加を決めている。
第1次トランプ政権の狙いは、5年以内の有人月着陸という短期的目標を設定することで政治的なモーメンタムを創出するとともに、月探査は火星に行くための準備であると位置付けることで火星探査派を取り込み、さらに国際協力の枠組みを固めることで、アルテミス計画の長期持続性を担保することにあった。また、米国の民間企業の能力を最大限活用することで、議会を中心とする米国内の政治的な支持基盤の強化も図った。アポロ計画の時代と違い、現代の有人宇宙探査には国民の強力な支持を得にくい中で最大限の工夫がなされていたとも言える。
なお、アルテミス計画は必ずしも中国との宇宙探査競争に勝つために設計されたものではないが、連邦議員やNASA高官は、中国よりも先に月面に宇宙飛行士を再び送ることの重要性を繰り返し訴えてきた。そこには米国こそが世界の宇宙開発におけるリーダーであり続けるという同国の宇宙政策の目標が示されていた。
大統領の宇宙政策アドバイザーとしてのマスク
第1次トランプ政権及びバイデン政権においては、ホワイトハウス内に設置された国家宇宙会議とNASAの間で、宇宙探査計画が練られてきた。しかし、第2次トランプ政権の発足後、同会議事務局の活動状況は不明であり、またNASAもネルソン前長官の辞任に伴い、政治任用の長官が不在な状況にある。すなわち、ホワイトハウスとNASAを中心とした宇宙政策の決定過程における要職不在の中で、マスクがトランプ大統領に直接働きかけることで、自身の意向を米国の宇宙政策に反映することができるようになっている。
例えば、マスクは、2030年までの運用が予定されている国際宇宙ステーション(ISS)について、すぐにでも軌道離脱の準備を始めるべき、2年後が望ましいとコメントした。ISSに米国人宇宙飛行士を継続的に滞在させることは、米国宇宙政策の一つの柱であるにもかかわらず、それを支えるべきNASAはマスクとの対立を避け、上記のコメントに対して正面から反論はしなかった。
政府効率化省(DOGE)の事実上トップとしてのマスク
マスクはDOGEの活動の一環として、連邦政府の歳出削減や人員削減を掲げ、これがNASAにも影響を与えている。連邦政府縮小の流れの一環で、2月末の時点で、約900名のNASA職員(フルタイム職員の約5%)が早期退職に応じたほか、3月に入って複数のオフィスの閉鎖を発表した。
試用期間中のNASA職員の一律解雇については当面見送ることとなったが、それでも5%の人員削減の影響は十分に大きい上に、政治任用の長官が当面不在の中で今後もDOGEからの人員削減の圧力がかかることを考えれば、NASAの各種のプログラムの実行にも大きな不安が伴うと言えよう。
さらに言えば、DOGEによる歳出削減の要請は、NASA予算の縮減につながる可能性もあり、すでに2026年度のNASA予算要求額が大幅に削減されるとの報道も出ている。予算削減はすなわち宇宙探査計画の縮小や延期につながりかねず、この面でもマスクが主導するDOGEの活動が大きな影響を与える可能性がある。
SpaceXのCEOとしてのマスク
NASAは大手防衛・宇宙企業に多額の契約を発注しているが、実は最大の契約企業はマスクがCEOを務めるSpaceXである(2023年時点[1])。例えばISSへの宇宙飛行士の輸送手段については、Boeingが開発する宇宙船(Starliner)が多くのトラブルを抱えているのとは対照的に、SpaceXの宇宙船(Crew Dragon)は安定的に運用されており、これが米国の唯一の有人輸送手段となっている。
また、SpaceXが開発中の大型ロケットであるStarshipは、もともと火星探査を主な目的として急ピッチで開発されており、NASAが開発している大型ロケットのSLS(Space Launch System)よりも輸送能力が高い上に、コストも大幅に安くなる見込みである。SLSが相次ぐ開発遅延とコスト増に苦しんでいるところ、Starshipという代替手段が出てきたことで、SLSの4号機以降の開発をキャンセルすべしという声も高まっている。
このようにSpaceXがもたらす技術革新やサービスが、NASAの各種計画を支え、時として新たな手段を提供している。これらはNASAや世界のどこの企業でも簡単に代替できるものではなく、だからこそ同社CEOであるマスクの発言に説得力と影響力が生じている。ただし、マスクがホワイトハウスの立場で政府の政策に関与することが、自身の経営する企業への利益誘導になるのではないかとの懸念も根強い。
マスクの影響力にどう対応するべきか
これまで見てきたように、マスクは主に3つのチャンネルで米国の宇宙政策に影響を与える存在となった。彼の影響力の最大の源泉は、トランプ大統領との距離の近さであり、両者の蜜月関係が長く続けば続くほど、彼が米国宇宙政策に大きな影響力を与える状況が続く。さらに彼がSpaceXという高度な宇宙活動能力を持った企業のトップであることが、その影響力を一層強固なものとしている。
しかし、一個人がインフォーマルなチャンネルで宇宙政策の方向性を左右したり、DOGEの活動を通じて、試用期間中の連邦職員を一律解雇しようとすることは、米国の宇宙政策にとってプラスにはならない。むしろマスクの影響力は、現状では米国の宇宙コミュニティに大きな混乱をもたらしている。第2次トランプ政権に本来的に求められるのは、宇宙政策の策定の公式なメカニズムを再確立し、その上で政策目標を再調整することであろう。
とはいえ、それが実現しない間には、連邦議会が宇宙政策の安定化のためにその権限を行使することが重要になる。議会は、授権法を通じて行政府の活動内容を規定することができ、また、毎年度のNASA予算も、最終的には議会の歳出法によって決定される。すでに議会の宇宙関係の両党の議員からは、アルテミス計画の継続性―すなわち月から火星に行く方針―を訴える声が出ている。
また、国際パートナーである日本が、宇宙政策の持続性が重要であることを、首脳レベルも含めた様々なチャンネルで訴えることも一つの手段であろう。日本は、月面での宇宙飛行士の移動手段である与圧ローバの開発をはじめとして、すでにアルテミス計画に深くコミットしており、日本人宇宙飛行士2名を月面に送ることを日米間で合意している。
長期的に考えると、マスクの影響力は、彼とトランプ大統領との関係が変化しても、SpaceXのCEOとして今後も続くであろう。米国の宇宙探査計画にとって、SpaceXはもはや不可欠な存在となっており、民間企業の役割は今後さらに拡大すると予想される。マスクの影響力がもたらす本質的な課題は、NASAと民間企業の役割分担をいかに再定義するかにあるのかもしれない。
(Photo Credit: Brandon Bell / Getty Images)

地経学ブリーフィング
コロナウイルス後の国際政治と世界経済の新たな潮流の兆しをいち早く見つけ、その地政学的かつ地経学的重要性を考察し、日本の国益と戦略にとっての意味合いを精査することを目指し、アジア・パシフィック・イニシアティブ(API)のシニアフェロー・研究員を中心とする執筆陣が、週次で発信するブリーフィング・ノートです(編集長:鈴木一人 地経学研究所長、東京大学公共政策大学院教授)。
おことわり:地経学ブリーフィングに記された内容や意見は、著者の個人的見解であり、公益財団法人国際文化会館及び地経学研究所(IOG)等、著者の所属する組織の公式見解を必ずしも示すものではないことをご留意ください。


研究員
2010年に防衛省に入省。主に海外の軍事動向に関する調査に従事するとともに、軍備管理・軍縮に関わる政策の省内調整も担当等も経験。 2015年に宇宙航空研究開発機構(JAXA)に入構。海外の宇宙政策動向の調査をはじめ、それを踏まえた戦略立案、海外宇宙機関との調整、機構内におけるサイバーセキュリティ規程の策定などを担当。2019年から2022年にかけては、JAXAワシントンDC事務所に駐在員として勤務し、NASAをはじめとする米国の政府機関や民間企業との関係構築を担当した経験もあり。 2025年4月より現職。関西学院大学総合政策学部卒業、京都大学大学院法学研究科修了。
プロフィールを見る