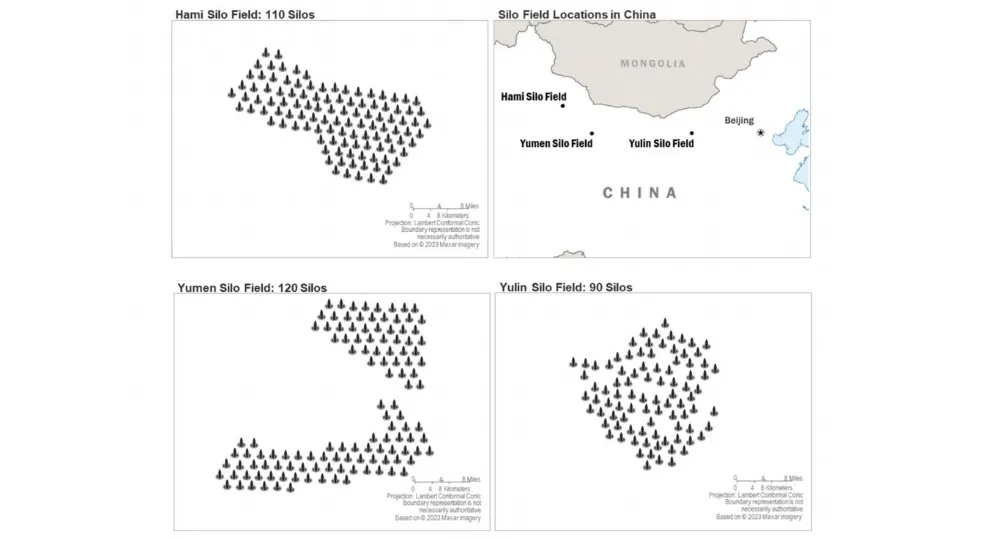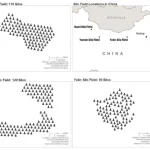日米関税合意の意義:米英合意との比較

日米関税合意の意義:米英合意との比較
7月23日、米トランプ政権は関税などについて日米合意に達した、と発表した。共通関税も自動車も15%とされ、産業界からは歓迎する声もあがる。今回の合意について、米国側の国内スキャンダルに助けられた、トランプ大統領が合意を発表することで世論の風向きを変えようとした、つまり日本は幸運、との論評もあるが、それにも増して、交渉における日本側の積み重ねが一定の成果を挙げた、と見るべきだろう。
第一に、いわゆる「ショッピングリスト」、今回に即して言えば「日本側のオファーリスト」を、官民できちんと積み重ねてきた成果であろう。日本製鉄によるUSスチールの買収(近代化への支援)、自動車関連の投資増、コメの輸入増、防衛装備品の調達、そして直前に発表された、日系エアラインによるボーイング機100機の購入などだ。
日本から米国への5500億ドル(約80兆円)の投資枠組みについては、詳細は不明ながら、日本側による投資、融資、融資保証を組み合わせて提供されるものとされ、エネルギー資源、半導体、重要鉱物、医薬品、造船など、米国の経済安全保障を強化する戦略的重点セクターに投じられる。このように、米国側の関税を低減する合意が、投資枠組みとセットで成立する一つのモデルとなり、合意に至っていない主要国・地域との合意のひな形になっていく可能性がある。欧州連合(EU)は関税率を15%に低減する合意のため、米国との間に何らかの投資合意を盛り込むとの報道もある。
第二に、関税の数字を釣り上げて脅された際に、安易な妥協に走らず、交渉を降りなかったことだ。日本車・部品関税25%など厳しい交渉が伝えられていたが、その時点で飲んでいたら、このような結果には至らなかった。「ラッキー」と言われようが、「その時」に丁度その場に居たことは、成功である。ただし15%関税は、例えば自動車部品関連の中小企業にとっては、依然として厳しい。
第三に、米英合意(6月17日)の文言と比較すると、「米英」では2国間関係にしか言及がないところ、「日米」ではこの合意のグローバルな意義、米国内の雇用へのインパクト(「米英」では英首相のみ言及)が強調されるなど、トランプ政権が日米合意にかける期待(および国内向けのアピール)が前面に出ている。米国が貿易黒字を計上している相手国に対しては2国間の問題として「軽めに」片づけ、赤字の相手国との「ディール」にグローバルな重い位置づけを与える使い分けが見られる。
付記すると、「米英」の10%が米国のベースライン関税として、米国が貿易黒字を計上する相手国に対して適用されるパターンが浮上しているように観察できる。例えばEUのように日本同様の赤字相手国・地域に対しては、投資措置の有無にかかわらず、15%が標準的な関税率となっていく可能性もある。さらにいえば、ベトナム、インドネシア、フィリピンのように中国から米国への迂回輸出が疑われる東南アジア諸国や他の途上国に対しては、20%前後の関税率が定着することも考えられる。
最後に、「米英」には繰り返し「非関税障壁」への言及があるが、「日米」には「(自動車・トラックに関する)非関税障壁」という言葉がなく、代わりに「longstanding restrictions(長期にわたる規制)」との表現に抑えられ、日本側への配慮も伺える。トランプ大統領はこれまで、日本の諸規制を非関税障壁と非難していたが、これを和らげた形だ。
これらの事実をもって日本側が「TACO(トランプは最後に引っ込む)」と揶揄することは早計であり、今回の合意は「勝利」ではない。情勢次第ではさらなる「新手」が繰り出されることも考えられ、日米合意に言及される半導体や医薬品など、引き続き注視が必要だ。
日米・米英合意テキスト比較表
参考文献
・President Donald J. Trump Secures Unprecedented U.S.–Japan Strategic Trade and Investment Agreement
・Implementing the General Terms of the U.S.-UK Economic Prosperity Deal
(画像出典:内閣官房ウェブサイト)




主任研究員
慶應義塾大学大学院法学研究科修士、European University Institute歴史文明学博士。新潟県立大学国際地域学部および大学院国際地域学研究科准教授、モナシュ大学訪問研究員、LSE訪問研究員、外務省経済局経済連携課、日本経済団体連合会21世紀政策研究所欧州研究会研究委員を経て、2021年に合同会社未来モビリT研究を設立。現在、東京大学先端科学技術研究センター牧原研究室客員上級研究員、フェリス女学院大学非常勤講師。2021年12月にAPI客員研究員兼CPTPPプロジェクト・スタッフディレクター就任。 【兼職】 合同会社未来モビリT研究 代表
プロフィールを見る
客員研究員
米国サンフランシスコ生まれ、2011年カリフォルニア大学バークレー校歴史学部卒業。専門は東アジアの外交史及び国際関係・政治経済。早稲田大学大学院政治学研究科修士修了、ロンドン・スクール・オブ・エコノミクス(LSE)国際史学部博士号。在日本米国大使館のアメリカン・センター・ジャパンを経て、2015年から2017年日本再建イニシアティブ/アジア・パシフィック・イニシアティブ研究員、元サントリー・トヨタ経済学・関係諸学科国際センター(STICERD、ロンドン)大学院生研究者。現在米国ワシントンDCの地政学リスク・コンサルタント会社PTBグローバル・アドバイザーズ研究主幹。
プロフィールを見る
研究員,
デジタル・コミュニケーション・オフィサー
専門はハンガリーを中心とした中・東欧比較政治、民主主義の後退、反汚職対策。明治大学政治経済学部卒業、英国・サセックス大学大学院修士課程修了(汚職とガバナンス専攻)、ハンガリー・中央ヨーロッパ大学大学院政治学研究科修士課程修了。埼玉学園大学経済経営学部非常勤講師、EUROPEUM欧州政策研究所アソシエイト・リサーチ・フェロー(チェコ)、国際NGOトランスペアレンシー・インターナショナル(TI)外部寄稿者も兼職。 TIハンガリー支部でのリサーチインターンなどを経て、アジア・パシフィック・イニシアティブ(API)に参画。API/地経学研究所でのインターン、リサーチ・アシスタント、欧米グループ研究員補(リサーチ・アソシエイト)やEUROPEUMでの訪問研究員を経た後、現職。APIでは、福島10年検証、CPTPP、検証安倍政権プロジェクトに携わった。シンクタンクのデジタルアウトリーチ推進担当として、財団ウェブサイトや SNSの活用にかかる企画立案・運営に関わる業務も担当。 主な著作に『偽情報と民主主義:連動する危機と罠』(共著、地経学研究所、2024年)、『EU百科事典』(分担執筆、丸善出版、2024年)、Routledge Handbook of Anti-Corruption Research and Practice(分担執筆、Routledge、2025年)などがある。 【兼職】 埼玉学園大学経済経営学部非常勤講師(秋学期担当、欧米経済事情、2単位) Visiting Research Fellow, EUROPEUM Institute for European Policy External contributor, Anti-Corruption Helpdesk, Transparency International Secretariat (TI-S)
プロフィールを見る