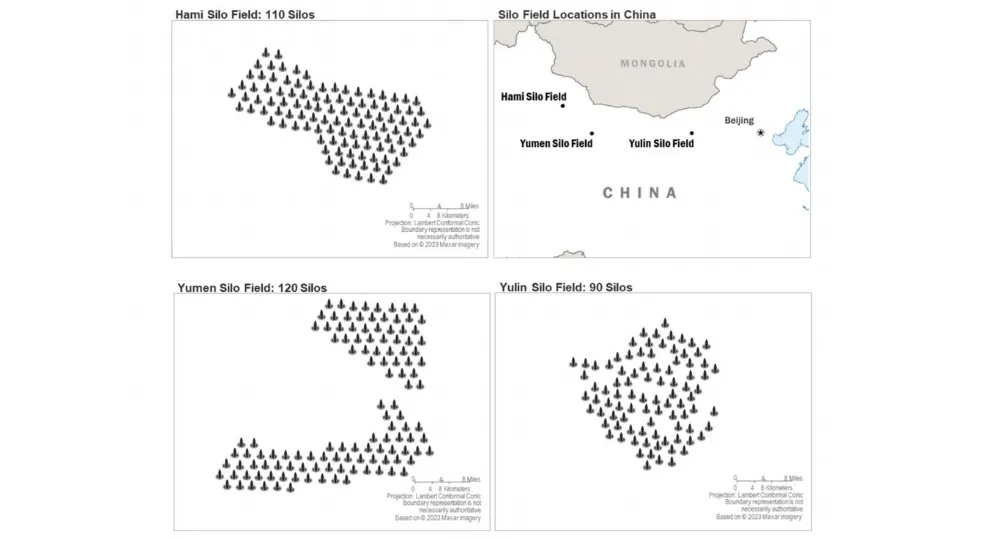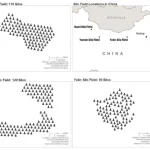アメリカの経済安全保障政策に見える2つの課題

アメリカでは昨年、半導体輸出規制強化策、サプライチェーン強靭化策を相次いで実行し、日本をはじめとする西側同志国との連携を強化しようとしている。こうした中で、先端技術において経済と安全保障をどのように両立させるか、或いは自国と同志国との経済的利益をどのように調整するか、といった課題が出てきている。
本論考では、産業界の視点も交えながら、昨年10月の半導体輸出規制強化策、および昨年8月に成立したCHIPS法(CHIPS and Science Act of 2022)とインフレ抑制法(Inflation Reduction Act of 2022)を通じてこれらの課題について見ていきたい。
アメリカの半導体輸出規制強化策
昨年10月7日、アメリカ商務省は中国を対象に先端半導体および先端半導体製造装置の輸出規制を大幅に強化する規制を施行した。今回の措置は、対象の中国企業が先端半導体の開発を目的とするだけで原則輸出不許可とする点や、また通常設ける例外規定を今回は設けないこと、さらにアメリカ人による先端半導体製造ラインでの技術提供禁止など、過去の輸出規制と比較してもかなり革新的な手法が含まれ、突出して厳しい内容となっている。
アメリカとしては、中国のサプライチェーン上の弱みである先端半導体を押さえることで中国の軍事技術の開発スピードを遅らせる意図を持っているとされる。
アメリカ商務省の輸出規制はアメリカの技術が含まれる場合、第三国にも域外適用されるが、半導体製造装置市場を日米蘭企業が独占する中で、オランダASML(半導体製造装置市場2位)、東京エレクトロン(同3位)は、アメリカの技術なしに自社製品の多くを完成できると見られている。そこでバイデン政権は、自国の輸出規制の手が及ばない部分を補完するため、日本政府、オランダ政府に歩調を合わせるように働きかけている。
一方、産業界の動きをみると、アメリカ産業界と歩調を合わせる姿勢を示す東京エレクトロンに対し、ASMLは自社の利益を失うことに強く反発している。またアメリカ半導体産業協会もアメリカのアプライドマテリアルズ(同1位)やラムリサーチ(同4位)の名前を出し「早期に同盟国と連携をしなければアメリカ企業だけが不利益を被る」と強い懸念を示している。
アメリカ商務省が規制強化を発表してからすでに3カ月が過ぎている中で、1月11日現在、日蘭が具体的な施策を発表していないことは、日米蘭の調整が簡単でないことを示すとともに、事前調整を十分に行う前にアメリカが今回の措置を実施したことがわかる。
特に産業界の視点から見ると、どの輸出品目を規制するかが各社の業績に直結し、業界勢力図を変えることにもなりかねない。今回の措置に留まらず、同志国間でのルール作りやすりあわせが今後の課題として残る。
アメリカのサプライチェーン強靭化策
アメリカは昨年8月にCHIPS法、インフレ抑制法の2つの法律を成立させた。
まず、CHIPS法は中国との競争を念頭にアメリカの競争力を強化するために総額2800億ドル(約37兆円)を先端技術の研究開発に投資するものでこの中に半導体生産支援として527億ドル(約7兆円)の施策が含まれている。
CHIPS法を念頭に、アメリカのインテル、マイクロン、韓国・サムスンなどの企業は相次いでアメリカで新たに先端半導体工場の設立を表明しているほか、台湾TSMCはすでにアリゾナ州でアップル向けなどに先端半導体工場を建設中で、各社ともアメリカ政府の補助金に期待を寄せている。一方で、補助金受給企業は今後10年間、中国を含む「懸念国」での工場建設を禁じられる条項も盛り込まれている。
もう1つはインフレ抑制法で、歳出合計4990億ドル(約66兆円)の内、気候変動対策・エネルギー安全保障に3910億ドル(約52兆円)を充てる法律である。この法律には、電気自動車(EV)の購入者に、最大7500ドル(約100万円)の税控除を適用する条項が含まれるが、電池部材の北米原産率や重要鉱物がアメリカと自由貿易協定(FTA)を結ぶ国で生産される比率などで、厳しい条件が課されるほか、中国を含む「懸念される外国の事業体」が関与する部品や重要鉱物が含まれないことなどの条件も課されている。
上記2つの法律は、台頭する中国を念頭にカーター政権以来の本格的な産業政策を復活させることで、先端技術を通じてアメリカの経済競争力を向上させようとする意図と、先端技術の流出を防ぐ意図を持った法律である。
一方で特にインフレ抑制法については、EUが独自の優遇政策でアメリカに対抗する可能性に言及し、韓国もWTO提訴の可能性に触れながら、ともにアメリカに条件を見直すように強く求めている。同様にアメリカとFTAを締結していない日本も条件を見直すようアメリカに強く働きかけている。
安全保障上の脅威を理由とした半導体輸出規制強化策と比べて、アメリカのサプライチェーン強靭化策にはバイデン政権の掲げる「中間層のための外交」によるアメリカ国内における雇用政策の側面も含まれており同志国間での調整を一層難しくしている。本特集第1回(アメリカと中国「半導体めぐる強烈な対立」の重み/1月9日配信)での論考の通り、日本とでは経済安全保障の概念が異なる点を意識する必要があるだろう。
経済安全保障に関する同志国間ルールの必要性
ここまで見てきたように、先端技術において経済と安全保障をどのように両立させるか、或いは、自国と同志国との経済的利益をどのように調整するか、といった課題が出てきているが、それはなぜ起こっているのだろうか。
背景として、近年、地政学・地経学の重要性が増し、経済安全保障(若しくは類似の概念)を各国が強く意識するようになったのに対し、経済安全保障に関する明確なルールがなく、同志国間でも思惑が異なるという点が挙げられる。
こうした課題に現実的に対処するためには、しばしばプルリラテラル(Plurilateral)やミニラテラル(Mini-lateral)などと呼ばれる少数の同志国での枠組みを設置し包括的なルールメイキングを中長期視点で実行していく考え方が持ち出されるが、今後はこうした点を一層考慮する必要があろう。
例えば、輸出管理の国際レジームである、現行のワッセナー・アレンジメント(通常兵器及び関連汎用品・技術の輸出管理の枠組み)では西側諸国と対立しているロシアをも含めた42カ国の会議体において全会一致で政策を決めるが、先の日米蘭の半導体輸出規制に反対が出ることは想像に難くなく、ワッセナー体制の下でアメリカが行っている対中輸出規制のような内容に合意することは現実的ではないだろう。
そこで現実問題としてワッセナー体制を補完するために、新たな同志国の枠組みにおいて安全保障上の脅威を特定し、どの先端技術を規制するか、規制をどのような基準に基づいて運用するかなどのルール作りが必要になると思われる。短期的には個々の問題を個別に解決せざるを得ないが、中長期的には円滑な政策の実行のために、より包括的なアプローチが必要だろう。産業界の視点から見た場合、企業のコスト増の心配はあるが、企業が何よりも嫌う不確実性を避けるといったメリットにもつながるだろう。
サプライチェーン強靭化策に関しても、どの先端技術を安全保障上の脅威と見なして管理していくかを協議できる枠組みを設けて、同志国の業界団体(例えば、アメリカでは商工会議所や半導体産業協会、日本では経団連等)にも一部オブザーバー参加してもらうなど、官民で連携して同志国間で受け入れ可能な施策を考える枠組みが必要ではないだろうか。
ここで重要なのは、戦後長い間、各国に支持されてきた現行の国際的枠組みを否定するのではなく、現行の枠組みでは対処できない課題に対してこれを補完するための枠組みを設けることである。また規制は狭くても厳しく行うといった「Smaller Yard Higher Fence」の考え方を取り入れることも必要であろう。
アメリカの経済安全保障政策における日本企業の役割
アメリカでは昨年11月の中間選挙で共和党が下院多数党を確保し、対中強硬派のマッカーシー議員が共和党内の保守強硬派の支援を受けて新たに下院議長となった。アメリカの対中経済安全保障政策は今後も強化されるとの声はワシントンDCでは多い。こうした中、2023年は、日本としては好むと好まざるとにかかわらずアメリカの経済安全保障政策を意識することがますます増えていくだろう。
一方で先端技術の規制において経済と安全保障をどのように両立させるか、或いは同志国間での経済的利益をどのように調整するか、といった課題で、日本はルールメイキングに貢献できる良い位置にいるとも言える。その理由として、日本は他国に先駆けて経済安全保障推進法を制定したことや、官民の対話がなされ、経済と安全保障を両立させるためのコンセンサスの経験があることがあげられる。
特に先端技術を抱える日本企業としても単にルールが決まるのを待つのではなく、自社にとって不利なルールが知らぬ間に決められないよう、業界団体などを通じて積極的に建設的な提言を述べていく必要もあるだろう。ルールメイキングに参加することは、日本企業にとってもますます重要となるような新たな時代に入っているためである。
(Photo Credit: AP / Aflo)

地経学ブリーフィング
コロナウイルス後の国際政治と世界経済の新たな潮流の兆しをいち早く見つけ、その地政学的かつ地経学的重要性を考察し、日本の国益と戦略にとっての意味合いを精査することを目指し、アジア・パシフィック・イニシアティブ(API)のシニアフェロー・研究員を中心とする執筆陣が、週次で発信するブリーフィング・ノートです(編集長:鈴木一人 地経学研究所長、東京大学公共政策大学院教授)。
おことわり:地経学ブリーフィングに記された内容や意見は、著者の個人的見解であり、公益財団法人国際文化会館及び地経学研究所(IOG)等、著者の所属する組織の公式見解を必ずしも示すものではないことをご留意ください。


主任客員研究員
2022年10月より現職。その前は日本企業に長年勤務(1996年入社)。直近では2018年から2022年6月にかけて、ワシントンDC駐在員として政策渉外チームの立ち上げに従事。産業界の立場から米業界団体や米シンクタンクなどともに、米政府(トランプ政権、バイデン政権)や議会向けに各種の政策提言を実施。 2018年以前は各国政府向けの社会インフラ事業に従事。新興国向け事業にも長年携わり、国際開発金融機関、援助機関などとも協働。 マサチューセッツ工科大学・スローン経営大学院修了(MBA)。 タフツ大学フレッチャー法外交大学院留学。
プロフィールを見る